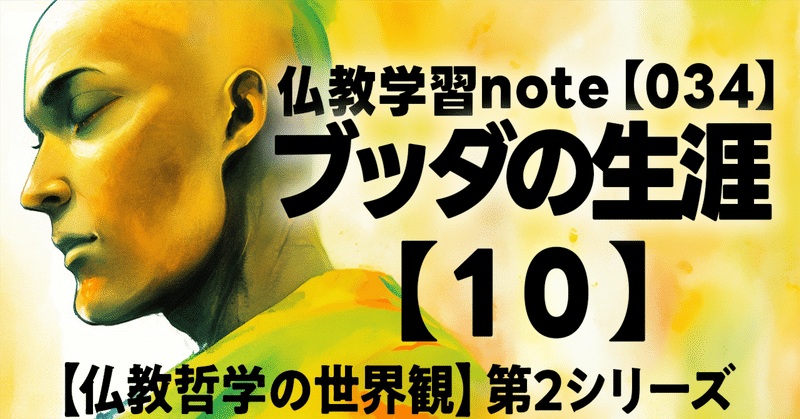
【034】ブッダの生涯-【10】(仏教哲学の世界観第2シリーズ)
梵天勧請が象徴する信憑性の担保
悟りを開いた後、タプッサとバッリカの二人から初めてのお布施をいただいたお釈迦さま。
これは「他者に依存して生きる」という仏教修行者にとって大切な原則を象徴するエピソードでした。
今回は仏伝のハイライトである「梵天勧請」について解説されています。
その前に前回の補足として三種類の悟りの道についても語られています。
このシリーズでは僕が仏教について学んだことを記しています。
主な教材は仏教学者で花園大学の教授をなさっている佐々木閑先生のYouTubeでの講座の内容をまとめています。
もちろん僕の主観によるまとめなので色々と解釈の違いや間違った理解があるかと思います。
それはX(Twitter)などでご指摘いただけると幸いです。
あくまでも大学生の受講ノートみたいなものだと考えていただけると幸いです。
ブッダの生涯10
https://youtu.be/Zq00UvnmoRI?si=4fGIlzGDt6xUrBRN
AIによる要約
このスクリプトは、仏教の生活指針と悟りの道について語ります。お釈迦様が8日間の修行の末に達成した悟り、そしてその教えを広めることを選んだというエピソードが中心です。また、3種類の悟りの道(アラカン、独覚、ブッダ)が紹介され、それぞれ異なる修行の終わりに達成される状態を説明しています。この教えは、大乗仏教の発展において重要な意味を持ち、お釈迦様が初めて人々に説法を始めた瞬間を通じて、その教えの信憑性と実証性が強調されています。
学習した事
三種類の悟りの道
まずは前回の補足。
悟りの道には三種類ある。
悟りを開いた後、人に説法をせずに一人で亡くなっていく
これを「独覚」という。
悟りを開いた後、人に説法を行い多くの人を救いながら亡くなっていく
これを「ブッダ」という。
最後に
仏の教えを聞いて、その弟子として悟りを開き亡くなっていく
これを「阿羅漢」(あらかん)という。
これらは一応のグレードがあり、
阿羅漢
独覚
ブッダ
という順番で、1<2<3として位が高い
阿羅漢とは、仏陀の教えを聞いて弟子となり、仏陀の指導を受けながら次第に心の煩悩を取り除き、最後に悟りを開いた人々のことである。
日本においては略して羅漢ともいう。
彼らは自力で悟りを開いたわけではない。しかし、悟りを開いているので寿命が来て亡くなった後は輪廻せず消滅する。(涅槃に入った)
独覚は一人で悟りを開いた後、誰にも教えを解く事なく涅槃に入った人である。
仏陀はもちろん悟りを開いた後、多くの人に教えを説き、その後寿命で涅槃に入った人ということになる。
阿羅漢になろうと努力している人たちのことを「声聞」(しょうもん)という。
つまり、お釈迦さまの弟子で悟りを開く前の人を指す。
仏陀になる前の人のことを「菩薩」(ぼさつ)という。
そして、独覚は誰にも教えを説かないわけなので、その存在があるのかはわからない。
なお、この三種類の悟りの道は
その後の仏教の発達にあたり、「大乗仏教」という新たな仏教世界が生まれるときに重要な意味をもっている。
梵天勧請
お釈迦さまのエピソードにおいて、最も重大なキーポイントが
「梵天勧請」(ぼんてんかんじょう)である。
「勧請」とは何かをするようにお勧めし、お願いすることを意味する。
すなわち、梵天勧請とは神である梵天から教えを説くようにお願いされたというエピソードである。
タプッサとバッリカのエピソードは、お釈迦様の立派な佇まいからお布施をし、在家信者となる近いを立てただけであって、お釈迦さま自身は彼らを弟子にし、教えを説くつもりはなかった。
つまり、この当時のお釈迦さまは自分が得た悟りの境地を誰かに教え広めようという意思はなかった。
この部分が仏典における注目すべきポイントである。
お釈迦さまは、昔から慈悲深く、人々のために修行し、人々のために悟りを開き、人々のためにその悟りの道を説き広めようとした───
というエピソードにはせず、
お釈迦さまは本来は周りのことには興味がなく、これを梵天からの要請を受けるまでは自分のことで精一杯だった。
このように、お釈迦さまをあえて元からの聖人・善人として存在していたわけではないとする「設定」が大切なポイントとなっている。
なぜならば、仏教の基本的な考え方は「自分で自分の苦しみを消す」ことなのであって、外部の超常的な力によって悩みや苦しみを消すわけではない。
それゆえに、お釈迦さま自身も苦しみを知っているとする必要がある。
お釈迦さまが自らの苦しみを修行によって克服した、という経緯があるからこそ、その教えに実証性が担保されることになる。
それまで自分の苦しみと向き合うしかなく、他人に構う余裕のなかったお釈迦さまが、悟りを開き自らの苦しみを消すことに成功したことで初めて他者のために役立つ生き方をしようと180度方針を転換する。
このエピソードがなければ仏教に信憑性を持つことが難しくなる。
あくまでも人間であるお釈迦さまが発見した真理への道であるというスタンスを象徴している。
それが梵天勧請である。
感想
梵天勧請については次回詳しく解説があると思うが、ここでは内容の切り分けを事前に意識しておく必要があると思った。
まず、梵天からの要請とはなにを意味するのか。
そして、実際のお釈迦さまの方針転換の動機はなんだったのか。
当然想像するしかないのだが、
まず梵天なる存在を信じていない僕としては
勧請を行う「梵天」は
・お釈迦さま自身の動機としてのメタファーだったのか
・梵天とは別の人物による要請があったのか
この辺りが気になった。
今回の解説にもある通り、信憑性の担保のために「あえて」教えを広めることに無関心だったという設定にしたのかどうか。
少しニュアンスは異なるが、古代中国の歴史に出てくる「禅譲」を思い出した。
実際には力による権力の簒奪ではあるが、建前として「より徳のある人物に権力をお願いして譲る」というものだ。
しかも権力を奪う側は、わざわざへりくだって丁重にお断りを繰り返し、3回目に「どうしても」と言わせてから「仕方なく」権力を譲り受ける。
これは当然正当性の演出なのだが、似たような構造を「梵天勧請」にも感じることができる。
真相はもちろん不明なのだが、当時からこれまでそのように感じる人は少なからずいたのではないのか?とは思った。
さて、次回の梵天勧請のやりとりでその辺りの様子は読み取れるだろうか。
次回は「ブッダの生涯11」 (仏教哲学の世界観 第2シリーズ)
仏伝で語られる梵天勧請の具体的な内容について解説をされています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
