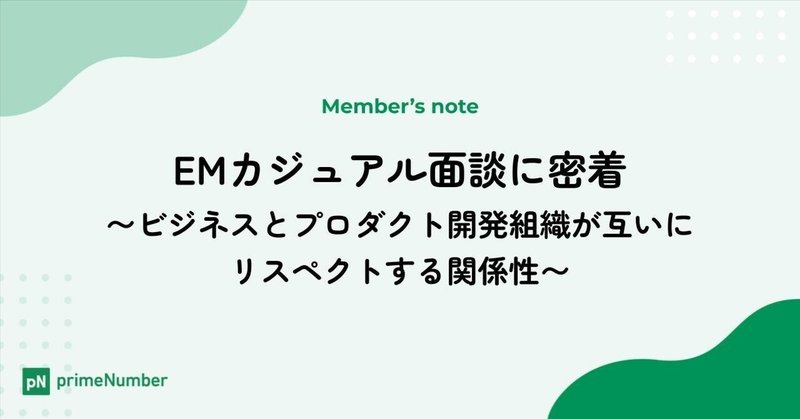
EMカジュアル面談に密着 〜ビジネスとプロダクト開発組織が互いにリスペクトする関係性〜
primeNumberのCTO 鈴木です。
今回は、カジュアル面談で「primeNumberがビジネス側と開発側が同じ方向を向き、顧客に対して価値を返す組織」であることを候補者に説明した内容を紹介したいと思います。
カジュアル面談希望者の秋田さんとは、trocco®のプロダクト開発のチームとは一度面談を実施させていただきました。ビジネス側のメンバーともぜひ話してみたいとのことで、プロダクト開発のチームと特に関わりがありそうなメンバーに声をかけて面談を実施したことが背景です。
当日は、セールスのトップであるCOOの下坂さんと、カスタマーサクセスのトップである中村さんを招いて、和やかな雰囲気でカジュアル面談がスタートしました。
以下にて、カジュアル面談の実際のやり取りを紹介していきます。
参加者
秋田さん:(当時カジュアル面談希望者 / エンジニアリングマネージャーで2024/2月入社)
※本記事の公開について、秋田さんの許可を頂いています。
※実際のインタビューの内容を一部再編しました。

trocco®の成長はプロダクト、セールスの両立によって実現される
秋田さん: trocco®の事業は、Sales-Led Growth(SLG) か Product-Led Growth(PLG) のどちらで伸ばしていきますか?
[補足] SLG: セールス主導での成長戦略 / PLG: プロダクト主導での成長戦略
下坂: 現時点では、セールス主導のSLGに寄っています。しかしながら、SLGとPLGは双方にメリット・デメリットがあり、顧客のターゲットセグメントなどにも依存し、どちらが適しているのか、どちらがベターなのかは変わってきます。最終的には、SLGとPLGの二者択一という考えではなく、間に落ち着く、顧客のターゲットセグメント等に依存し、両軸で動くような形になると考えています。

新プロダクトづくりは既存顧客の課題からはじめる
秋田さん: 新しいプロダクトづくりについては、どの様に取り組んでいますか?
鈴木(CTO): trocco®の既存のお客様から具体的な課題を日々いただくことができます。
そこで集まった実際の課題に対し、新しいプロダクトを当てていく形でプロダクトづくりを行っています。
課題のヒアリングについて、わざわざ我々のために時間を作ってくれるお客様も多くいらっしゃいます。
直近で進めている新プロダクトについては、お客様とタッグを組み、お客様に刺さるプロダクトづくりを行っています。
秋田さん: 具体的な課題に向き合ってプロダクト成功の確率を上げる事が出来るのは、素晴らしいです。
鈴木(CTO): セールス、カスタマーサクセスが顧客と素晴らしい関係性を築けているからこそ実現できていると思います。
これは、下坂さん、中村さんがこの場に居るから言っているのではなく、常日頃から言っています(笑)
既存のお客様との関係性や、具体的な要望は、我々のプロダクト開発、会社全体の大きな資産であり圧倒的な強みだと思います。
それらは日々のtrocco®の開発にも間違いなく活かされています。
trocco®を通した長期的な運用が可能になれば、プロダクトはさらに強くなる
秋田さん: カスタマーサクセスからみて、今後数年のプロダクトの課題は何がありますか?
中村(Head of CS): 既存のお客様は、trocco®を通して「素早く」「学習コスト低く」データ活用を始められることに大きな価値を感じられています。
一方、trocco®を利用して「長期的な運用」を実現するという観点では、まだまだプロダクトが解決するべき課題は大きいと考えています。
例えば、trocco®では「肥大化したワークフローを、trocco®上でどのように堅牢に運用していくのか」という課題が挙げられます
秋田さん: trocco®のチャーンレートはかなり低いと伺ったが、お客さんが感じる運用の課題は大きいのですか?
中村(Head of CS): trocco®は本格的にプロダクトの展開が始まってからまだ数年です。比較的新しいお客様が多くいらっしゃいます。
そのため、長期的な運用での課題にあたるお客様の課題が顕在化してくるのはこれからだと考えています。
プロダクトとしては「長期的な運用」を目指すべき価値の一つにおいており、そこへのプロダクト開発が行われていきます。

プロダクト/会社の成長を通して価値を返し、日本を強くする
秋田さん: 中村さんの入社動機を聞いてもいいですか?
中村(Head of CS): trocco®というプロダクトを知った時、ワクワクしたのを覚えています。
国内のエンジニア向けプロダクトで、アメリカを筆頭にした海外製品に負けずに市場をリードしているプロダクトはほとんど無いと思っています。
trocco®はデータエンジニアリングをリードしていけるプロダクトだと感じ、そこの一翼を担いたいと思ったのが入社のきっかけです。
実際、trocco®の国内の知名度は一気に上がり、多くの価値を返せるまでに至りました。
これからも、カスタマーサクセスとして、大企業だけではなく、日本を支えている多くのスタートアップ・中堅企業にも引き続き価値を返し続けていきたいと考えています。
下坂(COO): 会社の8 Elementsのひとつに「価値を返す」があります。私も価値を返すことを通じ、日本を強くしていきたいと思っています。
日本を支える多くのスタートアップ・中堅企業とともにprimeNumberが成長し、日本を成長させることに貢献していきたいと本気で思っています。
秋田さん: 私も日本企業を成長させ、日本を活性化するような仕事をしていきたいと考えていて、非常に共感しました。
ビジネス、プロダクト開発がともにリスペクトし、同じ方向を向く組織
秋田さん: 会社が成長して売り上げが増えると、セールスの影響力が大きくなり、ビジネスと開発の関係性が悪くなる会社もあるが、primeNumberはどうですか。
下坂: ビジネス、開発がお互いにリスペクト出来ている組織だと思います。
セールスとしては、自分たちが売るものはエンジニアが作ってくれているという感覚を強く持っていますね。
鈴木: 開発側としても、セールスの方達が適切に売ってくれるからこそ、自分たちの開発したものがお客様に使われるという感覚がある。
秋田さん: primeNumberはどうしてそれが実現できているのですか?
下坂: 個人の見解になりますが、エンジニアだけの組織だった事と、採用方針の影響が大きいと思います。
8 Elementsの「価値を返す」に繋がるのですが、ビジネスサイドでは中々できない「開発する」「ものをつくる」、それに伴い価値を返すという点に対して、自然とリスペクトが醸成されていると考えています。
鈴木: 価値をより大きく、より正しく返すためには顧客に近いビジネス側と目線を合わせてプロダクト作りをする事が必要不可欠で、自然とリスペクトする文化ができています。
エンジニアの採用方針としても、開発することがゴールではなく、ユーザーに価値を届けることを重視している方を採用しています。
そういったメンバーが揃っているからこそ、ビジネスと開発が同じ方向を向いてリスペクトし合う文化ができていると思います。
実際に、顧客に価値を返すために、開発のプロセスをカスタマーサクセスのメンバーと一緒に改善したり、セールスと開発でプロジェクトを組んで商品開発を行うなど、同じ方向を向いて健全な改善・開発活動が日々行われています。
秋田さん: そういった文化ができているのはとても良い。一方でユーザーに価値を届けることを重視しているエンジニアを採用するのは難しいのでは。
鈴木: めちゃくちゃ苦労しているので、助けて欲しいです(笑)
良い文化が維持できていると思いますが、一方で何もしないと確実に壊れていくため、常に維持し続ける努力が必要だと思います。
最近はプロダクトビジョンを改めて定義したりなど、改めてプロダクトの方向性に対して全社で目線を合わせることをやったりなどもしていました。
ビジネス側と適度な緊張関係でお互いが期待に応え続けることも大切だと思うので、開発側としては日々の開発を通して顧客だけではなく社内のビジネス側メンバーにたいしても価値を返し続けて行きたいと思います。

primeNumberは毎日がチャレンジ
秋田さん: 最後に、お二人がtrocco®、primeNumberに熱意を持てる理由を教えてもらえますか?
下坂(COO): 毎日がチャレンジの連続だからです。チャレンジすると、またその先に新たなチャレンジが生まれます。常に新しいことに挑戦し続ける環境にいるため、毎日が楽しく感じられています。
中村(Head of CS): 先ほど鈴木からも話がありましたが、どのメンバーも顧客への価値創出のために、同じ方向を向いて業務を行えている点です。誰しもが真剣にお客様に向き合って仕事を行うという環境は、言葉で言うのは簡単ですが、なかなかできることではないと思っています。
鈴木(CTO): 秋田さん、下坂さん、中村さん、本日はありがとうございました。3人の話を聞いて、改めてprimeNumberがビジネス側・開発側が協調して顧客に価値を返すことを重視していると再認識できた時間でした。
ここまで記事を読んでいただき、ありがとうございました!
少しでもご興味を持っていただけた方は、お気軽にカジュアル面談をお申し込みください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
