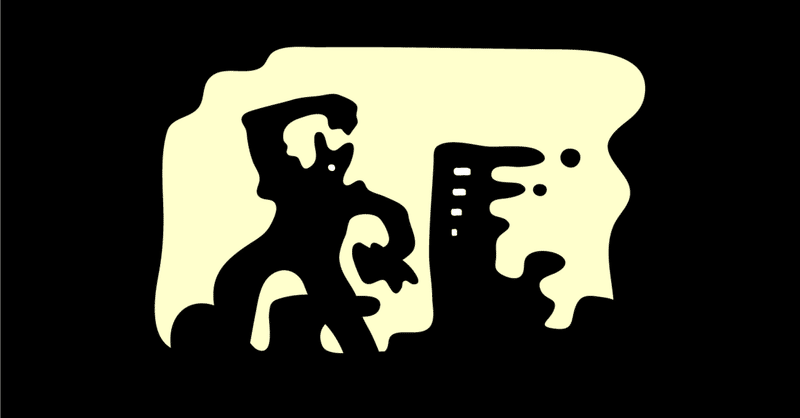
子どもの頃からインプットよりアウトプットが好きだった
振り返ってみれば子どもの頃から「お話を作る人」になりたいと思っていました。
自分のルーツについて聞かれた時はたいてい、金曜ロードショーでジブリ作品を見たこと(「天空の城ラピュタ」が特に今も好きです)を挙げますが、自分が「お話を作ること」を職業にしたいと考えるようになった大きな理由として「アウトプットの楽しさを知る機会があった」ということがあると思います。
その機会を生んでくれたのは、小学生時代に出会った2つのPCソフト。
「Microsoft 3Dムービーメーカー」と「RPGツクール95」です。
「Microsoft 3Dムービーメーカー」
windows95が発売され、一般家庭に普及し始めた1995年。まだインターネットも世の中に浸透していない時代に発売された「子どもでも簡単に3DCGアニメが作れる」ソフトです。
確か、映画「ジュマンジ」のCGの一部がこのソフトで作られた、みたいな触れ込みもされてました。
街とか家の中とか洋館とか「シーン」を選んで、どの位置から撮るか「アングル」を決めて、そこに3Dのキャラクターを配置して、動き「アクション」を指定して……という感じで映像を作る。
いろんなキャラクター、動物とか、パトカー、救急車なんかもあって、いろんなムードのBGMや効果音をつけたりもできて、簡単操作で映画が作れちゃうすごいソフトでした。
雑誌(たぶん「小学4年生」かコロコロコミック)で広告を見て「これ欲しい!」となったんだと思います。
教員だった父は90年代の早い時期から仕事でPCを使用しており、(NECのPC-9801シリーズ。MS-DOSにプロンプト打ち込んで操作してました)windows95も割と早いタイミングで家に来た記憶がありますが、簡単な操作で映画を作れる!これは画期的なソフトでした。
しいて言えば問題は、元からプリセットでセリフ用の音データがいくつかついているのですがさすがにバリエーションが少なく、全キャラクターがPCのしょぼいマイクで録った自分のアテレコになってしまうこと(これは今ならAIで簡単にクリアできるんだろうな)。
あと当時は気にもしてなかったですが「カメラ位置の指定」ができないこと(
これがクリアされてればより創作の自由度が上がったと思いますが、そこまでしちゃうと子ども向けソフトとしては逆に扱いづらいものになったのでしょう)。
小学校から帰って、パソコンを使える時間は1日15分と決まっていて、その時間の中でああでもないこうでもないと、誰が見るでもない映像をゆるゆると作ってましたね。長編の物語を構成する能力もなかったし、そこにはあんまり興味もなくて、キャラクターを動かして映像を作ることがシンプルに楽しかったなー、と。BGMが豊富で、今でも口ずさめるほど印象に残っています。
「RPGツクール95」

いわゆる「ドラクエ」スタイルのRPGを自分で作れるソフト。マップを作って、キャラクターを配置して、イベント(会話とか、戦闘とか)を作って……って感じでゲームを作っていく。はじめから「ドラクエ」を彷彿とさせるような味方・敵のキャラクター、魔法などのエフェクト、効果音、BGMなどが用意されていて、こちらもかなり簡単操作でRPGを作れる魅力的なソフトでした。
発売されたのが1997年、ダイアルアップのインターネットが家に来た頃でしたね。発売元のアスキーのサイトでゲームのコンテストをやってて、優秀作品をダウンロードしてプレイできたりして、「自分もこんなの作ってみたい!」って思える、そういう身近さも印象的でした。
これまたBGMが印象的で今も口ずさめるくらい覚えてますが、付属のBGMやグラフィックに触発されて、いろんなキャラクターやシーンを思い描く時間はとても楽しかった。
この頃のインターネットは電話回線を使うのでネットを使っている間は家の電話が使えなくて、さらに使っただけ電話料金がかかったのでめちゃシビアでしたね。パソコンをやっていい時間も1日30分だったから、パソコンに触ってない、想像力を働かせてる時間の方がずっと長かった。
ゲームのアイディアを書き溜めるためのノートを作って、スクリーンショットを印刷したものを貼り付けて、ああでもない、こうでもないと構想だけは壮大に膨らませてました。
思えばこの頃から「会話をキーボードで入力していく」という作業をしてたわけで、そこは30年近く経った今でも変わってないな……
賞金が出る大きなコンクールもあったりして「自信作でグランプリ取る!」みたいなことをぼんやり考えたりしてましたが、結局最後まで完成させられた作品って無かったですね。あれもたぶん、構想を練ってあれこれ想像する時間とか、とにかく自分の作ったものが動く、そういう単純な楽しさだったんだと思います。
*
「3Dムービーメーカー」も「RPGツクール95」も、自分にとっては懐かしさを強く刺激される思い出深いソフトなんですが、「うわこれ懐かしい!」ってなる人っているんですかねえ。
今までの人生で会ったことない。
けど、自分も今まで口にしてこなかったので、意外と身近に同志がいるのかも。
*
で、これらのソフトに触っていた当時、映画にせよゲームにせよ、「名作」みたいなものにほとんど触れてない状態なんですよね。
映画をちゃんと観るようになったのってもっとずっと後だし(なんなら映像を勉強し始めた大学入学以降だし)、今でも「ドラクエ」プレイしたことない。家にスーファミ、プレステ、ほか一切のゲーム機なかったし。
だから、自分にとってルーツって、観て衝撃を受けた作品、影響を受けた作品というのはもちろんあるんだけど、「作ることが楽しかった」っていう体験自体が、自分にとっては大切なルーツなんだよな、と、改めて思ったわけです。
なんというか、映画やドラマの仕事をしててルーツの話する時って、「どの作品が好き」とか「どの監督が好き」っていう話題から入るので、「小さい頃からとにかく『作ること』が好きだったんですよねー」みたいな話にならないというか。
そういう設問のしかたをしてこなかったから自分自身でも見落としていたんですが、思い出してみると記憶がするする湧き上がってきて、あれって案外自分にとって意味のある出来事だったんだな、と、はじめてそう感じました。
きっとこれからの世代ってそれがもっと顕著というか、ツールも進化してAIもあって、「イメージを具現化する」とか「作る」ことの面白さが、もっともっと身近な世代なんだろうなと。それってすごいことだよなあ。
一方で自分にはそういう「インプットよりアウトプット好き」傾向は今でもあって、手を動かすだけじゃなくてちゃんとインプットしろよ、という自省にも通じるのです。いやーほんと、もっと勉強しろよと思いつつ、何かを作る本質的な楽しさはきっとずっと変わらないだろうから、仕事にするとか人に感動を渡したいというのとはまた別のレイヤーで、この楽しい気持ちを大切にしていきたいなと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
