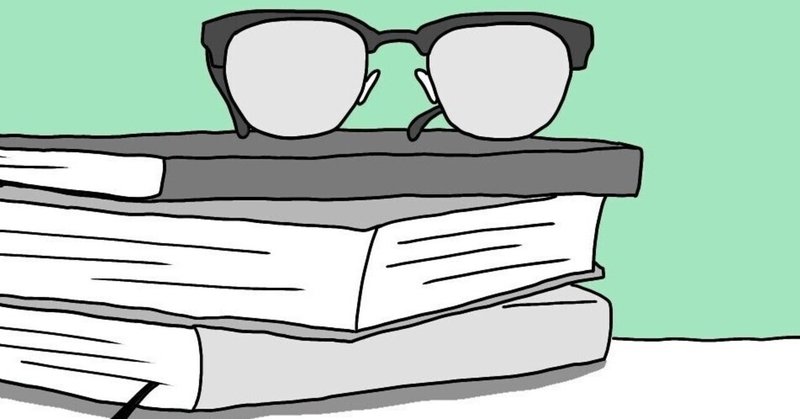
名作小説は微に入り細にわたる
最近フォローしてる書評家、三宅香帆。の著書がサイコーだった話。
YouTubeも。
最近、ジョージ・オーウェエルの1984を中田あっちゃんのYouTube見ながら、なんとか読み終えた。
巷では散々名著と崇められ、あたかも全国民が読んでると言わんばかりに煽られる。
「だったら読んでみるか」とページを進めるも、「うっ、意外に難しい、しかも途中若干面白くない」とか「気づいたら同じページ2回読んでた。。」とか。
この現象、実は昔から日常的にあって、特にひどいのが夏目漱石とかカラマーゾフとか。
ページを進めるのが本当に大変だった。
てか世の中の人、どんだけ読解力あるんだよ!
子供の頃から読書はしてたし、文系でそこそこの大学は出ているはず。
そんな自分が、なぜ全国民が読んでいる名著につまづくのかと不思議に思いつつも、「きっと自分には読解力が 足りないんだ」と無理やり結論づけて、なんとかシナリオのレールから外れないような読み方をしてきた。
そうすると今度は、迷子にはならないんだけど、なんだか全然楽しくないんだよね。
あらすじをなぞるだけのよう。
そこで、彼女のYouTubeとか長いタイトルの著書(『(読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法』)で書いていることに耳を傾けると、
・ネタバレしてから読んで、台詞のすみずみに込められた感情を味わえ(カラマーゾフの兄弟)
・作者の経歴、解説を読んで前提を先に知れ(我輩は猫である)
・ストーリーの起承転結よりも、小説に隠されたメタファーに潜む思想を味わえ(ペスト)
とどれも、小説を噛んで含めるような読み方を勧める。
よく考えたら、音楽の名作だってそうだよね。
マタイ受難曲のストーリーをなぞって何が楽しい?モーツァルトのオペラをハイライトで観たいか?っていうこと。
そのつもりで漱石の「猫」を読み直してみた。
すると、猫が大して可愛くないし、掴みどころなかっただけのストーリーに、漱石の自虐とかニヒリズムが溢れていてちょっとクスッともするようになった。
三宅香帆、救世主かも知れない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
