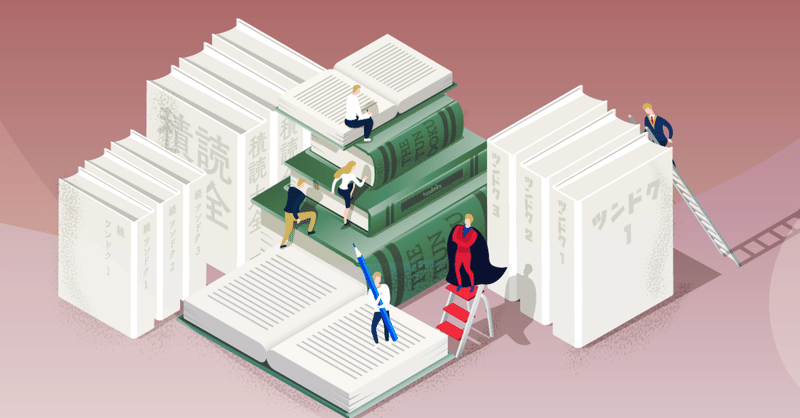
Photo by
ia19200102
【書評】予想通りに不合理
「予想通りに不合理」という本をレビューします。行動経済学について書かれた一冊で、タイトルの通り「いかに人間は不合理な行動を沢山しているか」を解説した本です。本のなかで重要な部分も伝えていきます。
【評価】
★4つ
【感想】
長い。とにかく長い本で500ページもある。行動経済学について書かれており、新しい発見は沢山あるが、実験が多くて表現が細かすぎるので内容の70%は要らないと思う。
バンカーとして思ったのは、口座維持手数料にこれだけ反対論が多いのは、今まで無料であったアンカーがあるからではないか?
【抜粋】
人間は、物事を絶対的な基準で決める事はまずない。他の物との相対的な優劣に着目して、そこから価値を判断する。
価格などで選択肢が3つあると、大抵の人が真ん中を選ぶ。「おとり」を設定することで選択を誘導できる。
おとり商法は、わざと見劣りする商品を提示することで本命を販売するものです。気をつけましょう。
「恣意の一貫性」
最初の価格が恣意的でも、いったん意識に定着すると、現在の価格ばかりか、未来の価格まで決定づける。(価格の刷り込み効果)
刷り込みを打破するには習慣に疑問を持つ。最初の決断は何年も影響を与えるため、十分に注意を払う。
無料は感情の引き金であり、不合理な興奮の源。
二者択一で無料(1つ買ったら2つ目無料など)があると、無料を選択しがち。「失うことを恐れる」という人間の本能があり、無料なら失うリスクはない。無料を得たいがために、余計なコストを払いがち。無料で人を呼び込むこともできる。値段ゼロは単なる値引きではない。ゼロは全く別の価格だ。
人は金が絡まない社会規範と金が絡む市場規範の2つの世界の中で生きている。お金が絡むと市場規範のみで行動する。市場規範に囚われることなく円満な人間関係を構築するのはプレゼントを贈ることだが、値段を言ってはいけない。値段を言うと市場規範に支配されてしまう。
社会規範は1度でも市場規範に負けると、まず戻ってこない。親しい人間関係に金を持ち込んではいけない。
プレゼントするときに値札は外しますが、こういう意味があったんですねー。
経済的交流の場では、私たちはどこまでも利己的で不公平だ。そして自分の財布に従うのが正しいことだと考える。やりとりに金銭が絡まない時、私たちはあまり利己追求をせず、他者の幸福を気にする。
「所有意識」
自分が既に持っているものを過大評価する。手に入るかもしれないものではなく、失うかもしれないものに注目してしまう。
価格とプラセボ効果は相関性がある。価格が高くなると、プラセボ効果も高まる。値引きされたものを見ると、直感的に定価のものより品質が劣っていると判断する。そして経験を本当にその程度のものにしてしまう。
不正行為は、現金から1歩離れたときにやりやすくなる。電子商取引は不正させやすくなる。現金を使わない取引では、自分を不正直な人間だと思うことなく、不正直になれる。
【雑記】
今月は1冊しか本を読まなかったので、内容を詳しく紹介してみました。月によって読書量が全く違いますが、まあいいことにします。人は不合理ですからね!ではまた次回の記事でお会いしましょう。
宇宙旅行が夢の一つなので、サポート代は将来の宇宙旅行用に積み立てます。それを記事にするのも面白そうですねー。
