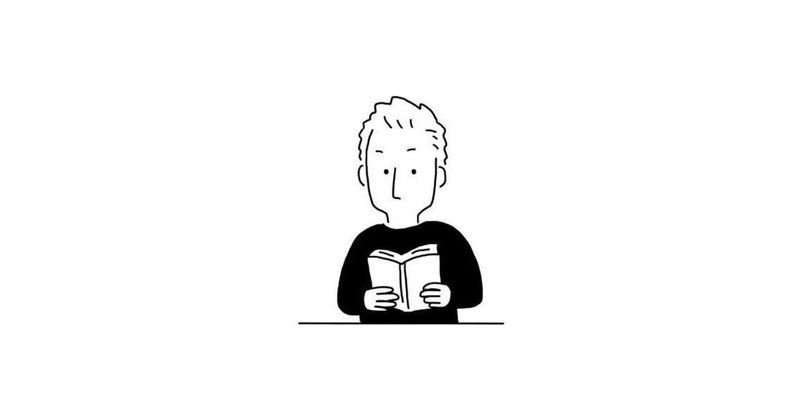
Photo by
ugto310
2020年5月の読書と書評
今月読んだ本のレビュー記事です。
【本の紹介とレビュー】
「知っておきたい感染症ー21世期型パンデミックに備える」 岡田晴恵
★5つ!
新型コロナで感染症について知ろうと思い、購入。内容については記事を書いたので、そちらをどうぞ。
「メンタルの強化書」 佐藤優
★2つ
数々の著書を出している作者に興味があり購入。しかし内容は一般論ばかりで面白くなかったし、活かせるものでもなかった。この作者の本は、もう買わないだろう。
「医者が教える正しい病院のかかり方」 山本健人
★4つ
医者と病院のトリセツ本。この場合はこうすることが具体的に書かれており、ためになった。かかりつけ医を見つけることと、お薬手帳は実践しよう。
【抜粋】
検査は万能ではない。インフルエンザ検査でも、症状が出てから1日以内だと61%の人しか陽性にならない。
症状の原因を突き止められないといってもヤブ医者ではない。症状の原因が完全に明らかになることの方が少ない。医師との相性が悪いからといって、こっそり他の病院に行くのは避けるべき。
がんになった場合の病院の選び方
①かかりつけ医に相談する
②自宅からの交通アクセスが良い病院
③がんの治療を専門的に行っている、症例豊富な病院
救急車を呼ぶか迷う時は
①市町村の救急相談窓口に相談(電話番号は#7119)
②アプリ「Q助」を利用
③救急車利用リーフレットを活用
目の前で人が倒れたら
①大きな声で呼びかける
②救急車を呼ぶ。AEDを要請する。
③呼吸を確認する
④呼吸してない、正常な呼吸でない場合は心臓マッサージする。AEDを装着。※心臓マッサージは、左右の乳首を結ぶ線の真ん中。胸が5cm沈み込むように圧迫。1分間に100回のテンポで。
「人工知能の核心」 羽生善治
★4つ
NHKとともに良く取材されており、人工知能について理解が深まった。仕事がAIに置き換わると言われているが、大事なのは「創造性」と「遊び」と「共感」だろう。
【抜粋】
ムーアの法則:集積回路の密度は1年半で2倍に向上するため、コンピュータの計算速度は天文学的な速度で上がる。
無駄な情報を扱うことを減らす引き算の思考にこそ、人間の頭脳の使い方の特徴がある。人間の知性の優れた点は、柔軟性と汎用性(応用力)。
人工知能には恐怖心がなく、問題を先送りする癖がある。人工知能には美意識が存在しない。美意識とは安心や安定のような感覚に近い。逆に人間の思考は美意識により狭められていて、選択肢を減らされているのではないか。
人工知能の開発の課題は、時間の要素を取り入れること。静止画像は得意だが、動画は不得意。もう一つの課題は、ある目的に対して関係のあることだけを選び出すことが人工知能にとってなぜか難しい(フレーム問題)。
人工知能の判断はプロセスがブラックボックスであり、100%正確なものではない。人工知能の判断を絶対であると信じないことが大事。
大事なのは「こうすればうまくいく」ではなくて、「これをやったらうまくいかない」を、いかにたくさん知っているか。取捨選択の「捨てる方」を見極める目こそが、経験で磨かれていく。
【雑記】
病気や健康についての読書が増えてますねー。ニュースだけだと表層的な情報しかないので、それを補完してる感じです。
5月も今日で終わりです。仕事面ではリモートワークが終了し、毎日出勤に戻りました。パンデミック前に比べて電車は空いてますが、明日から混みそうな予感が。。
では、良い休日をお過ごしください。
宇宙旅行が夢の一つなので、サポート代は将来の宇宙旅行用に積み立てます。それを記事にするのも面白そうですねー。
