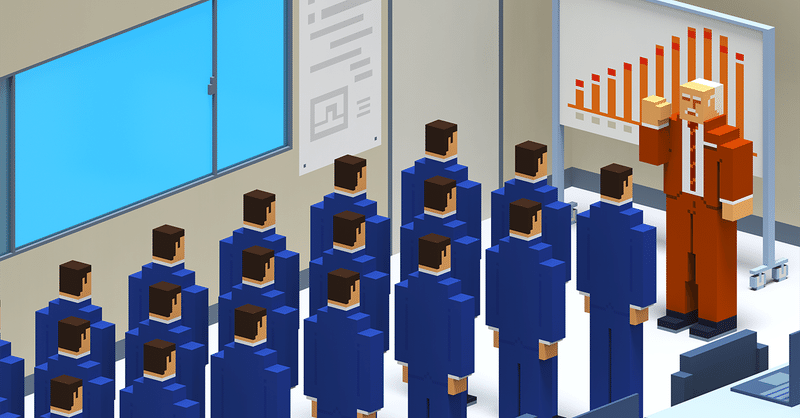
社長からの報連相
報連相、いわずと知れた「報告・連絡・相談」ですね。あたり前に使いすぎているので定義をあまり意識しない言葉でもあります。
よく使われるのは「報連相が足りない」のような言い方です。コミュニケーションが足りていないということですが「上司への」とか「社長への」という対象が省略されて使われることが多いように思います。
つまりは、上へ情報を伝えて、指示を仰ぐというのが隠れた前提になっています。「部下への報連相が足りない」とはあまり言わないですね。
似たような関係性の言葉に「聞いていない」というのがあります。「私は、その情報について知らされていない」という意味合いです。これを社長や上司に言われた側は、内心イラっとしながらも「すみませんでした」となります。
これ、部下が「聞いてません」というとどうなるんでしょうかね…?
昭和世代からするとほぼ禁句ですね。「言い訳してんじゃねえ」という世界です。最近の若い世代だとどうでしょう。「は? 聞いてませんけど?」なんて、普通にでてきそうです。あるいは「あ、そうでしたか。言ってくれれば全然やるんですけど」などと返ってくるとオジサンたちは、イラッを通り越して、困惑してしまいます。
そもそも、昭和的な報連相の前提となるのは、上司からの指示です。その際に十分に意図が伝えられているかというと、そうでもない。何をして欲しいとか、具体的な指示に加えて「なぜ、そのように指示をするのか」ということが伝えらていないケースがほとんどです。
その「なぜ」には、単に目的だけでなく、暗黙の了解になっている重要な情報が含まれます。
・大きな意味での目的
・その前提となる背景情報
・進めていく上で部下が留意しておくべきこと
・相談が必要になる条件、つまり、部下側の責任の範囲…
…です。
これらをあらためて明確に伝えることはないように思います。なぜなら、普段のやり取りの延長のなかで指示やタスクの設定がなされるので「分かっているだろう」という前提で話が進みます。
新入社員だと、このあたりの「分かっているだろう」が成立しないので、特に報連相が意識されます。上司側の伝え方も「求める成果や納期に加えて目的を明確に」などとマネジメント研修で指導されたりもします。
ところが、新入社員以外は、分かっている前提になっている。結果、部下側は「聞いてない」と言えない。社長や上司が「聞いてない」と言えば、実は部下はイラっとしている。つまり、前提を問い直すことが避けられてしまうのです。常に世の中は変わるし、行動した結果によって、判断も変わるし、仮説も更新されるべきなのにもかかわらず、です。
そんな中で右往左往させられ、徒労感を感じてしまう方が多いように思います。特に課長さんあたりは、上からも下からも「聞いてない」となってしまい気の毒です。
この解決策として「相談しやすい雰囲気をつくる」なんていう言葉がよく出てきますが、いつも「雰囲気って何?」と思ってしまいます。忙しそうにしていると言いづらいとか、小言の一つも言ってしまうと話しかけづらいからやめようとか、でしょうか。
結局それは、意見より機嫌の問題になってしまっている証拠です。部下がボスに意見を伺うのではなく、機嫌を伺う状況に気づいてはいるわけですよね。
何事も率先垂範が昭和世代の(?)美徳であるはずです。上司からの報連相、社長からの報連相、必要なのに足りていないのではないでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
