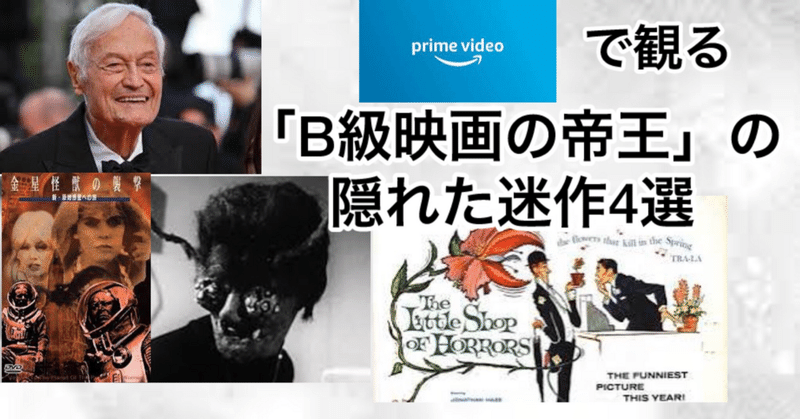
【隠れ迷作4選】デスレースだけではない帝王ロジャーコーマン監督生んだB級映画作品まとめ
「B級映画の帝王」の訃報が先日届いた。
ロジャーコーマンとは
1950年代から低予算を強いられる環境で100本以上の映画を製作、プロデュースし、その果てについた称号は映画界の帝王だった。
当時は映画製作における環境も全く整っておらず労働組合もなかったために、若い俳優や監督を目指すスタッフらは手当もない状況でコーマンはそこを利用して起用しまくったらしい。
それが低予算制作の成功と後年称えられる多数の著名人の「発掘」という言葉に繋がっている。
現代だとやりがい搾取とかいう言葉で批判されるのだろうが、芸術分野に携わる人間としては特に金より舞台経験の数に価値を置く。
記事中にあるスタローンやロバートデニーロの俳優を初め、現代では一線級の監督など数多に発掘した名が挙がる。
作品も見てみると低予算ながらどれも「質」が良く感じられるのもよっぽどオファーする若者の目利きと金儲けのセンスが良かったのは伝わる。
当然金にはケチだったらしいが、「ギャラが安い」と若い俳優に言われれば「3倍払うからもう2本映画に出てくれ」と言うことで、値段は同じでも俳優としては3本分の仕事をそこで決めさせることで交渉も上手く立ち回っていたようだ。
著作の話などを調べてるとプロデューサーとしてもそうしたやり口が上手いのが伺える。
作品は「デスレース」が代表作として挙げられるが若い世代の映画フリークではリメイク作に目を通しているのがギリギリだろう。こんな記事を書いている私も元祖は見ていなかった。
失礼ながら訃報をきっかけに帝王と呼ばれる彼の作品群が気になってしまい、アマプラで観れる限り振り返ることができたので私と同じようにこれから観るであろう若い映画マニアたちに向けてちょっとした一助になるようまとめたいと思う。
蜂女の恐怖(1959)

あらすじ
大手化粧品会社の年寄りの女性社長は、スズメバチローヤルゼリーから作られた若返り美容液で自分を対象に実験するが、その処方により、夜には恐ろしいスズメバチの怪物に変身してしまう。
はちみつ店を経営するおじいさんが、スズメバチローヤルゼリーを利用して若返りを図れる新たな新製品を実験していたところ、
売り上げが下がり続ける化粧品会社の女社長が食いつき自らが実験体になったことで徐々に蜂女になってしまうホラー作。
話はオーソドックスだが蜂女が何度も見どころを作ってくれるので飽きもなく見やすかった。蜂女になった社長の姿は子供がみたらトラウマになるデザイン。

作中何度も登場するので個人的にトラウマになった初代仮面ライダーの「蜘蛛男」を思い出すぐらい当時の独特の生々しさがどうにも彷彿させる。
実際にその後の仮面ライダーのエピソードでも「蜂女」は登場しておりこの作品がモデルになってる説もある。

蜘蛛男の画像は大人になっても自分の記事に乗せたくないので気になる人は各自ググってほしい。個人的にはそっちの方がやはり似ていると思う。
リトルショップオブホラー(1960)

あらすじ
風変わりな青年がある植物を育てるとそれは肉食性であり、話すことが出来るのであった。そしてその植物は食べるために彼に殺しを要求する。
とある花屋のバイト青年が店主から失った信頼を得るために外から持ち帰った植物が実は珍種であり、
客寄せパンダとして育てたら人間の血を養分にする植物になって育ってしまう。
コーマン作品ではデスレースの次に有名な作品にあたる。リメイク作もあり、調べると日本でも舞台リメイクがよくされていて馴染みやすい展開なのは分かる。
花屋の欲深い店主や、鈍感な女性客たちと店の娘、サディストな近所の歯科医、病気マニアの老婆や親戚を毎日無くす婦人など植物を囲う人間たちも個性強く描かれている。
低予算を活かした設定場所の少なさとカメラワークの固定、個性の強い人間たちの群像劇見ると、この辺はそのまま舞台リメイクしやすい作品だったのも見て取れる。
植物によって退場させられる人間は、不幸にもその管理も任された失敗続きのバイト青年に関わってしまう人達なのだが、自分の欲に罪意識がない人間だけが退場させられていくのは面白い。
肉食植物によって街はどんどんクリーンになってしまって終わっていく。
店の娘が全く危なげなかったのは欲も罪もなく、バイト青年とトラブルを起こす人間でも唯一なかった。
逸話として2日で撮り終えたという話も残っており、低予算で快作を生み出した伝説としてカルト的人気も誇っている。
ちなみに歯医者のシーンでのマゾヒストだった患者役はおそらくまだ無名時代のジャックニコルソンであった。

怪奇 アッシャー家の惨劇

あらすじ
フィリップは婚約者のマデリンを訪ねて、ニューイングランドにある彼女の実家であるアッシャー家にやってきた。しかし、マデリンの兄ロデリックは不気味な男で、さらにマデリンも痩せて青ざめていた。
古典小説でもあるアッシャー家の原作を扱った作品になる。
アッシャー家の崩壊
1839年に発表されたエドガー・アラン・ポーの短編小説。旧友アッシャーが姉妹と二人で住む屋敷に招かれた語り手が、そこに滞在するうちに体験する様々な怪奇な出来事を描く、ゴシック風の幻想小説である。
正直こちらは駄作気味だった。低予算であることを前提に観ると余計な現象や登場人物は現さず、被害妄想の会話だけで怖さを見せていく演出の工夫はらしさが出ている。
ただ会話の半分以上は「我々の家族はもう破滅する」「いやそんなこと言わずあなたの妹を僕にください」の平行線で全く核心に迫らない被害妄想同士の同じ会話を繰り返すので後半から飽きてしまう。
途中から某芸人チャンネルによる「天気の話しかしないローマの休日」のドッキリ動画を思い出してしまい終盤まではそういう楽しみ方になってしまった。
今見るとあんまり映画向きな作品では無かったと思うが、当時としては画期的な見せ方でオチもオカルトチックなショッキングな作品になっていたのかもとは感じる。
金星怪獣の衝撃 新・原始惑星への旅

あらすじ
初めて金星を訪れた調査団体がそこで古代生物、人喰い植物、そして超能力をもった美しい女性人種を発見する。
タイトルから怪しいが、ロシアのSFを勝手に改編しアメリカ向けに作ったのがこれになる。
そうした国外作品の勝手な改編をもコーマンは行っており、現代のようにネットでバレるはずのない当時は輸入する前にこちらでパクってしまえという意図は間違いなくあったのだろう。
ちなみに風の谷のナウシカも同じような改編で製作し宮崎氏に怒られた逸話も残っていて流石である。映画が余程好きだったのも伝わるし金儲けに敏感だったのも同時に分かるのも愛くるしい帝王。
本作は自分の名義も変えてしまいピーター・ボグダノヴィッチという弟子の名前で作品を出している。
元ネタは「火を噴く惑星」という映画で宇宙開発に命を懸けて冒険をする宇宙飛行士の主人公が描かれていたようだが、本作はその主人公は金星を荒らす「モンスター」として扱われていく。
金星では新種の美女やロボットが生息しており彼らモンスターを排除するために神に祈り自然の力で攻撃していく。
60年代の作品だったことも加味すると宇宙飛行士はソ連で、荒らされる金星の美女はアメリカといったところを嫌味ぽく風刺して描いたのだろう。アメリカとソ連の冷戦下の状況がここで伺える。
そういう見方ぐらいでしか観てられない作品なのでSFとしてはそれなりにきつい。
一般には薦めないがコーマンマニアになるなら味わうべき珍味だろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
