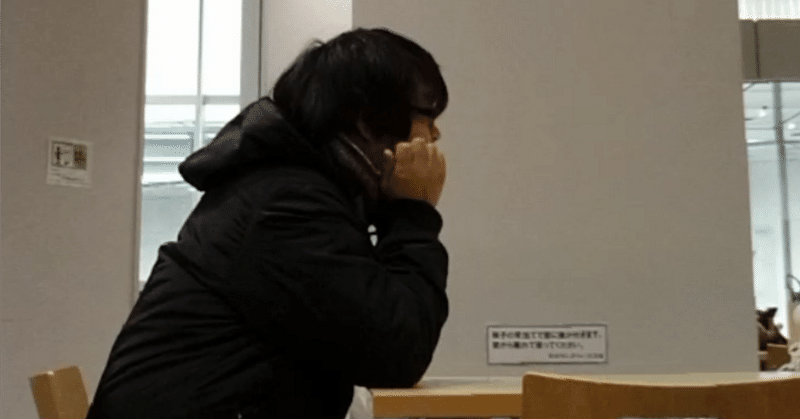
障害者の心得
自分は病気じゃない!
【健常者】だ!
その意識を改革する事こそが障害者として生き抜く生命線。
二度と戻れない障害者への憧れ。
あなたは捨てられますか。
障害者の発症リスクを軽減する可能性のマニュアル研究を進めている鹿月魅八です。
私は精神疾患当事者。【統合失調症】を抱え、現在、福祉就労を利用中の作家志望の男です。
ここで発症するまでの期間の簡単な経歴を紹介します。
高校生活卒業と同時に就職。
☆トラック運送正社員入社→ファーストフード店員→コンビニ店員→【発症】
私は23歳の秋に統合失調症という診断を受けました。 現在47歳。
入院した病院で私は1年間リハビリテーション生活を送りました。服薬についての勉強の時間を設けられてはいたものの学びに身が入らない。それもそのはず私の精神は正常だ!という意識の中での服薬指導。
自覚症状の無さから、その後の人生に【再発】という二文字がつきまとう事になるわけです。
障害者がなぜ、精神異常者【変質者】のような偏見を持たれてしまうのか。それは【脳】に異常をきたす病気だからです。正常な機能を失ったために起こる【幻覚や幻聴】
この症状が現れる段階でしっかり治療を受ける環境が整っていなければ症状は慢性化につながってしまいます。脳の乱れから精神【心】の乱れとなり言動に錯乱が現れる。この行動を外の世界で行ってしまう事を防ぐ為の閉鎖的環境に身を置く【閉鎖病棟】という病室での治療から始まるのが、いわゆる【精神病患者】というものなのです。
私が研究を進めているのは【再発予防】についての健康法。習慣について。
私は障害者として生きる中で二度の再発を経験し人生に空白【ブランク】が生まれ就労能力の低下につながりました。資本主義国のこの日本で生きる為には仕事に就く為の能力を身に付けないといけないと考えるのが常識的思考です。しかし、再発を繰り返すと、その【働く意識】さえも麻痺してしまいます。そこで再発予防について学び、それが今後の障害者福祉や医療業界に活用出来る障害発症リスクの軽減につながる生活習慣【音楽遊学論健康法】の研究を進めようと決めたのでした。
皆様、障害者と聞いてどんな事を想像しますか?
単に能力の低くなる病気を持つ人を障害者と決めつける風習がありますが、ただ、それだけではありません。服薬を継続する事での副作用から身体機能に何らかの影響が現れる。その為に楽しめるはずだった人生が若くして楽しめなくなる。そういう人生を生きる事になることも障害者になることのデメリットなのです。
ここで私の統合失調症を抱えて生きる者としての発症に至った生活の症例から個人的見解を記したいと思います。
【過労と人間関係のストレス】
これが原因として起きた私の障害の発症。発症には様々な要因が関係すると言われる中で【ストレス】をうまく解消出来ないことと、悩み、心配事から逃れたいという恐怖心を生活の中に抱えてしまうことが発症リスクを高める事につながると私は考えます。
服薬用として処方される薬剤の中に【頓服薬】というものがあります。
①不安になった時に内服するもの。
②落ち着きがなくなった時に内服するもの。
③眠れない時に内服するもの。
このような頓服薬が存在する理由はやはり【ストレスの軽減】が目的です。
【不安時】【不穏時】【不眠時】この頓服薬をうまく活用出来るかどうかは本人の感覚が大事になります。それは【症状が悪化してきた。と自ら察知する能力】いわゆる、【自覚症状】です。
この感覚が備わると症状の改善は加速を見せます。
ここで統合失調症の中で厄介な存在の症状のひとつ【陰性症状】について触れたい思います。
再発予防に欠かせない精神の安定。リラックス効果が重要なのですが主治医の許可を得て退院になり新生活への期待を持った生活の中での【壁】的存在。それが陰性症状です。
これは当事者、誰もが経験するものかというとそうではないように思います。
個人的に感覚のズレはありますが、伝えるべきは発症後体調が良く、前向きに人生に向き合っていても病気への自覚症状の無さから再発を繰り返す。そこで如実に現れるようになるのが陰性症状という意欲をコントロールする精神力が欠如する障害なのです。
これは体現時期がほぼ決まっているものと思われます。私の場合は二度の再発の後の治療生活から解放された、退院後の生活で6ヶ月経過した辺りから症状を感じるようになりました。冒頭で触れた通り、私は福祉就労を利用しているのですが、この陰性症状が現れるようになり福祉ネットワークの環境が必要になる理由はこれだ。と感じました。
障害を抱えて働いている人もいる世の中です。保障に頼らず生計を立てられる人もいるでしょう。私も以前はその【働き者】の部類に入る障害者でした。
しかしながら、陰性症状というものが症状として現れるようになってからモチベーションのコントロールの難しさに悩まされ、行動に移す力が衰えてしまったように感じます。それ故に福祉就労の定義【一般就労が難しい者が働く場所の提供】
この意味合いに納得してしまいます。
音楽遊学論健康法の習慣化
私がこの活動を意識するようになったのは寛解へ向かっている現状での習慣を分析し始めたことから、今、自然と習慣化し、日常的に出来ていることを自己啓発論として発信したい。
その活動繰り返す事で障害者福祉に何らかの影響を生み出したい。そう考えたところからの始まりでした。
それをマニュアル化したいという考えからの行動です。
陰性症状を乗り越え少しずつ手にしている行動力の向上への手応えが私の原動力となっているのかもしれません。
音楽遊学論健康法マニュアル
障害者生活を送る中で何度も経験した人生の後悔は【再発】という病気への知識不足から来るものでした。
ここで私の健康法マニュアル10のポイントを紹介します。
自己啓発論として参考にして頂きたい。
①服薬を守る
処方された薬は基本的に内服します。体調の変化からくる使用の変更は主治医、又は薬剤師さんのアドバイスを受けましょう。
頓服薬を効果的に内服する事で体調安定を維持しやすくなります。風邪薬感覚での御守り的内服をオススメします!
②睡眠を安定させる。
睡眠を安定させる=脳を休めるという休息の時間が体調安定には欠かせません。
精神疾患は睡眠障害を抱える事が多くあります。
生活リズムを整え6時間は休みましょう。
③自覚症状を持つ。
自宅静養を送る段階で自分の症状について自己分析しましょう。「将来の夢を考えると不安になる。」etc.といった症状の癖を把握出来るようになることが治療効果を倍増させます。自覚症状を身に付ける習慣としてに自己分析を習慣化しましょう!
④環境を作る。
再発予防。また発症リスクを軽減する生活環境を整えましょう。ストレスフリー(ノンストレス生活)を送る事を意識しましょう。ストレスは障害者にとって有害の元です。
⑤バランスの取れた食事療法。
自炊生活ではない方はヘルパーさんの生活援助を検討し調理をお願いしましょう。1日1食でも栄養の取れた食事を取る事で健康的になります。多少経済的余裕がある方はバランスの取れた「幕の内弁当」を時々摂取する機会を持ちましょう。
⑥軽い運動療法の継続。
朝散歩の習慣を持つ方は少ないかもしれません。通勤や通所時に徒歩習慣を取り入れる事で運動不足解消につながります。長生き効果もある運動習慣を今から身に付けませんか。
⑦音楽療法を取り入れる。
リラクゼーション効果のある音楽活動のある生活は認知症予防にも好影響というデータがあります。特に弾き語り等がオススメです。「生きがい」としての楽しみを持つ心を意識しましょう。お気に入りの音楽を入眠時に流すと不眠症の改善につながるそうですよ。
⑧リラックス効果を取り入れる。
「ホッとする瞬間」を感じながら毎日の生活を送る事で心の安定を生みます。癒し効果を取り入れましょう。
⑨やりたい仕事を選ぶ。
やりたいことを仕事にすることを考えるようにしましょう。これから社会復帰を考えたいという目標を持つ前に自分の「才能」を見つめる時間は大事です。努力を仕事にすることより【夢中になれること】を仕事として選びましょう。
⑩人間関係の整理
気心の知れた人間関係に包まれると環境が安定してきます。ネガティブ要素の持つ存在は断捨離。必要と思えるものだけ側に置く事で自然と必要な人間関係が集まって来ますよ。
まとめ
人間にとっての二大機能である【脳と心】その2つの機能の関係性のバランスが取りづらくなるというのが【統合失調症】という病気です。
福祉就労を活用し思考力は高められるでしょう。あとは行動力です。
自分の身に付けてきた能力を【再発】という形で失う事のないように生きられたらどんなに有意義な人生でしょうか。
障害を発症したとしても頼れる術がある。その参考材料として、この【音楽遊学論健康法マニュアル】を役立ててもらいたいものです。
では、皆様の健康生活を応援しております。
【自己啓発論・音楽遊学論☆鹿月魅八】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
