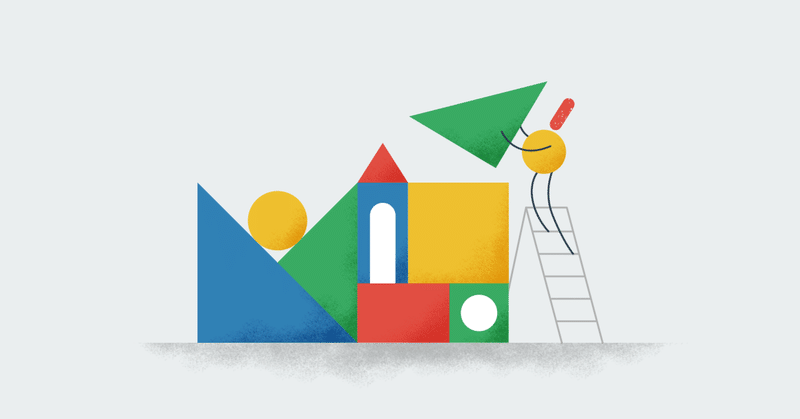
留学中に英語で話せないときは、「仮説思考」を巡らす。
海外留学のあるあるで「講義中にうまく発言できない」「グループワークで話せない」があります。
英語力が足りない、間(ま)を取らずに話し続ける文化に馴染めない、プレゼン重視で慣れない…。特に日本的なカルチャーで長年過ごしてきた人にとってはいろいろな理由が思い当たり、落ち込むことも少なくありません。
自分自身も控えめな性格柄、わりと苦労してました。もちろん上述した一連のこともあります。ただ何年か過ごすうちに「もっと根幹的な要因があるのでは」的に意識し始め、それから次第に変わっていったように感じます。(国内外に限らず!)
「仮説」がないと、質問/発言ができない
ずばり「仮説思考」があるかどうか。
日本語でも英語でも共通しますが、その講義で何を得たいと思っているのか? 自分なりにどこまで知識・意見がある状態か?に無自覚だと、「空白」になります。

特に準備していない・教授が与えてくれるものが全てだ、的な認識に陥った状態で講義に参列すると、そもそも自分のほうから相手(または周囲の学生たち)に投げかけるもの(=質問や発言に値するもの)が、何もない状態です。

では「仮説」はどう生まれるか? 講義の内容に関して、シラバスなどを参考にしつつ、下記を振り返ってみるあたりじゃないかと思います。
(例)
・すでに私がそのトピックについて知っていることは何か
→ (身近な事例とかニュースで聞いたこととか)
・なぜこのコースを取ろうとそもそも思っているのか
→ (何を期待しているのか/楽しみにしているのか)
・このコースを経た結果として、どんな着地点を思い描いているのか
→ (自分の目標に沿った内容を提示してくれるか)
もちろんこれから講義を受けるわけなので、「100%」の見識があるわけではありません。ですが、20~30%でも軽く頭にあると(=自分なりの仮説)、相手が講義を進めている最中で「ズレ」を感じることがあります。

自身がざっくりと抱いてる、ぼやけた解像度(20~30%)を、講義を担当する人の提示した考え方・見識(50~80%)と照らし合わせることで、細密にしていく。
その空いた「ズレ」こそが、質問・発言の契機となります。最初から何も準備しておらず、予習・考えが備わってなければ、この「ズレ」は当然発生しないため、議論やグループワークにつけ入る隙がなくなります。
予習用に文献を読ませる課題も出てきますが、まさに「ズレ」を発生させるためのもの。ある意味当たり前ですが、自主的に「私なりの仮説とは」を整理し再認識しておくと、多少ともブレない軸が生まれ、得られるリターンも増えるのかなと思います。
「ズレ」の大きさが、学びになる
この数値のズレが、そのまま学びの効果にも。

講義を担当する人のクオリティも、まちまちです。たまにあるのは、ゲスト・レクチャーで招待された人の話が、カリキュラム全体の文脈を把握できていないポジションがために、本筋から大きくズレた話をしてしまうことなど。(10~30%)
かと思えば、限られた時間内で手際よくプレゼンし、内容の関連度も高い上に、透き通った話で、充足した納得感を与えてくれる人もいます。(80~95%)

ここに仮説思考力(=どれだけ深い好奇心がある状態か・トピックへの基礎的な見識があるか等)を当ててみると。両者の乗算によって、得られる大きさが上下します。

逆に仮説思考がないと、どれだけ教員の力があっても、乗算させる対象がそもそもないので、どう転がっても得られるものがなくなります(優れた教え手は、学ぶ側の仮説思考をも引き出す力がありますが、ひとまず置いておきます)。
仮説思考を養うには
では、そんな仮説思考はどう作ればいいのでしょうか。結構、身近なところにあると思います。
普段からいろんな本を読んでいる
ニュースで気になることを個人的に調べている
おもしろそうな企業や人、特有の現象を追っている
ちょっと「意識高い!」的な例ですが、もっと日常的なことで全然良いと思います。友だちや家族との雑談、SNSやNoteでフォローして入ってくる情報でも。
さらに言うと、「今の自分と異なること・もの・ひと」にとにかく触れ続けること。異国の旅で新しい天候や地形を目の当たりにしたり、国籍・人種や社会的階層が違う人と話し合ったり。日頃からそうしてる中で、自分とは違う存在に「?」を抱くきっかけ(=仮説らしいもの)が自然と生まれてきます。
個人的な一事例を出すと、カトリック教圏の国々(イタリア・ベルギー)に留学した結果、なぜ日本では「労働」の価値観がめちゃくちゃ優先されているのだろう?と。夏休みやイースターがめっちゃ長かったり、公的なインフラ(滞在許可証の発布とか)が8ヶ月も遅れたり。今まで認識してたライフ・バリューがまったく普遍的ではないことを体感し、ますます疑問を生じさせました。

明確な「これ」という答えはないわけですが、いろんな仮説を想像しては、様々な人に問いかけるのが趣味と化してます。「歴史的にも自然災害が多い国だから、中途半端なものを作ってしまう=大勢の人の命に関わることが、世代を超えた理念として暗黙的に共有されてるからでは」とか、「島国で移民(=対立し得る価値観を秘めた集団)が少なくて同質性が高いがために、性善説に則った人助け=ハードワークさに美学を見出せつづけるのでは」とか。
明確な裏付けのない、妄想めいた話でもありますが、もしその分野でプロフェッショナルな専門家と遭遇する機会があれば、真っ先にその仮説をぶつける=質問するのではと思います。
「自分の未知」を自覚するのが、仮説思考
大事なのは、「自分がまだ何を理解していないのか」を自覚することです。質問する人というのは、すでに分かっている人ではなく、まだ分かっていない人がするからです。
基礎的な知識で、ネットで調べたらすぐに出てくるようなことであれば、人にぶつける前に自分で何とかできますが、「深いレベルの問い(=教科書に書かれてる以上のようなこと)」だと、誰かの知恵を借りる必要が出てきます。
まさに、そのために「講義」がありますね。普段から自分の仮説力を磨き続けてきた結果、「まだこれがわかってない(と思うこと)」を聞くことができます。
だからこそ、日頃から引き出しを様々なところから持ってくることがキーに。先述したように異なる体験をする中で、いろいろ想像が膨らみ、今まで感受の対象でなかったものに目(脳)が反応し、仮説を抱くきっかけめいたものが発生します。



上は有名なユクスキュルの環世界 (=同じ世界に生きていても、違う生物同士で全く異なる認識をしている)ですが、人間の間にも好きな趣味が違えば、考え方・価値観の種類は千差万別です。
ただ、そのまだ見れていない色こそが、自分の「未知(=仮説の源)」となるわけで。どれだけ意識的に「知らないこと」を認知し、問いかけることができるか。世界を見る眼に、多彩な色合いを塗り足していくのは、まさしくそんな仮説思考を実践する過程にあると言えます。講義で悩んだ際は、この根幹に立ち返ってみてはいかがでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
