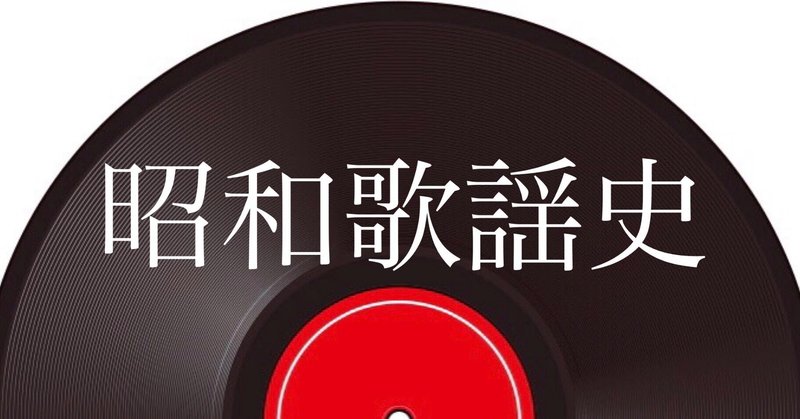
昭和歌謡史概説① 通史・前編
近年、若年層を中心に昭和歌謡が再びブームとなっているようです。この概説は、そんな昭和歌謡初心者や、歌謡曲の沼にはまってみたい者、興味はあるが難しそうだと感じている者などを対象にした入門編です。インターネット上では、なかなか手軽に読める歌謡史・流行歌史というものがありません。そこで、これさえ読めば基本はおさえられる!という保存版を目指して書きました。ぜひこれを機に、昭和歌謡の世界に魅了されてみてください。
まず第1編と第2編では、通史として、年代を追うかたちで歌謡史を見ていきましょう。
※注)文章中に登場する人物名は特に表記のない限り歌手名です。
1. 明治・大正期のはやり唄
昭和歌謡史を深く理解するためには、明治・大正期のはやり唄についてもある程度知識を蓄えておく必要があります。ここでは昭和への導入として、おさえておくべき事柄を簡単に確認しておきましょう。
1868年、時代は明治になります。西洋の文化が数多く取り入れられ、文明開化が起きました。
明治期では、昭和でいう流行歌のことを、「はやり唄」と言いました。そのはやり唄の歴史のはじめに登場するのが「書生節」と呼ばれる唄です。
書生節は、書生(現在の大学生的存在にあたる)が社会批判を詞に込めて作ったもので、1880年代に街頭で歌われるようになりました。次第に書生節は自由民権運動と強い結びつきをみせるようになり、弾圧を逃れるために演説を歌にしたものが登場します。川上音次郎の「オッペケペー節」などが有名ですが、これらの歌は「演説歌」と呼ばれるようになり、後の「演歌」の起源となりました(ただしこの時代の「演歌」は、現代における一般的な「演歌」のイメージとは異なる)。
1894年の日清戦争から1904年の日露戦争の頃には、書生節の流行は去り、軍歌が巷で歌われるようになります。この時期に作られた、「軍艦行進曲」や「戦友」といった歌の数々は第二次世界大戦の時代においても歌われたほど、長期的流行となりました。
自由民権運動の落ち着きにより書生節が衰退した一方で、大正時代には、政治批判のような社会的風刺の意味を込めた歌ではない歌を広めようと、添田唖蝉坊をはじめとした「演歌師」と呼ばれる人々が登場します。
当初はバイオリンやアコーディオンを持ち街頭で歌っていた演歌師ですが、昭和、特に第二次世界大戦後になるとギターを持って歌うように変化していきます。そして彼らは俗に「流し」と呼ばれるようになりました。
大正時代は、1914年に発表された「カチューシャの唄」やその翌年の「ゴンドラの唄」をはじめとして、唱歌や抒情歌が量産される時代となります。作家では、北原白秋や西条八十(ともに作詞)、中山晋平(作曲)といった人たちが数々の名曲を残しました。
一方、東京という街が帝都として認識されるようになると、街の様子を描写した歌も流行しました。典型例は「東京節(パイノパイノパイ)」(1918)でしょう。この歌は当時の東京がどのような街であったかを細かく表しており、歴史的資料としても価値があるのではないでしょうか。
大正末期の1923年には、「船頭小唄」が大流行します。この年の9月に起こった関東大震災で世の中が暗い雰囲気になった一方で、この唄や翌年の「籠の鳥」は、そのヒットをきっかけとして映画化され、小唄映画という映画ジャンルを開拓し、のちの映画主題歌の礎となりました。
そしてその3年後、いよいよ昭和時代が始まります。
2. 昭和初期〜終戦まで
1926年、昭和時代が始まります。
西洋文化の影響でモガ・モボが街を歩いていた昭和初期、音楽面でも西洋の影響を大きく受けます。それについては「日本の洋楽史」の方で解説するとして、ここでは日本独自の音楽について述べていきます。
大正から昭和初期にかけて、唱歌や新民謡(各地の役所や企業によって作られた、ご当地ソングの先駆け的存在)と呼ばれる歌曲が数多く作られました。これらのジャンルでは西條八十や中山晋平といった作家たちが活躍したと前に書きましたが、次第に彼らは流行歌の分野にも進出していきます。
昭和歌謡史におけるヒット第一号とも称すべき佐藤千夜子の歌った「東京行進曲」(1929)が、前述した西条・中山コンビの代表的作品でしょう。この曲がヒットした背景には、蓄音機やレコード盤の普及のほか、1ヶ月後に公開された同名映画の主題歌としてこの歌が用いられた(映画主題歌第一号とされている)こともあるようです。また、銀座の柳並木が復活したのもこの歌のヒットによると言われています。
1930年代半ばになると、新時代の歌手や作家らの台頭が見られ始めます。歌手では藤山一郎(「影を慕いて」「東京ラプソディ」)や東海林太郎(「赤城の子守唄」「旅笠道中」)、作家では作曲家の古賀政男(「酒は涙か溜息か」「人生の並木路」)や古関裕而(「船頭可愛や」「大阪タイガースの歌」)などです。彼らの残した作品の数々は、戦後も日本のスタンダード・ナンバーとして非常に多くの歌手たちに歌われています。
また、今では俳優が歌手活動も並行して行うということはよくあることですが、その第一号は松竹下加茂三羽烏のひとりである時代劇スター、高田浩吉だと言われています。小唄で鍛えた彼は、1935年、「大江戸出世小唄」でレコードデビューし、その歌だけでなく同名の映画もヒットさせました。
しかし1937年に日中戦争が勃発すると、歌謡界も大きく変化していくことになります。歌も含め、すべてが戦時体制に変わっていきました。
「国民歌謡」というラジオ番組を例にとってみましょう。 1936年に放送が始まったこの番組は、新曲を1週間にわたって放送するという、国民の音楽文化向上を目的としたものでした。
しかし、放送開始から約1年後、盧溝橋事件が起こった頃から、戦時色が強く表れてきます。真珠湾攻撃を機に太平洋戦争へと突入してからは、番組名が「われらのうた」、また「国民合唱」と変わるとともに、戦意高揚のための歌ばかりが放送されるようになっていきました。音楽文化までもが完全に国の政策の一部になってしまったのです。
この番組で放送された戦時歌謡を一曲取り上げておきましょう。戦局が悪化する一方にあった1944年、いよいよ学生が動員されるという際に作られた歌があります。「あゝ紅の血は燃ゆる(学徒動員の歌)」という歌です。まさに戦争一色という当時の状況が読み取れるかと思います。
一方で、戦時中にもかかわらずヒットした軍歌調ではない歌も存在します。例えば、1943年に発表された小畑実・藤原亮子共唱の「勘太郎月夜唄」が有名です。戦前から親しまれてきたいわゆる「股旅もの」のこの歌は、戦時下では珍しい軍歌以外での大ヒットとなりました。
また、いわゆる「シンガーソングライター」なるものが登場したのもこの時代であるとされています。その人物は林伊佐緒といい、戦前から作曲活動をしてきた人です。彼は兵隊を戦地に送り出すための歌が公募された際に一般人として作曲した作品でこれに応募し、当選。「出征兵士を送る歌」として彼自身とその他歌手の共唱により発売されたこの歌は大ヒットし、彼の名を一躍世に広めました。
3. 戦後復興期
1945年、日本は連合国に敗れます。街に漂う暗い空気を明るくさせていったのは、歌でした。
45年の暮れ、戦後日本初の映画「そよかぜ」が公開されると、その主題歌であった霧島昇・並木路子共唱の「リンゴの唄」が戦後初の大ヒットとなります。
それからというもの、敗戦下の暗い雰囲気を明るくするようなモダンな歌が続々と登場、ヒットしていきました。代表的なものとしては、敵性音楽が解禁されたため洋楽の要素を取り入れたもの(ブギウギなど)が有名ですが、これについては「日本の洋楽史」の方で解説しています。
日本オリジナルの戦後を代表する歌には、49年の「青い山脈」があります。新時代の幕開けを表現したようなこの歌は、藤山一郎と奈良光枝の共唱によって発表され、3か月後に公開された同名の映画とともに大ヒットしました。その後も多数の歌手によってカバーされ、昭和を代表する1曲となりました。
しかし一方で、シベリアに抑留されるなどして、終戦後もしばらくは日本へ戻れない人たちもいました。このような抑留された人々が生み出した曲もあります。竹山逸郎・中村耕造「異国の丘」や渡辺はま子・宇都宮清「あゝモンテンルパの夜は更けて」などです。これらは日本へ戻って来ることができた人々によって内地にもたらされ、50年代前半にかけてヒットしました。
また逆に、戦地から戻って来ない人を待つ人の心情が歌われた曲もあります。菊池章子の「岸壁の母」が代表的です。
他にも、この頃から外国への憧れが日本の歌にも表れるようになります。岡晴夫「憧れのハワイ航路」や灰田勝彦「水色のスーツケース」などは大ヒットしました。
そして、上記の岡晴夫のほか、「かえり船」の田端義夫と「山小屋の灯」の近江俊朗を含む3人は、40年代後半〜50年代前半にかけて多数のヒット曲を発売し、「戦後三羽烏」と称されるようになりました。
また、49年は、後の時代の活躍によって昭和の歌姫とも評される美空ひばりが「河童ブギウギ」でレコードデビューを果たした年です(当時11歳)。彼女は、この数年後にデビューする江利チエミ・雪村いづみとともに「三人娘」と呼ばれ、スターダムを駆け上がっていきました。
ちなみに、NHKの紅白歌合戦が始まったのはちょうどこの頃、1951年でした。初期の数年間はラジオ放送のみで、映像はありませんでした。
そしていよいよ、昭和歌謡の黄金時代へと突入していきます。
※第2編へつづく…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
