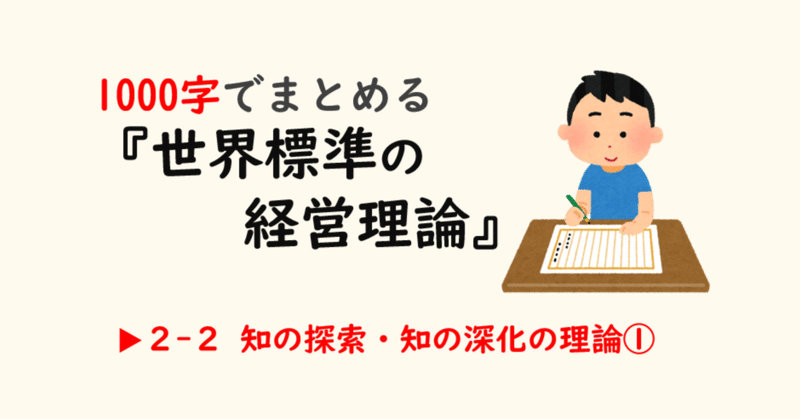
1000字でまとめる『世界標準の経営理論』~ 2-2 知の探索・知の深化の理論① (第2部 第12章) ~
2019年12月に早稲田大学の入山教授が出版した『世界標準の経営理論』。出版早々に購入するも、面白そうな章だけつまみ食いした以降は、3年ほど本棚の肥やしとなっていた。しかし、2022年10月にマネジメントへの一歩へを踏み出す中で【経営】への関心が再び高まり、この機会に丁寧に読み直すことにした。
本noteは自身の咀嚼を主な目的として、各章の概要を各noteで "1000字程度" で整理すると共に、読む中で感じたことを記録する備忘録である。なお、今の自分にとって目に留まった章から順番に触れていく。
(導入説明 300字、各章概要 1000字、振り返り 500~1000字 構成である📣)
1.本文概要:知の探索・知の深化の理論①
✄『世界標準の経営理論』該当ページ:P223~P234 ✄
ーーー
経営学では「イノベーション」は広義の「組織学習」であり、「何かを経験することで学習し、新しい知を得て、それを成果として反映させる」という意味では本質は変わらない。学習の結果、新しく得られた知の成果が極めて革新的なら「イノベーション」と呼ばれるだけのことである。
ーーー
経営学では「組織学習」を「一連の循環プロセス」として捉える。この循環プロセスは【組織・人・ツール】【経験】【知】という3つの要素で構成されると共に、この3要素つなぐ "3つのサブプロセス" で表現される。
■サブプロセス①『サーチ』( 組織・人・ツール ➡ 経験 )
"限定された合理性" を前提とする【組織・人】においては、何らかの意図を持って行動(サーチ)し、行動した結果として【経験】を得る。
■サブプロセス②『知の獲得』( 経験 ➡ 知 )
得た【経験】を通じて、新たな【知】を獲得する。獲得の仕方には大きく3つのルートがある。
[1] 知の創造:経験で得た知と既存知を組み合わせて、新しい知を生み出す
[2] 知の移転:自ら知を生み出すのではなく、外部から知を手に入れる
[3] 代理経験:組織自身の経験ではなく、他者の経験の観察により学ぶ
■サブプロセス③『記憶』 ( 知 ➡ 組織・人・ツール )
新しく生み出された【知】は、何らかの形で組織に記憶されなければならない。記憶されなければ学習したことにはならず前進はない。このプロセスは大きくに2つに分解される。
[1] 知の保存 :その名の通り組織に知を保存されること
[2] 知の引き出し:必要に応じて記憶された知を引き出すこと
ーーー
人や組織には認知に限界があるため、本当はこの世の自社にとって有用な選択肢があったとしても、その大部分を認識できない。そのため、『サーチ』を通じて「認知の範囲の外に出ること」が必要である。
この『サーチ』は「知の探索」と「知の深化」に分類され、「知の探索」は「組織の現在の知の基盤(と技術)からの逸脱」であり、「知の深化」は「組織にすでに存在している知の基盤に基づいた取り組み」である。この両立が『両利きの経営』と呼ばれる。
新しい知とは常に『既存の知』と別の『既存の知』の『新しい組み合わせ』で生まれる。ただし、人の認知には限界があるため、人・組織はどうしても本質的に「いま認知できている目の前の知同士だけを組み合わせる」傾向があったり、「見通しの確実性が高いものを選ぶ」傾向がある。
結果として「知の深化」に傾斜する。「知の深化」は既存知の活用であるために見通しの確実性が高くコストも小さいため、意思決定者から見れば、知の探索をおろそかにして「知の深化」した方が短期的には合理的でもある。
~メモ( ..)φ:「Organization Science」p71 by March,J (1991) ~
知の探索は「サーチ」「変化」「リスク・テイキング」「実験」「遊び」「柔軟性」「発見」「イノベーション」といった言葉で捉えられるものを内包する。知の深化は「精錬」「選択」「生産」「効率」「選択」「導入」「実行」といった言葉で捉えられるものを内包する。
2.本章に対する振り返り
「イノベーションとは広義の組織学習である」という観点が印象的であった。一層の事業成長を目指す中ではイノベーションの必要性がうたわれるが、"何か特殊なことをしなければならない印象" が独り歩きしている様に感じる。「イノベーションも組織学習であり "程度" に違いがあるだけ」 という認識を持つだけで、身近なものとして手繰り寄せられる様に思う。
ーーー
この循環プロセスにおいては、サブプロセス③『記憶』が蔑ろにされがちな実態があると感じる。と言うもの、実際の仕事の場面ではサブプロセス②『経験』までで一旦完結する場合が多い。その時点でも、担当者には『記憶』されているがあくまで属人的な状態である。ここで担当者をひと呼吸だけ踏み止まらせ、組織に『記憶』させる対応を促せるか?がやはり重要であると考える。
ーーー
全体を通して、自身における日々の判断が「知の探索」に位置するものか?「知の深化」に位置するものか?について、都度振り返る姿勢を持ちたいと考える次第であった。現場寄りの仕事を担っている関係上、そもそも「知の深化」側に偏りやすい傾向にはあるが、その中でも「知の探索」側への振り幅がある判断の場面では意識的にそちら側に振っても良いのかもしれない。
【参考資料】
ここまでお読み頂きましてありがとうございました!💐
この記事は「自分のための学び」を公開している形ですが、一読頂いた方にとって、何かお役に立つ部分があったなら甚幸です!
「知恵はかい出さんとあかん、井戸から水を汲み上げる様に」を大事にしながら、日々のマネジメントに対する振り返りをツイートしています👇
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
