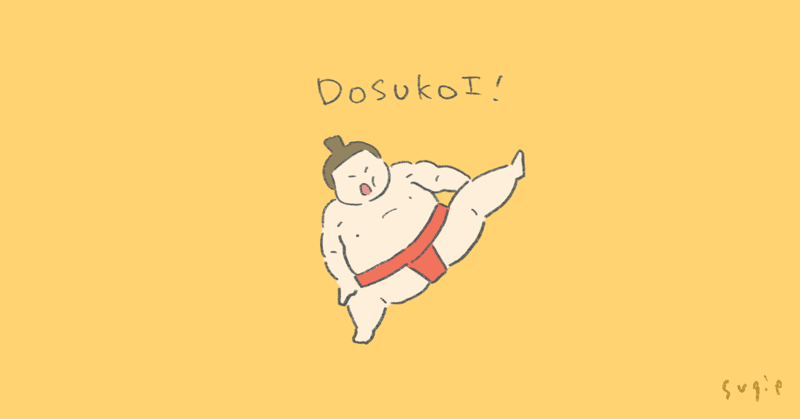
【日記】アイディア出しは『転地効果』を使うべし
脱コロナの動きがかなり強まった2023年が終わろうとしている。最近は2024年、さらにその先数年を見越した事業開発や事業計画の議論の場にいる機会が増えてきていて、ああまた非連続成長への挑戦がやってくるのね、なんてワクワクしたり。
まぁぼくはアイディア出し担当だったりするんだけど。
この手の議論はだいたい型がきまっていて、まずは数回のよもやま、ブレストの機会をつくって課題や一次情報を洗い出すことからはじまる。アンケートやデータも使って広く材料集めをするのである。そして、向き合うべき課題の優先順位をつけていく。
実はこの課題設定のプロセスはけっこう大事。ずれた問いに対して時間や労力をかけるとどこにもたどりつかないままムダに時間と労力を消費してしまうからだ。それに気づいたときの『やっちまった感』はキツイ。
さらに組織運営の種類の中でもコミュニティ運営は属人性が高いだけにモチベーションの起伏がそのままコミュニティの活性・不活性にまで影響する。関わるひとが身も心も健全だからこそひとは集まってくる。そんなものだよね。
さてさて、今日はそんなアイディア出しの話なんだけど、議論するときに意識しているポイントがある。それは『転地効果』を使うことだ。
転地効果…場所を変えることによって脳が活性化する効果
企画を考えたことがあるひとならばピンとくるかもしれない。同じ机の上でずっと考えていてもなかなかアイディアがわいてこなくて苦労した経験はないだろうか。
これは、なれた環境が脳の活性化の妨げになるという現象に関係している。慣れた環境は身の危険もないし、ストレスもないので脳が楽をして省エネモードに入るというのである。逆に、見知らぬ土地に身を置くと周りの状況を把握しようと脳が活性化する。
アイディア出しは脳が活性化する環境に身を置き、動き出すのを利用して行うのがいいよ。というわけである。
ちなみに、ぼくが師匠とあがめている元リクルートの先輩『くらたまなぶ』さんによると、リクルートの新規事業は転地効果を使いまくって生まれてきたらしい。
ボロボロの会議室や、ときにはラブホテルのピンクな照明の中で脳が活性化してゼクシイやタウンワークが生まれてきた。ぼくもちょっと前に事業開発の合宿に参加したけど、夜23時ころ頭が疲れたタイミングででっかいゴキブリが登場して大騒ぎになりブレストもはかどった。
ゴキブリは極端だけど、ちょっと色々おこりそうな場所でアイディア出しをしてみるのはどうだろうか。
それでは今日はこの辺で!
頂いたサポートは、次に記事を書く時のアイス代にしたいと思います!
