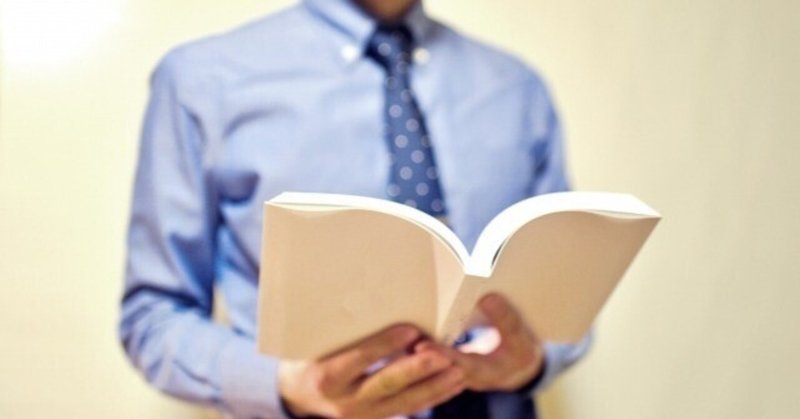
読書会主催者 読書会を学ぶ
川口市出身の自称読書家 川口竜也です!
平日は仕事終わりに図書館に行きnoteを書くか読書ばかりしている。職場と駅の途中に図書館があるため、ほぼ毎日通っている。
久方ぶりに「本を読む本」系の書籍でも読もうと思い、たまたま同じ棚にあったのが山本多津也さんの「読書会入門」幻冬舎 (2019)。著者は日本最大規模の読書会コミュニティ「猫町倶楽部」の主宰者様である(しかもフリガナがタツヤで共感を覚える)。
うまく行く人はうまく行っている人や成功している人の真似をするのが定石だと、初心に帰って入門から読み始めた次第。
内容は、山本さんが読書会をはじめたきっかけや、猫町倶楽部さんを運営していく中で意識していることが記されている。
合議制にしない、ヒエラルキーを作らない、参加者を囲い込みしない、考えの違う人を排斥しないなど、今後規模を大きくしていく上で、意識すべきことが多々ございました。
中でも「読書会の主宰者が尊敬される必要はない」が特に興味を引いた。
私自身、読書会というコンテンツ(商材)が同じならば、最後は「人が集まる人になりたい」と考えている手前、また川口さんに会いたいと思うような読書会にしたいと考えてます。
けれどもそれは、尊敬が欲しいからという理由ではあまりない(ないことはない)。
そもそも私よりも本を読んでいる人や、知識や経験を積んだ主催者が数多くいるのに対して、私のようなただの自称読書家が尊敬されようなど烏滸がましい。
山本さんの言葉を借りれば、読書会の主宰者は、楽しいからやっている、飲み会の幹事のようなものである。幹事は重宝がられるが、尊敬はされない。なるほど!と思いました。
合コンの幹事を思い浮かべたらわかると思いますが、日程や人数調整、お店のセッティングに当日場を回すなど、とにかくその場が盛り上がるように楽しませているものです(ちなみに私は合コンに一度も行ったことがない)。
そう思うと、私の読書会の方向性は少なくとも間違っていないのだなと思った次第です。
もうひとつ、第四章の「読書は遊べる」も考えさせられました。
山本さん自身も、最初はビジネス書や自己啓発本の勉強会としてはじめた読書会でしたが、徐々に「読書のハードルを下げたい」と思い始めたそうです。
読書はやはり、硬派で一人で楽しむものだというイメージが強い。俺活字がダメなんだよなと書店すら足をあまり運ばない人もいる。だが、よくよく考えると、読書を神聖なもののイメージを与えたのは、私のような一人(寂しそうに)本を読む人を見てきたかもしれない。
本を読む人=ひとりぼっち の印象を与えたのは、私の責任かもしれない。だからこそ、その誤解は我々が解かねばならないのだと思う。
だからこれからも、私は読書会を続ける。まだ読書会自体行ったことがない方は、是非読書の楽しみを味わってみてほしい。それではまた次回!
今日もお読みいただきありがとうございました。いただいたサポートは、東京読書倶楽部の運営費に使わせていただきます。
