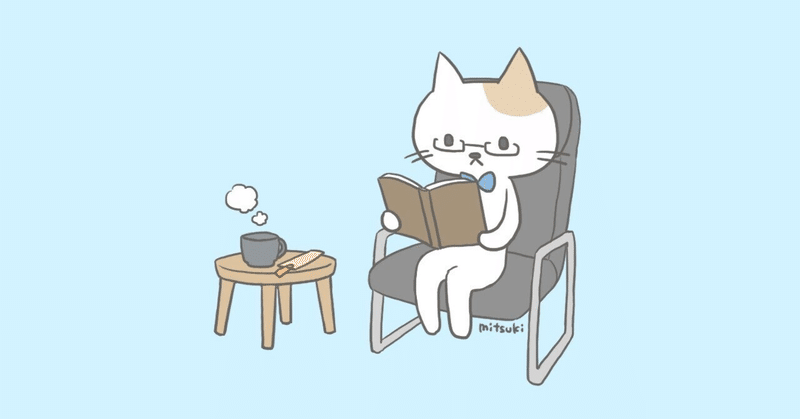
『スラヴォイ・ジジェク』/本・現代思想
内容(「BOOK」データベースより)
哲学、精神分析、映画などのポップカルチャーを結合して文化理論を練りあげるジジェクは、政治的想像力における幻想の役割を暴き出す。リベラル資本主義の幻想を突き抜けて、象徴秩序の変革を透視するジジェク思想への明快な体系的案内。
いつも「記事のタイトルどうしよっかな……」と思いつつ、作品名(プラス"感想”)だけ入れてたんだけど、タイトルだけでは本なのか映画なのかドラマなのかゲームなのかわからなくて不親切な気がするので、ちょっと手を入れてみるよ。媒体とふんわりしたジャンルを入れておこう。
(この記事、だいぶ前の『空色勾玉』の記事より先に書き始めてたのでいまさら上記の説明が入ってます)
結構長くなりそうなので、一章ずつ取りあげてその都度アップ、続きを追記しながら書いていこうかなあ……とか思ったけど、一章ずつさらっていくと、どうしても要約的になるし、それだと自分としてはwebにあげる意味があんまりないからやめました。というかそもそも、webにあげる意味を考え始めてはイケマセン。
なぜジジェク?(個人的な)
『人はなぜ物語を求めるのか』の感想記事でも書いたけど、同じような思惑なのでコピペしちゃう。
まあまあな年齢になってきて、ふと思ったんです。どうせ時間が足りないのなら、この先本を読んでいくにあたって、おおまかにでも何かテーマがあったほうがいいんじゃないかなと。
で、自分はたぶん「物語」に惹かれてるんじゃないか。その周辺も含めて読んでいったら人生楽しくなりそうじゃないか。
って感じで手に取った本。
もうちょっというと、たぶん精神分析、それも特にラカンのものは、言い方アレだけど作品分析に便利っぽいイメージがあって。なんなら便利すぎるかもしれないくらい。でもいいじゃん、RPGの序盤で強めの武器を振り回せるみたいな感じでさあ(謎の言い訳)。
で、ラカンってのは難解さで有名で、それをうまいことサブカルチャーと絡めて語るってのがジジェクのイメージ。求めるテーマで使う強めの武器としては、少しは初心者が振り回しやすくなるはずで、その入門書としてこの本を読みました。
ついでに、(たぶん)ポスト・ポスト構造主義の現在にジジェクを読むのもどうなのか、ってのはあるけど、ジジェクさんまだまだ現役っぽいし。それに、読みたい本のあたりがちょうど自分の学生時代の頃なので、少しは読みやすい可能性があるかなあって。
以上前置き。
久しぶりに思想書、たぶんやわらかめの本だけど……を読んで、いやあ、我が身の知性のなさを痛感する。1日1章ずつ読んだけど、だいぶ読み返した。むずい。わからん。
ジジェクの発想源と三界と主体について
この記事の大きな流れを考えずになんとなく書き始めたので、いろいろごちゃごちゃだ! ほら、冒頭で一章ずつまとめるとかなんとか、一回その方向で書き始めちゃったその名残でね、ええ、分かれてたものが混ざったり、混ざってたものが分かれたりしてね! いい、もうこのまま行く!(怠慢)
・哲学:ヘーゲル。ただしヘーゲルの弁証法とちがい、ジジェクのそれは総合されずに「矛盾はあらゆる同一性の内的な条件である」とする。
先ほどの例を使うと、「あらゆる映画はよいものだ」がテーゼであり、「『タイタニック』はじつは
相当ひどい映画だ」がアンチテーゼだとすると、ジジェクの総合は「『タイタニック』がじつは相当ひどい映画であるからこそ、あらゆる映画はよいものだ」になるだろう。もちろんこれは一見意味をなさないし、矛盾している。しかしこの断定の真理は、この矛盾のなかにこそ潜んでいるのだ。悪い映画がなかったとすれば、比べるものがないのだから、どんな映画がよい映画かわからない。したがって、よい映画が存在するためには、少なくともひとつの悪い映画がなくてはならず、この場合『タイタニック』が、文字通り規則を証明する例外なのである。
この辺りは次章の主体の定義についてもかかわる。ジジェクの得意技っぽい。
・マルクス:政治学。のちにイデオロギー定義について出てくる。
・ラカン:精神分析。有名な〈想像界〉、〈象徴界〉、〈現実界〉について整理される。
ここがもっとも興味のあるところで、かつ、もっともわかりにくくて難儀する。物語論と重ねて見れば、物語は〈象徴界〉そのものに思えるし、〈現実界〉は物語られる前のもの、解釈できないものみたいに思える。
コラムのトラウマのところがわかりやすいし面白い。狼に食べられることを恐れている神経症患者について。
狼男が最初に両親の性交を見たときには、それは彼にとってほとんど意味をもっていなかった。それは〈現実界〉の一部であり、〈象徴化〉に抵抗したのだ。しかし三年後、彼は簡単な性の理論、とくに去勢の理論を身につけ、それによって両親がしていたことを解釈できるようになった。この時──〈象徴化〉の時点──で、この場面はトラウマ的になり、彼は狼を恐れるようになったのだ。ここで重要なのは、できごとないし〈現実界〉そのものは変わっていないことである。できごとの意味を変えているのは、〈象徴界〉のほうなのだ。(中略)できごとそれ自体が変わっていなくとも、その理解されかた、意味の与えられかた、〈象徴化〉されかたは変化する。(中略)〈現実界〉はただ執拗に存続し、ただその解釈しかたが、〈象徴界〉とともに変化するのである。
いまいちわからないのが、〈想像界〉と〈象徴界〉の関係。〈想像界〉の説明で鏡像段階のあたりの話はわかるのだけど……
広い意味でとれば、〈想像界〉とは、休むことなき自己の追求、自己は統一されているという物語を支えるために、次から次へとおのれに似た複製を取りこみ、融合しつづける動きのことだ。こうして〈想像界〉には、ラカンもジジェクも冷淡な侮蔑を投げつける。われわれにとっては不幸な話だが、ラカンは、現代は人類の〈想像的〉絶頂をしめしている、という判決をくだしている。ひとびとが自分自身に、そして自分自身を見ることにとり憑かれた時代であり、人間の創造したものが世界中を覆っているからだ。
このあたりが第二章の主体論と併せるとどうもうまく飲み込めない。以下の部分。
われわれは〈象徴界〉の諸要素を個人的なやり方で束ねる能力を維持しているが、それをおこなうのが、ジジェクが「自己」と名づけるもの、すなわち「物語の重力の中心」(CATV:261)と定義するものなのだ。言いかえると、〈自己〉は主体という空無を埋めるものであり、主体はけっして変化しないのだが、自己は絶え間ない修正に向けて開かれているのである。
あとついでに「主体とはなにか」の要約文も引用しておく。
ほとんどの現代思想家と異なり、ジジェクは、デカルトのコギトが主体の基盤であると主張する。しかしながら、たいがいの思想家が、コギトを実体のある、透明で、自身の運命を完璧に統御できる完全に自意識的な「わたし」であると解釈するのに対し、ジジェクは、コギトはある空っぽの空間、つまり世界の他の部分が自分自身から排出されたとき残るものであると提唱している。〈象徴秩序〉は、世界の直接性が喪失したあとその代わりになるものであり、主体化の過程によって、主体という空無が埋められる場なのである。主体化の過程は、主体が自己同一性を与えられると同時に、自己同一性が〈自己〉によって書きかえられる場でもあるのだ。
うーん……
〈想像的〉──自己を見つめる、統一
〈象徴的〉──外の物語を取り入れる、絶え間ない修正
みたいなことかなあ……?
とか考えたんだけど、あとで読んだ本でこんなふうに書かれてた。
ただ、これが一つの見方に過ぎないってことだけは、念を押しとくね。想像界・象徴界・現実界という区分は、常に位相的な区分でしかないんだから。位相的っていう意味は、互いの位置関係が常に相対的に決まるっていうこと。すごく雑ばくな捉え方だけど、一種の座標軸みたいなイメージかな。x、y、zの三つの軸があるとして、x軸だけ取り出したい、と言われても、それは無理な話。同じように、この三界区分も人間の認識における座標軸の一種と、さしあたりは考えてくれて構わないと思う。というのも、どんな認識においても、そこには言うなれば「認識のモード」として、この三界区分が存在するからだ。
なんていうか、あんまりこれが〈想像界〉でこれが〈象徴界〉で……みたいにカッチリと考えてもしょうがないというか、あくまで都度都度の認識のモードとして考えることと、〈現実界〉を切り離してもダメってことかしらね。
ポストモダンについて
・大学に入るまで、ろくに人文学のことを知らなかった。そのせいか(?)、ポストモダンといえばリオタール、リオタールといえばポストモダンみたいな、大学で孵化した雛の刷り込みがあったんだけど、フレドリック・ジェイムソンも大きいのね。名前も初めて知ったけど。第三章のコラムで面白いところがあったので引用しておく。
ジェイムソンにとって(じつは、このモデルにゆるやかに依拠するジジェクにとっても)ポストモダニズムは、後期資本主義の文化理論であり、後期資本主義が推し進めた、商品による植民地化に対する文化的応答なのである。ジェイムソンがあきらかにした
ポストモダニズムのおもな特徴をいくつかあげるなら、以前は分離していた文化的ジャンルの統合〈高級芸術と低俗芸術の混合や、西部劇とSF映画の融合のような別個の様式の組み合わせ)、歴史感覚の喪失(ノスタルジアの希求において一目瞭然)、そして表層や浅薄さへのうっとりとした愛着(言語に対するイメージの優越に見出される)などがある。
ジャンルの話として面白いというか興味深いよね。
・ジジェクはポストモダンを大〈他者〉の崩壊といってて(まあこれはだいたい、いわゆる「大きな物語」みたいなもの……ともちょっと違うのか)、それによって、われわれはもはや自然や伝統に服従していない、選択の主体となり、もっといって、あらゆる集団的な行動様式と関係を断ったとして、新しい問題に対処を迫られていると主張している。
そうした問題のひとつとして、服従への愛着が増していることがあげられる。ジジェクによれば、われわれは、もはや大〈他者〉の〈法〉に従属していないとき、「私法」や主従関係に頼ることで、公的権威の喪失を埋め合わせしがちである。
このへんは、なんていうか「個人的な肌感として」としか言えないけど、すげえわかる気がする。「敷かれたレールの上を走らされるのはイヤだ」から、「歩いていく道標がほしい」みたいな変化というか……。
生きかたの問題としてもそうだけど、ゲーム(特にオープンワールドなんか)でもそんなとこない? めっちゃ雑語りで怖いけど、とりあえず言ってみる。
ある程度マシンパワーが使えるようになってからのオープンワールド(GTA3くらいを想定)から、しばらく自由、自由なゲームが作られたけど、遊びづらさや話の盛り上がりのために、わりとストーリー主導のオープンワールドが増えた感じがあるのよね。ただまあ、マインクラフトはいつも人気でそのうえちゃんと遊んでないから、これについてはなんも言えないんだけど。あとゼルダが舵をふった(らしい。やってないので!)発想の自由さもまた、別路線であるからなあ……。
まあ、このへんはその……これからも考えながら……(お茶を濁してから飲み込む)
あと、この辺も面白かったな。
もし、小さな大〈他者〉の構築が、「大〈他者〉」が崩壊したことへのひとつの反応だとすると、ジジェクが見出すもうひとつの反応は、大〈他者〉は実は〈現実界〉に存在する、という考えである。ラカン派精神分析は、この〈現実界〉における〈他者〉に、〈他者の他者〉という名をつけた。〈他者の他者〉を信じること、つまり社会を操る糸をほんとうに操作し、あらゆるものごとをまとめあげている誰か、なにかが存在するという確信は、パラノイアの徴候のひとつである。広い影響を与えたジェイムソンのポストモダニティ分析にならって、今日支配的な病理はパラノイアである、と論じるの
は、いまやお決まりである。最近では、どんな映画もペーパーバックのスリラーも、なんらかの秘密結社への言及なしには完結しない。たいがいその秘密結社は、政府、新聞、市場その他をひそかに支配する、軍事-産業複合体である。このパラノイアは、大〈他者〉の崩壊に対する反応として生じたとジジェクはいう。
フィクションが好きなので、このへんはとても興味深い。「いまやお決まり」だったのか……まったく知らなかったぜ。
この本の原著は2003年だけど……いまはどうかな。たしかにそういう時期があった、といえるほど作品群を知らないのでなんだけど、ちょっと覚えておきたい。
イデオロギーの定義
・第四章のイデオロギーについて、この辺が面白かった。
マルクスの定義:「彼らはそれを知らない。しかし彼らはそれをやっている」
これなら現実認識がいかに歪んでいるかを指摘すればよい。しかし、われわれが経験しているのは歪んだ現実でしかないことは、いまや誰もがすでに知っている。ので以下のように変わる。
スローターダイクの定義:「彼らは自分たちのしていることをよく知っている。それでも、彼らはそれをやっている」
シニカルな主体はこうだと、新バージョンで定義される。しかも公式の文化は、そのような冷笑主義をすでに考慮に入れているとする。
ここでジジェクはマルクスの定義に戻り、「知っている」から「やっている」に重点を移し替える。
わたしは、男女は平等であると十二分に知りながら、知らないかのごとくふるまっている。同様に、ナチズムを真に受けていない自分では思っていても、ニュルンベルク決起集会に参加してヒトラーに敬礼すれば、行動によって、本気であることが示される。(中略)われわれはいまだイデオロギー社会
に生きており、シニシズムによって、自分たちはものごとを真剣に受けとめてはいないと考えるように自分たちをごまかしているだけで、ところがわれわれの行動を見れば、じつは真剣なのだと如実にわかる。イデオロギー的幻想は、われわれが考えることよりむしろ、われわれがとる行動という現実のなかに存在する。このようにジジェクは、スローターダイクの定式──「彼らは自分たちがしていることをよく知っている。だが彼らはそれをやっている」──を書き換えて、われわれの行動にイデオロギーが書き込まれているという点を考慮にいれることができる。「彼らは自分たちがその行動において従っているのが、幻想であることをよく知っている。それでも彼らは幻想に従う」。われわれはいわば、理論上ではなく、実践におけるイデオローグなのである。
というわけでジジェクの定義:「彼らは自分たちがその行動において従っているのが、幻想であることをよく知っている。それでも彼らは幻想に従う」
これは面白いよね。なんなら第三章のポストモダンにおけるフィクションに出てくる秘密結社も同様だったりしないか──「そのような秘密結社は幻想であると知っているが、それでもそのような作品群を愛する」みたいな?──とも読めるけど……どうかしら……?
男と女のあいだの関係とはなにか?
・ラカンから引いてきている「女は存在しない」、「女は男の症候である」、「性的関係は存在しない」については、説明はわかりやすいが振り回すのに危険度の高い道具だよね! って感想。ほかの章と比べてもわかりやすい気がするので、なんかちょっと騙くらかされてるのでは……と不安にすらなる。
でもこれ、相当振り回せるやつだよね……うっかり語っちゃいそうなやつだよね……(ゴクリ)
幻想と欲望について
・欲望とは、そもそも他者の欲望だというのは、少しでも精神分析を聞きかじると振り回したくなるアレだけど、もうちょい踏み込んだというか、別バージョンの面白い話があった。
精神分析における幻想と欲望についてその1としてまず以下。
注意すべき最初の点として、欲望それ自体は、満たされたることもかなけられることもけっしてない。(中略)ジジェクによれば、(中略)「われわれは、すでに「モノ自体」であるものを、「モノ自体」の延期を取り違える。つまり、欲望につきものの探求や迷いであるとわれわれが思い込んでいるものは、じつはすでに欲望の実現なのである」(LA: [『斜めから見る』二六])ということだ。言いかえれば、幻想において実現される欲望は、満足を先延ばしし、欲望を永続化することによってのみ、「満足する」。欲望は、十分に実現するという意味で満足してしまうと、その瞬間に消え去るのだ。
このあたりは『マイ・アントニーア』のジムとアントニーアとリーナの関係に刺さる気がしている。
んで幻想と欲望その2。フロイトの娘がいちごのケーキを食べる夢を見た事例から。
主体は〈他者〉の欲望の深淵、つまり〈他者〉はわたしになにを欲しているのか、に直面する。この欲望を「満たし」、深淵を隠蔽するために、主体は幻想で反応する。こうして、その幻想が他者の欲望を実現する。わたしは他者がなにを欲しているか確信していないが、彼らはわたしにいちごのケーキを食べてほしそうに見える。だからわたしは彼らの欲望を満たすために、いちごのケーキを食べるのだ。
これまた面白く振り回せそうなやつだな……。ううむ。楽しい。
訳者あとがきから
おそらく本書でいちばん役に立つのは、ジジェクがなにを言っていないかをはっきり述べていることだろう。ジジェクはなにしろ多作なので、読者は、「ここではいまひとつ納得できないが、どこか未読の本でもっと自分の立場を鮮明に語っているのでは」という思いに駆られがちだ。そんな読者にとって、本書は、「いや、そんなことはどこでもやっていない」とサポートしてくれるのである。
そ、そうなのか! 思わず笑ってしまったが、素晴らしくありがてえ! この指摘がめちゃくちゃ役に立ちますよ!!!
巻末読者案内から
・もともと『斜めから見る』は、求めているテーマ的に読むつもりだったけど、最初の英語の単著『イデオロギーの崇高な対象』を先に読んでおくといいよ、と書かれていたので、まずはこの2冊からとっかかってみようと思う。
の、前に、ラカンとフロイトを軽くでいいから押さえておかないと、やっぱ読むのがキツそうなのでなにか探してみよう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
