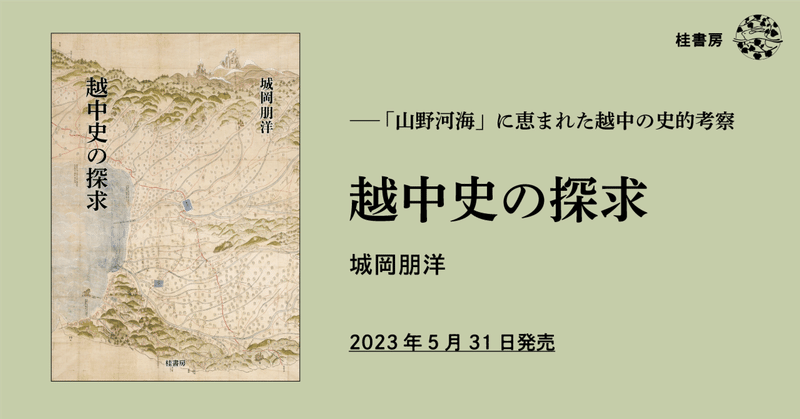
富山廃県の危機!幻の「28道府県」——「山野河海」越中の史的考察 『越中史の探求』城岡朋洋
明治時代に「府県廃置法律案」という法案が作成されていたことをご存じだろうか?
明治時代に、日本を「28道府県」に再編する計画が持ち上がりました。
富山廃県の危機に富山県民はどうしたのか?その行動と考え方を、新刊『越中史の探求』からお届けします。
明治36年(1903)に1道3府43県を1道3府24府県にしようという法案が、第一次桂太郎内閣で閣議決定され、帝国議会に上程されることとなった。
本書で取り上げる富山県(越中)は三度廃県の危機に直面している。
一度めは、明治四年(1871)の廃藩置県で設置された富山県が同年十一月の府県廃合で新川県になったときである。この最初の富山県は旧富山藩がそのまま富山県に移行した県であった。旧越中域内での併合なので、さほど大きな衝撃はなかったであろう。二度めは、明治九年四月の新川県の石川県への併合のときである。正式な県名では「富山県」ではなく「新川県」なので、厳密には富山廃県ではないが、明治五年九月以降の新川県は旧越中国全域を一つの県としている。越中人にとっては自分たちの県が無くなることを意味した。この衝撃がのちに分県運動として噴出する。そして三度めである。明治十六年五月にようやく石川県からの分県がなり、その記憶がまだ薄れていない段階で富山廃県が政府から提案されたのである。
「府県廃置法律案」は「交通機関発達ノ今日、府県区域ノ拡張ヲ計ル」などの理由から作成され、富山県は、岐阜県・福井県の一部とともに石川県と合併し、「金沢県」となる予定であった。

廃県の危機にさらされた各県では強い反対運動が展開され、富山県民も強い反対の声をあげている。
本書では、当時提出された建議書や、新聞にて報道された内容などから廃県の危機に際して当時の富山県民がとった行動と考え方を考察している。
富山県存置之儀ニ付建議
仄ニ聞ク。今回行政及財政整理ノ結果、府県廃合ヲ行ヒ、本県及福井県ヲ廃シテ石川県ニ合併セラレントスト。依テ熟々之ヲ惟フニ、本県ノ地タル地理上明ニ一ノ区画ヲナシ、人情風俗モ亦頗ル相異ルニモ関セス、明治九年ヨリ仝十六年ニ至ルマテ一時石川県ノ治下ニ立チシト雖、百般ノ差異ハ常ニ紛糾ヲ来ス因トナリ、柄鑿相容ルル能ハサリシヨリ、終ニ之ヲ割キテ、別ニ富山県ヲ置クノ已ムヲ得サルニ至リシナリ。爾来茲ニ二十年、本県ハ本県特殊ノ行政ニ依リ、従来石川県ニ比シテ大ニ遜色アリシ各種ノ施説モ亦僅ニ緒ニ就クヲ得タリ。殊ニ土木事業ニ至リテハ、北陸七大川中石川県ハ手取ノ一ヲ有スルニ過キサルニ、本県ハ庄神通常願寺黒部ノ四ヲ有スルヲ以テ仝一県治ノ下ニアリシニ当テハ、我河川ヲ説ケハ、彼ハ道路ヲ説キ、多数ノ圧伏スル所、本県ノ地ハ常ニ河伯ノ暴威ヲ逞ウスルニ委セサルヲ得サリシカ。分県以来一ニ力ヲ此事業ニ尽シ、多大ノ費用ヲ擲チテ河川ノ整理僅ニ今日アルヲ致シ、八十万県民稍々枕ヲ高クシテ寝ヌルヲ得ントスルニ至レルモ、尚大ニ力ヲ尽シ、完成ヲ図ラサルヘカラサル状態ニアリ。
(県債未償還・県税・歳出予算・事業費・土木費内訳・市町村土木補助・教育費・勧業それぞれの三県比較は省略)
是等、皆特殊ノ奨励保護ヲ待チテ、将来ノ発達を企図セサルヘカラサルモノニ属ス。然ルニ今一朝、二十年来ノ歴史ヲ滅却シ、人情風俗ノ差異ヲ顧ミス、財政及各種ノ施設如何ヲ問ハス、強ヒテ今日ニ此廃合ヲ敢テセラルルニ於テハ、啻ニ円満ヲ欠キ、紛擾を醸ス原因タルニ止マラス、又以テ地方民衆ノ福利ヲ増進スル所以ニアラスト信ス。依テ本会満場一致ノ決議ヲ以テ、府県制第四十四条ノ明文ニヨリ、本県ノ存置アランコトヲ建議ス
明治三十六年十二月九日
富山県会議長 大橋十右衛門
内務大臣伯爵 桂 太郎殿
『越中史の探求』本文より
12月8日に富山商業会議所が「府県廃合ニ関スル県議書」を、12月9日に富山県会が党派を超え満場一致で「富山県存置之儀ニ付建議」を決議、直ちに県会議長大橋十右衛門らが上京し、建議書を桂太郎内務大臣(首相兼任)に提出、陳情も行った。
「富山県存置之儀ニ付建議」の、「八十万県民」「満場一致」の語は、富山県民の総意であることを示している。
なお、12月に衆議院が解散となり、結局法案は提出されず、さらに翌年には日露戦争が勃発し、「府県廃置法律案」は幻で終わった。
今回取り上げた以外にも、本書では「山野河海」に恵まれた越中史を、「第Ⅰ部 古代の越中」「第Ⅱ部 立山と越中」「第Ⅲ部 富山近代化と越中」の三部構成とし、越中の始まりの時代である古代から富山県へと転換していく近代までを対象とする12本の論文を収録している。
「第Ⅰ部 古代の越中」
一 大伴家持と越中の自然風土 —雪と山野河海—
二 越中国の御贄
三 古代越中人の生業
四 征夷と越中国
「第Ⅱ部 立山と越中」
一 中世の飢饉と立山信仰
二 冷泉為広の〈タテ山ミユ〉
付論 守り伝えられた立山古文書
「第Ⅲ部 富山近代化と越中」
一 民権前夜の越中青年 ―新川県から提出された建白書―
二 富山廃県の危機
三 越中七大河川と鉄道架橋
四 「時の記念日」の誕生と工業立県
五 「越中史」の発見
富山県は立山連峰から富山湾と、高低差4,000mの変化に富んだ地形をしている。かつて越中と呼ばれていた時代から富山県は自然と関わり、生活を構築し、文化を蓄積してきた。史資料を読み解き、歴史を探求することで富山(越中)の進むべき未来が見えてくる。
(桂書房・編集部)
◉書誌情報
『越中史の探求』
城岡朋洋
2023年5月31日刊行|A5判・310 頁|ISBN978-4-86627-134-7
◉著者略歴
城岡朋洋(しろおかともひろ)
1960年、富山市に生まれる。
1987〜2021年富山県立高等学校教員、その間、富山県公文書館、富山県[立山博物館]に出向。2017年から富山県立大門高等学校長、2019年から富山県[立山博物館]館長を勤めた。
現在、富山近代史研究会会長、越中史壇会副会長、富山国際大学非常勤講師、射水市文化財審議会委員。
共著に『古代の都市と条里』(吉川弘文館、2015年)、『歴史と観光』(山川出版社、2014年)、『古代の越中』(高志書院、2009年)、『富山県の歴史散歩』(山川出版社、2008年)、『富山県土地改良史』(富山県土地改良史編さん委員会、2004年)、『情報と物流の日本史』(雄山閣出版、1998年)、『とやま近代化ものがたり』(北日本新聞社、1996年)。その他『福光町史』『続下村史』『大沢野町史』『豊田郷土史』など地域史・郷土史の編纂に関わる。ほか
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
