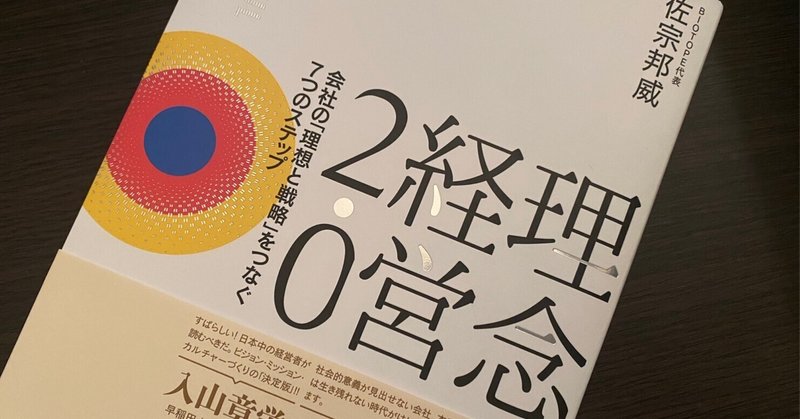
「人治」を「法治」に変えて。
昨年読んでいた本を通して、こんな言葉に出会いました。
「人治」が、「法治」に変わっていく。
この言葉に出会って、抱えていた自分の悩みが一つ解決した気がしていて。
思考整理のため、なにをどう考えたのか残してみようと思います。
1.ゼミ活動での悩み
私は学校でゼミ活動に取り組んでいた時、ゼミ長という立場についていました。主にゼミの中での議論をファシリテートすることがわたしの役割でした。あとは、一応リーダーという立場だったため、議論を踏まえて、
「この方向でいきましょう」という具合に、漠然とした決定権を持っていました。
ゼミ活動の内容は、ある分野の広報施策を考え、コンテストに応募するというものです。活動を通して議論を進めていく中で、ある日、事前に決めたスケジュールより議論が送れていることが分かったんです。
「事前に決めたスケジュールに間に合わせたいから、早く議論を進めてやるべきことをやっていきたい。でも、今まで通りのペースで議論していてはコンテストの応募締切に間に合わない。」私は焦りを感じていました。
そして、次第にメンバーとのコミュニケーションを省き、相談をせず私からチームの同級生に指示を出すだけの状態が続いてしまっていました。
結果としてなんとか軌道修正できていたものの、ゼミ活動がひと段落した後に先生からいただいたフィードバックは、
「少々進め方が強引だったんじゃないか」
「他のゼミ生と、丁寧に合意形成しながら進めることはできていなかった」
というものでした。あのとき、自分はどうすればよかったんだろうという悩みがずっと頭の中にありました。
2.「人治」と「法治」
そして、ある本を読んでいく中で、冒頭に取り上げた言葉に出会ったんです。呼んでいた本は、佐宗邦威著『理念経営2.0ー会社の「理想と戦略」をつなぐ7つのステップ』。会社経営におけるビジョン、バリュー、ミッション・パーパスとはなにか、またそれらの作り方から活用方法などが体系的に書かれているビジネス書です。
本書では、特に企業の「バリュー」について解説する章で、「人治」と「法治」という言葉を用いています。
「バリュー」の定義は、「組織を束ねる共通の価値基準」だとした上で、
その効果に、価値基準を明確にすることで、コミュニケーションコストを減らすと共に、一人一人が自律して動けるようになることを挙げています。
組織全体に共通する価値基準が定まることで、組織のメンバー1人1人が、
「うちのバリューから考えると、これはやめといたほうがいいな」
「私たちのバリューに沿っているから、投資すべきだ」
といった自律的な判断を行うことができるようになります。
逐一上司に判断を仰いだり、上司の方から指示を出す必要がなくなります。
組織の中で合意形成をするために、MTGを何度も開く必要もなくなります。リーダーの指示に従って組織が動く「人治」から、
組織の中に浸透した価値基準によって組織が動く「法治」へと変わります。
組織の価値観、つまりバリューを定めることで、自律的組織が性質上持ちやすい「人治」が、「法治」に変わっていく。
3.「人治」を「法治」に変えていたら。
ゼミという組織の中で、みんなで共有できる価値観が定まっていたら、
たとえ時間が無くてコミュニケーションが十分に取れなかったとしても、各自が自律的に動くことができたのではないか。
定期的なMTGの一つ一つを、もっと意義ある時間にできたのではないか。
と考えるようになりました。
私による人治を、皆で共有した価値観による法治に変えていれば、もっと個々の力を発揮して活動することができたのではないかと、自分の行動を省みるきっかけになったんです。
「人治を法治に変えていく」という言葉は、既に私の体にすごく馴染んでいます。今後どこかでチームの舵取りを任されることがあったら、必ず思い出したい言葉になりました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
