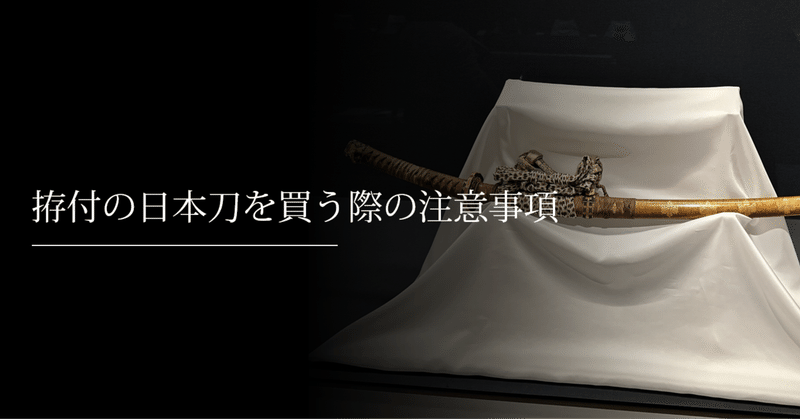
拵付の日本刀を買う際の注意事項
日本刀を初めて買う人の中には、刀身だけの物よりも拵が付いていた方が良いという人が多いそうです。
特に海外の方はその傾向が顕著なようで。
私が初めて刀を買った際は刀身のみだったのですが、あれから刀装具や拵なども趣味で買うようになってからというものの、やはり拵があって初めて日本刀として完成するなという気もします。
まぁ刀身は刀身、拵は拵で楽しめはするのですが、武士は白鞘の状態で持ちませんし、そういう意味での気持ちの問題です。
とはいえ実際は気に入った刀に拵が付いていない事も多いです。
刀身を先に買ってそれに合う拵を後から探す、という事も出来なくはないのですが「反りが合う」という語源となっているように、なかなか身幅や反り、長さの合う拵というのは見つからない。
反りや長さが合っていても目釘孔の位置がずれていたりなども。
更に言えば刀身と拵の「格」が合うかも大事になってきます。
例えば重要刀剣などに安物であるウレタン塗装の鞘は合いません。
細かく言えば目貫などの金具も刀身の格が上がればそれに合わせて上げなければ違和感が生じます。
目貫なんて小さいし見えないから…と思いがちですが、遠くから見た時にどこかバランスが悪かったり、色味が変だったりと違和感を生じます。
質の良い拵を見て「凄い」と感じるのは1つ1つの作業が全て丁寧に行われているからであって、そこに何か1つ適当な物が入っていると「浮く」のです。
反対に適当な物しか付いていない拵に、力作の金具などが付いているとこれまた浮きます。
そんな事もあり、実は刀身に合う拵を探すのはとても難しい事なのです。
古名刀などは大名家の太刀拵に合わせやすいとか、定尺の決まる新刀以降は合わせやすいとか、時代によって合わせやすいものは存在していると聞いた事はありますが…。
拵付の刀を見た時に格好いいな、美しいなと何となくでも感じたら、それをコーディネートした人の眼、知識が素晴らしいとも言い換えられるでしょう。

・拵付を買う際の注意点
さて話は少し変わるのですが、今日動画を見ていたら国宝の稲葉江を所有する柏原美術館館長である柏原さんが対談されている動画に辿り着きました。
(Youtube「殿×刀 最強の武器にして最高の芸術品!日本刀の真実」毛利家歴史チャンネル より)
刀を拵に入れる時は手放す時と「買う時」だけ
動画内でさりげなくこう仰っていましたが、ハッとさせられました。
数々の名刀、刀装具を手にされてきた柏原さん、「若い頃には失敗も沢山しましたよね?」という問いに対して「ひと財産使っていますよ」と笑顔で答えられていましたが、それを経ての言葉と思うと重みがあります。
例えば拵に徳川の家紋が入っているからといって刀身が徳川家伝来品とは限らないわけです。
拵にピッタリ刀身が合えば共に伝来した可能性もありますが、切羽と鐔に隙間が生じていたりなどピッタリとはまっていない場合はその伝来そのものが怪しくなります。
伝来を裏付ける何か別の資料があれば良いですが。
立派な刀身と拵私などは拵と共に売られていたら入る物と思って確かめずに買ってしまいがちですが、ちゃんと入る事を確認しないと後で痛い目を見る事もありそうですね。
拵付で残ってきた刀も勿論ありますが、刀身だけの物の方が多いです。
そうした中で売りやすくする為に見栄えの観点から合いそうな拵を見繕って付けている場合も多いです。
そうした事実を分かっていても目の前にしたものが立派に見えれば見えるほど、どうしても刀身や鞘を傷つけないように合わせたいという気持を抑えてしまいます。
ですがそのチェックはお店に一言伝えてさせて頂いた方が良いのかもしれません。
購入後は実際に拵に入れて使うわけではないので、必ずしもキッチリと合っていなければ…という事は私としては無いのですが、やはり伝来品などはそうもいきません。
刀身と拵がそのまま伝来していたのか、その事実関係だけは把握して所持しておきたい所です。

今回も読んで下さりありがとうございました!
面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです。
記事更新の励みになります。
それでは皆様良き刀ライフを!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
