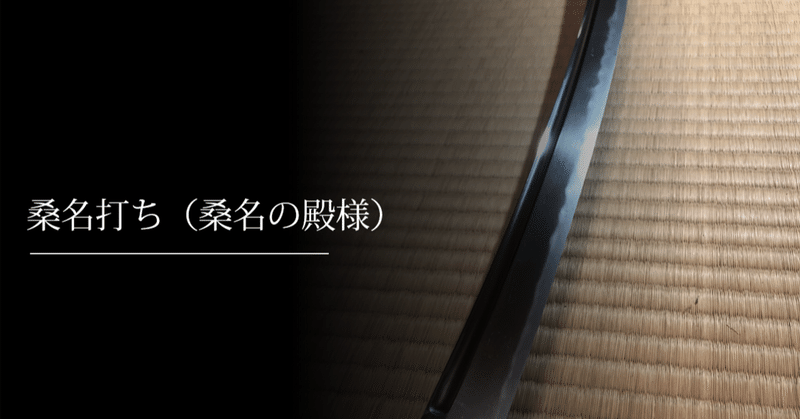
桑名打ち(桑名の殿様)
「桑名打ち」と聞いて何を連想しますか?
恥ずかしながら私がこの用語を知ったのはつい最近で、最初は伊勢国桑名(村正とかの)で打たれた刀の事をこう呼んでいると思っていました。
実際は幕末頃に桑名で打たれた室町期の備前刀の偽物の事を指すようです。
日本刀大百科事典には以下の様に書いてあります。
・桑名打ち
幕末に復古の波に乗り備前刀が愛好されたので、桑名において義明斎広房、千子正重、固山宗次らが、室町期の備前刀を狙って打った偽物。地鉄が弱く無地肌で、刃文の頭が崩れたり、堅く締まったりするが、良く似せているので、今日正真として通っているものがある。
(引用元:「日本刀大百科事典」より)
また「寒山刀剣教室 基礎編」では以下の様に書かれています。
桑名打ちというのは、幕末に備前刀専門の偽物が、勢州桑名あたりで盛んに作られたというのです。大体は応永備前にはじまり、末備前が多いのですが、よくできたものは、油断をすると引っ掛かります。
これをシャレて桑名の殿様などと申します。
銘の位置なども本物そっくりであり、書体も本物に負けないほど達者なものがあります。
地鉄も綺麗で、刃もあざやかで、本物よりもかえて立派に見えるものがあります。
(引用元:「寒山刀剣教室 基礎編」より)
以下は成瀬関次著『実戦刀譚』 - 偽刀談義 “幕末仕込み”と“桑名打ち”とタイトルのあるブログからですが、非常に詳しく桑名打ちについて書かれていたので引用させて頂きます。
“幕末仕込み”と“桑名打ち”
古い鞘に合わせて偽作した“身鞘物〔みざやもの〕”という手は、幕末あたりに流行した偽作の方法で、“幕末仕込み”の一要素であったという事であるが、こうした事は、“桑名打ち”という言葉と共に、刀剣社会で偽物を云為〔うんい〕する時の慣用語術語になっているそうである。
幕末には、今事変に於ける日本刀熱の勃興と同様に、刀剣熱が一時に湧きあがったけれども、やっぱり誰も彼も古い業物にばかり目をつけて、新しい物、特に当時の現代刀にはふり向きもしなかった。
そこで、当然の帰結として、刀匠連が古い刀の偽作に猛然とのり出したのであって当時の名匠前記水心子正秀をはじめ、その門下の細川正義などは、盛んに虎徹忠吉から、正宗、義弘と手当たり次第に偽刀を打ちまくり、その一派であるかぢ平こと細田平次郎直光のごときは、こうした偽作偽銘物の一手販売所長を兼ね、当時一流鍛冶の門下生で、腕達者な連中を総動員して盛んに偽物を市に出したもので、それが今日でいう“幕末仕込み物”なのである。
水心子正秀などは、常々数十名の門下生を養っていたから、相当生活が苦しかった事は、その当時の書簡にもあらはれているほどであるが、そのためか時々は古刀模作と称して上物を打ったらしく、時に妙な方面からばれて苦しい弁解をしている。彼の書簡に「あの長光は元来私の打ったものに、誰かが銘を切っておき、中心を古くしたもので、これもこの間喜代太殿にお目にかけた。
するとせがれが耳にして大いに立腹し、そんなものは取りのけるように懸け合ったが、私の作も色々の作になっていて、その中には正真の物となっているものもあり、またよく誤って正真といわれるものもあって閉口してる」。という意味の事を、上野和吉という人に宛てて書いている。
当時の巨匠直胤などでさえも、ちょいちょい古作を模造したらしく、ある時、薩州の侍が見学に来て、たまたま直胤の鍛えているのが、古刀の模造なのに不審を抱き、その旨をなじったところが、直胤は、新刀風に鍛えれば折れるから、古刀風に鍛えるのだと、苦しい弁解をした事も載っている。
勢州桑名は、名工村正代々の故地であり、東海道の要津で、海上七里の渡しの発着地であった関係上、大井川の川どめと共に、旅客の滞在が多く、
船待ちのため、二日三日と宿泊する者が少なくなかった。
ちょっと風雨でもあると、城下繁栄の経済政策からも、七日や八日はとめられた。
こうした事から、自然柳暗〔りゅうあん〕の巷と共に、偽刀製作なども発達し“桑名打ち”の名で高からしむるに至ったもので、今でもある鍛冶町通りには、偽物専門の刀匠の家がずらりと並んでいて、今日よく見る全国名物売店のように、各國各伝の偽物を大量につくって並べ、求める客の望むがままにこれを売った。
多くは末古刀〔すえことう〕(末期の古刀)から、初期新刀時代のもので、こうしたものの売れ行きが益々多くなるにつれて、ほど近い美濃の町々からも多量に製作して、そのレディーメードを持ち込んできたので“二分の大小、二朱の女郎”などとまでいいはやされるに至った。
事実、道中で召し抱えられた俄侍〔にわかざむらい〕が、桑名まで丸腰で来て、ここで侍の恰好となるのに、一両で足りたというような話も残っている。
かくのごとき偽物鍛冶の真っただ中に、ただ一人律儀な刀匠がいた。
それは三品藤右衛門廣道といって、この人は決して偽物は打たなかったので、泥中の蓮のように逆効果をあげ、かえって繁昌した。
その子は藤九郎廣道で、義専齋と称し、明治初年頃まで打ったが、廃刀令と共に農具鍛冶となり、今でもその子孫が栄えているけれども、偽物屋のあとは次第々々に絶えてしまった。
海上がしけて、十日も船の出ないような時には、西国大名の大身〔たいしん〕な家来などが入りびたって、監督しながらよく打たせたもので、腕のよい弟子がたくさんいたから、徹夜仕事の早づくりでも有名だったと、故山内長人男爵から直接承った話である。
(引用元:成瀬関次著『実戦刀譚』 - 偽刀談義 “幕末仕込み”と“桑名打ち”)
・終わりに
このように今日でも結構紛れている可能性がありそうなのが「桑名打ち」という事が分かりました。
特に末備前の刀など購入する際はこのような物があることを知っておくだけでも少し注意深くなれるかもしれませんね。
因みに桑名打ちをしていた1人、義明斎広房の刀が刀剣ワールドさんのHPにも載っていました。
もしかすると最近オープンした名古屋刀剣ワールドさんでも展示されていたりするのでしょうか。
もししているとしたら一度見てみたい所ではあります。

あさひ刀剣さんのHPにも1振掲載されており、解説も詳細で非常に参考になりましたので是非リンク先から一読される事おすすめします。

今回も読んで下さりありがとうございました!
面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです。
記事更新の励みになります。
それでは皆様良き刀ライフを!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
