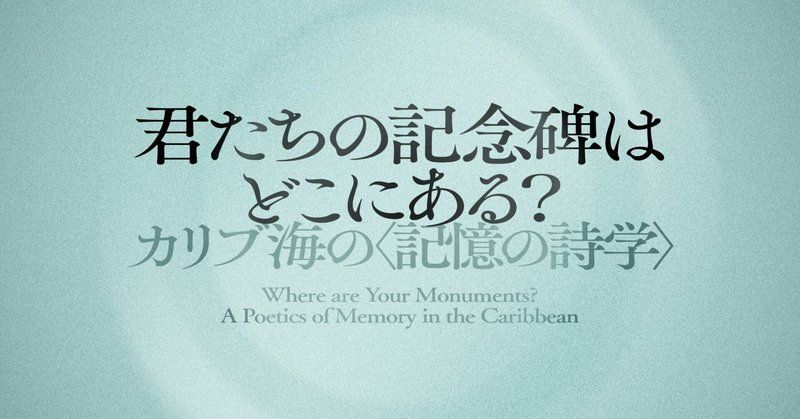
第2回 ホモ・ナランス 「遭遇」の記憶を物語ること|君たちの記念碑はどこにある?――カリブ海の〈記憶の詩学〉|中村達
【連載の概要】
西洋列強による植民地支配の結果、カリブ海の島々は英語圏、フランス語圏、スペイン語圏、オランダ語圏と複数の言語圏に分かれてしまった。そして植民地支配は、被支配者の人間存在を支える「時間」をも破壊した。すなわち、カリブ海の原住民を絶滅に追い込み、アフリカから人々を奴隷として拉致し、アジアからは人々を年季奉公労働者として引きずり出し、彼らの祖先の地から切り離すことで過去との繋がりを絶ち、歴史という存在の拠り所を破壊したのだ。西洋史観にもとづくならば、歴史とは達成と創造をめぐって一方通行的に築き上げられていくものだから、過去との繋がりを絶たれたカリブ海においては何も創造されることはなかったし、大文字の歴史からも零れ落ちた地域としてしか表象されえない。だからこそカリブ海作家たちは、西洋中心主義的な歴史観に抵抗する。〈記念碑や偉大な建築物、世界を形作る出来事といった「目に見える」歴史でなくとも、ここには歴史がある〉――本連載では、記憶をめぐる彼らの詩学的挑戦を巡ってゆく。
「遭遇」の記憶
ジャマイカ人小説家・批評家のシルヴィア・ウィンターは、人間に固有な特異性として「物語る」能力を挙げている。彼女は批評活動を開始した1960年代には、カリブ海の文芸活動を主な執筆の題材としていた。しかし1980年代に入ると、彼女はいかに西洋が人類史を通して植民地的、そして帝国主義的な知見にもとづいて西洋中心的な人間科学を構築してきたかを考察し始める。この考察によって彼女がたどり着いたのが、批判的「人間」の系譜学である。この系譜学は、西洋がその想定する「人間」の理想像により、いかにして人間の意味を寡占的に支配し享受し続けてきたか、そしてどのようにその「人間」であることの条件を満たさない他者という存在を都合よく捻出するかを見事に暴露したのである。そのような他者化の論理の上に成り立つ西洋中心的「人間」観を脱植民地化すべく、ウィンターは人類をひとつの「物語る種」と捉え直すことの必要性を説く。エメ・セゼールやフランツ・ファノンたちカリブ海思想家たちと共鳴しながら、彼女の特徴的な脱植民地的詩学は人間の「新たな言葉の科学」を提唱する[*1]。そしてそこから彼女は、人間の物語る能力が、「人間とは何か」という問いへの答えであることを示すのである。
カリブ海の存在がいわゆる「世界史」に現れるようになるのは、あの1492年の出来事、すなわちクリストファー・コロンブスによる「発見」以降である。この人類史的な西洋と非西洋の「遭遇」の瞬間は『テンペスト』や『ロビンソン・クルーソー』、『ガリバー旅行記』、『オルノーコ』に『ソロモン王の秘宝』と『ジャングル・ブック』、そして『闇の奥』といった文学作品に見られるように、西洋文化において幾度となく繰り返され、発見する主体としての西洋と発見される客体としての非西洋という一方的な図式が再生産され続けてきた。そしてこの図式は西洋という領域を超え非西洋文化にも問題視されることなく浸透し、今なお世界各地の社会に巣食っている[*2]。この西洋による「遭遇」の記憶を物語る行為は、カリブ海の人々の他者化を決定的にしてしまっている。ウィンターが主張するように、物語る能力はひとつの種たる人間に属するものである。にもかかわらず、西洋はこの「遭遇」の記憶を一方的に語り、カリブ海の人々に語られる対象としての他者という役割を押しつけるのだ。
しかし「遭遇」は、カリブ海の人々を永遠に他者の地位へと縛り付ける過去の楔ではない。その記憶は常に再解釈へと開かれている。カリブ海作家たちは、「遭遇」の記憶を西洋とは異なる視点で物語る。
「第3の出来事」
批判的「人間」の系譜学において、ウィンターは「人間」(the human)が西洋の「『ヒト』の発明」(the invention of Man)によって独占されるようになったと主張する[*3]。この西洋による「『ヒト』の発明」は、その歴史を中世まで遡る。「あたかもそうであるかのように自身を表象するが、『ヒト』は人間のことではない。それは、特定の地域文化的な人間の概念、すなわちユダヤキリスト教的西洋による人間の概念が完全に世俗化した形態である[*4]」。中世ヨーロッパでは、「人間」の理想像は「真のキリスト教的自己」という宗教的人間、つまり「ホモ・レリギオースス」(homo religiosus)にあった[*5]。宗教的に考え教義に従い生きてゆくことのできない人間は、例外なく「キリストの敵」=「他者」なのである。当時の地理学の枠組みでは「神の恩寵の中にある居住可能な地域と、その外にある居住不可能な地域という非均質な2つの地域に分かれている」と信じられていた[*6]。そのため「真のキリスト教的自己」も「他者」も神の庇護下にある「居住可能な地域」に存在し、その外には「居住不可能な地域」が広がっていると考えられていた。
コロンブスによる1492年の「発見」は、ヨーロッパ西洋史における「人間」観に転回を呼び入れた。先住民との「遭遇」から、西洋の人間観はキリスト教的なものから「ヒト(1)」(Man (1))という新たな人間のあり方へ移行した。この「ヒト(1)」は、「国家の法律に何よりも従うことにより自分の理性を表す主体である。以前のような教会の戒めに何より従うことで原罪への隷属状態からの解放を目指すような主体ではない[*7]」。理性的・政治的白人男性像、つまり「ホモ・ポリティクス」(homo politicus)という人間のあり方である。「ヒト(1)」は1492年の「発見」に端を発し、啓蒙の時代に全盛期を迎えた。この「ヒト(1)」は、今までの知の枠組みであった神学を参照することなく、理性的な意志決定を行い、法律を制定し守る能力があること、すなわち理性的・政治的であることが「人間」の理想像であるとした。その規範に沿わない人々は、非理性的な他者となる。「その『他者』とは、すべての先住民、そして最も極端に、絶対零度にまで除外されたすべてのアフリカ系の人々だ。[……]『人間』であるとは何かという認識において、不完全な人間として否定的な烙印を押されるのだ[*8]」。こうして、神に守られることのなかった地域で生活する原住民や黒人は、「人間」としての理性を与えられていない存在であるため、自分たち西洋人のような理性的主体が文明を与えることによって理性的な救済が彼らにもたらされる、という認識が形成されたのである。
そして19世紀のダーウィンの進化論と資本主義の台頭から、西洋の「人間」観にさらなる転回が生じる。ウィンターいわく、この転回によって人間の新たな理想像として確立したのが、「ヒト(2)」(Man (2))、すなわち「最も望ましく経済的な人間」である[*9]。この「人間」のあり方は、理性的・政治的・経済的白人男性像、つまり「ホモ・エコノミクス」(homo oeconomicus)である。この人間の尺度では、経済的な生産性や安全性という観点から、優れた人間性が選別される。この規範では、「他者」は原住民や黒人に留まらない。現代の「他者」は、「貧者の枠組みなのである。つまり、無職やそれに近い者、そしてグローバルシステムの観点でいえば、概していわゆる『開発途上』の国々だ。(……)どれも、不完全な稼ぎ手という否定的な他性を持つ地位を象徴させられているのである[*10]」。自然から得られる資源の希少性に脅かされる生命体としての人間という、生物学的・経済学的レベルにおいてさらに発展した人間観に移行するにつれて、人間の理想像は都合の良い搾取可能な経済的貧者という他者との関係において形作られるようになったのである。
この「人間」観は、西洋という世界のひとつの側面に過ぎない地域から導き出されたものでありながら、それ自身をあたかも普遍(不変)的なものとして見せかけるものである。その人間としての普遍性に沿わない人々は。不自由な他者として差別化される。ウィンターによる系譜はこのように整理できる[*11]。

この「人間」の系譜学を通して、ウィンターは「人間」として自身を演出するヒト(1)とヒト(2)という西洋中心的に粉飾され続けてきた人間像を明らかにするだけでなく、人間が自分の起源について「物語る」能力の重要性を指摘している。彼女は、生命体の起源にかんする出来事を整理し、人類が経験した「第3の出来事」というものについて語る。
第1の出来事と第2の出来事は、それぞれ宇宙の起源とあらゆる形態の生物学的生命の爆誕のことを示している。第3の出来事は、ファノン的な用語を使えば、雑種的で/自ずと/始まり/言語を用い/物語る種としての人間の起源、すなわちビオス/ミュートイ(bios/mythoi)である。第3の出来事は、人間の脳が[……]、言語を用いる、物語を語るという創発的能力と共-進化を遂げたという特異性によって定義される。この共-進化は、人間の脳の神話形成を司る領域に伴って理解されなければならない。
ウィンターは、人間を人間たらしめている特異性というのが、単に生物学的な有機性にあるのではなく、「生物進化的にあらかじめ自ずと始まり自身を記すようにプログラムされた、自然/文化、ビオス/ロゴスの雑種的な生命の形態」にあると主張している[*14]。つまり、その脳が言葉を使って物語る能力と結びつきながら第3の出来事(共-進化)を経験したため、人間はただ生物学的(ビオス)であるというだけではなく、物語る(ミュートイ)行為を通しても進化した種であるということだ。それゆえ第3の出来事を経た人間存在は、「自然/文化」、「ビオス/ミュートイ」、そして「生物/物語」の「雑種」なのである。
人間という「物語る種」
ウィンターはこの「ビオス/ミュートイ」が織りなす雑種性を説明するために、ファノンによる「皮膚/仮面」の関係性を参照する。『黒い皮膚・白い仮面』において、ファノンはカリブ海の黒人の人々が経験する疎外を、このように説明する。「黒人の疎外が個人の問題でないことは明らかであろう。系統発生学と固体発生学とならんで社会発生学がある。[……]。そうはいっても〈社会〉は、生化学的プロセスとは逆に、人間の影響を免れない。人間によってこそ、〈社会〉は存在にいたるのだ。その見通しは、建物の蝕まれた根底を真に揺り動かそうと欲する人々の手に委ねられている。/黒人は二つの次元で戦闘を行わなければならない[*15]」。ファノンは人間がただ生物学的な次元のみで進化するようにプログラムされたわけではないと考える。だからこそ、彼はこのように力強く言い放つ。「私は、私のナルシシズムを両手一杯でにぎりしめ、人間を機械にしようとするものの卑劣さをしりぞける[*16]」。ファノン的に言えば、人間は生物学的かつ社会発生学的な進化を遂げた。その生物学的な側面は「皮膚」であり、社会発生学的な側面は「仮面」である。この議論によってファノンは、精神分析学やダーウィンの進化論における「適者生存」に支えられた「ヒト(2)」という枠組みの生物学中心的な人間の定義に、社会発生学的側面を強調して介入したのだ。この「皮膚(生物学)/仮面(社会発生学)」という図式を参考にして、ウィンターは人間の雑種性を見つめ直す必要性にたどり着くのである。「私たちはそれゆえこれから、新たな知の形式の再概念化を探求し始める必要があるのだ。それは、人間であることを皮膚(系統発生/個体発生)と仮面(社会発生)という知の形式としてファノンが再定義したことで必要とされるようになった[*17]」。
ウィンターにとって、この「社会発生学的」次元に言語能力という根幹を見出すことを可能にしたのが、セゼールである。1944年にハイチに滞在していたセゼールは、ある会議で講演を行った。その台本がもととなった論考が「詩と認識」である。この論考の中で、彼は「科学は世界観を人間に提供する。ただし要約されたもの、表面的なものである」と述べ、科学的認識がもたらす功利主義的で単一的な世界観に固執することで、人間が「自身を非個性化してしまっている」と批判している[*18]。そして彼は詩的認識を、科学による「貧しく半飢餓状態にある」認識よりも深い水準で世界を見せることができるものとして高く評価する[*19]。セゼールの詩的認識の議論は、人間の生物学的側面にしか興味を示さない科学が見落としてきた、言葉という人間の「社会発生学的」次元に光を当てたのである。ウィンターが述べるように、セゼールによる「言葉の科学」とは、「『言葉』(すなわち私たちが『文化』と呼んでいる現象)の研究が、自然(脳の神経生理学的メカニズムにまつわる)の研究を条件づけ、彼が『半飢餓状態』と定義する現在の自然科学を終わらせる新たな科学たらしめ、それによって新しい『世界の尺度に合わせて作られたヒューマニズム』を可能にする」科学なのである[*20]。
セゼールとファノンというふたりの知の巨人に倣いながら、ウィンターは人間が生物学的かつ社会発生学的に物語る文化を育む種であると主張する。こうした「物語る種」としての人間の存在を、ウィンターは「ホモ・ナランス」(homo narrans)と呼んでいる[*21]。この「ホモ・ナランス」を図としてまとめれば、このようになる。

ウィンターはこの系譜学によって、「人間」の理想像が「中世キリスト教徒」、「ヒト(1)」、「ヒト(2)」を通して西洋により支配されてきたことが明らかにした。そしてその一方で、あらゆる人間はその進化を物語る能力を持つ脳と共に遂げてきた、「物語る種」であることを示した。しかしながら、この「物語る種」としての人間のあり方すら、西洋は非西洋の人々から奪い取り、独占的に享受し続けてきたのである。それは、アーレントによる「人間」の記憶の言説に表れている。
アーレントと『闇の奥』
アリストテレスは『政治学』で、人間とは何かという問いに有名な定義を与えた。「人間は自然本性的に国家を形成する動物である[*22]」。ここでアリストテレスは人間のみがポリス(古代ギリシアの都市国家)的動物であると主張しているわけではない。彼は蜂や羊や牛といった群生動物など共同体的生活を営む動物も国家を形成する動物であると認識している。そうしたうえで、人間が「あらゆる種類の蜂や群生動物のすべてにも優り、国家を形成する動物になっている」と述べる[*23]。そして彼はその理由を人間が用いる言葉の役割にあるとする。「言葉の役割は、有益性と有害性を明示するところにあり、したがってまた、正義と不正も明示できるのである。なぜなら、善と悪、正義と不正などの感覚を人間だけが持つことこそ、他の動物と対比される固有の特性だからである。つまり、〔言葉による〕善と悪、正義と不正などの共有が、家と国家を作り出すのである[*24]」。人間の言語能力は倫理的判断能力が結びついており、それによって人間は国家形成に必要な「善と悪、正義と不正などの感覚」を得る。アリストテレスはこれが人間固有の特徴であり、人間を「言葉(ロゴス)をもつ」動物として他のポリス的動物から区別するものであると述べている[*25]。
アリストテレスの言語に支えられた国家を形成する動物という人間観を継承しつつ、アーレントもやはり、人間の根幹に「物語る」能力を見出している。『人間の条件』において、彼女は人間が言語を含んだ活動によって人間の共同体に生まれ入ってゆく生物、すなわち「活動と言論を通じて自分を人間世界の中に挿入し、それによってその生涯を始める」生物であると述べる[*26]。人間はひとりひとりが唯一の存在であり、自分が誰であるかを、言葉を使用して表現することができる。この言葉はその人間のアイデンティティを示すユニークな物語を紡ぎ出す。そしてその人間が現れる共同体には、新しい生涯の物語がもたらされるのである。「人びとは活動と言論において、自分がだれであるかを示し、そのユニークな人格的アイデンティティを積極的に明らかにし、こうして人間世界にその姿を現わす[*27]」。そして「新参者のユニークな生涯の物語」は、「新参者が接触することになるすべての人びとの生涯の物語にユニークな形で影響を与える」ようになる[*28]。こうして人間は、「人間関係の網の目」の中に自分たちのユニークな生涯の物語を持ち込みあい、多様性と複数性のある共同体的生活を営む[*29]。この公共空間として代表的に描かれているのが、ポリスである。「正確にいえば、ポリスというのは、ある一定の物理的場所を占める都市=国家ではない。むしろ、それは、共に活動し、共に語ることから生まれる人びとの組織である。そして、このポリスの真の空間は、共に行動し、共に語るというこの目的のために共生する人びとの間に生まれる[……][*30]」。
この人間の物語と国家形成の議論から、アーレントは人間の記憶の考察も展開する。アーレントいわく、「人間の本質が現われるのは、生命がただ物語を残して去るときだけである[*31]」。人間といういずれ死ぬ存在、言い換えれば可死性を伴って生まれた存在は、記憶されることでその死から救済される。言い換えれば、共同体内にその人間がもたらしたユニークな生涯の物語が人々によって語り継がれることで、何らかの痕跡として自身の存在を死後世界に残すことができるのである。この記憶を語り継ぐ空間が、アーレントにとってはポリスである。
ポリスという形で共生している人びとの生活は、活動と言論という人間の活動力の中で最も空虚な活動力を不滅にし、活動と言論の結果である行為と物語という人工の「生産物」の中で最もはかなく触知できない生産物を不滅にするように思われたのである。ポリスという組織は、物理的にはその周りを城壁で守られ、外形的にはその法律によって保証されているが、後続する世代がそれを見分けがつかないほど変えてしまわない限りは、一種の組織された記憶である。
ポリスは「組織された記憶」である。その公共空間に「出現」し、人間は「共に活動し、共に語る」。各々がもたらすユニークな生涯の物語は、その共同体に属する人々によって語られ、そして文書や記念碑などに記録され、偉大な行為と言葉の記憶が刻まれる。こうしてポリスは記憶の共同体として、死にゆく人間の物語を記憶してゆくのである。
しかしアーレントは、西洋と非西洋の「遭遇」の記憶を、西洋の視点からのみ認識しているように見える。興味深いことに、彼女は『全体主義の起原』においてアフリカを暗黒大陸と呼ぶのだが、その根拠を物語に見出している。彼女はアフリカの「前史的人間」が「何ひとつ痕跡も記憶も残さず」、人間であるが人間ではないほどのあまりの野蛮さと激情ぶりを見せるという長い一節をジョセフ・コンラッドの『闇の奥』から引用している[*33]。彼女にとって、『闇の奥』は「アフリカにおける実地の人種体験にかんして最も理解させてくれる作品」である[*34]。彼女が引用した一節は以下だ。
その原始人たちは俺たちを呪ったのか、祈ってくれたのか、歓迎してくれたのか――それはわからない。俺たちはもう周囲の状況を理解できなくなっていた。俺たちは幻影のように滑っていきながら、戸惑い、秘かに怖気をふるっていた。たとえば精神病院で患者たちが突然興奮して騒ぎだしたら、正気の人間はそうなるに違いない。まったくわけがわからなかった。なぜなら、俺たちはあまりにも遠くまで来てしまい、普通の世界を憶い出せなくなっていたからだ。原始の夜を旅していたからだ。遠く過ぎ去り、痕跡も記憶もほとんど残っていない時代の夜を。
地上の光景はこの世のものとは思えなかった。[……]。[……]原住民は――いや、彼らは、人間とは思えないというわけじゃなかった。わかるかな、そこが最悪なんだ――ああいうのも非人間的とは言えないんじゃないかと思えることがね。徐々にそんな気がしてくるんだ。吠える、跳ねる、くるくる回る、怖ろしげな顔をする。だがぞっとするのは、彼らも俺たちと同じように人間だと考える時だ。自分たちもこの野性的な熱い興奮と遠いつながりを持っていると思う時だ。
アーレントにしてみれば、「人間」が生きる西洋という世界の外に存在する地に呪われたる人々は、「一つの世界を築くことも」できず、記憶にも残らない人々なのである。それゆえ彼女は、彼らが世界を持たないと言い放つ。その「非実在性」と「無世界性」こそが、彼らが人間としてのリアリティを欠いていること、つまり人間であることの条件を満たしていないことの証左であり、だからこそ彼らが生きる地域では非文明的な破壊や野蛮さが蔓延するのだと言う。
彼らの非実在性、彼らの亡霊のように見える行動は、彼らの無世界性に由来している。彼らは世界を持たないがゆえに自然が彼らの存在の唯一のリアリティと見える。そして自然は観察者に対してすら圧倒的なリアリティとして迫ってくる――世界を持たない人間を相手にするとき自然は思いのままに跳梁し得る――から、自然に較べれば人間は幻か影のようなもの、完全に非現実的なものと見えてくる。この非現実性は、彼らが人間でありながら人間独自のリアリティをまったく欠いていることから来る。世界を持たないことから生ずる原住民部族のこの非現実性こそ、アフリカに怖ろしく血なまぐさい破壊と完全な無法状態とを招き寄せたものだった。
「人間」の分割
比較文学研究者でホロコーストを中心とする記憶文化の研究者であるマイケル・ロスバーグは、『多方向的記憶』において、アーレントが見ているのは確かにトラウマ的な経験としての西洋とアフリカの「植民地的遭遇」であるが、「そのトラウマは被植民者側のものではなく、植民者側のものである」と批判する[*37]。アーレントは「植民地的な遭遇において何が本当に衝撃的でトラウマ的なものであるか」を追究するのではなく、単純にコンラッド(そして主人公のイギリス人船乗りマーロウ)による物語のみをその「遭遇」の記憶として受け止め、西洋人だけがトラウマを経験したかのように語っている[*38]。それによって彼女は「植民地的暴力そのものを一貫して周縁に追いやり、植民地的言説の用語(「怪物性」、「野蛮人」)を再生産しているように見えるし、ヨーロッパ人らしさという覇権を付与された概念(「ヨーロッパ人ではない」など)を再生産しているのである[*39]」。つまり、アーレントは「野蛮」であるアフリカと出会ったことにより、「文明」としてのヨーロッパがいかにトラウマ的衝撃を被ったかということにしか目を配らず、その記憶を語る権利を西洋人にしか与えないのである。それゆえロスバーグはこのように批判する。「語りの視点と語りの声がヨーロッパ人の視点へと統一されているため、彼女がはっきりと見ている――と彼女の名誉のために付言しておく――『敵国民の虐殺』や『原住民の根絶』という潜在的なトラウマ的影響が軽いものになってしまっているのである[*40]」。
「遭遇」の記憶を語る機会を西洋側が独占していることを疑わないアーレントの姿勢が加担するのは、ロスバーグの言葉を使えば「人間の分割」(the splitting of the human)である[*41]。アーレントは一方では西洋人による「遭遇」の記憶の物語を唯一の判断材料とし、他方ではアフリカ人が「世界を持たない」、「独自の歴史の記憶も、記憶に価する事蹟も持たない」存在であると認識することで、人間をふたつに「分割」してしまっているのである。ロスバーグはこのように指摘する。「ヨーロッパとアフリカの遭遇において、人間という概念が分割される。怪物を人間として認識することで、アフリカ人をテキストに引き込み、ただ置き去りにするという『遠い親族関係』の物語が成立する[*42]」。つまりコンラッドの物語が見せているのは、「俺たちと同じように人間だ」と思える存在を野蛮な怪物として物語に登場させ、彼らの人間性を回復させることなくテキスト内に放り投げたまま物語を終了する「遠い親族関係」の物語である。このような「遭遇」の記憶を西洋は繰り返し色々な媒体で再生産してきたのである。ロスバーグが言うように、アーレントにとって「アフリカとアフリカ人の『不可解さ』は、ヨーロッパとその難民や収容所の犠牲者のそれとは異なる次元のものである。アーレントは認めてはいないが、彼女の議論は、トラウマ的な極限状態に直面したヨーロッパ人という主体を保護し保存するのに必要な距離を提供してくれる、既存の文化的差異にもとづいている。書かれた実践としての歴史というヘーゲル的な理解を駆使して、アーレントは一貫してアフリカを『先史時代』として、アフリカ人を『先史時代の人間』として表現しているのである[*43]」。
ロスバーグいわく、アーレントの言説で「最も議論を引き起こしそうなのは、アフリカでヨーロッパ人が経験した『衝撃』は、啓蒙思想が誇った普遍主義とヒューマニズムそのものから生じているという可能性である。その思想のせいで、植民者たちは同一のものと出会うと期待していたのだ。差異がトラウマとなるのは、均質的な普遍性という期待からなのである。人種というカテゴリーは、彼女が認める以上にアーレントの議論と歴史的説明にとって根源的なものである[*44]」。人種という問題が深く入り込んだ西洋中心的・白人至上主義的議論を通してアーレントが行った「人間の分割」は、まさしくウィンターが「人間」の系譜で辿った「人間」観に合致するものだろう。アーレントは、理性を備え経済的にも優れた西洋文明人である「ヒト」を「人間」として当然のように表象し、西洋人にトラウマをもたらす野蛮なアフリカ人は「人間」として欠如を抱えた他者として隔離しているのである。そしてこの「人間の分割」は、ウィンターが人間の特異性として語った物語る種としてのあり方をも分割してしまっている。すなわち、「物語る」西洋人と「物語られる」非西洋人という人間の分割である。

それゆえアーレントの思想において、西洋とアフリカの「遭遇」がもたらしたトラウマの記憶は西洋文明においてのみ認識され、被植民者側から見たその記憶の物語は排除されているのだ[*45]。
現在私たちが生きる世界でも西洋とアフリカの「遭遇」の記憶は西洋によって都合よく生産され続け、彼らの物語はアーレントの思想に見られるように世界の支配的な言説となってしまっている。この西洋による「遭遇」の記憶の独占に、私たちはどのように抵抗したらいいのだろうか。
種の視点から
コロンブスの1492年の「発見」以降、5世紀近くにわたり西洋列強がその欲望のまま虐げ続けたカリブ海では、1960年代にイギリス領だった島々が次々に独立を迎えた。だが独立は、カリブ海が西洋による支配から抜け出したことを意味しない。ウィンターは、現在も人間の意味の決定権を掌握している西洋が、独立したカリブ海の島々を「新植民地主義的に、ゆえに模倣を通して、再統合しようとしている」と指摘する。西洋は、「私たちの問題が、帝国主義的に従属させられてきたことでもなく、社会文化的に支配され経済的に搾取されてきたことでもなく、私たちが未開発であったことなのだと告げることで」、カリブ海が「人間」(つまり「ヒト(2)」)として欠如を抱えた存在であると言い続ける。「ほら、もう土着民ではなく、我々のようなヒトになれ! ホモ・エコノミクスになれ!」と、西洋は自分たちが作り上げた理想的な「人間」の立場から、他者であるカリブ海に命じるのだ[*46]。このように理性で「人間の分割」を実行していた西洋は、現代では経済を用いて人間を分割している。今なお続く西洋による人間の言説の支配に抵抗するためにウィンターが提案するのは、1492年の記憶の再訪である。
2017年、文化・哲学研究誌の『パララックス』が「人文主義後の記憶」という特集を組んだ。比較文学研究者のブリジット・カイザーとジェンダー研究者のキャトリン・ティーラは、「種の記憶とは何か? または人文主義、記憶、『1492』とその後」という論文で、理論的枠組みをウィンターの思想に依拠して構築し、このように主張する。「ウィンターがするように1492年の記憶を問うことで、私たちは歴史的な出来事とその余波をめぐる集合的記憶のダイナミクスの分析を超える。ウィンターは『1492年』を、『私たち』が人間であることの意味を問い直す重要な場として捉えているのである[*47]」。この問い直しは、単純に1492年の記憶を「植民者/西洋」か「被植民者/非西洋」どちらかの視点で再訪することではない。ウィンターは1492年の「発見」がもたらし、その後5世紀にわたって地球全体に影響を及ぼした功罪それぞれを強調する。
一方では大規模な残虐行為があり、最終的にはアラワク族の絶滅を招きました。1518年以降は、奴隷にされたアフリカ人に中間航路というトラウマを植え付け、大量死をもたらし、そしてたどり着いた先では奴隷プランテーションのためだけの存在に変えられるという恐怖を与えました。しかし他方では、私たち自身の存在を可能にする出来事でもあります。近代世界を誕生させ、私たちすべてにとっての現実を変え、私たちが今生きている単一の歴史に私たちを挿入する出来事でもあるのです。では、私たちはそんな出来事にどのようにアプローチするべきなのでしょうか。
西洋と非西洋の対立、もしくはカイザーとティーラの言葉を使えば「(「私たち対彼ら」という論理にもとづく)この対立的な追憶のモデル」は、1492年を輝かしい功績として祝い追憶する植民者の視点と大量虐殺や生態系破壊を引き起こした暴力的侵略として追憶する先住民の視点から成り立っている[*49]。この対立する立場のいずれかから1492年の記憶を論じても、植民地主義が作り出した「人間」の秩序からまだ抜け出せていないとウィンターは考えるのである。
「1492――新しい世界観」という論考において、ウィンターはこの対立的な追憶のモデルを乗り越え、新たな視点から人類が「遭遇」を語ることのできる可能性を問う。「ならば私たちは、現代の状況下で生態系とグローバルな社会生態系が持つ『相互関連性』の両方を出発点とし、種の視点からそしてその種の幸福という利益を参照しながら、1492についての新しい世界観を提唱することができるのだろうか[……]?[*50]」。1492年に由来する対立的な追憶のモデルは、現代でも色々な文化的媒体で再生産される「遭遇」が内包する記憶の植民地的構造を問うことができていない。ここで要請されるのが、従来の人文主義が依拠していた二元的な視点ではなく、その後奴隷とされたアフリカ人や年季奉公制によって搾取されたアジア人を巻き込んだ全世界的な「種としての」視点だ[*51]。この種としての視点とは、人間を「ホモ・ナランス」、つまり「物語る種」として認識するということである。西洋が仕掛けた「人間の分割」を乗り越え、今一度人間をひとつの「物語る種」と考えることこそが、「1492のまったく新しい解釈」のためにウィンターが必要と考えることである[*52]。
物語る種としての人間という視点から、1492年以降西洋が独占してきた「遭遇」の記憶を語りなおすことなどできるのだろうか。ウィンターは「1492――新しい世界観」において、「このエッセイの中心的なテーゼは、私たちにはそれができるということである」と言う[*53]。彼女に倣って、私も断言しよう。群島的記憶を描くカリブ海作家たちには、それができると。彼らも、「物語る種」なのだから。
カルペンティエール、『ハープと影』
『ハープと影』(El arpa y la sombra)は、キューバ人作家アレッホ・カルペンティエールが生涯最後に出版した小説である。本作品は3部構成となっており、第1部「ハープ」では、後に教皇ピウス9世となる聖堂参事会員のマスタイが、独立直後のチリに教皇使節団のひとりとして招かれ、そこでの光景から新世界と旧世界を繋ぐ架け橋のような聖人が必要であると認識し、その後コロンブスの列福を思いつく。第2部「手」では、死の間際のコロンブスが聴罪師を待ちながら過去を回想し、聖人とは程遠い自身の人となりを語る。第3部「影」では、ヴァチカンでのコロンブスの列福裁判が舞台となり、様々な人物が登場し賛否の声を飛び交わせる。コロンブスは幽霊としてその裁判の行方を一喜一憂しながら見守る。地理的には広くラテンアメリカ全域を背景とした作品であるが、ファビエン・ヴィアラが言うように、キューバ人作家によるこの物語は「カリブ海の記憶」を描いている[*54]。
1842年、チリのサンティアゴ・デ・チレに使節団として到着したマスタイは、独立にもかかわらず人々が熱心に信仰を実践し教会を尊重していることを知り、独立戦争によって新世界と旧世界の溝が深まる中、信仰こそが両者を統一すると確信する。そこでふたつの世界を繋ぐ様々な聖人候補の可能性を考えるも、「旧世界と新世界のキリスト教信仰を一枚岩にし、そこに、アメリカでも驚くほど多くの信奉者を得ている有毒な思想に対する解毒剤を盛りこむために理想的で完璧なのは、普遍的な信仰の対象となる聖人、その名声が国境を持たない聖人、疑問の余地なく宇宙的な広がりを持つ聖人、その巨大さにおいて伝説的な〈ロードスの巨像〉をはるかに凌ぎ、片足をこの大陸の海岸に置き、もう一方の足をヨーロッパ大陸の地の果てにかけながら、大西洋を越えて広く両半球を視野におさめるような聖人」として最適な人物がいない[*55]。そこで彼が思いついたのが、「すべての人に知られ、諸国民によって崇拝され、その偉業と威信において普遍的な〈キリストの運搬人〉、〈キリストを支える者〉、聖クリストバル」であった[*56]。1846年にピウス9世として教皇に選出されると、彼はコロンブスの列福の請願を提出する。この請願は、「あらゆる信望に価する、真摯で厳密でしかも情熱的な歴史家」であるフランスのカトリック作家ロゼリー・ド・ロルグ伯爵による「最近の研究成果や新たな文献・資料」に支えられたものだった[*57]。
しかし、コロンブスはその生涯が不明な点が多い人物であった。コロンブス研究家のミシェル・ルケーヌが述べるように、「その後500年間におびただしい伝記が書かれたが、最小限の意見さえ一致をみない。コロンブス自身も、沈黙や矛盾した言動、多少の嘘や韜晦ゆえに、その生涯を探りやすい人物でないことは確かだが[*58]」。彼の息子フェルナンドによる最初の伝記も、そのカスティーリャ語による原本が失われ、何かしらの改変が加えられているのではという疑いがあるという[*59]。『ハープと影』でも、カルペンティエールはコロンブスの生涯の謎めいた側面を利用しながら、時には歴史的事実をも捻じ曲げ脚色を加えつつ、私たちの目に見えない歴史の角度から彼を描く。そうすることで、普遍的に尊敬された聖人としてではなく、ただ一般人としての彼の肖像を提出する。
カルペンティエールは、死の床に伏すコロンブスに自分の過去の記憶を巡らせる。その追憶の中で、コロンブスは「いわゆる七つの大罪のうち、わたしとまったく無縁なのは唯ひとつ、怠惰の罪でした」と述べる[*60]。ロルグ伯爵が最新の歴史的アプローチを用いて書き上げた伝記が物語る聖人にふさわしい人物像とはかけ離れた、幼いころから父が経営する酒場で酒をあおり女を漁って淫蕩そのものの生活するようなコロンブスの像が浮かび上がる。そして彼の後悔は科学的計算と歴史的知見による裏付けもなく、ヤコブ親方という人物が語るノルマン人の〈サーガ〉を聞いたことがきっかけであること、さらにはスペインの女王イサベル1世と肉体関係も結んでいたことなどが語られる。彼の日誌には神という言葉は14回しか出てこない一方で、金という言葉は200回以上出てきたということも触れられる。こうして本人の追憶を通して、コロンブスがいかに欲にまみれた単なる俗な人間であったかが示される[*61]。
そして19世紀末、コロンブスの列福裁判が開かれる。その舞台には裁判長や儀典聖省長官だけでなく、〈悪魔の弁護士〉、フランスのカトリック作家レオン・ブロワ、ロマン主義作家ヴィクトル・ユゴー、そしてバルトロメ・デ・ラス・カサスといった人物が現れ、コロンブスの聖人認定の是非について争いあう。請願者として登壇したホセ・バルディは、「母親の胎内から彼の名を呼んでいる胎児たちの叫び声を聞いたように、彼、クリストバル・コロンはその苦しくも虚しい航海に費やした十八年の間、魂の中に人類の半分の発する途方もない叫喚を秘め続けていた」と述べたり、「ロゼリー・ド・ロルグ伯爵は何ら躊躇することなく、〈大提督〉をノア、アブラハム、モーセ、バプテスマの聖ヨハネ、聖ペテロに伍して位置づけ、彼に〈神の使者〉という至上の肩書を授けているのであります」と主張したりして、コロンブスを称賛する[*62]。するとユゴーが現れ、「クリストバル・コロンが本当にすぐれた宇宙形状誌家だったなら、彼が新世界を発見するようなことは決してなかったでしょう」とコロンブスを批判する[*63]。聖人化賛成派と反対派の意見が飛び交う中で、コロンブスが先住民のインディオを拿捕し売り飛ばしたことにユゴーが触れると、幽霊のコロンブスは全身が冷たくなるのを感じた。
ここでラス・カサスが現れる。この「1492」の記憶をめぐる裁判で、彼は「その名声が末代にまで伝わっているイサベル女王は、コロンの部下によってアメリカの奴隷がセビーリャの市場で売買されているのを知った時ひどく立腹され、『提督は私の臣下を勝手に他人の手に引き渡すような権限をいったい誰から授かったのでしょう?』とお訊ねになったのです」と述べ、新世界での奴隷制はコロンブスが自分の意志で始めたという証言を行う[*64]。また彼は「まず最初に、インディオは外見の美しさにおいても知性においても、また創意の面においてもきわめてすぐれた人種であると申し上げておきましょう……アリストテレスが、それ自体で充足するような完璧な共和国を形成するために必要だとして挙げた六つの条件を、彼らは過不足なく備えているのです」とも主張する[*65]。ラス・カサスによって、先住民たちがアリストテレスのいう「国家を形成する動物」、アーレントが記憶の共同体と見なしていたポリスを形成することのできる生物、つまり人間であったことが告げられるのである。こうして裁判は自分の欲のために人間を捕まえ売り飛ばし、奴隷制を始めたコロンブスの新たな姿を照らし出したのだ。結果として列福賛成派はわずか1票となり、請願は棄却される。失意のコロンブスは、サン・ピエトロ広場の大気の中へ消滅してゆくのだった。
1492年以来、西洋は「遭遇」の記憶を語る権利を牛耳ってきた。たとえばフランスの作家ポール・クローデルによる劇『クリストファ・コロンブスの書物』では、冒頭で解説者が「まことに、かれこそは、この普遍の大地を統一し、この茫漠たる大地をただ一塊の球体として、十字架の下にすえおいた者」と述べ、コロンブスの神格化された人格を語る[*66]。しかしながら、そのような西洋が独占してきたコロンブスの記憶は、こうしてカルペンティエールのようなカリブ海作家たちによって転倒されるのだ。実はコロンブスの裁判が、実際に1993年にマルティニークで実現したということはご存じだろうか。マルティニーク人弁護士でファノンとも親しかったマルセル・マンヴィルが、コロンブスを人道に対する罪、そして先住民の虐殺という罪で訴えたのだ。カルペンティエールが1979年に描いた物語が、現代の私たちの記憶となった瞬間だった。きっとコロンブスも、幽霊となってこの裁判をやきもきしながら見ていたことだろう[*67]。
カリブ海作家たちは、アーレントが行ったような「人間の分割」を拒否する。彼らは人間をひとつの「物語る種」として受け止め、自分たちの「種の記憶」を物語る。そして彼らによって描かれる群島的記憶は、カリブ海の目に見えない歴史を照らすのである。
註
[*1]Sylvia Wynter, “Towards the Sociogenic Principle: Fanon, Identity, the Puzzle of Conscious Experience, and What It Is Like to Be ‘Black,’” National Identities and Sociopolitical Changes in Latin America, ed. Mercedes F. Durán-Cogan and Antonio Gómez-Moriana (New York: Routledge, 2001), 58.
[*2]たとえば今年出版された『正義とは何か』で、森村進は正義の「道徳的性質」を説明する際に、このように語っている。「それは第一に、一人の個人の生だけの中では問題にならず、複数の人々の間の関係に関する道徳的性質だ。たとえば無人島に漂着したロビンソン・クルーソーの場合、自分にとっての〈善いものと悪いもの〉は存在するが、他の人々との関係における〈正と不正〉は存在しない。正不正は彼がフライデーと出会ったときに生じたのである」(森村進『正義とは何か』〈東京:講談社、2024年〉、16)。ロビンソン・クルーソーの「遭遇」をもちいて説明される「正と不正」は、クルーソーとフライデーのどちらを主体にしているのだろうか。
[*3]Sylvia Wynter, “Unsettling the Coloniality of Being/Power/Truth/Freedom: Towards the Human, After Man, Its Overrepresentation — An Argument,” CR: The New Centennial Review 3, no. 3 (Fall 2003), 263.
[*4]Sylvia Wynter, “Africa, the West and the Analogy of Culture: The Cinematic Text after Man,” Symbolic Narratives/African Cinema: Audiences, Theory and the Moving Image, ed. June Givanni (London: British Film Institute, 2000), 25.
[*5]Wynter, “Unsettling,” 266.
[*6]Sylvia Wynter, quoted in David Scott, “The Re-Enchantment of Humanism: An Interview with Sylvia Wynter,” Small Axe, no. 8 (September 2000), 191.
[*7]Wynter, “Unsettling,” 277.
[*8]Wynter, “Africa,” 25.
[*9]Wynter, “Unsettling,” 314.
[*10]Wynter, “Africa,” 25–26 (original emphasis).
[*11]ウィンターの「人間」の系譜学を簡単にまとめたが、ここでは触れなかった「過剰表象」や「解呪」などの議論も含めた詳しい解説は、拙著『私が諸島である――カリブ海思想入門』の第2章、「1492を越えて、人間であること――解呪の詩学」を参照。
[*12]この図はアフリカ学研究者で政治理論家のニール・ロバーツによる表を参考にしている。Neil Roberts, “Sylvia Wynter’s Hedgehogs: The Challenge for Intellectuals to Create New ‘Forms of Life’ in Pursuit of Freedom,” After Man, Towards the Human: Critical Essays on Sylvia Wynter, ed. Anthony Bogues (Kingston, JA: Ian Randle Publishers, 2006), 163.
[*13]Sylvia Wynter and Katherine McKittrick, “Unparalleled Catastrophe for Our Species? Or, To Give Humanness a Different Future: Conversations,” Sylvia Wynter: On Being Human as Praxis, ed. Katherine McKittrick (Durham: Duke University Press, 2015), 25.
[*14]Wynter, “Africa,” 25.
[*15]フランツ・ファノン『黒い皮膚・白い仮面[新装版]』海老坂武、加藤晴久訳(東京:みすず書房、2020年)、34。
[*16]同書、45。
[*17]Wynter and McKittrick, 23.
[*18]Aimé Césaire, “Poetry and Knowledge,” Refusal of the Shadow: Surrealism and the Caribbean, ed. Michael Richardson, trans. Krzysztof Fijałkowski and Michael Richardson (New York: Verso, 1996), 134 (Césaire’s emphasis).
[*19]Ibid (Césaire’s emphasis).
[*20]Sylvia Wynter, “Black Education, toward the Human, after ‘Man’: In the Manner of a Manifesto: Framing a Transformative Research and Action Agenda for the New Millennium,” Black Education: A Transformative Research and Action Agenda for the New Century, ed. Joyce E. King (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2005), 359.
[*21]Wynter and McKittrick, 25.
[*22]アリストテレス『政治学(上)』三浦洋訳(東京:光文社、2023年)、32。
[*23]同書、32–33。
[*24]同書、33–34。
[*25]野家啓一「総論:ホモ・ナランスの可能性」、『ヒトと人のあいだ』、野家啓一編(東京:岩波書店、2007年)、8。
[*26]ハンナ・アレント『人間の条件』志水速雄訳(東京:筑摩書房、1994年)、299。
[*27]同書、291。
[*28]同書、298。
[*29]同書、298。
[*30]同書、320。
[*31]同書、312。
[*32]同書、318–319。
[*33]ハンナ・アーレント『全体主義の起原 2――帝国主義[新版]』大島通義、大島かおり訳(東京:みすず書房、2017年)、129–130。
[*34]Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (New York: Penguin, 2017), 241.日本語訳の『全体主義の起原』はドイツ語版を対象としているため、この言葉がない。
[*35]コンラッド『闇の奥』黒原敏行訳(東京:光文社、2009年)、90–91。
[*36]アーレント『全体主義の起原 2』、139–140。
[*37]Michael Rothberg, Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization (Stanford: Stanford University Press, 2009), 55.
[*38]『『闇の奥』の奥』において、藤永茂はアーレントがその人種思想論をコンラッドの物語に依存して展開したことを「軽く看過すべきことではない」と主張している。小説内でクルツが犠牲となった西欧文明から野蛮状態に逆行するという人種的経験を、アーレントはブーア人の祖先となるオランダ人にのみ帰しているが、藤永いわく「ヨーロッパ白人が『個々の輸入品としてではなく』集団としての多数の黒人に接する機会は、これ以前にも、いくらもあったはずである」。そのためブーア人の祖先だけが「集団としての黒人に接して、実存的な戦慄的恐怖を味わったというのは、あまりにも文学的な誇張」であり、「その誇張の上に人種理論を構築すべきではない」。(藤永茂『「闇の奥」の奥――コンラッド・植民地主義・アフリカの重荷』〈東京:三交社、2006年〉、156、160)。
[*39]Ibid.
[*40]Ibid., 55–56.
[*41]Ibid., 58. 『野蛮の言説――差別と排除の精神史』において、中村隆之もアーレントによる『闇の奥』の読解に言及し、それが「当時の西洋知識人の常識、すなわちアフリカの奥地に住むのは『未開の野蛮部族』だと『人類』の名のもとに語るという、今日では西洋中心主義というほかない驕りを正当にも示しているのです」と指摘している。(中村隆之『野蛮の言説――差別と排除の精神史』〈東京:春陽堂書店、2020年〉、195)。
[*42]Ibid., 57.
[*43]Ibid., 58.
[*44]Ibid., 62
[*45]ロスバーグはその後セゼールを引き合いに出しながら、アーレントによる「人間の分割」がいかに20世紀ドイツで生じた全体主義思想によって強制収容所に送られた人々と植民地支配によって虐げられたアフリカの人々との差異化を引き起こしてしまっているかに論を回している。カリブ海思想にとってはその議論も非常に有益なため、ぜひ読んでもらいたい。ロスバーグはこう述べている。「全体主義において起こる人間の縮小と分割を説明するために、アーレントは植民地的遭遇においてすでにそのような分割が起こっていると仮定する必要がある。しかし、その遭遇がどのようにして人種の顕在を生じさせ、人種差別の力を生み出すのかを説明しようとする彼女の試みは、結局人種的差異が遭遇の前に存在していることを要求することになる。こうして彼女は、植民地的遭遇と収容所において生み出されると見なした人間の中に、まさに一線を引いてしまうのである」(Ibid., 61)。なおロスバーグは『多方向的記憶』の次の章をセゼールに充てている。これは必読である。
[*46]Wynter and McKittrick, 20 (original emphasis).
[*47]Brigit M. Kaiser and Kathrin Thiele, “What Is Species Memory? Or, Humanism, Memory and the Afterlives of ‘1492,’” Parallax, no. 23, vol. 4 (2017), 404.
[*48]Wynter, quoted in Scott, “Re-Enchantment of Humanism,” 191.
[*49]Kaiser and Thiele, 403.
[*50]Sylvia Wynter, “1492: A New World View,” Race, Discourse, and the Origin of the Americas: A New World View, ed. Vera Lawrence Hyatt and Rex Nettleford (Washington D. C.: Smithsonian Institute Press, 1995), 8 (my emphasis).
[*51]Kaiser and Thiele, 404.
[*52]Ibid., 405; Wynter, quoted in Scott, “Re-Enchantment of Humanism,” 191 (original emphasis).
[*53]Wynter, “1492,” 8.
[*54]Fabienne Viala, The Post-Columbus Syndrome: Identities, Cultural Nationalism, and. Commemorations in the Caribbean (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 104.
[*55]アレッホ・カルペンティエール『ハープと影』牛島信明訳(東京:新潮社、1984年)、45。
[*56]同書、45。
[*57]同書、48。
[*58]ミシェル・ルケーヌ『コロンブス――聖者か、破壊者か』富樫瓔子、久保実訳、大貫良夫監修(大阪:創元社、1992年)、21。
[*59]同書、20。
[*60]カルペンティエール、『ハープと影』、60。
[*61]訳者の牛島によれば、実際には神の名が50回ほど、金が約120回ほどである(同書、247)。
[*62]同書、202–203。
[*63]同書、207。
[*64]同書、211。
[*65]同書、210。
[*66]ポール・クローデル「クリストファ・コロンブスの書物」、『筑摩世界文学大系51 クローデル・ヴァレリー』鈴木力衛、山本功訳(東京:筑摩書房、1960年)、126。
[*67]マンヴィルによるこの裁判は、当時パリ市長だったジャック・シラクが、マルティニークはサン=ピエールの市長に手紙を送り付け、コロンブスによる「発見」はアメリカ大陸が現代性へと参入することを可能にした歴史的出来事であったとして、マルティニークとグアドループで1492年を記念する日を設けることを提案したことに端を発する。植民地支配と現代性を結び付けていると厳しくシラクを非難し、マンヴィルはこの裁判を実行した。3日にわたる裁判の結果は、人道主義に反する罪でコロンブスを有罪とし、彼にアラワク族の人々に1フラン賠償することを命じるというものだった。この1フランにかんして重要なのはその金額ではなく、コロンブスの罪をカリブ海の人々が記憶するための象徴としてのその価値である。ヴィアラが述べるように、裁判自体は「大量虐殺や文化破壊といった過去に行われた植民地化による被害への正義と修復の要求であると同時に、現在もカリブ海で続いている新植民地的・経済的搾取に対する政治的闘争行為でもあった」が、その最大の関心ごとは、「歴史的知識が人々に連帯感、集団的な力、政治的自覚を与えるという考えのもと、記憶を呼び覚ますことによって集団的な追憶を育むことであった」(Viala, 184)。
参考文献
● Arendt, Hannah, The Origins of Totalitarianism, New York: Penguin, 2017.
● Césaire, Aimé, “Poetry and Knowledge.” In Refusal of the Shadow: Surrealism and the Caribbean, edited by Michael Richardson, translated by Krzysztof Fijałkowski and Michael Richardson, 134–146. New York: Verso, 1996.
● Kaiser, Brigit M., and Kathrin Thiele, “What Is Species Memory? Or, Humanism, Memory and the Afterlives of ‘1492,’” Parallax 23, vol. 4 (2017): 403–415.
● Roberts, Neil. “Sylvia Wynter’s Hedgehogs: The Challenge for Intellectuals to Create New ‘Forms of Life’ in Pursuit of Freedom.” In After Man, Towards the Human: Critical Essays on Sylvia Wynter, edited by Anthony Bogues, 157-89. Kingston, JA: Ian Randle Publishers, 2006.
● Rothberg, Michael, Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization, Stanford: Stanford University Press, 2009.
● Scott, David, “The Re-Enchantment of Humanism: An Interview with Sylvia Wynter,” Small Axe, no. 8 (September 2000): 119–207.
● Viala, Fabienne, The Post-Columbus Syndrome: Identities, Cultural Nationalism, and. Commemorations in the Caribbean, New York: Palgrave Macmillan, 2014.
● Wynter, Sylvia, “Africa, the West and the Analogy of Culture: The Cinematic Text after Man.” In Symbolic Narratives/African Cinema: Audiences, Theory and the Moving Image, edited by June Givanni, 25–76. London: British Film Institute, 2000.
● ---, “Black Education, toward the Human, after ‘Man’: In the Manner of a Manifesto: Framing a Transformative Research and Action Agenda for the New Millennium.” In Black Education: A Transformative Research and Action Agenda for the New Century, edited by Joyce E. King, 357–359. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2005.
● ---. “Towards the Sociogenic Principle: Fanon, Identity, the Puzzle of Conscious Experience, and What It Is Like to Be ‘Black.’” In National Identities and Sociopolitical Changes in Latin America, edited by Mercedes F. Durán-Cogan and Antonio Gómez-Moriana, 33–66. New York: Routledge, 2001.
● ---, “Unsettling the Coloniality of Being/Power/Truth/Freedom: Towards the Human, After Man, Its Overrepresentation — An Argument,” CR: The New Centennial Review 3, no. 3 (Fall 2003): 257–337.
● ---, “1492: A New World View.” In Race, Discourse, and the Origin of the Americas: A New World View, edited by Vera Lawrence Hyatt and Rex Nettleford, 5–57. Washington D. C.: Smithsonian Institute Press, 1995.
● Wynter, Sylvia, and Katherine McKittrick, “Unparalleled Catastrophe for Our Species? Or, To Give Humanness a Different Future: Conversations.” In Sylvia Wynter: On Being Human as Praxis, edited by Katherine McKittrick, 9–89. Durham: Duke University Press, 2015.
●アリストテレス『政治学(上)』三浦洋訳。東京:光文社、2023年。
●アレント、ハンナ『人間の条件』志水速雄訳。東京:筑摩書房、1994年。
●アーレント、ハンナ『全体主義の起原 2――帝国主義[新版]』大島通義、大島かおり訳。東京:みすず書房、2017年。
●カルペンティエール、アレッホ『ハープと影』牛島信明訳。東京:新潮社、1984年。
●クローデル、ポール「クリストファ・コロンブスの書物」、『筑摩世界文学大系51 クローデル・ヴァレリー』鈴木力衛、山本功訳、126–160。東京:筑摩書房、1960年。
●コンラッド『闇の奥』黒原敏行訳。東京:光文社、2009年。
●中村隆之『野蛮の言説――差別と排除の精神史』東京:春陽堂書店、2020年。
●野家啓一「総論:ホモ・ナランスの可能性」、『ヒトと人のあいだ』野家啓一編、1–33。東京:岩波書店、2007年。
●ファノン、フランツ『黒い皮膚・白い仮面[新装版]』海老坂武、加藤晴久訳。東京:みすず書房、2020年。
●藤永茂『「闇の奥」の奥――コンラッド・植民地主義・アフリカの重荷』東京:三交社、2006年。
●森村進『正義とは何か』東京:講談社、2024年。
●ルケーヌ、ミシェル『コロンブス――聖者か、破壊者か』富樫瓔子、久保実訳、大貫良夫監修。大阪:創元社、1992年。
凡例
・引用文中の亀甲括弧〔 〕は原著者・翻訳者による補足を、角括弧[ ]は引用者による補足を意味している。
・引用文献のうち、邦訳のないものはすべで引用者が原文から訳し起こしている。
著者略歴
中村 達(Tohru NAKAMURA)
1987年生まれ。専門は英語圏を中心としたカリブ海文学・思想。西インド諸島大学モナキャンパス英文学科の博士課程に日本人として初めて在籍し、2020年PhD with High Commendation(Literatures in English)を取得。現在、千葉工業大学助教。主な論文に、“The Interplay of Political and Existential Freedom in Earl Lovelace's The Dragon Can't Dance”(Journal of West Indian Literature, 2015)、“Peasant Sensibility and the Structures of Feeling of "My People" in George Lamming's In the Castle of My Skin”(Small Axe, 2023)など。日本語の著書に『私が諸島である――カリブ海思想入門』(書肆侃侃房、2023)。
