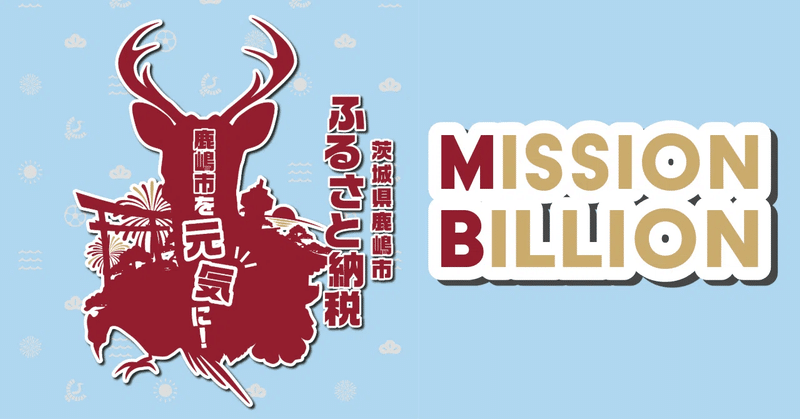
なぜ10億円なのか?MissonBillion①
みなさん、はじめまして。しかふる1号です。

この4月にふるさと納税戦略室に異動となりました。
ふるさと納税は、鹿嶋市でふるさと納税制度を立ち上げた時に担当していて、6年ぶり2度目のふるさと納税担当カムバックとなります。
え? しかふる2号もなんか被ってたけど、1号はなんでタコ?ですか?
鹿嶋市の特産品のひとつ、「鹿島だこ」にちなんでです。
鹿嶋市は →被り物キャラクター推し自治体← なんです(知らんけど
見た目もこんな感じですので、堅苦しい「役所」っぽい雰囲気を脱ぎ捨てて、「間口は広く敷居は低い」ふるさと納税戦略室を目指していこうと思っています。今後とも、よろしくお願いします。
ふるさと納税戦略室に課されたミッション「MissonBillion」
ふるさと納税戦略室には、以下のミッションが課されています。
令和8年度 ふるさと納税寄附金収入10億円
10億円の収入を目指すミッションということで、しかふる2号が
「Misson(使命)Billion(10億円)」
と(勝手に)名付けてくれました笑
令和5年度実績が1.5億円ですので、3年で約7倍にする…
なかなかの、いや、めちゃくちゃハードミッションです。
この「10億円」という数字。
単なる「お金を稼ぎたい」という資本主義的欲求なんかじゃありません!10億円達成しても、我々のボーナスは1円も増えません泣
では、なぜ10億円を目指しているのか?
実はとても意味のある「10億円」なんです。
少し長くなりますので、全2回に分けてお話しさせていただきます。
【今回】なぜ10億円なのか?MissonBillion①
【鹿嶋市の現状】
①鹿嶋市は「鉄の街」
②税金で市を支える「働く世代」の人口が減少
③「働く世代」の人口減少スピードが加速する恐れ
【次回】なぜ10億円なのか?MissonBillion②
【これからの鹿嶋市】
④10億円が必要になる根拠
⑤長期的には洋上風力発電建設による新しい産業による活性化
⑥短期的にはふるさと納税寄附金収入で市民サービスを維持
なぜ10億円なのか?MissonBillion①
まず、鹿嶋市の現状から。
①鹿嶋市は「鉄の街」
鹿嶋市は、昔から鉄鋼業を主幹産業として発展してきており、「鉄」やその周辺産業に関わって生計を立てている市民がたくさんいらっしゃいます。
そんな鉄に関わる市民のみなさんを含め、市民のみなさんが鹿嶋市に納めている個人市民税の金額は、年間約36億円。
市税収入の約32%(令和4年度決算ベース)を占めるものとなっています。

②税金で市を支える「働く世代」の人口が減少
消滅可能性都市が話題になるなど、少子高齢社会の進展が進む日本。
鹿嶋市も他の自治体同様に、人口が減少する局面に差し掛かっていて、特に生産年齢人口という「働く世代」(=税負担をする中心世代)の人口減少が顕著に進み始めています。
一方で、これまで社会を支えてきた高齢者の人口は、増加ないし横ばいの傾向が続きます。この歪な人口構造の状況で、少子高齢社会の進展に伴う社会福祉にかかる経費などが増えている(歳出の増加)中で「働く世代」の人口減少が続くと、市に納めていただく税金が減り(歳入の減少)、現在の市民サービスを維持していくことが困難になってきます。

③「働く世代」の人口減少スピードが加速する恐れ
少子高齢社会という日本全体の動きにより人口減少、特に「働く世代」が減少していく中、鹿嶋市では、この減少スピードが加速していく恐れが出てきています。
上の②でお示ししたグラフには,これによる影響は反映されていません!「働く世代」の加速度的減少の要因の一つが、基幹産業である鉄鋼業の構造改革により、鹿嶋市内にある鉄の製造に係る主要設備の一部が休止になることが見込まれていることです。
この影響により、この主要設備で働いてきた、また、この設備に関わる仕事をしてきた「働く世代」が配置転換などで市外へ転出してしまう恐れがあります。また、「働く世代」≒「子育て世代」でもあるため、従業員の家族ごと市外へ転出するという、人口減少に拍車をかける現象も想定されます。
まだまだその規模は計りきれないものの、鹿嶋市の市税収入が少なくない影響を受ける可能性があると見込んでいます。
鹿嶋市の置かれた現状、難しい言葉も出てきていますが、少しでもご理解いただければ嬉しいです。
次回は、引き続きしかふる1号から、この現状を踏まえて「なぜ10億円なのか?MissonBillion②」そして「これからどうしていこうとしているのか」についてお話しできればと思います。
では、また、次回。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
