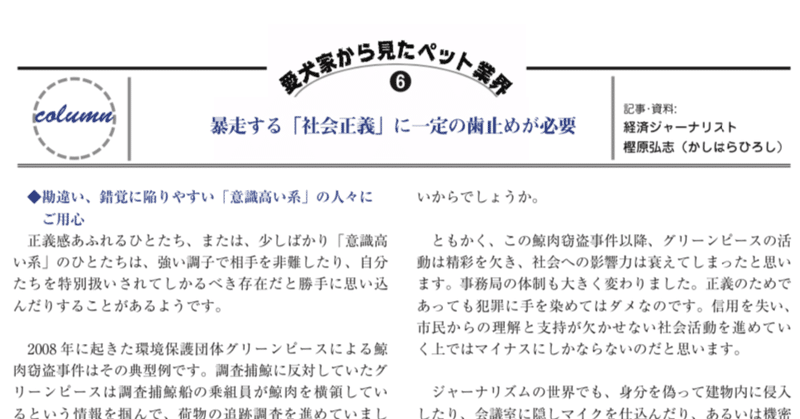
暴走する「社会正義」に一定の歯止めが必要 ①「意識高い」人たちの勘違い
◆勘違い、錯覚に陥りやすい「意識高い系」の人々にご用心
正義感あふれるひとたち、または、少しばかり「意識高い系」のひとたちは、強い調子で相手を非難したり、自分たちを特別扱いされてしかるべき存在だと勝手に思い込んだりすることがあるようです。
2008年に起きた環境保護団体グリーンピースによる鯨肉窃盗事件はその典型例です。調査捕鯨に反対していたグリーンピースは調査捕鯨船の乗組員が鯨肉を横領しているという情報を掴んで、荷物の追跡調査を進めていました。
それは社会正義という目的にもかない、証拠を集めて告発できれば称賛を浴びるはずでした。しかし、結果は逆でした。彼らは青森県内にある宅配便ターミナルに侵入して鯨肉を証拠品として勝手に持ち出したため窃盗罪で逮捕されたのです。お粗末というほかない事件でした。
グリーンピースの組織としての危機管理をアドバイスしているという米国人のボランティア(といっても大きな会計事務所の会計士でした)2人から意見を求められたことがあります。私は「日本のスタッフたちはあまり勉強もしないのに不遜で、見苦しい。日本社会はもとより国際社会でも受け入れられないだろう」という趣旨のことを伝えました。
◆環境団体グリーンピースの失敗~鯨肉窃盗を契機に信用失墜
当時のグリーンピースはずいぶんと思い上がっていて、専門知識など持ち合わせない広報担当者までもが日本のクジラ研究者を平気でバカモノ扱いにしていて不快でした。取材を通して、彼らのそうした姿を知っていたので、鯨肉窃盗事件を聞いても驚きませんでした。彼らが正義のために罪を暴いた英雄であるかのようにふるまうだろうということ、そして日本の世論は彼らの行動を支持しないということが容易に想像できたからです。
調査捕鯨を請け負う共同船舶の運営には問題が多く、水産庁は同社と日本鯨類研究所に事業のリストラを迫ったこともあります。私は1980年代後半の商業捕鯨撤退のころからクジラ問題を取材していて、調査捕鯨が経済的にみても持続困難であることや利益相反が疑われる共同船舶実力者ファミリーに対する支出などを記事にしたことがあります。
グリーンピースやシーシェパードなど反捕鯨団体はこうした情報には見向きもしません。団体自ら告発し、視覚的に訴え、目立たなければスポンサーからお金が集まらないからでしょうか。
ともかく、この鯨肉窃盗事件以降、グリーンピースの活動は精彩を欠き、社会への影響力は衰えてしまったと思います。事務局の体制も大きく変わりました。正義のためであっても犯罪に手を染めてはダメなのです。信用を失い、市民からの理解と支持が欠かせない社会活動を進めていく上ではマイナスにしかならないのだと思います。
ジャーナリズムの世界でも、身分を偽って建物内に侵入したり、会議室に隠しマイクを仕込んだり、あるいは機密文書を盗み出したりして問題になったケースは少なからずあります。誘惑にかられてしまう気持ちもわからないではありませんが、取材方法としては邪道です。「この人なら真実を伝えてもらえる」と信頼される記者でなければ決定的な内部情報に触れることはかなわず、深層をえぐる記事は書けないものなのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
