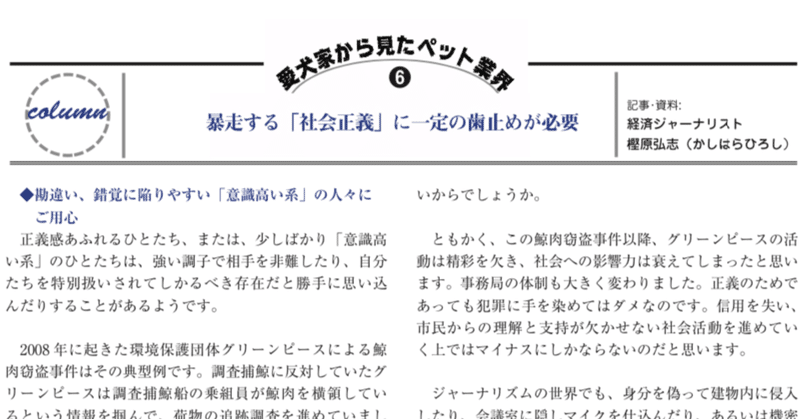
暴走する「社会正義」に一定の歯止めが必要 ③
◆PFIによる広島県動物愛護センター開業、譲渡活動を推進
ところで、8月1日から広島県動物愛護センターが広島空港脇に移転しました。死亡動物の焼却炉などがある旧施設を残したまま、新しい施設を流行のPFI(プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)で建設したものです。設計、建設、そして15年間の維持管理運営費としておよそ14億円(うち維持管理運営費は5.5億円)を投じたそうです。
移転後の最大の使命は譲渡活動の促進です。そのために移転先として交通アクセスがよい広島空港わきを選び、従来休みとしていた土曜日は県、日曜・祝日はPFI事業者が担当して譲渡活動を行います。

いままでは犬猫みなしご救援隊(広島市)、ピースワンコ(ピースウィンズジャパン、広島県神石高原町)、エンジェルス(滋賀県高島市)の3つのNPOに実質的に丸投げして、愛護センターの庭先だけきれいにしているのが実態でした。
広島県の割り切り方は徹底していて、猫の場合、動物愛護センターが公用車で片道60キロメートルあまりの犬猫みなしご救援隊のシェルターまで定期的に搬送しています。殺処分対象になりそうな猫たちを「終生飼養」組として引き取ってもらう見返りとして県が無料搬送を約束したのです。里親への譲渡を前提とする団体登録も免除しています。
◆限界に近い団体への丸投げ、野良犬・猫の蛇口対策重視を
しかし、この丸投げ方式も限界にきているとみていいでしょう。譲渡が思うように進まず、団体側の引き取り能力が衰えているからです。
ピースワンコのシェルターには2千頭以上の犬が滞留していて、殺処分対象の犬の引き取り頭数をひと頃より大きく減らしています。もっと心配なのは犬猫みなしご救援隊で、この団体の指導を担当する広島市動物愛護センターでも猫をはじめとする動物の飼養頭数を把握しきれていません。

犬猫みなしご救援隊への猫の大量引き渡し、無料搬送は知事・副知事も了解したうえで県動物愛護センターの業務として遂行されていますから、本来なら広島県も収容先である救援隊の飼養環境をしっかり聴き取っておく必要もあるでしょう。
数値規制の導入に伴い、ペット業者(第1種)であれ愛護団体(第2種)であれ、動物取扱業者は、従業員数により飼養可能な犬猫の数が制限されています。犬猫みなしご救援隊のような例をみれば、第2種業者にも飼養頭数の報告を義務付ける必要がありそうです。
新しい動物愛護センターが週末や祝日にも譲渡活動をすることによって、少しは個人家庭への譲渡も増えることでしょう。しかし、ハコモノの建設に10億円単位のおカネを投じて里親探しを進めるくらいなら、収容される犬猫が減るよう蛇口を締める対策に資金を投じるべきでした。動物愛護センターに収容される前の野良の犬猫の数自体を減らさないことには殺処分問題は解消しないからです。
例えば、広島県での殺処分ゼロ達成で知名度を上げたピースワンコのもとにはふるさと納税を含めて巨額の寄付が集まり、年間2億円以上もの黒字(収支差)を出しています。県動物愛護センターの予算を上回るほどの潤沢な資金を持っているわけですから、県はこの際、ピースワンコと提携して、その資金をピースワンコの地元神石高原町はじめ広島県内にあふれる野犬を捕獲し、繁殖を根っこから抑え込んでいく事業に投じてみてはどうでしょう。両者の評価はぐんと高まることでしょう。
◆動物に関わる人たちの意識改革が最も大切
私は郷里尾道市で猫の不妊去勢専門クリニックを運営しているNPO法人西日本アニマルアシスト(NAA)を支援していますが、野良猫を手術してくれる獣医師確保に四苦八苦しています。県や広島市、呉市、福山市の動物愛護センターがそうした獣医師を斡旋したり、あるいはセンター自らが手術を行う体制を整えたりすれば、県内で活動する猫の愛護団体の負担はかなり減るでしょう。
ここ数年、広島県の犬猫事情をつぶさに調べてみて、NAAの活動に注目したのは、この団体が野良猫の捕獲、不妊去勢手術に加えて、飼い主や町内会との話し合いを積み重ね、繁殖予防の知識も普及させているからです。
代表の箱崎千鶴さんはNAAの取り組みを「動物愛護活動」とは呼ばず「社会活動」と呼んでいます。目の前にいる犬、猫の命も大事ですが、動物の世話をする人たちの意識を変えて、不幸な運命をたどる犬や猫を生まない社会にしていくことの方がもっと大事というわけです。
愛護団体、ペット業界、あるいは一般家庭の飼い主であっても、動物を大切にするこころやそのための方法を磨かなければならないという点では同じような課題を抱えています。「アイツが悪い」「コイツが憎い」という罵り合いばかり聞いていると、うんざりします。それぞれにもっと謙虚に自分たちの足元を見つめなおすことがあってもいいですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
