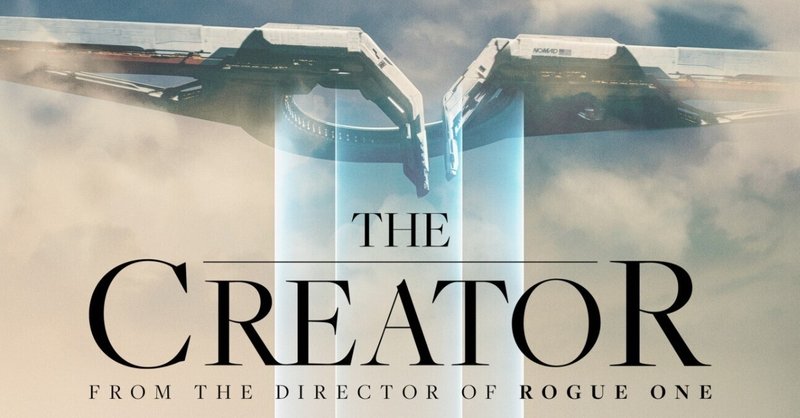
『ザ・クリエイター/創造者』田園とロボットの風景
やってきました『ザ・クリエイター』。こちらは今年公開の中でもひときわ純なガチンコSF映画。しかも新規IP作品なので、これ一作でちゃんと楽しめるんですって奥様。あらまあ素敵ですわね~。それじゃあ行くぜ、あらすじ紹介。
ロサンゼルスで起きた核爆発を機に、AIを危険視する西洋各国と、AIテクノロジーの開発を継続するアジア圏が分断。アジア圏は「ニューアジア」と呼ばれるようになり、西側諸国と10年近く戦争が続いていた。2065年、AI開発者であるニルマータ(=創造者)を探すため潜入任務についていたジョシュアは、ノマドと言われる上空を飛ぶ兵器からの攻撃で妻であるマヤを失うこととなる。5年後、精神的にひどい傷を負ったジョシュアは今もトラウマを抱えながら生きていたが、ニューアジアを勝利に導くとされる新兵器「アルファ・オー」とマヤ生存の可能性の話を聞かされ、しぶしぶながら再びミッションに参加を決める。ハウエル大佐指揮の元、ミッションを開始したジョシュアは幼い少女の姿をした「アルフィー」と出会い、運命に逆らうように彼女と逃避行を開始することとなる――。
まあつまり、あえて雑に説明するとSF版『子連れ狼』です。全体的にテンポが良く、よすぎてちょっと置いてきぼりになるくらいなので、快速列車に乗ってる気分でニューアジアの旅を楽しみましょう。
キャストはジョン・デヴィッド・ワシントンやアリソン・ジャネイ、渡辺謙などで、みんないい感じ。AI役を務める渡辺謙は頭の半分が機械に覆われていて髭の生え際どこいったんって感じですが、機械と化した謙さんを見たい人は必見です。選曲は冒頭のアメリカ軍突入の場面でレディオヘッドの「Everything in Its Right Place」を流したり、ドビュッシーの「月の光」を使ったりとギャレス・エドワーズ監督の趣味がバリバリでております。なんてーかもう自分と趣味が近すぎて少し恥ずかしくなるくらいに。
さて、映画においてSFを語るとき中でも重要になるのは「風景」であり、その世界を構築するディテールと全体像によって私たちはその場所を"異世界"であると認識します。んが、難しいのはそこに「清新さ」を付与することであり、例えば『2001年宇宙の旅』における余分なものを排除し、清潔感のある白を貴重とした空間設計、あるいは『ブレードランナー』における暗く、荒廃した街並み、アジア圏の文化が雑多に入り乱れ、雨が降り注ぐその光景を"美しい"ものとしてとらえたデザイン。そんな私たちが見たことのない、それでいて魔力のように目を釘付けにしてしまう風景にこそSF映画をSF映画たらしめる、物語以上に雄弁な「清新さ」は宿るのです。
でも、上記した作品と全く同じような景色をいま映画内で描いても、おそらくそこに清新さは宿りません。前述した映画がSFの風景をとても魅力的なものとし、機能させていたのは、歴史的な背景も関係していて、宇宙開発競争だったり、資本主義社会やテクノロジーの行く末を案じる時代精神が乗っかることで、多くの人にとってのリアル(とまではいかないにしても)かつ、納得感のある風景になっていたのですから。
だからいまSFにおいて「新しい風景」ってやつを作るのは難しい。時代精神が乗る現在地点というのは捉えにくいもので、高速に行きかう情報や、多様化する文化の中ではみんなにとってのリアルな未来の風景は描きにくいものです。2010年代においてはポストアポカリプスや、もっとすぐ近くにある10年後くらいの近未来像を描いた作品が多く登場していて、つまり「何かが終わったあとの世界」あるいは「すごく身近で手の届く範囲にある不安」みたいなものにSF映画は寄っていた印象。でもそれは結構後ろ向きな未来像でもあり、新しい何かを提示するというよりも、かつて見た光景の焼き回しに近いものでもあります。それはそれで時代ごとに形を変えて語り直すことに意味はあるので良いのだけど、私はもっと作り手の趣味やエゴが出まくってる風景を見たいなあとも思っていた。
では、今作『ザ・クリエイター』はどんな形でその清新さってやつを表現しようとしたのでしょう。
『ザ・クリエイター』が示す未来の世界は「AI対人類」という古くから、ほんとにSFでは古くからある対立構造の世界観であり、なんならちょっと安心感を覚えてしまうほど見慣れた風景だ。でもここで、本作をSFの風景として素敵なものにしてることは2つあって、ひとつが「AIと人間の境界を限りなく薄くしている」点。彼らAIは元々人間であった者の記憶を転写された存在であり、模造人間と呼ばれている。その為思考回路も行動も人間と非常に似通っており、さらに言えば苦悩する表情だったり、あわてて走り出す姿もぜんぜん人間と変わらない。ここでは、彼らAIと人間との境界線は融解しており、パッと見では区別が付かないくらいだ。
そしてもうひとつがタイ、ベトナム、カンボジア、日本、ネパール、インドネシアなどでロケを行い、アジアのどこかにある田園風景の中にロボットやジェット機、近未来のガジェットを溶け込ませ生み出した光景にこそ本作のSF的な風景の良さがある。おそらくイメージの中心はベトナムの農村であり、樹が生い茂り、豊かな田園が広がり、竹屋根で覆われた民家とそこで暮らす人々、そんなエキゾチックな情景に近未来の風景を重ねることで異化効果を演出しています。私がこの映画を観ていて最もいいな~と思ったのはこの部分であり、監督の持つSF像とプロダクションデザインが見事にはまっていました。見方によっては「ベトナム戦争時代をSFの物語に置き換えた話」でもあり、視点としてアメリカを”敵”としている点も特徴かな。そんなわけで私にとってこの『ザ・クリエイター』は物語よりなにより、そういうSFとしての風景にビビットな感動のある映画でした。
まあ、あえてツッコむと、舞台となる「ニューアジア」は2070年という設定であり、超重要なAIの少女が匿われていたり、軍と戦争をしているんですが、施設や住宅がほとんど今と変わらない(なんなら時代がさかのぼってるくらい)のは変だよなあと思いますし、AI側の武器や施設管理における供給原もいまいち謎です。アルフィーの能力としてある「手近にある電子機器を支配下に置くことが出来る」という能力や、「身体も能力も成長するAI」という設定もいまいち活かしきれていないし、アイディアはいいのになんかもったいない。
でも監督が描きたいものはよくわかるんだよなあ。「田園風景にロボットが歩いてる」って光景は観ていて心躍るものがあったし、上空を飛び回る巨大兵器「ノマド」もすごく素敵。なんたって地上をどんどんスキャンしていって標的を補足、狙いを定めてミサイルを投射というSF版「ラピュタ」みたいな存在で、これが登場したら基本的にその場所は壊滅する前兆みたいなもんであり、見た目のごつさも相まってオタク心を刺激します。日本、中国、ベトナムなどアジアの文化や言葉が入り乱れている会話も物語的にはぜんぜん必然性が無いけども、観ている側には十分”異世界感”を演出するハッタリとして機能してますし、そういうディテールに現れる作り手の自己満足が作品にケレンみと愛らしさを与えています。
一応言っておくと私は作り手の自己満足はあって然るべきだと思ってますし、むしろ良いものだと思ってます。というか自己満足こそが映画に可能性を与え、広がりと豊かさにつながるものだと思ってるくらい。だからこの映画は脚本的に多少ガサツなところはあるにしても、監督がやりたい、見せたいSFのビジョンがちゃあんとあって、それだけで私は嬉しくなっちゃうし肯定したくなる。
例えばジョシュアを追う軍人のハウレルが、死亡した仲間の記憶を探るため、30秒間だけ意識を復活させるという倫理的にやばい上、グロテスクかつちょっとコミカルなシーンがある。他にも屠った敵兵の顔を自分の顔として使うことで潜入捜査をしたり、こういうその世界におけるテクノロジーの延長線上にある捜査方法みたいなのは観ていて興奮しちゃいます。っていうか短時間だけ死者蘇生させるってアイディアはイーガンの『万物理論』で同様の場面があったはずなんですが、元ネタはもしかしてそこからでしょうか?でもそういうこと言い始めたら『フランケンシュタイン』とかまでさかのぼれちゃうか。
あと、この映画時限爆弾のシーンがやたら多く、銃で撃たれた!→なんだ大丈夫だった…→時限爆弾だった!→ボカーンみたいな場面が2、3回あります。精鋭部隊であるはずの軍人がこれで死ぬシーンを何回も見せられるともはやギャグにしか見えんなあと思ったり。いやというかギャグですよね監督?
でもやっぱりこの監督はビジョンにしっかり欲望と理想があって信頼できるよ。ジョシュアが最後にたどり着いた場所で起こる奇跡は、タイトルで一瞬見せた美しさと重なり涙がこぼれたもん。
これはこの世界に住む人々が自由になるための旅と戦いの物語であり、その意味でジョシュアもアルフィーも自由になれたのだと思う。そういう希望を描いた話であり、SF愛ほとばしる愛すべき映画。私にとって『ザ・クリエイター』はそんな作品です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
