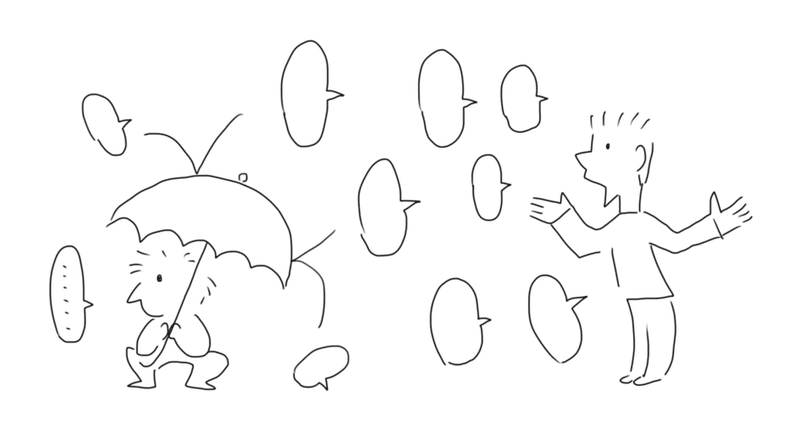
終わりなき謎の者たちの対話劇:『闇の自己啓発』書評
「私」は、何もかもわかるような光の下にいるのが耐えられなかった。生で始まり死で終わるような配役「私」の台本が、どうもしっくりこなかった。だから闇を求めた。それが魔の手でもよかった。「この世界から外へと取り去ってくれるあの異様な手」(ひでシス、note公式による本書リリース記事に寄せたコメントより)。それに半ば身を委ねてでも「外」を求めた。けれど「私」は全き闇にも耐えられないのかもしれない。――闇は「私」と相容れないのか?(これは逆転させてもよい。光は「私」と相容れないのか?)
――江永泉「補論 闇の自己啓発のために」
前置き
友人・知人がいくつか書評を公表して、それに端を発した小論戦も終わったあとだから、なんだか遅ればせな感もあるのだけど、よく考えたら発売日(1月25日)から1ヶ月すら経っていませんでした。
周囲で起きた直近のできごとをふり返ると、この書評への反響を受けてこの書評が書かれ、さらにこの記事が書かれ、その応答としてこの記事が書かれました。前後の経緯はこのまとめに詳しいです。
ざっと調べたところ、それらとは別のところで、発売日に書かれた書評もあります。2日後には出版取次のオウンドメディアで書評が出ていて、私的な思い出を書いた記事もありました。発売前に話題にしていた個人の記事も、大手メディアによる内容紹介、著者コメントと読者のTweet紹介もありました。
Amazonレビューには今夜(2021/02/12)時点で2件の投稿があって、どちらもしっかり字数が割かれています。hontoにはブクログと連携した投稿が2件表示されて、ブクログ本サイトには5件(4件(紙の本)+1件(電子書籍))。読書メータ―には29件(23件(紙の本)+6件(電子書籍))もあり、これらの読書記録サービスでは今後も感想投稿が増えるでしょう(*1)。紙誌の書評はもう少し先の掲載になるだろうし、すでに3刷に達しているという本書には、これからしばらく反響・論及が続きそうです。
(版元による書評の依頼も含めた)利害関係者ではない立場で、いまのうちに感想をまとめておくと、だれかしらの参考にはなりそうです。備忘も兼ねて書評を書きます。
これまでの感想
発売まもない書籍の既往論点をまとめるのは無粋ですから、ここでは「読者の感想」からキーワードを拾ってみます。本書は次のような言葉で語られています。
たとえば、健康/不健康、正常/異常、狂気/正気、有害/無害、資本主義/希少性/オルタナティブ、セルフマネジメント/管理、都合のいいファクト/不都合な現実、(非)生産性/無価値/無意味、過剰/剰余、破壊/逸脱/外部、幻想/夢/迷妄、成長/成功/学び、強者/弱者、生きづらさ/行き詰まり、人格改造/自己変革/自己実現、逃走/闘争/脱出/解脱/EXIT/反逆、ぶっ飛んだ/驚く/笑う/興味深い/癒やし、素直/けなげ/真面目。
もちろん、それぞれに複数のコンテクスト(文脈と背景)があって、雑駁に要約した解釈を付すつもりはありません。よくある誤解や牽強付会(こじつけ)も散見されますが、その訂正はこの記事の狙いではなく、さしあたっては企画発案者の江永泉さんによる「『闇の自己啓発』の遠回りな紹介(本の「第一印象」に基づくと見られる、幾つかの質問への応答)」をすすめるに留めます。
この記事の位置づけ
ひとつ言えるとすれば、これまでに書かれた論評は、主として本書の「内容」を――より正しくは、登場人物たちの「発言」をめぐるものです。この書評では切り口を変えて、本書の「体裁」や「構成」について書きます。
せっかく印刷書籍として刊行されたのだし、テキスト投稿プラットフォーム(note)に掲載された「発言・内容」が、どのような編集・装幀を経て、その含意を変質させたのかに注目したいからです(ネタバレ回避の意図も少しあります)。
思い出話や内心の叫びは、文章をおもしろく読ませる技術のひとつだし、未読者の購買意欲をそそるのにうってつけの方法だけど、(狭義の)書評(review)というより(広義の)感想(sentiments)に近い気もして。この記事では(なるべく)禁欲するつもりです。油断すると、すぐさま持論の代弁めいちゃうしね。
どのような装いの「書籍」か
ぼくには造本の専門知識がないのですけど、本書の表紙には艶っぽい黒(漆黒や濡羽色方面)ではなく、燻ぶった黒(消炭色や鈍色方面)が使われていて、収録内容がまったくの暗黒ではないのだろうと予期させます。
文字まわりは金文字の箔押し印刷で、著者名、題名、英題、版元を載せる簡潔なデザイン。高級感のある、けれどもカジュアルな価格帯のレターセットを思わせます。
題字は「闇 の 自 己 啓 発」と字間がたっぷりとられていて、中央にぎゅっと寄せる組み方よりも、横への広がりを――書物の「外」へ出ようとする動きを――ほんのりと感じさせます。
裏表紙や両そで、カバーを外した背の文字は、くすんだ銀っぽい灰色。とびらは黒地の紙で、文字は銅色でしょうか。どちらの配色も光沢はなく、「なんとなく、キラキラ」した質感からは縁遠い。
微妙なテイストの調整
かといって、上場前のヴィレッジバンガードが体現したような、メジャーにマイナーな感性をくすぐる禍々しさはない。(たまたま)同時期に買った『「ディズニー ツイステッドワンダーランド」公式ガイド+設定資料集 Magical Archives』と比べると明らかで、『闇の自己啓発』は、邪悪で・魔術的な・野蛮さといったスタイルではなく、シックで・モダンな・クラシックといった装いを目指したようにみえます。
傍証が足りなければ、「闇の自己啓発会」のヘッダー画像におどろおどろしい絵画のトリミングが採用されていることや、note自体のページデザインがニュートラルな無色を志向していることに照らし合わせてもいいでしょう。
つまるところ本書は、その出自こそ「オンライン連載されたヤバい読書会の記録風」でありながら、印刷出版のための編集作業を経るなかで、原作の持ち味を損ねないようにしつつも、微妙なテイストの調整が施されているわけです。
言わば、この「書籍」は、読者に――もちろん書評者にも――複数人の制作工程によって生まれた細かな作為について、大なり小なりの注意深さを求めていると分かります。少なくとも、大味な要約とか、雑駁な論及とか、けんか腰の批評は歓迎されない感じがする。
「画面」を染める・汚す・縁どる
そう思って本文をめくろうとすると、ホワイトノイズのような「染め」が天・地・小口に入っていて、途中とちゅうにブラックなページが挟まって、序盤と終盤だけがやけに白く感じる。
ちょっと先取りして本文デザインを見ると、全6章ある「読書会」の四隅は墨汁をこぼしたように「汚され」ていて、パラパラめくると機械的なテンプレートのくり返しだと分かります。
対照的に3回の「雑談」は、見開き全体が侵食する闇のような模様に「縁どり」されていて、紙色もグレーだから、どことなくほの昏い。
無地の「まえがき」と「補論」がその分だけ明るく感じられて、だけどその明るさは、よくある・ふつうの色彩なのが特徴的です。
これらの仕掛けは、それに気づいた読者に、本書がどういったリズムで読まれるべくして構成されたのか、それとなく示してくれます。ストーリー展開の抽象的な起伏が、意図されたパターンの反復によって伝わってくる。
きりのいい長さのシナリオ
本書の目次はまえがきで始まり、3部構成(各2章ずつの全6章)の本編と、合間に3回の雑談が挟まって、最後は補論(参考文献付)で終わります。その11本のテキストが、謝辞と参考文献に行きつく構成です。
近年の連続ドラマ/テレビアニメは全10話+αで完結することもしばしばで、それを思うと本書にも、「各話ごとの独立したエピソード」だけでなく、「全体を通じて語られる大きなシナリオ」がきっとあって、そこを読みとるかどうかも読者の裁量でしょう。
映画が写真でないように、長文は短詩ではなく、座談は箴言ではないわけで、片言隻句を切り出して何事かを語ろうとするのは、あまりにありふれた情報消費のスタイルになってしまったけれど、よく考えたらお行儀が悪いよなぁ、と思わせる。
むしろ繊細な「明暗」の設計
ある1日になぞらえると、昼下がりで始まって明け方で終わるみたいな明暗があります。はっきりと光ることも、すっかり暗くなることもない、都会のプライベートな空間がはめ込まれた「画面」の設計。
それがだれの着想であれ、こう読むのは不自然ではないでしょう。役所暁さん(原作である「闇の自己啓発会」の構成・編集担当)の「まえがき」と、江永泉さん(読書会の発起人)の「補論」には、本書の構成において、メインコンテンツの読み心地をある狙いにフィットさせる役割が与えられている。
その狙いは、上述した「本の姿」からも察せられるように、過激さ、乱調、猥雑ではなくて、無難さ、繊細、整然といったニュアンスで形容されるべき何かであるようです。そんなの「読めば分かる」ことかもしれませんが。未読の方も多いでしょうから、忘れないうちに書いておきます(*2)。
濫読者に親切なエディトリアル
なかなか「発言・内容」の話にたどり着けないのですけど、部立て/章立てごとの「構成」にもふれておきます。本書の中扉には部立てごとに3つのシノプシスが付記されていて、たとえば第1部にはこう書かれます。
法の支配が及ばないインターネットの暗黒領域・ダークウェブ。共産党が強大な権力をふるう監視国家・中国。両極端な2つの「社会」の様相が合わせ鏡となり、人間の作動原理を映し出す。議論は白熱し、「幸福」の定義が練り直される。
――本書より
どのシノプシスも140字に満たない長さで、極端なことをいえば、これらを読むだけでも、本書を「読んだふりをして堂々と語る」ことはできそうです。気になって買ってはみたけれど、1冊すべてを読み通すのはしんどいと感じる読者にも、まともに読むつもりはないけれど、流行っているからひと言もの申したい読者にも、親切なつくり。忙しい濫読者向けの気配り。
そもそも原作はいまだにnoteで全文無料公開されていますし、「課題図書について複数人で思いつきを語り合う」という企画性質からして、「何が語られたのか」を仔細に・厳密に・精読する類いのテキストではなさそうです。
本書の――と当たり前のように言っていますが、こう言えるのも、本書が「18本のアーカイブを工夫なしに製本しただけのもの」ではないからで、読みどころはむしろ、未収録回も含めて、本書がどういった編集の手つきで生まれたかのほうではないでしょうか。
たどれるキュレーションの足跡
というわけで、テキストアーカイヴから「のれん分け」以外の投稿のタイトルを抜き出して、本書に「章」として収められた回に「★」と「収録順」をつけると、こうなりました(公開日が新しい順)。
・愛を問い直す術はまだあるか? ベルサーニ+フィリップス『親密性』読書会【闇の自己啓発会】(★6)
・モラルを捨てたら儲かるか?『不道徳な経済学』読書会【闇の自己啓発会】
・ヒトに意識は必要か? 稲葉振一郎『銀河帝国は必要か?』読書会【闇の自己啓発会】(★4)
・生きる苦しみよ、こんにちは。『現代思想 2019年11月号 反出生主義を考える』読書会(★5)
・「幸福」とは何か?『ジョーカー』と『幸福な監視国家・中国』読書会【闇の自己啓発会】(★2)
・そこに世界を革命する力はあるか?『ラディカルズ 世界を塗り替える〈過激な人たち〉』読書会【闇の自己啓発会】
・闇の自己啓発会『ルポ中国「潜入バイト」日記』読書会
・著者と読む『ニック・ランドと新反動主義』読書会
・ゼロ年代から加速して 海猫沢めろん『明日、機械がヒトになる』読書会(★3)
・著者と語る『ダークウェブ・アンダーグラウンド』読書会 【闇の自己啓発会】(★1)
・品川の中心で不平等を語る 『不平等との闘い ルソーからピケティまで』 【闇の自己啓発会】
――江永泉「闇の自己啓発会」より
本文を読んでいなくても、本書には「時系列順」とは別の編纂意識が働いていて、主題の統一感や移り変わりを考慮したうえで、毎回の開催記録がいくらか再構成されたのだろうと察しがつきます。
もしも掲載順を(★6)から(★1)に逆転させていたとしたら、反-社会的な親密さについての語りが、没-人格的な無法による支配をめぐる語りで締めくくられて、本書の読後感はずっと殺伐とした、荒寥たるものに変わったでしょう。
あえていえば、そのほうが読者は、仮想敵たる社会通念を、ためらいなく唾棄できたのかもしれませんけどね。だけど本書はそうならなかった。
死なないための暇つぶし
営利事業たる出版ビジネスであることを抜きにしても、本書の構成には、編著者それぞれのキャラクター(人柄、役柄、持ち分)を中和させ、極端にふれないような減速機のようなものが組み込まれています。致命的な危険を防止するために、安全への配慮が行き届いたエンターテインメントなのだと期待させる。
それを刺激的だと感じるか、物足りないと思うかは、つまるところ体験者によってちがうとしか言えないけれど、この時点で――本文についてひと言もふれなくても――言えることはあるのでしょう。
おそらく本書は用意周到に作られた"大人しい"フィクションであって、生死を賭けて真剣に直面するようなものではなくて、もっと気楽に、深く考えずに、話半分で、切れぎれに経験してもいいのだろうということです。折りしも、ぼくたちの人生がそうであるように。
登場人物を「擬人化」する注釈
本文を開いてみましょう。そこには何が書かれているか。けば立った刷毛でざっと塗ったような太い線を装飾とした見出しがあって、脚本によくある人物名の表記がずらりと並んでいます。
共著者と同じ氏名を与えられた4人の登場人物(キャラクター)は、それぞれの立場と狙いに沿った台詞を「話すように」語ります。ときどき組み込まれる挿画は、ちょっとした豆知識と控えめな自己主張に用いられ、4人のキャラクター設定をそれとなく伝える小道具。
そして、語釈にしては長すぎる傍注が次々と挿入されるから、しばしば不穏で・不可解な本文に、冷静と良識の体現みたいな注釈という関係が話者ごとに成り立ちます。たくさんの注釈が、解読でも、風刺でも、余談でもなく、文脈の補いに徹することで、本文の演技めいた語りがいっそう際立つ。
選びとられ、作られた「声」
言い換えれば、登場人物たちの語りが本当の・現実の・生身の「発言」でないことは明らかです……というのは言いすぎか。とはいえ少なくとも、即興の・肉声の・フリートークに似せて/寄せて書かれてはいませんね。
もちろん、ライブっぽい言い回しも書き込まれているけれど(うれし~/ハァ~~~/ひえっ/うーん/ふふふ/あっ)、朗読には適さない表現(!!??/→/(!))がためらいなく使われてもいて、それぞれの台詞には作劇上の役割が(多かれ少なかれ)しっかりと与えられています。
成立経緯を知るに、各章の課題図書を扱った読書会はじっさいに対面して行われたようですが、この記事でぼくが注目するのは、そこでの会話は本番セッションのためのリハーサルみたいなもので、note連載の当時から加筆・修正・再編集が当然に許容されていたようだという作業プロセスです。
温かくつづく、冷たい信頼
記録し損ねた好演があり、カットされたNGシーンがあり、追加されたシークエンスがあって、紆余曲折を経てできあがった完成形としてのテキストを、さらに再加工して「売りもの」に仕立て上げる。
この手続きは、書かれた言葉を(すべてが実在のできごとではないという意味で)まったく信頼できないものに変え、同時に(存在を認められた唯一のドキュメントであるという意味で)すべからく信頼すべきものに変えるでしょう。
どう言えばいいかな。たとえ思い残すところがあったとて、書き手は「それでいいのだ」と思って書いたのだから、読み手もそのつもりで読むほかないというか。密着でも絶交でもなく、その場だけの冷たい信頼を、しかしなるべく温かく持ち続ける態度で臨まなければ、一発勝負の緊張感が失われて、いつまでも終わらない「ないものねだり」にしかならないというか。
この距離感は、読書にさほど愛着のない方にとっては「別に珍しくない」かもしれません。だけど、あるできごとを熱狂も軽蔑もしない姿勢で読むというのは、本書の場面設定である「読書会」のポリシーとも通底していて(作中におけるスナッフフィルムの扱いが典型例)、構造的にみると、「作中人物のできごと」と「読者の身に起きるできごと」が徐々に重なる、ありていに言えば「同じ目線に引き込む」ような作りです。
言葉はどうしても沈黙できないから
「ありがたいお話」でも「くだらないイタズラ」でもなく、登場人物たちのふるまいに、「共感/反発しやすい物語」に仕上がっている、とも言えるでしょうか。
少なくともぼくは、一つひとつの発言を厳粛な思想の表明としては読まなかったし、そうさせるほどの強度は本書にないでしょう(マシュマロに鋼鉄の硬さはないように)。
書かれた言葉の往復に目を向けると、本書における登場人物たちの役割は章立てごとに少しずつちがって、その場に持ち込まれる固有名詞の「座持ちのよさ」までもが見えてくる。
あくまで一例ですが、江永さんが振り出し、木澤さんが広げ、ひでシスさんが変化をつけ、暁さんが受けるとか。ひでシスさんが進行して、暁さんが膨らませて、木澤さんが脱線させて、江永さんが要約するとか。
そういう関係の変化とバリエーションこそが、本書を(音声や映像のライブ配信やアーカイヴ視聴ではなく)固定された印刷物として消費するときの「読みどころ」なのかもしれません。
仲良くケンカしな?
対話の役割分担がなんとなく出来上がっては崩れていく。その場面の積み重ねで、かろうじて「お話」が続いていくようなところがある。だれも何も言わなくなったら、それこそ「お話」になりませんしね。
座興のために、うっかりしたことを言うひとも現れるでしょう。露悪的にふるまうひともいるでしょう。横道にそれたり、遊びたくなるひとも。そういう「憂さ晴らし」が記録された著作だから、大げさな宣伝文句に囚われなければ、いくばくかの時間を過ごせる「息抜き」としてたのしめる。
逆にそれ以上のことを――例えば革命のファンファーレを――求めるのは、過度な期待というものでしょう(*3)。
「自称変わり者の寝言」から20年
実用的な読書記録として本書をだれかにすすめるなら、少数の例外を除いて、多くの参考文献が21世紀以降に日本語圏で流通していることに価値を見出だせます。ちょうど著者たちが(つまりはこの記事の評者が)生まれた頃に、『読書の快楽』『活字中毒養成ギプス』がそうしたように、ぼくらの時代の読書案内として。
もっとも本書は、20世紀後半に不定期に流行ったらしい選書企画とはちがって、歴史に残るすぐれた古典に溺れることではなく、検索と連想によって紐付けられた類書の網の目をたどり直すことに重きが置かれています。
終盤にかけて「自己への配慮」がゆるやかに主題となるように、登場人物たちの対話のベクトルも、「浅く・広く・開かれ・戯れる」ことよりも、「深く・密に・きちんと・まとまる」ことに向かう。
国家を越える巨大な情報流通プラットフォームが普及しきった現代にあって、合理的な労力で実現可能な「超人」のあり方を探るなら、きっとそのほうが戦略的に妥当なのでしょう。分かりやすい「人でなし」ではなく、謎めいた「変わり者」として、ちゃんと/勝手に生きること。
「自己」のオーナーシップを手放さ(せ)ない
そう読むと、本書の「まえがき」と「補論」が、「人形」「台本」「テンプレート」「開花」といった言葉を選んだことは示唆的です。何しろ本書では、自己(私的なもの)の問答、管理、変革、放棄、救済ではなく、あくまで「啓発」が、単独ではなく複数人で――ごく小さな大きさの社会で――試みられているわけですから。
ひとの社会が「自己」という登場人物に何らかのアイデンティティ(苦しみ)を負わせてくるとき、そこで交わされるのは無数の与えられた言葉であって、その解釈と実演はそれぞれの「自己」に委ねられているのだから、「自己」を形づくる言葉を擬人化し、客体化し、形式化して、多少なりとも思いどおりに操作できれば、いくらか間接的にではあれ、「自己」のオーナーシップ(よろこび)を手にしたままで、その「自己」が及ぶ限りのところを、ほどよい明るさ/暗さに保ったまま、事実らしさと謎めきのグラデーションのなかで、思いのままに書き換え/読み換える力が身につくのではないか。
ぼくなりにまとめ直すと、本書の主要人物ふたりはそのような考えを述べていて、それが安心できる「留め金」のようになっています。「ぎょっとするような話」を次々と放り込んでも、「話し合いの場」が破綻しないための。
これは本書への不満ではなく、ぼくの近頃の気がかりに由来する雑感ですが、身近なひとに恋して、平凡に老いて死ぬのは、本当にむずかしいですね(*4)。
*1:ブクログと読書メータ―のレビュー件数を加筆しました。「電子書籍」の検索結果だけを参照していました。「紙の本」の書評なのに……凡ミス……。ハインリッヒの法則めいたことを言えば、1件の重い書評の背後には29件の軽い感想があり、その背景には300件の読了記録がありえます。いわんや発行部数をや。
*2:ちなみに、この記事のタイトルはこちらとこちらが元ネタです。本書内で主題のひとつとされ、刊行後に著者たちも付言するように、「闇の自己啓発会」は、通俗的にホモソーシャルな集まりではありません。個人の属性をいったん不問にする曖昧さ(The Obscure)が認められていることも、原作(および本書)の落ちついた雰囲気を形づくっています。
*3:書評者はいぬのせなか座という集まりの一員で、「編集著作物としての座談・鼎談」という形式が好きなほうだというバイアスがあります。
*4:2月13日に「すばらしき世界」を観た影響下で書かれた一文です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
