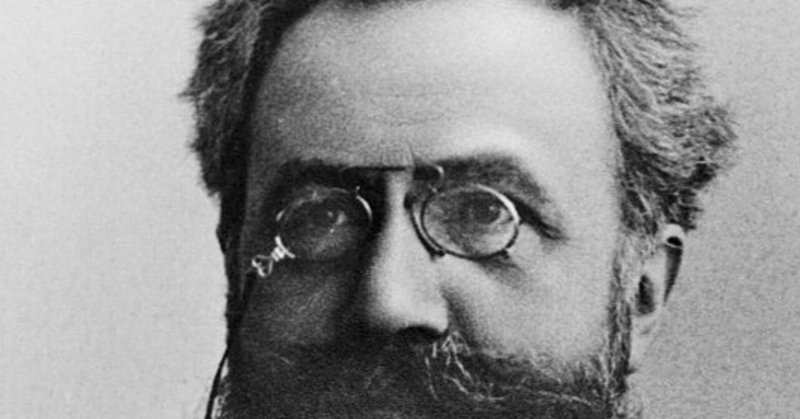
美術鑑賞の混雑対策
先日とある展覧会で、コロナ禍前かと思うぐらいのすごい混雑を経験した(なに展かは想像できると思う)。あれだけの混雑は個人的にも久しぶりだったし、観に行った人によっては「混雑のせいで楽しめなかった⤵」というような報告も聞く。毎週何かしらの美術館に通っているようなタイプだったら「まぁ、そういうこともあるかな」と割り切ることもできるが、半年に一回ぐらいしか行かない、もしくは行けないという人であれば、その一回が楽しめなかったというのはかなりの致命傷だ。
現実問題として人がいる以上、いかんともしがたいケースもあるのだけど、対処する方法が全く無いわけでもないと思う。使う使わないは一旦置くとして、ここでは私の方法を紹介してみることにしたい。
①文字情報を読む時間を減らす。
ある学芸員さんによると、一般的な企画展の場合、文字情報だけでも5000字ほどあるのだという。原稿用紙にすれば12.5枚、小説ならショートに分類されそうな分量だが、そこに作品という情報も加わってくるため、特に混雑している状況で、その全てに付き合うのは現実的にはなかなかキツい。制約下でより濃厚に楽しむためにも、時間をかけるべき箇所とそうではない箇所を選別し、前者に時間を費やすといったことが必要になってくる。
たとえば、美術館の最初にある主催者、作品を貸し出している美術館の「ごあいさつ(挨拶文)」を、どこまで丁寧に読む必要があるのかどうか。確かに秀逸な挨拶文自体は存在するけど(例えば「河鍋暁斎の底力」(2020、東京ステーションギャラリー))、その一方、明日には忘れてしまう類の、社交辞令のようなコメントも決して珍しくはない。
そういうものを一字一句付き合う必要は無いと思っていて、そういうのを全く読まないまでしなくても、流し読みで済ませてしまうということは(混雑しなくても)よくやる方法である。
もう一つ「必ずしもしっかりと読まなくて良い」と思うのは、(回顧展などの場合)作者の年譜などの年表だろうか。これも事前に調べておけば済むことだし、図録に同様のものが掲載されることもある。ホームページに大雑把な情報が載っていることもあるし、足りないと思うのなら適宜コトバンクやWikipediaで補足する方法もある。こういう風に前提となる知識があれば、展覧会の場で年譜を読む時間もかなり省略することができる。
その他、解説パネルでも、気になった作品のパネルのみをしっかり読み、そうでない作品はやっぱり流し読み・斜め読み…なんていう感じでスキップする方法もある。細々としたルールは各自で考えてほしいところだけど、いずれにせよ通常の読書と同様、展覧会においても緩急をつけることがポイントになると思う。
②10〜15分程度で展覧会を一周し、二周目以降は「どうしても見たい作品」にのみ集中する。
10〜15分というのは目安だが、私の場合、混雑の有無を問わず、ほぼ全ての展覧会でこの手法を用いて鑑賞している(疲れている場合、またはよほどつまらない展覧会を除き、少しでも考えさせられる、面白い萌芽のある展覧会なら大小を問わず2周することにしている)。興が乗ってくれば3周、4周となっていく可能性も全くないわけではない。
空いている展覧会であれば一周目でも30〜40分費やしていたりもするけど、混雑している場合は滞在時間も短縮傾向になるため、一周する時間はより短くなっていくことになる。「どうしても見たい作品」というのは、多くて全体の10%というところだろうか。100点あれば10点、3周目もあるとすれば1,2点程度の作品に絞られるところになるのかと思う。
①で述べた方法は、読書で言うところのいわゆる「拾い読み(スキミング・スキャニング)」に近い方法で、この方法を文字情報のみならず作品・資料にも適用していく…というところだけど、この手法について抵抗感を感じる人も少なくないかと思う。「一般的」にはそうではないからだ。
美術館で人の流れを見ていると、前述の挨拶文をはじめに、最初からじっくりと見て回るという人が多いというか、むしろそれが「一般的」だと思う。「鑑賞順序はありません」「空いている作品からご鑑賞ください」と係員が呼びかけても、「順番に見て回りたい」と考える人は(印象としては)だいぶ多い。また、美術展を1周で終わらせてしまうことも「一般的」で、しかも混雑状況ではそうせざるを得ないこともある。
同行者の都合などもあるし、こうした「一般的」な鑑賞を頭ごなしに否定するつもりもないけれど、「忘却曲線」で知られる心理学者のエビングハウスによれば、1時間ほどで記憶の半分以上(ネット情報によれば56%)は失われていくのだという。1日後だと実に3分の2(同66%)だ。美術鑑賞は「一般的」には視覚のみで行われ、さらに混雑という無意識のストレスを踏まえるとその「忘れやすさ」はさらに上がるものと考えられる。
エビングハウスの忘却曲線は復習の重要性を説いたものとして現代のビジネス書なんかでも援用されたりする。しかし趣味的な美術鑑賞の場合、受験勉強のように丁寧な「復習」する機会が無い以上、「忘れてしまう作品」というものがどうしても存在する点を念頭に置く必要がある。「一つ一つの作品を均一に鑑賞する」「1周のみで鑑賞を完結する」という「一般的」な方法は、この「忘却」が存在する以上、あまり良い方法であるとは思えない。
そして、「忘れてしまう作品」に「忘れたくない作品」と同じぐらいの時間をかける必要は、私はあまり無いと思っている。それならば30分、40分と、それにかける時間をもっと費やしていたい。そして私の場合、記憶・印象にはっきりと残るのは間違いなく、そういう経験をした展覧会についてである。
③美術館の訪問時間を検討する。
これはごく割と普通な方法だと思う。一般的には平日の午前、または閉館時間間際が混みにくい時間帯として言われがちである。もちろん平日の午前は予定が取れないなど、各人の事情があることも承知しているが、これに関しては私としても「頑張って」としか言えない。
あと、混雑回避の観点からはチケットの事前予約も大事だと思う。チケットサービスによっては予約変更不可だったりの制約もあったりするが、確実にこの日、この時間に行けるという確約が取れるのなら、積極的に事前予約は済ませておきたい。
最後にキワモノな技として、東京都美術館でゴッホ展(2021年)が開催されたとき、過去の経験から間違いなく混むことが予想されること、しかし私が朝に弱く、神奈川県の少し遠いエリアに住んでいることもあり、グッドコンディションで開館直後に入館することは難しそう…ということで、上野の美術館にほど近い鶯谷の東横INNに一泊したことがある。ホテルから美術館までは15分ほど、普段とは明らかに違う新鮮な感覚で、開館30分前である9時過ぎに美術館に到着することができたものの、それでも私の前に10人ほどの「先客」がいたことを覚えている。
🙇よろしければサポートお願いします🙇
