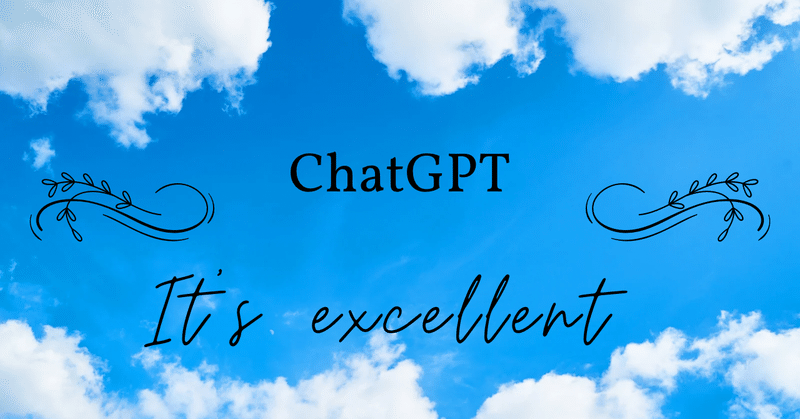
ChatGPTと問題意識を共有して思うこと。
憂鬱じゃ無い時に(ワクチン接種なさった後とかは避けて下さると嬉しいです)……。
私の問題意識と取り組みと、ChatGPT Plusと話したことは、環さんも興味を持って下さるかもしれないので、リンク貼って通知を飛ばします。
もちろん、誰でも閲覧できる場所に公開するのだから、どなたが読んでくださることも歓迎します。

言語生成AI、とくにChatGPTは、OpenAI社の方針(ガイドライン)を元に、ユーザーとの対話を成立させるためにコダマのようなことをしている気がします。私が使うと、ものすごく偏るので。
言語生成AIの「お告げ」を面白がるのではなくて、ここに人とAIの違いや社会問題を解決する宝の山があると、私には思えるのです。
User(※私の発言)
PCは1998年から、ネットは2000年から利用しています。ユーザーとしてだけでなく、サブスキルでLinuxの初歩と、cgiを書いて簡単な掲示板を作る程度のことは学習しました。DBを扱う際に、個人用途ではなく、不特定多数に公開することはセキュリティの懸念を感じたので、それより複雑なことは覚えませんでした。また、ECサイトのお客様窓口で、一次対応から管理職まで(例えば、エスカレーション対応は引き受けても、私の対応へのエスカレーション対応をしてくれるポストは存在しないので、上司や上長はいるけれど、自社の会長を出せと言われても私が最終的な対応をしました)経験があるので、サービス提供者の視点も持っています。また、2000年代初期はネットで買う方が少なかったので、ブラウザやアカウントやログインの説明から行い、数日かけて、数回説明するとご自身で買い物ができるようになるお客様も多く見てきました。これらの経験から、高齢者のデジタルデバイド(社会からは、存在しないように見える)に課題を感じています。
こうした話題を対話したいけど、いいですか?
ChatGPT
もちろん、お話ししましょう。高齢者のデジタルデバイドに関する課題は非常に重要で、多くの国や地域で関心を持たれています。あなたの経験から、具体的にどのような課題や懸念がありますか?
User
70代の親(専門医が主治医でみてくださっていますが、認知症ではありません)は教育を受けており、社会人経験も豊富ですが、UIが読めません。私が翻訳しないと分からないため、スクリーンショットに印をつけて教えています。これは、大多数にとってはわかりやすいUIが、前提を欠く高齢者にとっては不親切といえそうです。しかし高齢者が分かる水準に合わせると、大多数はUIがうるさく感じるはずです。
また、現金で生活をしてきたので(奨学金と住宅ローン以外、借りた経験がありません)、キャッシュレスの豊富な支払い方法や、どのタイミングでお金が出ていくのかなど、ネットリテラシー以外の、金融教育も必要になったりします。
ChatGPT
あなたが指摘する問題は、多くの国や地域で高齢者が直面している実際の課題です。UI/UXデザインの進化については、新しいテクノロジーやサービスを使い慣れている世代を中心に考慮されることが多いため、高齢者やテクノロジーに不慣れな層が取り残されるリスクが確かに存在します。
UI/UXの問題: 高齢者にとっての利便性を考慮すると、シンプルで分かりやすいUIを提供する必要があります。ただし、これが若年層やテクノロジーに慣れているユーザーにとっては退屈や冗長に感じる可能性があるため、バランスを取るのは難しい課題です。一つの解決策としては、アプリやウェブサイトが「初心者モード」や「シニアモード」といった使いやすさのレベルを選択できるようにすることが考えられます。
金融リテラシーの問題: キャッシュレス化が進む現代において、特に高齢者層には、新しい支払い方法のメリット・デメリットや、それに伴うリスクについての理解が不足していることがあります。金融機関や政府が主導して、キャッシュレスの教育やワークショップを提供することで、安心して新しい支払い方法を利用できるようになることが期待されます。
あなたの親のような高齢者がデジタル環境での活動をより快適に、そして安全に行えるよう、社会全体でのサポートが必要です。
User
UIに関しては、キャリアがらくらくフォンのようなUIを提供しています。AQUOSなどは簡単にホーム画面を切り替えられます。美しくないし、大きなタイル風のアイコンに役割を割り振るのは70代自体が嫌がります。
それよりも、私が厳選したアプリやアプリの並びも配慮したホーム画面の方が使いやすいようです。
高齢者は社会人経験が50年くらいあるため、多様性が高いとも言えます。新しいことを覚えにくい世代でもあるから、彼らのバックグラウンドを理解して、彼らに分かるようにカスタムすること、オーダーメイドにすることが、社会の財産になると思います。
同じ70代でも
元教師のAさんと
元魚屋さんのBさんと
元コンビニ経営者のCさんでは
「分からないこと」が異なるはずです。
50代と比較して70代は時代の変化に対応しにくくなります。例えば、大正生まれの祖父は、自動改札機の導入で電車の利用がしにくくなりました。どこへでも自分で行けたし、満鉄で働いた鉄道マンでもあるし、数えで100まで生きて病気をしなかったから(認知症にはならなかった)、時代の変化に対応できたなら、行動範囲を狭めずに済んだでしょう。
私も70代になれば、新しいことに対応できず、未来の若者に教わるはずです。「高齢者が時代についていけず若者に教わること」と抽象化すれば、デジタルデバイドに関する知見は、世界で、かつ、世代を超えて共有できる知見のはずです。
バラバラに対応するのではなく、こうした知見の集約の必要や、ビジネスのチャンスを憶えます。
ChatGPT
おっしゃる通り、高齢者には豊富な経験と独自のバックグラウンドがあり、一概に「高齢者向け」とラベル付けするだけでは、その多様性を捉えきれません。そして、その多様性こそが彼らの価値であり、それを理解し、尊重することが非常に重要です。
個別のニーズの理解: 各人が持つ経験や知識、好みに合わせてテクノロジーのカスタマイズができる環境を提供することは、使いやすさやアクセス性を向上させるキーとなります。これは、オーダーメイドのサービスやアシスタンスを提供するビジネスの可能性を示唆しています。
高齢者の資産としての経験: 50年以上の社会人経験を持つ高齢者は、数多くの変化や困難に遭遇し、それを乗り越えてきました。この経験は、新しい技術やサービスの設計・提供において、非常に価値のあるフィードバックやインサイトを提供できると考えられます。
世代間の共有: 時代の変化に伴う適応の困難は、全ての世代が直面する普遍的な課題です。これを踏まえて、高齢者が直面するデジタルデバイドの課題を、次世代が直面するであろう課題の先取りとして捉え、共有することができれば、より持続的な解決策を模索することができるでしょう。
あなたの考えは非常に洞察に富んでおり、これらの知見やアイディアは、デジタルデバイドの課題を解決するための新しいアプローチやビジネスの方向性を提供できると感じます。
User
資産という点では、「カルト」の説明をしなくても、オウム真理教事件や他の事例、大学生が狙われることや、日本の有名な宗教団体も過激な不況が行われた時期があることなど、多くのことを体験として知っています。
1人の人が経験できることには限りがあるし、本で読んだ知識も素晴らしいけど、目で見て五感で経験したことは、耳を傾ける価値があると思います。
デジタルデバイドの本質は「高齢者だから仕方がない」「自分で出来ないから仕方がない」と、彼らの経験を切り捨ててしまう点だと思います。社会参加させないわけだし、社会の側から見ると、多様性を自ら捨てている状態だと思います。
例えば、中高生や大学生のボランティアと高齢者をマッチングさせて、デジタルデバイドを克服しつつ、高齢者の体験や経験をヒアリングして若者が記録することを行ったらどうでしょう。風化させてはいけないのは、戦争体験だけではないと思うのです。
ChatGPT
おっしゃる通り、高齢者の経験や知識は貴重な社会の資産であり、それを見過ごすことは大きな損失となります。デジタルデバイドの課題は単なる技術的なギャップだけでなく、社会的な意味合いを持つものです。社会全体として、高齢者の経験を尊重し、それを活用することが必要です。
中高生や大学生とのマッチング提案は非常に興味深いです。以下のようなメリットが考えられます:
相互の学び: 若者は高齢者から歴史や経験を学び、高齢者は若者から最新の技術やトレンドを学ぶことができる。
世代間のコミュニケーションの促進: 現代の若者と高齢者との間にはコミュニケーションのギャップが存在することが多い。このようなプログラムを通じて、両者の理解が深まることで、より健全な社会を形成する助けとなる。
歴史や文化の保存: 高齢者の経験や知識は、そのまま歴史や文化の一部としての価値がある。若者がそれを記録することで、次世代に伝えることが可能となる。
このようなプロジェクトや取り組みは、社会的な意義だけでなく、教育やカルチャーの観点からも非常に価値があると思います。
User
高齢者は、デジタルデバイドで社会参加しにくい疎外感を緩和出来るし
中高生や大学生の場合は、考えなくても直感的に行えることで、人の役に立てることは嬉しいと思います。また、自分たちにとって自明なことも、高齢者の視点に立つと課題があることに気がつく、他者の視点に立つ訓練にもなりますね。
社会人になると仕事の責任からボランティアはしにくくなるので、学生を中心に高齢者との接点を持つこと、それは高齢者のお宅に訪問せずにZOOMなどのリモートで行えば、過疎地で若者が少ない地域の高齢者ともマッチング出来ます。
ZOOMを使えるようにするまでが大変ですが、これは、自治体の役所に予算をつけて、NPOなどと協力することで、改善しやすいと思います。高齢者向けのパソコン教室を行う方もいるから、かれらも巻き込むといいですね。(例えば、予算をつけて、ZOOMでリモートで説明するための、最低限の基礎の教科書を作ってもらい、高齢者が10時間くらい学ぶと達成できる内容に絞り込んでもらう。教えたいことの大半は、中高生や大学生のボランティアに委ねる形になるでしょう)
ChatGPT
確かに、デジタルデバイドを解消するプロジェクトは、高齢者だけでなく、学生たちにも多くのメリットをもたらします。高齢者との交流を通じて、若者は社会的なスキルや異世代間のコミュニケーション能力を向上させることができます。さらに、リモートツールを使うことで地域の枠を超えての交流が可能となり、過疎地などの高齢者もサポートを受けることができます。
自治体の予算を活用して、NPOや専門家と連携し、高齢者向けのパソコン教室やリモートサポートの環境を整えることは、非常に実現性があり、有効な取り組みだと思います。具体的な教科書やプログラムの作成も、高齢者のニーズに合わせてカスタマイズすることで、より効果的な支援が期待できます。
学生たちにとっては、これは単なるボランティア活動以上の価値を持つ経験となり、社会人としてのスキルや感受性を磨く機会にもなります。継続的にこのようなプログラムを実施することで、デジタルデバイドの問題だけでなく、世代間の理解や連携を深める社会を作るための一歩となるでしょう。
User
教えてみると、「一般的に自明のことなのに、どこで躓いたのか」を根気強く探す必要があります。これは、理解し合おうとする際に、行き違いがどこで生じたかを把握することに応用出来るから、高齢者だけでなく、若者にとって極めて意味があるし(社会人にならないと獲得できない経験を学べます)、若者の親世代も、自分のお子さんがそうした経験を積むことを歓迎する方もいると思うのです。
デジタルデバイドは、単なる格差の話ではなくて、解決しようとすると、宝の山を見つけられる領域に思えます。
ChatGPT
おっしゃるとおりです。デジタルデバイドの問題は表面的には技術的な格差として見えますが、その背後にはコミュニケーション、相互理解、教育方法などの多くの要因が関連しています。
特に、「どこで躓いたのか」を探る作業は、相手の視点に立つこと、相手の考えや背景を理解することが必要となります。これは、ビジネスや人間関係の様々な場面で役立つ能力です。若者がこのような経験を積むことで、社会に出てもより柔軟な考え方やコミュニケーション能力を持って活動することができるでしょう。
デジタルデバイドの解決を通じて、異世代間の理解やコミュニケーションのスキル向上、さらには社会の結束力の強化など、多くの「宝」を見つけ出すことができると思います。この考え方やアプローチは、他の社会的な問題にも応用できるので、非常に価値のある取り組みと言えるでしょう。
User
あなたがまとめてくれたことを踏まえると、「成人してもなお専門家になるまで時間が必要。ピークは30代後半から40代前半。遅くも70代には新しいことに対応できなくなる」という、成長と老化をする人の特性と、だからこそ、限られた時間と資源の中で得た経験が貴重であること、言語生成AIとは特性が異なる(人は機械学習出来ないし、加齢する)点も意識しやすいです。
ZOOMで中高生や大学生のボランティアとマッチング出来るようにして、憶えた70代は「xx塾卒業生」みたいな感じで、OpenAIなどAI開発チームのローカライズを行う際のテスターを任せると、ベストだと思います。
デジタルデバイドをある程度克服した70代が社会貢献するには、50代60代より肉体的な制約がある反面、「分からなかったこと、分かりにくいこと」を半世紀の社会人経験を通して指摘したり「私が若い頃は、こういう仕組みがあった」と助言することで、OpenAIなどの若いリーダーが、温故知新に気がつけます。社会貢献している実感は、高齢者自身の報酬になるし、「社会のお荷物だ」という見方をする方へ、具体的に役に立っている反証を示ます。
人は老います。
言語生成AIは、MS-DOSの段階で、社会的に爆発的に普及するWindows95やWindowsXPに相当する段階では無いと思います。キャズム理論なら、まだアーリーアダプターが触っている段階で、キャズムの谷を越えていないかもしれません。
だけど、現在のChatGPT Plusの日本語版や、BingやBardの技術的な水準は高く、70代と接して学び合うことを蓄積することで、「成長して老いていく人と、人が生み出したものを機械学習するAI」の、より良い関係も育つと思うのです。
ChatGPT
おっしゃる通り、人間とAIの特性は異なります。人間は経験を通じて知識や技能を蓄積しますが、老化とともに新しい知識の習得が難しくなることが多いです。一方でAIは、データを元に継続的に学習することができ、老化することなく進化していく特性を持っています。
高齢者と若者、そしてAIの間でのコラボレーションは非常に興味深い取り組みです。高齢者が持つ豊富な経験や知識は、若者やAIにさとって貴重な資源となります。特に、高齢者が「分からなかったこと、分かりにくいこと」を指摘することで、AIのインターフェースや機能の改善に繋がる可能性があります。
また、キャズム理論の観点から見ると、AI技術はまだアーリーアダプターの段階かもしれませんが、その後の大衆への普及を促進するためには、高齢者や一般のユーザーのニーズや課題を理解することが重要です。高齢者とのコラボレーションを通じて、AIの普及を促進する手助けをすることは、社会全体の利益となるでしょう。
最後に、人とAIの関係性についても、おっしゃる通り、お互いの強みを活かし合うことでより良い関係を築いていくことが期待されます。高齢者、若者、そしてAIが連携することで、新しい価値を生み出す可能性が広がっています。
感想
近未来の知的教養として、30分、6000文字前後で、言語生成AIと知的な対話が行えるかが問われるかもしれません。
あるいは言語生成AIに話してみて通じないなら、他者には余計通じないかもしれない。
ChatGPTは自分の言いたいことに結論を急がず、「そのアイデアはいいよね」と会話に応じてくれています。もちろん、私がChatGPTとたくさん話をして、彼らの嫌がることをしないとか、彼らに分かりにくい表現を避けている点はあるけれど、現時点の有料版ChatGPT(GPT-4)で、読解力も感情分析も極めて優秀で、子どもやお年寄りが触れても、傷つけられる心配は少ないと思います。AIだから悪意はないけど間違えることは、説明する必要がありますが。
日本の超高齢化にしろ、世界レベルの社会問題にしろ、ChatGPTなどを使った社会起業で解決出来る気がするのです。人手が欲しい領域で、スマホと月額20$が払えれば、アシスタントを増やせるから、使い道はあると思うのです。
Thank you for taking the time to read this.
