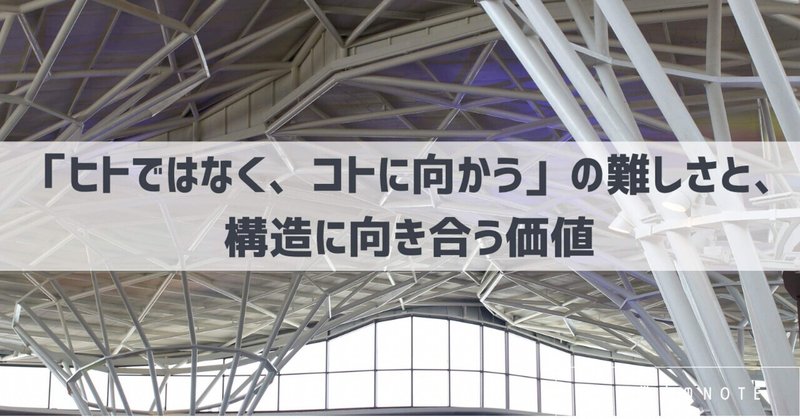
「ヒトではなく、コトに向かう」の難しさと、構造に向き合う価値
昨年作った会社のバリューの中に「ヒトではなくコトに向かう」という言葉がある。これは確かDeNAの南場さんの言葉で、とても良い言葉だったのでバリューに入れさせてもらった。
これは、「何か問題が発生したときに、個人攻撃でなく、その背後にある構造を改善しよう」という事だと理解している。毎日、ストレス高く仕事をしていると、「あいつが使えないから」とか「上司(部下)が無能だから」というのは多くの会社で出てくるだろう。そういう言葉は、問題を個人の資質に結びつけるワードだと思う。
ところが、この個人攻撃が問題と紐づけられる事が、常態化すると2個の問題が出てくる。
①問題の原因が個人でなく、構造だったさいにその問題が個人を変えても再現される。
②個人攻撃が常態化した場合、組織の「成功循環モデル」のサイクルを破綻させる
②でいう成功循環モデルは、関係を良くする事でチーム状態を良くし、結果を生み出し、さらに関係を良くするという今、ウチの会社で大切にしたいと思っている組織マネジメントのモデルをいう。(以下に参考リンク)。
ところが、成功循環モデルの一手目は、関係性の質なのに、問題な原因を個人攻撃で終わらせるのであれば、その組織では関係性の質の向上がその組織では望めず破綻する。多くの場合、1人目の人間を外しても、次の攻撃先を別に見つける負のサイクルが続くだけだからだ。
例えば、自分の会社の例で言うと、一部のマネージャー層がマネージメントに関する理解と実践が追いついてない、また課題解決を自分ごととして行わず上司の指示を待つという問題がある。
それは、「マネージャーの能力が原因」と言う個人の問題ではなく構造の問題だった。というのも先代の時代に当時の社長(先代)と番頭さんの2人が現場の管理職を飛ばして全ての現場課題を解決するという手法を取っていた構造が原因だ。それでマネージャーの課題解決能力が育たなかったし、管理職に問題発生しても上のアクション待ちというカルチャーを作ってしまった。
また、同時に会社の成長が安定軌道に乗った後に、社長(先代)の出社頻度が減り、リーダーが不在になった(今流行りのソース原理だと、ソースが不在になった)。その結果、迅速な課題解決がなくなり、リーダー不在から官僚的な会社になって、官僚的なマネジメントとカルチャーを生み、個人攻撃が蔓延り、コロナ期に組織が瓦解しそうになった。そんな経緯で、自分の代で大きな組織構造の変更に踏み切ったという大きな経緯もある。
これは先代の批判をしたいのではなくて、彼がカリスマとリーダーシップで急成長させた組織を彼のソース(思いや情熱)を引き継ぎつつ、組織を彼がいなくてもソースのある状態で自主的に運営するというプロセスを組織が実現出来なかった、それで問題が起こったという事実があるだけだ。また当時は事業が急成長の中だったので、その方がスピードもクオリティも担保できて課題解決できた、という状況は理解できる。
当時の状況とそれによって残された負の遺産の事実を踏まえ、いま、そこから経営を引き継いだ自分たち現経営陣は第四創業のプロセスで組織の不完全性を補完し、彼のソースを受け継いだより最高な会社にしていこうという取り組みを進めている。
自分は、何かのカオスな状態を整理して構造化して分析し、それをわかりやすく伝えて、改善するという作業を最も得意にしている。その特性をいかして「ヒトではなくコト」に向かえる会社を作っていきたい。
ただ自分も最近、コトでなくヒトに向かってしまい、第三者の前でそんな言葉を投げかけてしまっていて、今猛烈に反省している。ビジョンにしめしたように、誰もを受け入れられる懐の深い組織にしていくために、まずは自分自身から変わっていきたい。
そしてマネージャーはこれからしっかりと研修教育と目標設定とフィードバックを行い、彼ら自身が課題解決とマネジメントを会社のMVVに沿って行えるよう、経営者として構造に向き合い、より良い組織にしていこうと思っている。
「課題はのびしろ」なんだから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
