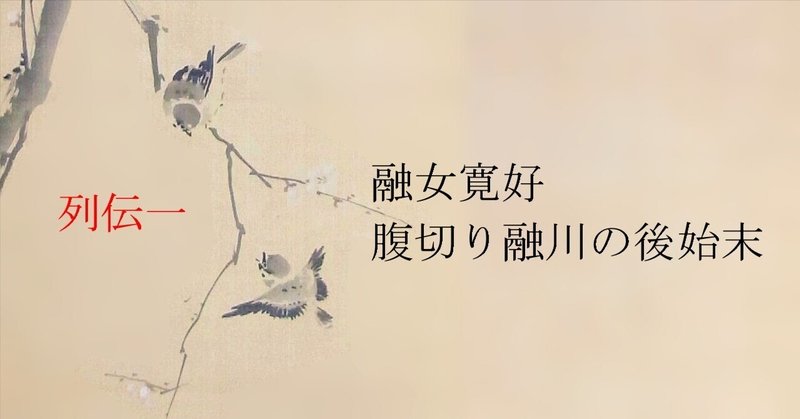
【第4章・悲しみの行方】融女寛好 腹切り融川の後始末(歴史小説)
第四章 悲しみの行方
両国の栄とほぼ同時刻、もう一人、浜町狩野家の使者により融川の死を知らされた者がいる。狩野素川章信である。素川が住む浅草は、今も昔も繁華街だ。取る物も取り敢えず通りに飛び出すと、町駕籠を拾って駆けさせた。
「まったく、どうなっているんだ。融川の野郎が死んだって。ほら、駕籠屋、しっかり駆けねぇか!」
素川章信は、奥絵師四家の下の表絵師十五家のひとつ、浅草猿屋町代地狩野家の隠居である。隠居と言ってもまだ四十七歳。なんと、三十五の若さで隠居し、その後は吉原の妓楼や柳橋の料亭などに入り浸っているという変わり者だ。
ただし、腕はいい。
木挽町狩野家の伊川栄信などと並び、後期狩野派を代表する名手と言える。天下の狩野派らしい格調高い作品から、庶民的な浮世絵の手法を取り入れた作品、遊び絵のような洒落を効かせた作品まで、多くの傑作を残している。妓楼や料亭で散財する金もすべて自分で画を描いて稼いだと伝わる。
頭にのせた頭巾がトレードマークで、人前では絶対に脱がない。若禿を隠すためとか、何かの願掛けだとか、様々言われているが、本当のところは本人以外わからない。何かと面白い人である。
素川を乗せた町駕籠が柳橋を渡った。今は真冬だ。川沿いに数珠つなぎに繋がれている屋形船がどこか寂し気である。
素川と融川は長年の遊び仲間で、毎夏、この柳橋から屋形船を仕立て、川風で涼を取りながらどんちゃん騒ぎをしてきた。
歳は素川がひと回りも上だが、二人とも豪放磊落、酒好き、女好き。何より新規で珍しいものが大好物。絵画についても、古い作品の研究だけでなく、新しい技法にもどんどん挑戦していく点で意気投合していた。
それにしても、年始の挨拶にかこつけて浜町屋敷を訪れ、近くの小料理屋で杯を酌み交わしてから何日も経ってねぇだろ。あの野郎が死んだって? ふざけるのもいい加減にしろ!
垂髪を揺らしながら駆けてきた栄と、頭巾の素川章信が、浜町屋敷の門前で鉢合わせしたのが、八つ半(ほぼ午後三時)ちょっと過ぎであった。
「あっ。これは、猿屋町代地家のご隠居様!」
「ご隠居はよせ。爺になった気分になるだろ」
「失礼しました。素川様のところにも行ったのですね、使者が」
「ああ。しかし、死んだとしか言わねぇから、訳も分からず、すっ飛んで来たところさ」
栄と素川が門を入ると、すぐに一人の家臣が寄ってきて、書院横の座敷に案内された。二人は融川が寝かせられた布団の両脇に分かれて座った。素川が融川の顔を覗き込む。
「なんとまあ、ほんとに死んじまったのか。顔に布がかかってないが、死んでるよな、これ」
栄は言葉が出ない。この段階ではまだ、まさか恩師が割腹して果てたとは思わなかった。融川の死に顔は、どちらかと言えば、穏やかな部類だったからである。
そこに家老の長谷川が入ってきた。
「素川様、よくおいで下さいました。お栄もご苦労」
さらに素川に向かって、「大変なことになりました。これをご覧ください」と言いつつ、掛布団をめくり上げた。
栄は、「あっ」と発してのけ反った。
横たわる融川の上半身は主に腕も含めて右半分が、下半身は袴の裾まで全体的に真っ赤な血で染まっている。端の方はすでに血が凝固し、赤黒くなり始めているところもある。
「長谷川様、これは一体?!」と栄。
「ふざけるな、誰にやられたんだ!」と素川。
素川の物騒な物言いに長谷川が慌てたように、枕元を指さして言った。
「ち、違います。違うのです。そちらの脇差で、殿が自らお腹を召したのでございます」
「何だと? 自分で腹を切った、なんで?」
「そっ、それは、分かりかねます」
「何だそりゃ。お前、家老だろうが。主人が腹を切って理由も分からんとは何事か!」
今にも長谷川に掴みかかりそうな勢いの素川。それを制するように栄が言う。
「取り敢えず、ご遺体を清めましょう。先生をこのままには出来ますまい」
栄が長谷川に目を向けると、自分には無理だ、と彼の目が訴えている。栄は小さくため息を吐いた。
「わたくしがいたします。長谷川様、まずお水を。その後で、お湯をどんどん沸かして下さいませ。あと、そうですね。布巾を出来るだけ多く。さらしも。使い古しの風呂敷も何枚か。それが済んだら、先生のお召し物と綺麗なお布団を一組、こちらの横に。長谷川様、分かりますか。お願いできますか」
長谷川は、青い顔でうなずいてから出て行った。
作業中に自分の着物が汚れないよう、画塾の作業場から前掛けを持ってきてもらった。師の体から血まみれの着物を脱がせ、それを綺麗にたたんで風呂敷で包む。濡れ布巾で体を清めていく。
傷は左の腹と首筋の二ヶ所。恐らく、右手で脇差の柄を握り、右袖で包んだ刀身に左手を添え、脇差を左の脇腹に突き立て、右に引いた。臍のところでそれ以上引けなくなったのか、刃を引き抜いて、首筋に当て、前にのめる勢いで頸動脈を切断。出血多量により絶命したと思われる。
腹部は半分ほどしか切られていないせいか、内臓は出ていない。丹念に血をぬぐってから傷口を隠すようにさらしを巻いた。
何も言わずに手伝ってくれていた素川が、「絵師にしては立派な腹の切り方だよ」とつぶやいた。
この時代、切腹も形式化していて、ちょこんと腹に刃を当てたところで、介錯人が首を落として済ますというやり方が多くなっていた。それを思えば、確かに立派な切腹と言えるだろう。
しかし、そんなことは褒める気にもなれない。一体、なぜ。なぜこんな?
作業が終わると、栄と素川は自分たちの衣服を整え、手と口をすすいだ。そして、融川の遺体に対してきっちり並んで姿勢を正し、改めて拝礼した。
栄が立ち上がりかけると、素川が、「どこへ行く?」と尋ねた。
「その脇差も清めてまいります。確か、ご先代が尾張公から拝領したものと伺った記憶がございますから」
「そうか。しかし、お前、すげぇな。顔色ひとつ変えず」
「子供の頃、小太刀の習い始めに、自害の仕方、刀傷の処置の仕方、ご遺体の清め方など一通り習いましたが、これほど身に付いていたとは、自分でも驚いています」
「武家娘の鑑だね」
「恐れ入ります。ただ、先生のご遺体を前にして、悲しいことは悲しいのですが、訳が分からず、怒っていいのか、悔しがっていいのか、涙も出ないというのが正直なところです」
「それは同感だ。行ってきな。お前が戻ったら、長谷川からゆっくり話を聞こうや」
「はい」
次章に続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
