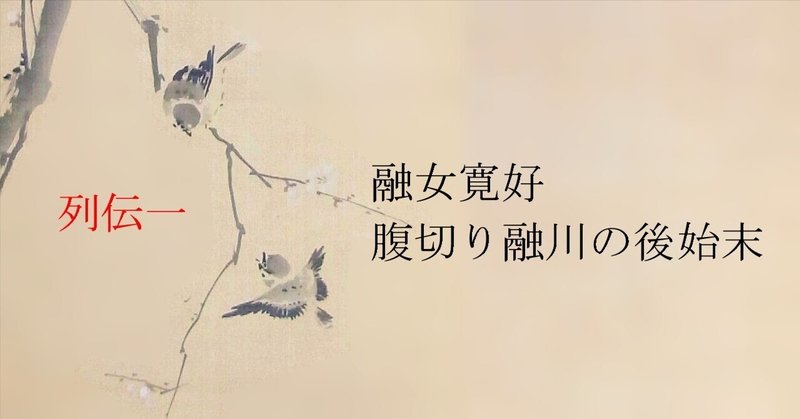
【第16章・姉弟子(後段)】融女寛好 腹切り融川の後始末(歴史小説)
第十六章 姉弟子(後段)
栄が大久保屋敷の近くまで来ると、門脇のくぐり戸の前で狩野新十郎が立っているのが見えた。寒いのか、さかんに腕や腰を回している。一向にこちらに気付かない。
「新十郎さん、どうでしたか」
栄が声をかけると、新十郎はビクッとして振り向いた。
「あっ、お栄様。はい、大丈夫です。お会い下さるそうです」
屈託のない新十郎の笑顔につられて栄も表情を緩めた。しかし、こうも人の気配に鈍感では、剣術の才能はなさそうね。折を見て、絵画修行に専念するように言おうかしら、などと思ってしまった。
いけない。私こそ、こんな時に変なことを。しっかりせねば。
門内に入ると大久保家の家臣が案内してくれた。新十郎は玄関脇のお供の控え部屋で待機だ。栄の案内は、男性家臣から奥向きの女中に引き継がれた。邸内すでに暗いので、女中は手燭で足元を照らしつつ案内してくれる。
最初の家臣も、この女中も、その挙措動作に一分の隙もなく、志津の教育が屋敷の隅々まで行き届いていることが分かる。
浜町狩野家の奥様・歌子は、何事も家臣や女中任せの典型的なお姫様タイプだが、志津は真逆である。
家中全般を統率し、必要とあれば表の人事や夫の職務についてまで堂々と意見する。いわば、共同経営者タイプの奥様であった。
無論、優劣ではない。それぞれの個性であり、夫婦の相性や家風による違いと言えるだろう。
志津はすぐに出てきた。歳は三十半ば。はっきりした目鼻立ち、見惚れるほど姿勢がよい。屋敷内のことでもあり、髪はシンプルな丸髷で、俗に「大久保藤」と呼ばれる藤の花をデフォルメした紋様を所々に散らした上品な打掛を羽織っている。
非常識な時間の急な訪問だが、それについての文句はない。
この二百年、戦はないものの、江戸城下は何度も大火事、地震、風水害などに見舞われた。また、飢饉に伴って江戸周辺で流民が発生し、治安が悪化するということもあった。
その都度、幕府から城下の武家屋敷に対して、警戒態勢の強化や緊急出動の命令が出された。ひとかどの武士の家の者であれば、昼夜を問わず、「常在戦場」なのである。
栄が簡潔に挨拶をして頭を上げると、志津が静かに問うた。
「何かありましたか」
「はい。少々急いでおりますので、いきなり本題に入らせていただきますが、その前に、お人払いをお願いいたします」
「いいでしょう」
志津が左右の女中に下がるように命じると、二人はこれまた綺麗な動作で下がって行った。
「それで、何があったのですか」
「本日、融川先生が亡くなりました」
「急ですね。ご病気? それとも・・・」
栄は、ここではたと思った。志津の人柄については信用できるが、一方で、師への恩義と主君への忠義を天秤にかけた場合、迷いなく忠義を優先する人だ。今回のことが、浜町狩野家だけの問題に収まらず、公儀に関わる問題と判断されれば・・・。
「正直、どこまでお話しすべきか、迷っております」
取りようによっては失礼な物言いだが、志津は特に気にする風もなく言った。
「ならば、尋ねたいことだけを尋ねなさい。わたくしも答えられることだけを答えましょう」
栄は、まっすぐに志津の目を見て小さく頷いた。
「では、遠慮なく。お志津様は、阿部備中守様というお大名をご存知でしょうか」
「ええ。備後福山の阿部様ですね」
「どのような方でしょうか」
特定の個人名を出したことで、志津の警戒度が跳ね上がった気がした。しかし、志津はそのまま続けた。
「阿部家は譜代の中でも屈指の名門です。当代の備中守様も、上様の信任極めて厚く、重用されていると聞きます」
「お人柄については如何でしょうか」
「上様がお引き立てになっている方のことですから、そこは控えるべきでしょう。備中守様と何かあったのですか」
「それについては、控えさせていただきたく・・・」
空気が、どん、と重くなった。これ以上は、多少なりとも融川の死について説明しないと情報を得られそうにない。栄は覚悟を決めた。
「詳しくは申し上げられませんが、本日、ご城中において、融川先生と阿部備中守様の間で諍いがあったようなのです」
「その諍いが、先生の死に関係があるということですか」
「わたくしはそう考えています。それで、今後の対応のためにも、備中守様がどのような方であるのか知っておきたいと思っているのです」
ただし、この後すぐに阿部家の上屋敷に赴くことは言わなかった。
志津は、栄をじっと見つめている。何かを見定めようとしている目だ。目を逸らしたくなる圧迫感。ふと、昔、小太刀の稽古でやたらと、丹田に意識を置け、と言われたことを思い出し、必死に耐えた。
「お栄、あなたは上様のお側用人・水野出羽守様を知っていますか」
「お名前だけは」
「目下、上様の一の側近と言えばその水野様です。そして、二番手に挙げられるのが阿部備中守様ということです」
「に、二番ですか。公方様の側近のお一人とは思いましたが、そこまでとは」
「そうなのです。役職は奏者番兼寺社奉行で、普通であれば、老中まではまだ遠いと言えます。しかし、京都所司代や大坂城代を経験することなく、近々老中に昇進するだろうと言われています。半年ほど前からですが、これまで老中しか出席を許されなかった会議や、携われなかった職務にも水野様と共に阿部様も関わるようになっていると聞いています。すべて、上様ご直々のお指図だそうです」
そこで思わず、「はぁ」と大きなため息が出てしまった。
「何ですか。お行儀の悪い」と、志津がすかさず咎める。
しかし、悪いのは行儀ではなく相手だ。ため息も出ようというものだ。
「十万石のお大名で、ほぼ老中ということですよね。とても勝ち目がありません」
「勝ち目ですか。何か勝負をするつもりなのですか。正直、阿部家と事を構えるのは利口とは言えませんね。ただ、老中職に関してはあくまで内定に過ぎません。人事が土壇場でひっくり返ることなど、よくあることです」
「そう、でしょうか」
「しかし、だからこそ、実際に老中に就任するまで、如何に些細な障害でも容赦なく排除しようとするでしょう。お気を付けなさい」
「ありがとう存じます。重々気を付けます。他には何かございませんか」
「そうですね。さらに詳しくは寛令殿にでも伺えるとよいのだけど・・・」
寛令とは、融川の門人筆頭とも言える小栗与九郎のことである。家は旗本千二百石。志津同様、求められる以上に絵画修行に真剣に取り組み、融川から一字をもらって、「寛令」の筆名を使う。
与九郎は、融川と歳も近く気も合って、師弟であると同時に、親友でもあった。浜町屋敷にもちょくちょく顔を出していたが、二年前、御三卿一橋家の近習番頭を拝命して以来、自分の屋敷にも戻れないほど多忙となっている。
「小栗様は最近、一橋家のお屋敷からほとんど戻らないと伺います。一橋家の敷居はさすがに高すぎます」
「そうですね。あの方は、人は良いのだけど、間が悪いのですよ。まったく、使えないこと」と、志津の物言いには容赦がない。
「他に誰かいるかしら。しかし、あまり方々に訊いて回るわけにもいかないのでしょう?」
「はい」
「お栄、結局、あなたは何を望むのですか」
「正直わかりません。後は、あちら様と話してからのことになるかと。あっ」と、栄は口を押さえた。
「ふふ、そうですか、この後。あなたが行くのですね。家老の長谷川殿ではなく」
「は、はい。奥様のご下命にて」
「あらあら。あのお姫様も、人を見る目だけはあるのですね。見直しました」
栄は苦笑を含みつつ、黙って頭を下げた。
「わたくしの立場では、お膝元での騒動をそそのかすことは出来ません。されど、一家の代表として赴く以上、いざとなれば、刺し違える覚悟で行きなさい。融川先生の下で十年修行したあなた自身の目を信じなさい。その目で相手を見極め、自分の望むものを必ず掴み取るのです」
志津はそう言って、武家の女性が懐剣をさす帯の上の辺りを、ポンとひとつ叩いた。
栄は、大久保家を辞し、いよいよ阿部家上屋敷に向かう。時に、文化八年(一八一一年)一月十九日、夜の五つ半(ほぼ午後九時)過ぎ。恩師・狩野融川の切腹から、四時(八時間)が経っていた。
空に月が出ていたか否か。後年尋ねられた際、栄は、憶えていない、と答えたという。
次章に続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
