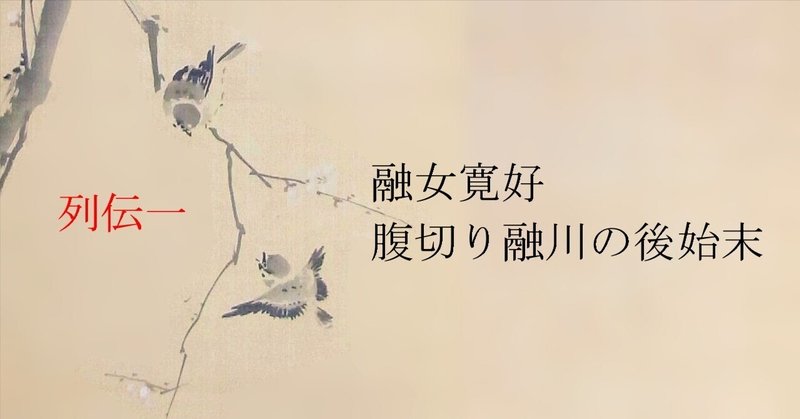
【第5章・阿部備中守】融女寛好 腹切り融川の後始末(歴史小説)
第五章 阿部備中守
栄と素川章信が浜町狩野屋敷に入った八つ半(ほぼ午後三時)少し過ぎ、阿部備中守正精が、城での執務を終え、阿部家上屋敷に帰着した。
阿部家は備後福山十万石、泣く子も黙る三河以来の名門譜代大名である。藩主が居住する上屋敷は、現代の東京駅の真ん前、新丸ビルから堀端までの一帯を占め、およそ七千五百坪もの広さがあった。
さらに、城の出入りに使う桔梗門(内桜田門)からわずか四百メートルほどしか離れていない。位置的にも超一等地である。
現当主である第五代藩主・備中守正精は、働き盛りの三十七歳。今に残る肖像画を見ると、色白で面長、典型的な殿様顔である。しかし、目元の辺りがいかにも利発そうで、そこらのボンクラ大名と一緒にするな、という声が聞こえてきそうだ。実際、将軍家斉の側近として奏者番兼寺社奉行という要職に就いている。
備中守が近習の介添えで着替えを済ませ、屋敷の執務室である御成書院に出ると、江戸家老の阿部頼母が待っていた。頼母は藩主家の分家の出で、備中守の幼少期の教育係でもあった。何かと気安い存在である。
「殿、お城で何か変わりはございませんでしたか」
「いつもの通りだ」
続けて、「屏風の見分は如何でしたか。殿のお眼鏡にかなうものはありましたか」と、頼母が尋ねたのは、備中守が書画などにも造詣が深いことを知っているからである。
「うむ。なかなかであった。ただ、ひとつ随分と貧相なのがあってな。奥絵師に描き直すように注意しておいた。顔を赤くして怒っておったな、ははは」
「さすがは殿でござるな」
「まあ、屏風などは些細なことだ。それよりも、年末に大坂の商人たちに課した御用金の集まりが悪いらしい。そちらの方がよほど大事だ」
「相変わらずご多忙なことです。本来の奏者番や寺社奉行の職務に加え、今やご老中方が処理すべきところまで関わっておられる。公方様も早いところ正式に老中にご指名くださればよいものを」
「それは気が早い。予はまだ大坂城代も京都所司代も務めておらぬ。物には順序というものがあろう」
そう返した備中守であるが、自分がすでに老中就任目前まで来ていることは十分承知している。むしろ、老中など単なる通過点でしかない。目指すところは、その上、常設の将軍補佐職としては最高官たる「老中首座」である、と強く思っている。無論、口には出さない。
その後、頼母から藩政に関する報告を受けていると、廊下から取次ぎを願う声がした。
「ご家老、よろしいでしょうか。殿に、水野出羽守様から書状が届いております。火急の用件とのことです」
「火急とな。お使者は待たせておるな。分かった。すぐ行く。殿、よろしいですな」
「ああ、頼む」
頼母はすぐに一通の書状を手に戻ってきた。
「こちらでござる。お使者は何も存ぜぬとのこと。お返事も不要とのことでした」
「返事はいらぬと。どれ」
何事かと思いつつ、備中守は封を切って書状を読み始めた。見る間に表情が曇って行く。
「殿。出羽守様は何と」
「奥絵師の狩野融川が死んだらしい。しかも、下城途中に血まみれとなって」
「なんと。それは、先ほど殿が屏風の描き直しをお命じになったという絵師でござるか」
「そうだ、な」
「それにしても、出羽守様は随分と早耳ですな」
「町奉行から報告が来たらしい。しかし、血まみれというのは何だ。訳が分からん」
「殿、まさか、殿中で刃傷沙汰を?」
「馬鹿を申せ!」
「殿には本当にお心当たりはないのでござるか」
「当たり前だ!」
「されど、出羽守様は、この一件、殿に責任があるとお考えなのでは?」
「いや、そうではあるまい。万が一にも大事となり、上様を悩まし奉ることのないよう、速やかに事態を把握して対処した方がよかろう、と気を利かせて知らせてくれたのだろう」
「なるほど。さすが公方様の側近同士ですな。心強い限りです」
頼母はひとまず納得したようだが、備中守の内心はまったく違う。断言してもいいが、水野出羽守は、仲間意識や親切心から知らせてくれたわけではない。あれがそんな甘い男であるものか。
水野出羽守、名は忠成、駿河沼津二万石の大名である。岡本家という中級旗本の次男に生まれ、二千石の旗本水野家に末期養子として入った。それだけでも破格の出世だが、名門水野一族に名を連ねたことを利用し、さらに上位の沼津藩主・水野忠友の養子となる。そして数年後、養父の死により、遂に大名に成り上がった。
その後も出世は続き、奏者番、寺社奉行、若年寄を経て、今や将軍側近団の筆頭・側用人となっている。出世の鬼、と言っていい。
出羽守の関心は、将軍家斉のご機嫌取り以外は何もない。家斉の機嫌さえ良ければ、天地がひっくり返ろうとも気にしない。そういう性質である。
目下、幕府内は、寛政の改革で松平定信を支えていた一派と、実権を将軍に取り戻したい家斉派で、真っ二つに割れている。
松平定信が老中首座の地位から追われて既に十八年が経つが、いまだにその一派が力を維持しているのは、天明の大飢饉以来の幕政の混乱がいかに深刻であったかということだ。
定信は、幕政を立て直すために改革を断行した。そしてその際、反対派を容赦なく排除するとともに、幕府の隅々にまで彼の支持者を配置した。定信失脚後もその勢力は残った。現実問題として、彼等の行政手腕なしには幕府は回らなくなっていたのだ。
しかし、世の中が落ち着きを取り戻すに従い、ここ数年、ひたひたと家斉派が力を付け、遂に優勢を得つつあった。
備中守は脇息に体を預けつつ考える。上様による幕府全権の掌握まで今一歩。この時期に将軍側近が不祥事を起こすのは確かにまずい。今後の派閥内での競争を考えれば尚更だ。
現時点で、家斉からの信頼度で言えば、出羽守が頭ひとつ抜けている。恐らく、側近団の中では、出羽守が最初に老中首座に就くだろう。しかし、出羽守は、年齢的に自分よりひと回りも上である。当然、奴の方が先に死ぬ。その次は、家柄、能力、どの点から見ても、この備中守以外いないではないか。こんな所で、つまずいていられるか。
そうだ。下手に騒がれるとまずい。何とか相手を黙らせなければならないだろう。狩野融川は、浜町の狩野家だったか。とりあえず、詳しい状況が知りたい。
「頼母、心利きたる家臣を浜町の狩野屋敷に派遣し、様子を探らせてくれ。くれぐれも目立たぬようにな」
次章に続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
