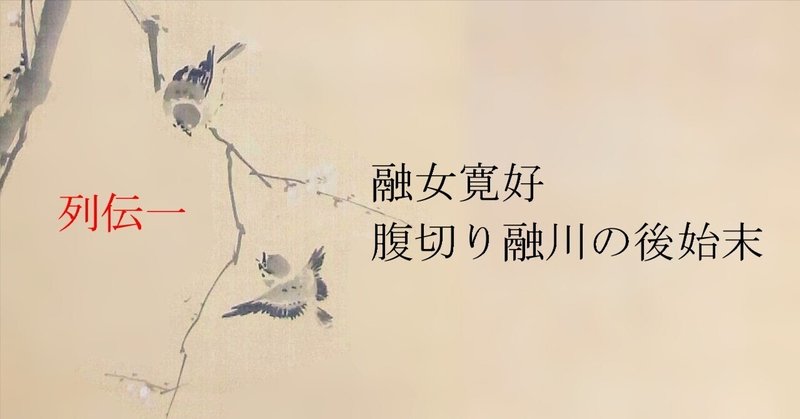
【第6章・疑問】融女寛好 腹切り融川の後始末(歴史小説)
第六章 疑問
栄が井戸端で脇差の血を洗い流していると、画塾の後輩絵師が寄ってきた。
「お栄様、こちらでしたか。長谷川様が屋敷中の者に集合を掛けました。場所は工房です。すぐにお越しください」
「承知しました」
浜町狩野家の拝領屋敷は、五百坪ほどの広さがある。禄高二百石の旗本にしてはかなり広いが、それは、奥絵師という職務上、通常の旗本屋敷にはない施設を屋敷内に建てる必要があるからだ。
当主の執務や生活の場である母屋、家臣とその家族が住む長屋などは普通の旗本屋敷と同じだが、それ以外に、画塾と作業場を兼ねる工房があり、さらに、絵画に関する道具類、各種の資料、伝来の作品群などを保管しておく蔵もある。
工房は約五十坪の広さで、時代劇でよく見る剣術道場、現代なら学校の体育館のような、基本的に何もない屋根と床と壁だけの建物であった。
床は板張りで、全体を大きく二つに分けて使っている。すなわち、半分は、画塾で修行中の絵師たちのためのスペースだ。彼等には、一人に畳二枚分の広さが与えられ、昼間はそこで画を描き、日が暮れると片付けてそこに布団を敷いて寝る、という仕組みである。
残りの半分は、屏風や障子などの大型の作品、又は何枚もの連続した作品を描くようなときに使われ、普段は空きスペースとなっている。
この時、浜町狩野家の画塾には三十五人が在籍していた。内弟子は二十一名。男性十七名は工房で寝泊まりしている。四名の女性については、作業スペースは男性と同じく工房に与えられるが、寝泊まりは母屋の女中部屋を使う。
栄も十一歳から五年間は内弟子として女中部屋に住み、午前中は女中として奥の手伝い、午後になると工房に入って絵画の修行をするという生活をしていた。内弟子修行を終えて屋敷を出た彼女は、今は九名いる通いの弟子の列に名を連ねている。
さらに、絵師であると同時に、当主の業務全般を補佐する士分の家臣として、家老の長谷川を含めて五名。彼らは工房での修行を終えた弟子の中から選ばれ、屋敷内の侍長屋に住んでいた。妻帯も許される。
屋敷には他に、絵画と無関係な奉公人として、奥様付きの女中二名、下働きの男女各二名がいる。
栄が工房に入ると、空きスペースの側に三十名足らずの人間が集まっていた。この日、通いの弟子はほとんど来ておらず、これが、奥様と二人の若様、その世話をする女中一名を除いた屋敷にいる全員であった。
家老の長谷川から皆に対して、融川の急死と、その件に関する口止め、当面屋敷から出ることを禁じる旨の申し渡しがあった。一同、さすがに動揺の色を隠せない。
その様子を見て素川が口を開く。「おいおい、しっかりしろよ。ここは絵師の家だが、立派な直参旗本だ。くれぐれも見苦しい振る舞いは慎まなければならねぇよ」
長谷川が一同を解散させると、栄、素川、長谷川、本日城に供した家臣の四名が残った。
「それで、一体なんであんなことになったんだ?」
「それが、まったく分かりません」
「城からの帰り道だろ。城中で何かあったと考えるのが普通だ。今日は十九日か。一でも六でもないぞ。なぜ登城したんだ?」
奥絵師の登城日は、毎月、一と六の日と決まっていた。奥絵師は若年寄支配なので、登城して若年寄からの指示を受ける。特に用がない場合、城中の表から大奥まで、膨大な数に及ぶ襖絵や屏風、数々の調度類の状態を確認する。傷んだものがあれば修復し、修復できないものは新調の手配をする。また、種々の季節行事の美術面での準備をしたり、将軍が家臣に褒美として与えるための画を描きためておいたりもする。
奥絵師は、そうした多岐にわたる業務について、自らこなすと共に、必要に応じて配下の御用絵師にも割り振って行わせていた。
「はい、本日はご老中方による朝鮮国王贈呈屏風の最終見分がございまして、その立ち合いでございます。奥絵師は、殿様以外も、皆様登城されました」と長谷川。
「ああ、あれか。準備のご下命が出てからもう三年だろ。長かったなぁ。しかし、最終見分なら、問題が起きるって段階でもないよな。ひょっとしてあれか、酒でも飲みながら描いて、出来損ないでも持ち込んだのか」
「滅相もない!」と、栄と長谷川の声が被った。
長谷川がさらに、「あの屏風は、公方様のご高徳を慕い貢物を贈ってくる他国の王への返礼の品。下手なものでは公方様のご威光に関わります。隅から隅まで殿様ご自身が筆を入れ、それはもう素晴らしい出来でございます」と続けた。
「画題は、何を描いたんだっけ?」
「はい、本間屏風六曲一双に近江八勝を」
「そうだったな。お栄はどう見た?」
「はい、長谷川様のおっしゃる通り、あの屏風に文句が付くとは思えません。墨で近江八景を軽やかに描き、たなびく雲を金泥と金砂子の濃淡で見事に表しております。近頃、先生が金泥や金砂子の使い方を工夫しておられたことは素川様もご存知でしょう。それがようやく。あれは、先生のこれまでの作品の中でも屈指の出来と心得ます。正直、国の外に持ち出されてしまうのが惜しいと思うほどです」
「それほどの出来か。俺も見たかったな。しかし、そうなると、ますます分からねぇな」
「他の事でどなたかと揉めたとか、でしょうか」
「しかしよ、腹を切るなんざ、余程のことだぜ。城中でそれだけ揉めりゃ、騒ぎになるだろう」
「そうですな。お城の御用以外で、何かお悩みだったのでしょうか。妓楼や料亭なんかで何か。そちらの事情は私よりも素川様の方が詳しいと存じますが」
「う~ん、思い当たらねぇな。毛利のご隠居と売れっ子の妓女を取り合ったのも随分前だし、それもすっかり仲直りしてるしな。おっと、金銭問題はどうだ?」
「あり得ません。ご承知の通り、殿様は派手に散財する御方ですが、お城の御用を疎かにしたことはございません。正規のお禄とお手当で十分賄える上、大名家などからの画の注文や古画の鑑定依頼などもひっきりなしで。お屋敷も殿様ご自身も、お金に困っているということはありません」
「やはり、屏風見分の場で何かあったとしか思えねぇな。屏風の出来はともかく、何かあったんじゃねぇか」
「そうなると我々には分かりません。本日は供の者も城中には入っておりませんから」
「その場にいた者となると、他の奥絵師の連中に尋ねるしかないか」
「はあ、どなたに?」
「どなたにって、順当なところで、木挽町の伊川殿でいいんじゃないか」
「木挽町家の伊川法眼様でございますか。それはちょっと。御当家は元々木挽町家の分家ですが、文昭院様(六代将軍・徳川家宣)のご意向により、御当家の初代・隨川岑信様が、本家や宗家(中橋狩野家)を差し置いて狩野派総上席とされたことで、その・・・」
「おいおい。それって百年も前の話だろ。まだ揉めてんのか」
「今の殿様同士は歳も近く、お仲もよろしいのですが、ご先代同士は険悪でした。家と家の関係となると、まだまだ油断できません」
「かと言って、宗家や鍛冶橋は、どっちも若造で頼りないぞ。事が事だ。下手な奴には話せんからな」
「困りましたな。いやはや、困った」と、長谷川が頭を抱える。
すると、それまで黙って素川と長谷川のやり取りを聞いていた栄が発言した。
「では、板谷先生はどうでしょうか。板谷先生なら融川先生とも懇意でした。お人柄も信用できると存じます」
「しかし、他流だぜ」
「今は流派より人柄が大事ではないでしょうか。わたくしが参ります」
「う~ん、そうだな。流派より人柄ってのは一理あるか。迷っていても仕方ねぇ。よし、お栄に任せよう。誰か、駕籠を呼んでやってくれ」
次章に続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
