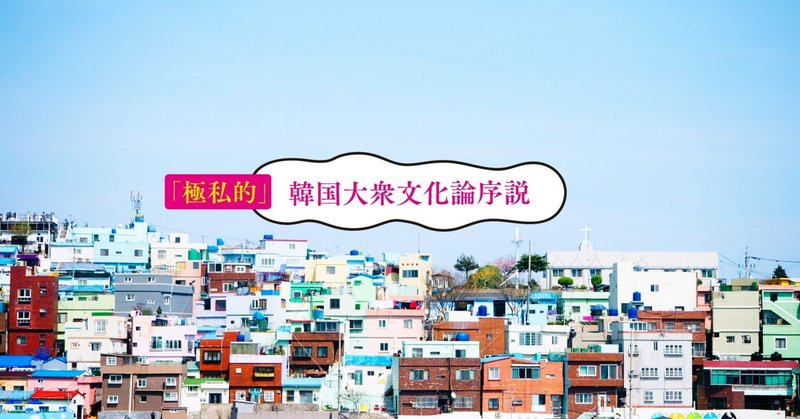
【「極私的」韓国大衆文化論序説】第3回 「パクリ」か「影響」か――コンビニから見える日韓よもやま話(崔盛旭)
日本に来て、もう20年以上になる。初めの頃は毎日がカルチャー・ショックの連続で、両国の似ているところ、逆にまったく違うところを発見しては、密かに面白がっていた。
なかでも「コンビニ」はネタの宝庫だった。日本に来る前、当然韓国のことしか知らなかった私は、「セブンイレブン」や「ファミリー・マート」、「ローソン」も日本の会社とは知らず、アメリカの会社だろうくらいに思っていた。言われてみれば、ハングルで「家族」を意味する英語「Family」は「패밀리(ペミリー)」と書くにもかかわらず、ファミリー・マートは「훼미리마트(フェミリー・マート)」と表記することを不思議に感じていたが、それが日本のカタカナ表記「ファミリー」を韓国式に表記したからだと合点がいった(ハングルでは総じて「F」と「P」は区別せず「ㅍ(ピウッ/P)」に発音する)。
当時日本のコンビニでは、成人向けのエロ本と一般向けの雑誌が一緒に並べられており、サラリーマンが普通に立ち読みしている光景も非常に新鮮だったが、それ以上に、韓国で慣れ親しんできた定番商品が、日本のコンビニにも陳列されていることに私はすっかり驚いてしまった。定番スナック菓子の「かっぱえびせん」(カルビー)は、まさに韓国の「새우깡(セウカン)」であり、グリコの「ポッキー」は韓国の子どもたちが愛してやまない「빼빼로(ペペロ)」だった。栄養ドリンク「リポビタンD」(大正製薬)は韓国の「박카스D(バッカスD)」と瓜二つだ。これらは、単にお菓子の味や形が酷似しているだけでなく、パッケージや絵柄に至るまで「ほぼ同じ」だったのだ。
最初に「かっぱえびせん」を目にしたとき、韓国の「セウカン」が日本にも輸入されているのだとおめでたい勘違いをした私だが、すべてはその逆で、日本の商品を韓国側が丸パクリして商品化した、というのが真相だった。「セウカン」は1971年に発売されてから現在まで、韓国お菓子界で不動の地位に君臨し続けている「国民的お菓子」である。子どものおやつ、大人の酒の友としてはもちろん、動物園の動物たちにも喜ばれる餌でもあり、単なるお菓子を越えた存在感をもっている。90年代に始まった「♪手が行くよ~手が行くよ~セウカンに手が行くよ~(手が止まらずついつい食べてしまうという意味)」のCMソングは、この歌を知らなければ北朝鮮のスパイかと疑われるほどの知名度を誇り、約30年にわたり、その時々のスターたちがCMに登場して同じ歌を唄い続けている。
「セウカン」に続く韓国の国民的お菓子は、1983年にロッテが発売した「ペペロ」である。名前からはピンとこないかもしれないが、画像を見れば一目瞭然、グリコの「ポッキー」に他ならないのである。日本の人気菓子がほぼ丸ごと韓国で商品化されるケースは、ロッテ製品に多いように感じられるが、その背景には、ロッテという会社の創立者である重光武雄(本名:신격호(辛格浩))が戦時中に朝鮮から日本に渡り、1948年に日本での創業後、1967年に韓国ロッテが創設されたという歴史も関わっているかもしれない。日本の業界に精通していたロッテが、他社の売れ筋商品を真似て韓国ロッテで商品化していたというわけだ。日本でバレンタイン・デーにチョコレートを贈る習慣がこれほどまでに普及したのは企業の戦略的な仕掛けが大きかったと言われるが、韓国では11月11日を「ペペロ・デー」と位置付けたことで若者人気が過熱し、さらなる普及が進んだ。今や日本でも「11月11日=ポッキーの日」が定着しているが、このイベントばかりは韓国が先だったようだ。
「バッカスD」は、1963年の発売以来、地球何周分もの数を売ったと言われて愛飲されている、韓国を代表する栄養ドリンクだ。映画やドラマで、警察に挨拶代わりの「賄賂」として渡す場面も多く登場する、まさに人気ものである。ギリシャ神話の酒の神「バッカス」に由来し、二日酔いにならないという効果を謳ったこの「バッカスD」が酷似しているのが、「リポビタンD」である。世界初の栄養ドリンクと言われている「リポビタンD」とは、味の面では少し異なっているのだが、パッケージを見ると、糸車をかたどったその絵柄はまさにパクリとしか思えない。
これらの商品の発売時期を比べてみると、カルビーが「かっぱえびせん」を発売したのが1964年、棒状のものに線の入った形、えびのイメージをそっくり真似して韓国で「セウカン(えび缶)」が発売されたのが1971年、グリコの「ポッキー」が1966年に発売され、韓国ロッテの「ペペロ」は1983年に発売されている。そして大正製薬の「リポビタンD」が1960年に発売、「バッカスD」は1963年に発売が開始された。このように、日本の人気商品をあからさまに真似た(パクった)商品を平気で韓国で売り出すことが可能だった背景には、第1回のnoteにも書いたように、1998年に日本の大衆文化が開放されるまで、日本に直接的に関わるものが禁止されていたことが挙げられよう。再び日本の資本が入ってくると経済的植民地化されるのではないかという警戒意識から、日韓の企業が直接的にライセンス契約を結ぶことが極めて難しかった時代、ある種の必然として、日本の人気商品を韓国がこっそりと真似をするという手法が蔓延していったと言えるだろう。
これらはすべて、日韓両国での定番商品であり、私が日本に来てまもなくその酷似ぶりに驚愕した経験だが、後に私が韓国に一時帰国した際に発見したケースも存在する。
ガッキーこと新垣結衣がイメージキャラクターを務める「十六茶」。今、韓国には「17茶」なる商品が売られている。こちらも大人気女優のチョン・ジヨンがCMに出演し、明らかに「十六茶」を真似ているが、タチが悪いと思うのは、真似るばかりかさらに材料の種類をひとつプラスしているところだろうか。
そして、近年では独特の噛み応えで大リーグのプロ野球選手の間でも大人気だという「ハイチュウ」。韓国には、同じような「マイチュウ」という商品が発売されている。当初、韓国のコンビニでは「ハイチュウ」が1000ウォンで販売されていたが、「マイチュウ」が500ウォンで登場したために、市場から姿を消したと言われている。「マイチュウ」は、「ハイチュウ」を販売している森永製菓からクレームを入れられたこともあったが、開き直って頑なに「パクリではない」と主張し、うまく逃れたようだ。
そして極めつけは、2002年に日本で発売されて人気を博した明治乳業の「おいしい牛乳」に続いて、翌年、韓国で「맛있는(マシンヌン=おいしい)우유(牛乳)」が発売になったことだ。だがここまでなら、日本でも森永が「森永のおいしい牛乳」を発売していることもあり、まだ理解できる。その後韓国では、「マシンヌン牛乳」のライバル会社が「참(チャン=本当に)맛있는 牛乳」を発売し、2社の間で訴訟問題に発展したのである。「マシンヌン」は「チャンマシンヌン」に勝訴したわけだが、ここに明治乳業が絡んだらどんな結果になっていただろうか。韓国ではもはや、真似ることが癖のようになってしまったのかもしれない。このように韓国国内で類似商品を出し合う現象は「Me Too商品」と呼ばれているという。
訴訟との関連で近年話題になったのが、百円均一ショップの「ダイソー」である。韓国にはこのような雑貨店がなかったため、韓国に進出したダイソーは、瞬く間に全国に出店し人気を得た。そこに登場したのが「다사소(ダサソ)」という雑貨店だ。韓国語の南東部の方言で「全部買ってくれ」を意味する「ダサソ」は、誰が見ても商標の盗用であり、ダイソーはすかさず訴えた。一審ではダサソが勝訴するも、控訴したダイソーは最終的には勝訴、ダサソは姿を消したのである。
こういった事例は他にもいくらでも挙げることができる。日本での「おっとっと」「ポポロン」「きのこの山」「森永のミルクキャラメル」…。正直、開き直って堂々とパクる韓国の図々しさには辟易してしまうが、良し悪しは別として、韓国の近代は常に日本を手本として発展してきたことは歴史的事実であり、日本でのヒット商品が韓国でもヒットするというのも、さすが文化や趣向を共有する隣国同士であり、こういったパクリの歴史を通して日韓両国の顔が見えてくるというのも、興味深いと言える。最近では、韓国のヒット商品や食べ物が日本に輸入されて人気を博すケースも増えており、今では良きライバル国として互いに刺激し合い、影響を与え合っているのも確かだろう。「パクリ」と捉えて怒ることは簡単だし、自社の利益にかかわる企業側からしたらたまったものではないかもしれないが、私たち消費者としては、互いの商品をつまみながら、ケラケラと笑い飛ばして会話のネタにしたいところである。
プロフィール
崔盛旭(チェ・ソンウク)
映画研究者。明治学院大学大学院で芸術学(映画専攻)博士号取得。著書に『今井正 戦時と戦後のあいだ』(クレイン)、共著に『韓国映画で学ぶ韓国社会と歴史』(キネマ旬報社)、『日本映画は生きている 第4巻 スクリーンのなかの他者』(岩波書店)、『韓国女性映画 わたしたちの物語』(河出書房新社)など。日韓の映画を中心に映画の魅力を、文化や社会的背景を交えながら伝える仕事に取り組んでいる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
