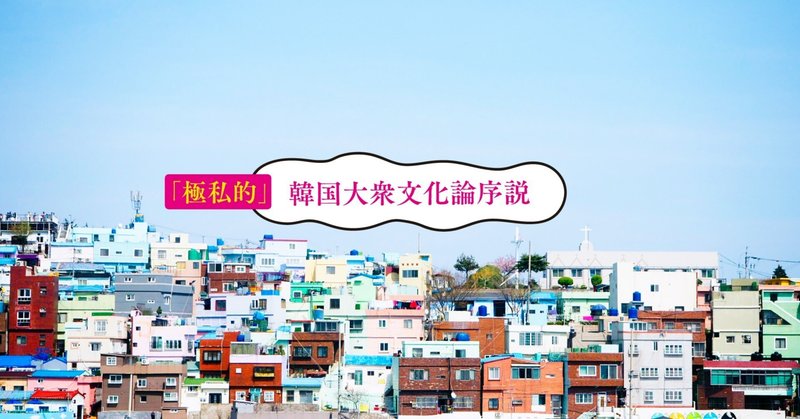
【「極私的」韓国大衆文化論序説】第4回 君は「チャン・ヒョンチョル」を知っているか―私のK-POP史―(崔盛旭)
高校時代、私には相棒とも呼べる親友がいた。教室では3年間ずっと隣の席に座り、少しどもりがちな彼との日々は平凡そのもの、一緒にいるのが当たり前で、これといった思い出すらも残っていない。私たちは二人とも文系志望だったが、異なる大学の国文学科と経済学科に進学してからは会う時間も減ってしまった。入学直後、ギターサークルの可愛い女の子に片思いした彼は、サークル活動に熱中した。教育者だった彼の父は、息子のギター熱を許すことができず、勢い余って家出した彼は、大学のサークル室に寝泊まりしていた。
ある日、家出息子の説得を頼まれた私は、「お父さんも許してくれるから家に戻ってこい」と伝えたものの、家に戻った息子の前で父親は、彼の頭にギターを叩きつけ、ギターには頭の形の穴が開いた。「二度と帰ってくるか!」のセリフもどもって上手く言えないまま、泣きながら走り去っていく彼の後ろ姿が今も瞼に焼き付いている。
その後、私は軍隊に入り、彼とは疎遠になってしまった。ところが除隊後まもなく、彼から「MBC大学歌謡祭」に出演するとの連絡を受けた。当時、韓国には大学生を対象に、テレビ局が主催する複数の歌謡祭が存在していた。それらの元を辿れば、1970年代に朴正煕(パク・チョンヒ)軍事政権が政治から大学生たちの目を少しでもそらすために、苦肉の策でテレビ局に作らせたものだが、いつしかプロへの登竜門という意味合いも帯びるようになっていたのだ。
彼がそこまで本気で音楽に打ち込んでいるとは知らず、私はとても驚いた。どもり癖のあいつが歌を歌えるのか?と心配したが、歌謡祭の舞台に立った彼は見事な歌唱力で歌い上げていた。そしてとんとん拍子に優勝を果たすと、その場にいたプロデューサーの耳に留まり、あれよあれよという間に、1993年に大人気を博したテレビドラマ『걸어서 하늘까지(歩いて空へ)』の同名の主題歌に起用され、音楽番組で1位を獲得するまでになったのである。その友人の名は、チャン・ヒョンチョルという。
思い出の彼方にいってしまった友人の話から始めたのは、近年、日本のみならず世界的な音楽コンテンツとなっている「K-POP」という言葉に対する違和感を、私自身が拭えないでいるからだ。先日、韓国の大衆文化を紹介する授業でK-POPを取り上げる機会があった。だが、広く流布している「K-POP」という言葉は、実際にはアイドル・グループと彼らの楽曲を指す場合がほとんどで、韓国(Korea)の大衆音楽(Pop)全体を指しているとは言い難い。韓国の大衆音楽には当然ながら、ロックやポップス、ヒップホップ、日本の演歌にあたるトロットなど、様々なジャンルが存在している。もちろん、K-POPがここまで世界を席巻したのはBTSやBLACKPINKなどのアイドル・グループがあってこそだし、それによって韓国の大衆音楽(K-POP)のイメージが築かれたことは紛れもない事実である。だが昨今のK-POPが決してK-POPそのものを指しているわけではないこと、そこには大きな偏りがあることは認識しておく必要があると思う。
韓国大衆音楽の始まりは、日本の植民地だった1930年代、日本の演歌の影響を受けて誕生したトロットに遡る。そして戦後になると、日本のみならず、アメリカン・ポップスの影響も受けながら、少しずつロックやフォークソングへとジャンルを広げていく。日本の影響は、韓国の大衆音楽の発展には欠かせないものだったが、時としてそれが日本のヒットソングのパクリや盗作といったネガティブな形で現れることもあった。日本大衆文化が公式には「禁止」されているのをいいことに、無断で韓国語の歌詞をつけてそのまま歌ってしまうのだ。今振り返るとその図々しさに呆れかえるが、日本で大ヒットした曲は当然ながら韓国でも人気を博した。例えば、長渕剛の名曲「とんぼ」をそのままコピーしたホン・スチョルの「보고싶다 친구야(会いたいぜ、友よ)」、キム・ミンジョンの「귀천도애(帰天道哀)」(TUBE「SUMMER DREAM」)、キム・ヘリムの「있는 그대로(ありのまま)」(TUBE「THE SURFIN' IN THE WIND」)、ルーラの「천상유애(天上有愛)」(忍者「お祭り忍者」、発覚によりルーラは解散)、EOSの「넌 남이 아냐(君は他人ではない)」(シャ乱Q「上京物語」)・・・そして今年、人気音楽番組のMCを13年も続けてきたシンガーソングライター、ユ・ヒヨルが長年にわたって坂本龍一の曲を盗作し続けてきたという、韓国社会を揺るがした事件まで、例を挙げれば切りがない。中でもユ・ヒヨルの場合は、言い訳と嘘ばかりを並べ立てた姿勢もさらなる批判を招き、慢性化が犯罪であるという自覚すら消し去ってしまう危険性も露呈した。
このような事実が深刻な社会問題として一般に知られるようになったのは、1998年の日本大衆文化の全面開放後である。これを韓国大衆音楽における黒歴史と言ってしまえばそれまでだが、表面的には文化交流がなかった時代でも、実は日本と韓国が音楽的感受性を共有していたことは、日韓交流史の面では重要な点と言えるだろう。
その意味で、80年代に「釜山港へ帰れ」で日本デビューを果たし、当時100万枚以上の売り上げを記録した韓国大衆歌謡界のレジェンド、チョ・ヨンピルを筆頭に、キム・ヨンジャやケ・ウンスクが演歌歌手として次々と日本で成功を収めたことは、日本からの影響がポジティブな結果として現れた現象のひとつである。そして韓国から日本に進出する流れの中で、90年代には3人組のガールズ・グループ、S.E.Sが大きな注目を集めた。J-POPの主な消費者である若者をターゲットにしたS.E.Sは、音楽番組だけでなく、バラエティ番組にも積極的に出演したが、メンバーの中で日本語が話せたのが在日出身の一人だけだったこともあり、日本での活動は言葉の壁にぶつかることになる。
S.E.Sの失敗から学んだのが、2000年代前半に日本で活躍したBoAである。日本の視聴者は次第に流暢になっていく彼女の日本語(=努力)を見守るうちに親しみを覚え、いつしか彼女を応援するようになっていった。こうして人気者になったBoAの成功によって、海外進出には言語の習得が不可欠と実証され、同じ事務所の後輩である東方神起をはじめ、現在のBTSやBLACKPINKまで、外国語能力は韓国のアイドルには欠かせないスペックとして踏襲されている。
そもそも韓国ではアイドル・グループという存在自体、日本の少年隊をモデルにしたと言われる消防車(ソバンチャ)が登場した80年代後半から始まっている。そして時を同じくして、アメリカのM-TV発のミュージック・ビデオが世界的に旋風を巻き起こし、韓国でも大衆音楽の新しい表現スタイル「音楽映像」として莫大な影響を及ぼした。ビジュアルやパフォーマンスなど、視覚的な要素が歌手が備えるべき「基本条件」になっていたのである。
そしてこの時期の韓国に、韓国大衆音楽(K-POP)の流れを大きく転換させたアーティストが登場する。ボーカルと2人のダンサーから成るソテジワアイドゥル(ソテジと少年たちの意)だ。中心となるソ・テジは、当時X-JAPANのメンバーだったTAIJIの熱狂的なファンで、東(日本)のTAIJIに対して西(ソ=韓国)のTAIJIというのが名前の由来である。ヒップホップの要素を取り入れ、ハードロックからヘヴィメタルまで、あらゆるジャンルを行き来しながら、当時の韓国が抱えていた政治的、社会的問題への批判的なメッセージ性を込めた彼らの音楽は、(私自身を含む)若者たちに熱狂的に支持された。とりわけ甘いマスクと舞台の上での爆発的なダンスパフォーマンスで「文化大統領」と称賛されたソ・テジは、まさに若者たちの偶像(アイドル)だったのである。このような新しいアイコンの登場によって、K-POPは、もはや歌唱力だけで勝負するような時代ではなくなりつつあった。うねりを上げて新しい方向へと突き進もうとしていたのだ。
グループとしての活動は4年で終わりを迎えたが、ソロになってもソ・テジの勢いが衰えることはなく、現在に至るまで第一線で活躍し大きな影響力を与え続けている。その象徴と言えるのが、2017年にソ・テジのデビュー25周年を記念して開催されたコンサートだ。このステージでソ・テジは、今や世界的な人気を誇るBTSと共演を果たした。現在のK-POPの原点を作ったソ・テジと現在のK-POPを担うBTSが、まったく古びることのないソ・テジの代表曲「난 알아요(僕は知っている)」や「교실 이데아(教室イデア)」などヒット曲を発表当時の振付で一緒に唄い踊る姿からは、ソ・テジが打ち出した流れが確実に受け継がれていることを実感できたばかりか、これまで海外では十分に知られていなかったソ・テジというミュージシャンを世界に向けてアピールする機会にもなったのではと、往年のファンにとっては実に感動的な出来事であった。
わが親友、チャン・ヒョンチョルのデビューもまた、K-POPの大きな変革期と時を同じくしていた。ヒョンチョルは歌唱力は抜群だったものの、失礼ながらいわゆるイケメンや美少年とは程遠い地味な顔立ちだったため、声とビジュアルとのギャップにがっかりしたというファンも多く、1曲の大ヒット曲を残していつしか忘れ去られていった。新曲やアルバムをリリースし、生き残りのために努力してはいたが、時代が彼に味方しなかったのだろう。ヒョンチョルの挫折は、K-POPがアイドル中心になっているアンバランスな昨今の前兆と言えるかもしれない。
それからおよそ30年、ひょんなことからバラエティ番組「(韓国版)あの人は今」に出演するヒョンチョルを久しぶりに目にする機会があった。そして韓国に暮らす妹から、彼がソウル近郊のミサリという街で、音楽カフェを営んでいることを知った。表舞台から消えた後も、彼は諦めずにカムバックを夢見ながら、小さなライブを続けてきたという。今度韓国に行ったらヒョンチョルの音楽カフェを訪れて、彼の歌声を是非ライブで聴いてみたい。そんな再会を心待ちにしている。
プロフィール
崔盛旭(チェ・ソンウク)
映画研究者。明治学院大学大学院で芸術学(映画専攻)博士号取得。著書に『今井正 戦時と戦後のあいだ』(クレイン)、共著に『韓国映画で学ぶ韓国社会と歴史』(キネマ旬報社)、『日本映画は生きている 第4巻 スクリーンのなかの他者』(岩波書店)、『韓国女性映画 わたしたちの物語』(河出書房新社)など。日韓の映画を中心に映画の魅力を、文化や社会的背景を交えながら伝える仕事に取り組んでいる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
