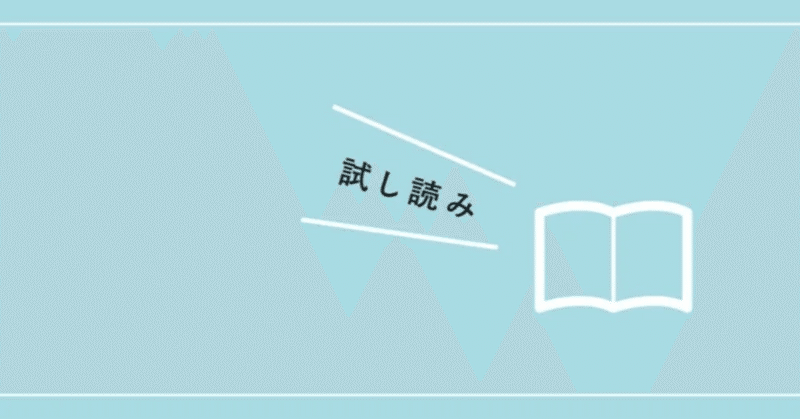
【試し読み】カワイ・ストロング・ウォッシュバーン『サメと救世主』(日野原慶訳)より(第一章「マリア、一九九五年 ホノカア」)
【訳者・日野原慶さんからのメッセージ】
小説はフローレス家の母親、マリアの回想からはじまります。ハワイ島ワイピオバレーでの、ある晩のことを思いだしながら、息子ナイノアに語りかけます――闇の中を歩くハワイの戦士たちの亡霊、ナイトマーチャーズを目にしたあの晩、おまえができたんだ、と。少年になったナイノアにふりかかった事件のことも語られます。一家で乗った遊覧船から落ちたナイノアがサメに救われるという、夢のような、ほら話のようなできごと。それをきっかけに、一家全員の人生がおおきくねじまがります。
小説がたどる一家の波乱に満ちた運命。時に神話のようで、時に痛いほど現実的な家族の物語。そこにはまた、ハワイの伝統と、アメリカの、いや世界の今のありようが、ともに刻まれてもいます。本心と規範、奇跡と常識、自然と文明とのあいだで揺れうごく、人間の姿が描かれてもいます。そんな『サメと救世主』のはじまりを、ぜひ読んでみてください。
「第一章 マリア、一九九五年 ホノカア」
目をつむりゃ、家族みんなまだぴんぴんしてて、神さまたちがあたしらになにを求めてたのかはっきり見えてくる。いろんなひとたちが言いふらすうちの家族の物語じゃ、あるすっきり晴れた日のコナ、サメがすべてのはじまりですってことになってるかもしれない、でも、まちがいだってあたしにはわかる。あたしらはもっと早くはじまってた。おまえも、もっと早くからね。ハワイ王国なんてのはとっくにつぶれてた―息する熱帯雨林も、歌う緑の珊瑚礁も、ビーチリゾートと高層ビルを建てるハオレ(白人)たちの手で壊されてた―そうして、土地が呼びかけてくるようになった。いまならわかるんだ、おまえのおかげさ。神さまたちは変化を待ちのぞんだ、そしておまえがその変化だった。はじめの頃、あたしもしるしは山ほど見た、信じなかっただけだ。しょっぱなはワイピオバレー、あたしとおまえの父ちゃんはトラックで素っ裸だった、そしてふたりで見たんだ、夜の戦士たち(ナイトマーチャーズ)をね。
ワイピオバレーまで行くのは金曜日のパウハナ(仕事終わり)で、カイキおばさんがおまえの兄ちゃんを世話してくれてた、あたしも父ちゃんもこういう子どもぬきの夜は、羽目を外すためにあるんだってわかってた、考えるだけで体がしびれた。だめなわけないだろ? どっちの肌もおひさまになでられて濃い色をしてたんだ、あのひとはまだフットボールの体だったし、こっちだってバスケットボールの体だ。愛をたしかめあうってのは、なにより燃えあがるあたしたちの習慣のようなものだった。それにワイピオバレーだ―緑がうっそうとしげる深い谷、それをつらぬく銀茶色のガラスみたいな川、そしておおきな黒い砂浜のむこうは泡だつ太平洋さ。
あのひとのトヨタのぼろトラックでゆっくり谷底にむかった。急カーブからの急カーブ、右むきゃするどい崖、砂利をタールでかためただけの道、きつい坂のせいで焦げたエンジンのはらわたのにおいが運転席にまでひろがった。
つづく泥の道はぐらぐらゆれた、谷底のぬかるみは腰の深さだった、それでも砂浜が見えてきて、そこをぐるりと囲むまだら模様の黒卵に似た岩のそばに、トラックをとめた―あのひとはあたしを笑わせてね、そのうち頬がちくちく熱くなって、かすんだ木の影が地平線にむかってのびてった。海はうなってざわめいた。あたしたちはトラックの荷台に寝袋をひろげた、あのひとはあたしの下にだけ石のにおいがするスポンジマットを敷いてくれてた、最後まで残ってた十代の若者たちもいなくなって―レゲエのずぶとい低音が森にきえてって―ふたりで服を脱いで、おまえをつくった。
あたしの思い出がおまえにまできこえるとは思わない、まさかね、だからそこまでピラウ(くさいもの)じゃないだろ、それに結局、あたしは思いだすのが好きなんだ。あのひとはあたしの髪を手のさきでにぎった、ハワイが黒く染めてねじったこの髪に惚れこんでた。あたしの体はだんだんまるまってあのひとの腰とおなじリズムを打ちはじめた。うなって、はあはあ呼吸して、まるい鼻を押しつけあって、体を引きはなして今度はまたがって、また体をくっつけると熱くって、寒い時のためにずっととっときたいほどだった。あのひとの指があたしの首をなでて、舌が茶色い乳首をこすった。あたしだけが知ってる、あのひとのやさしいとこだった。セックスの音が鳴ると思わず一緒に笑って、目をとじてひらいてまたとじて、一日から最後の明かりがきえても、かまわずつづけた。
寝袋の上で寝そべってた、涼しい空気がじめじめしたあたしたちをミントのようにつつんでた、その時あのひとが大まじめな顔になって、転がってあたしからはなれた。
「あれ見たか?」あのひとはそう言った。
なんのことかさっぱりわからなかった―あたしはまだ半分霧のなかで、あそこがもぞもぞするからふとももをすり合わせてた、あたしたちの愛のオイルの残りが漏れてきてたから―でもつぎにあのひとは跳ね起きて座る姿勢になった。あたしは膝だちになったけど、まだセックスに酔ってはいた。胸はゆれてあのひとの左脇腹にあたった、髪はあのひとの肩にかぶさった、そりゃ怖かったさ、でも色っぽい気分もあって、もういちどあのひとをあたしのなかに引きこみたいくらいだった。その場で、危ない目に遭うとかまあ置いといて。
「見ろよ」って、あのひとはささやいた。
「いいから」あたしは言った。「騒がないでよ、ロロ(おばかさん)」
「見ろよ」ってそれでも言った。だから見た、あるものを見てぎゅっとかたまった。
はるかとおくのワイピオの尾根の上で、明かりがながい列になってゆれてたのさ。尾根のさきをなぞるように、ゆっくりぷかぷかと進んでた。緑と白が、ちかちかまたたいてた、五〇はあったにちがいない、そのまま目を凝らしてると明かりの正体も見えてきた―炎。たいまつ。夜の戦士たちのうわさは知ってた、でもずっとただの迷信だとばかり思ってた、ハワイからきえちまったものを美しく歌おうとしてるだけだって、大昔に滅びたアリイ(首長)のオバケみたいな話だって。でも出てきやがった。尾根にそってすこしずつ行進してた。むかうさきは谷の真っ黒なふところさ、じめじめした暗闇のなかで、よくわからないなにかが、死にそこなった王たちを待ちかまえてたんだろ。ならんだたいまつの足どりは重かった、木々のあいだでまたたいて、しずんで、うかんだ。最後いっせいに火がきえる瞬間までね。
ばかでかい、きしむようなうなり声が谷に響いた。そこらじゅうをつつみこんだ。鯨が死ぬ前には、こんなふうに鳴くんだろうって思った。
おまえの父ちゃんもあたしも喉で言葉がつっかえた。体を起こすと荷台からとびおりて、体を服にねじこんで、つまさきをざらざらした黒い砂に突っこんで、とびはねてぜえぜえ言いながら運転席に乗りこんで、鍵をまわして、父ちゃんがばかでかいエンジン音をとどろかせて、谷の道を大急ぎで引きかえした。ヘッドライトは、岩や、ぬかるみや、あざやかな緑の葉っぱを照らしてった。そのあいだも覚悟してた、ふりむきゃオバケがうかんでる、そこらじゅうにいるって、見えやしないけど感じてた。ぼろぼろのアスファルトにできたわだちを踏むと車体がはねあがって、フロントガラスからは木が見えて、空が見えて、しずんだと思ったら泥に突っこんで、上下にゆれながら走った。ヘッドライトがとどくとこ以外すべて黒と青で、隠(かく)れ処(が)のような森をトラックですりぬけて、ながい道を出口まで突っ走った。あっというまに谷底からはぬけ出た、下を見ても谷の奥にとりのこされたような家の明かりがぽつぽつとあるだけで、なにもいなかった。真夜中でも、水を張ったタロイモの畑の影は白くうきでてた。
高いとこまで来てようやくとまった。車内はすこしも落ちついてなかった、エンジンも悲鳴をあげてた。
あのひとはゆっくり息を吐いてから言った、「どうなってんだよ」ってね。
神様がどうだとか話すのは、ほんとうに久しぶりだった。もうたいまつはきえてた、夜の戦士たちもいなくなってた。耳がどくどく動くのをきいてた。生きろ、生きろ、生きろ、って言われてる気がした。
よくあることだ。って、あたしたちは言いあった、直後も、何年たっても。まあ、ハワイで似たようなのを見たひとなら山ほどいる。カニカピラの(みんなで騒ぐ)時にはビーチのバーベキューでもラナイのハウスパーティでもいろんな話をたっぷり語ったけど、そこでもこういう話は尽きなかった。
夜の戦士たち―あの夜におまえをしこんで、生まれると何年かは妙なことばかり起きた。おまえのそばじゃ動物たちもおかしくなった―いきなりおとなしくなって、鼻をすりつけて、まるで仲間のように輪をつくった、にわとりだろうと、やぎだろうと、馬だろうと、すばやくしつこくね。裏庭でおまえが土や草や花を手いっぱいにつかんで口に放りこむのも見た、とりつかれたように。まわりのケイキ(子ども)たちがまぬけに見えるくらい、おまえの好奇心は強かった。植物のなかには―かごで吊るしたランなんかがそうだった―夢みたいな色で花をつけるのもあった、ほとんど一晩のうちにね。
よくあることだ。ってそれでもあたしたちは言いつづけた。
でも、いまならわかる。
一九九四年のホノカアは憶えてるかい? いまとそんなには変わらない。ママネストリートは、サトウキビ畑ができた頃からの低い木造の建物にはさまれてて、何度正面のドアを塗りなおしても、骨組みはむかしのまんまだった。色あせた自動車修理屋、いつもおなじチラシが窓にはってある薬屋、食料品店。町外れにあるあたしたちの借家は、塗装が何枚もめくれて、部屋は狭くてがらんとしてて、間に合わせのシャワー室はガレージの裏にあった。おまえがディーンと使ってたベッドルーム、あそこでおまえはサトウキビだか死だかの悪夢を見るようになった。
そういう夜。おまえはよくしずかにあたしたちのベッドのわきにたった、シーツに絡まったまま、体をゆらして、ぺしゃんこになった髪があちこちをむいてて、鼻をすすりながら息をしてた。
母ちゃん、またあれが起きたんだ、とか言ったもんさ。
なにを見たんだときくと、おまえの口からいろんな光景があふれでた―ひび割れてなにもかもきえた真っ黒な地面。土じゃなくて、あたしやあのひとやおまえの兄ちゃんやみんなの胸、腕、目から突きでたサトウキビ。それから蜜蜂の巣の内側みたいな音―それを話す目はおまえの目じゃなかった、おまえは目の裏にいなかった。まだ七歳だったのに、おまえからはとんでもないものがこぼれだしてた。でも一分くらいそうやって話すと、いつものおまえが戻ってきた。
ただの夢さってあたしが言うと、おまえはなんのことかききかえした。悪夢はこういう意味なんじゃないかって、あたしはくりかえし教えようともした―サトウキビも、あたしたちが刈りとられるのも、蜂の巣も―でもあたしに話したばかりの夢を、おまえはいつも憶えてなかった。まるでたったいま目覚めたら、すぐ前であたしが他のだれかの話でもしてるかのような、そういう反応だった。はじめ悪夢は二、三ヶ月にいちどだった、それが二、三週間にいちどになって、毎晩になった。
サトウキビ農園はあたしたちが生まれる前からあって、島のこっち側にはサトウキビがぼうぼうと生えてた、マウカ(山の方)からマカイ(海の方)まで。たしかにはじめから、みんないつか収穫できなくなると話してた、でもそのいつかはやってきそうにもなかった―「ハマクアはいつでも人手を探してる」って、あのひとも言った、うわさを散らすように手首をおおきく振りながら。でもそれから、おまえが悪夢を毎日見るようになってすぐ、サトウキビトラックの低いクラクションの音がいくつもママネストリートをかけぬけた。一九九四年の九月の午後だ、おまえの父ちゃんも運転手のひとりだった。
町の上から見おろしてたら、こんな光景が目に焼きついたはずさ―町に何台もトラックが入ってくる、たくさんの荷台と固定用のチェーン、載せるものがなきゃ腹をすかした動物のあばらみたいで、それをゆすりながらずんずん進んでくる。サルベージョンアーミーの事務所、教会、むかしは安っぽいプラスチックの輸入品を瓶に詰めてならべてた店先、通りをはさんでむかいあった高校と小学校、フットボールや野球やサッカーをするグラウンド。クラクションを鳴らしてトラックが通ると、みんな銀行や食料品屋から出てきて歩道や路肩にならんだ。出てこないひとにもきこえてたにちがいない、クラクションのあわれな音も、ブレーキの鳴き声も、仕事の寿命が尽きたのを悲しく歌ってたんだ。新しいからっぽのはじまりを告げてたんだ。にどと畑に出ることがないから、トラックは鏡みたいに磨かれて、作業汚れはあとかたもなかった。だから、家族そろって通りに出てきたフィリピン人やポルトガル人や日本人や中国人やハワイ人はみんな、自分らの浅黒い顔がつやつやの車体を滑るようにつぎつぎ映しだされてくのを眺めながら、これまでとはちがう真実を悟った。
あたしたちも人混みにまじってた、あたし、ディーン、カウイ、そしておまえ。ディーンはたちつくして、ちいさな兵隊のようにこわばってた。九歳だってのにばかでかい手でね、かさかさの手のひらでつつむようににぎってきたのを憶えてる。カウイはあたしの股の下でふらふらしてて、息で髪がゆれてふとももがくすぐったくて、そのあと二、三本の指をぎゅっと押しつけてきた。おまえは余った手のほうにいたね。ディーンの指とかたまった首からは混乱と怒りが伝わってきたし、カウイは四歳らしくぼうっとなにも感じてなかった、でもおまえはどっちともちがって、すっかり落ちついてた。
おまえがずっとなんの夢を見てたのか、いまならわからないこともない―死ぬってのがだれのことだったのか、あたしたちの体なのか、それともサトウキビなのか。まあ結局、おなじことだ。おまえはだれよりも前から、終わりが来るのを見てた。あれはふたつめのしるしだった。おまえのなかに声があって、でもほんとうはなくて、つまりおまえの声ではなくて、ただ喉を貸してただけ。その声は知ってることを、おまえに伝えようとしてた―あたしたちにもね―でもあたしたちはきこうとしなかった、まだその時は。
よくあることだ。ってあたしたちは言ってたんだ。
サトウキビのトラックは食料品店の前でつぎつぎ曲がってった、そのまま急な坂をのぼって町を出ると、もう戻ってこなかった。
農園がつぶれてからの数ヶ月、あたしたちはどんぞこだった。だれもが働くとこを探してた、おまえの父ちゃんもだ。あのひとは車で島のあちこちに何時間もかけて出かけてって、オバケみたいに逃げまわるお給料を追いまわしてた―そこだ、と思った瞬間、いなくなるようなやつを。オレンジの陽の光が木の床に反射する日曜の朝なんかにキッチンカウンターにいて、コナコーヒーの湯気がもくもくとわくお気にいりのマグカップ片手に、求人欄に指をあてながら読んでたよ、呪文のように唇を動かしながらさ。目ぼしいのがあった日にゃ、記事をゆっくり切りはなして指さきでつまむと、電話のそばに置いたバインダーにしまったもんだ。そういうのがない日は、鳥の群れがとびたつような音で新聞をぐしゃぐしゃにまるめた。
でもそんなことじゃ、あのひとの笑顔はきえなかった。どんなことでもね。物事がもっと落ちついてた時も、おまえたちがハナバタ(子ども)だった頃も。鼻水が上唇でかりかりにかたまって、よちよち歩きだしたばかりのガキんちょさ。そんなおまえたちをあのひとは宙に放りなげて、おまえたちの髪はばっとうきあがって、目は楽しそうに吊りあがった、いちばんに明るい声できいきい叫んでた。高いとこ目がけて力いっぱいなげてさ―雲にとどくようにって、あのひとは言ってた―だから、おまえたちが落っこちてくると、あたしも陽気じゃいられなくなった。いい加減にしてくれ、ってたのんだもんさ。カウイが相手の時は、とくに強く。
落とさねえよ、ってあのひとは言った。それにさ、首なんかが折れちまったら、もうひとりつくりゃあいいだろ、ってね。
こんな日もあった。朝なのに、あのひとはしつこくベッドにとどまった―たいていは早起きで、サトウキビトラックに乗らなくなっても変わらなかった―まるまってあたしにすり寄ってくると、薄いあごひげからくすくす笑ってるのが伝わってきた。ベッドカバーをもみくちゃにして逃げようとしても、あのひとはでっかい屁をこくと、あたしをそこにとじこめた。腹んなかでたっぷり寝かして火をつけたチーズと豆みたいなにおいだった。
引っこぬくほうが、入れるよりいい気持ちだろ、なあ? とか言いながら、あのひとは笑ってた。高校で五時間目をさぼってた時に戻ったみたいだった。ベッドカバーの下で屁をこいて、そうきいてきたのははじめてじゃなかった。前は、わかんないよ試させてみな、ってこたえて、あのひとの下着に指を突っこんで、けつの穴に突きさしてやったんだ。きーっとか叫んで、のけぞってたね、おい、行きすぎだ、そりゃやりすぎだ、とか言うもんだから、あたしは笑って笑って笑って、それでもまだ笑いつづけたよ。こうやって、お互いやりあうこともあったけど、しずかにしてるほうがうまくいくこともあった。洗面所で鏡越しに歯を磨いてる相手をただ見てたり、あたしたちの車を運転して―そうそうおまえが生まれるすこし前に、ぼろぼろのトラックから、ぼろぼろのSUVに乗りかえてたんだ―子どもたちをサイエンスフェアやバスケットボールの練習やフラの発表会につれていこうとしてたりね。
でも、もしも家の金すべてをカップに注いでも、半分くらいにしかならなかったはずさ。あのひともホテルのひとつでアルバイトにはありつけた、それだってだれもがうらやましがった、でもフルタイムの仕事はなかったし、レストランでチップをたっぷりってわけでもなかった。単に部屋掃除係のひとりさ、帰ってくるといろいろ話してくれた、ほとんど手をつけてないアヒ(マグロ)の皿がバルコニーに置かれててムクドリがむらがってたとか、床には火山みたいにたくさん洋服がつまれてたとか。ああいうハオレ(白人)たちはバケーションに来て一日二回服を着替える、っていうのも教えてくれた、「一日二回だぜ」ってね。
そのホテルの仕事だって、ほとんど舞いこんできたそばからきえてった、季節ごとの人員整理さ。あたしもマックナッツ(マカデミアナッツ)倉庫での仕事時間をぶった切られた。夕食は簡単なものになって、フードピラミッドなんて頭になかった。あのひとはできることをなんでも引き受けた、こっちじゃ家塗り、あっちじゃ庭師、友達の畑で腰を曲げて働くのも一日どころじゃなかった。ワイプアウトグリルでテイクアウトする晩もわずかだけどあった。背中をずたずたに痛めて帰ってきた。足も痛かった。目頭はドラムのように脈打ってた。たいていは入れちがいで、これから働くどっちかが、もう働いたどっちかにおまえたちをあずけて出かけてく。でもカレンダーを見れば、そんなシフトでさえ隙間がどんどん増えてった。それで、ある時ぷつりと出かける必要さえなくなって、計算機をにらんで残り時間ばかりを考える日々に変わった。
「これじゃもたねえよ」って、あのひとはあたしに言ったよ。夜おそくのことで、おまえたちはみんなぐっすりだった。吠える犬たちの声が道路に響いてた、でもやわらかな音だったし、慣れっこだった。テーブルランプの金色の明かりのせいで、あたしたちの肌はハチミツが塗りたくられたように見えた。あのひとの目は濡れてた。こっちをまっすぐ見ることもできなかった。しばらくあのひとの冗談をきいてなかったって、そこで気づいた。その時さ、ほんとうに怖くなったのはね。
「いくら残ってる?」ってきいた。
「厄介なことになるまでは、たぶん二ヶ月だ」って、あのひとはこたえた。
「で、そのあとはどうなる?」ってまたきいた、でもこたえは知ってた。
「ロイスに電話する」って返ってきた。「相談はしてたんだ」
「ロイスってオアフに住んでんだろ」って、あたしは言った。「航空券は五枚。別世界みたいな島だ、街だろ。街じゃあ安くはすまない」でもあのひとはもうたちあがって、バスルームに歩きだしてた。明かりが点いて、換気扇がまわって、水がしゃーしゃー流れて、排水口ではねる。顔を洗いながら、濡れた息を吸って、まき散らしてた。
動きも音もぱたっとやんで、いっそなにか割ってやろうかと思うくらいだった。あのひとはベッドルームに戻ってきた。
「だから思うんだよ」って言いだした。「おれの体を売ろうってな。相手が男ならオコレ(けつ)をやる、女ならボト(あそこ)をやりゃあいい。みんなのためにやる」
「おまえのためにやるんだ」ってつづけた。すこし間をおいてね。シャツは脱いでて、全身鏡にうつる自分を見てた。「ってのはよ、見てみるといい、なあ? この体はいつだってやる準備ができてんだ」
思わず笑っちまって後ろからあのひとを抱きしめた。胸のふくらみを手のひらでつつみこんだ。だらしない女の乳みたいに、だんだん垂れてきてるのはまあ、勘弁してやった。「あたしなら買うかもね」って言った。
「いくら出すよ?」にやにや鏡を見たままで、きいてきた。
「そうだね。どこまでしてくれる?」あたしは左手を下にずらして、あのひとのウエストのゴムのなかに滑りこませた。
「その時によるねえ」
「まあ、二、三ドルってとこだと思う」
「おい!」あのひとはあたしの手を引っこぬいた。
「それを一分ごとに払ってやるさ」肩をすくめながら言った。あのひとは鼻で笑った。でもそのまましばらく、かたまってた。
「売るのはあそこだけじゃ済まねえよな」って、あのひとは言ったよ。
ベッドのすみに、ならんで腰をおろした。
「カウイとナイノアにはディーンのおさがりを着せてる」って、あたしは返した。「給食もタダにしてもらってる」
「知ってる」
「昨日の晩飯はなにを食べた?」
「サイミンとスパム」
「おとといの夜は?」
「ライスとスパム」
あのひとはまたたちあがった。机まで歩いてって、体を落としながら手をついた。まるで机を押しだそうとでもするように。
「これは一五ドル」
また体をのばすと、ため息をつきながらドレッサーに手を置いた。「こいつは二五ドル」
「四〇ドルだよ」って、あたしは言った。
「二〇だ」あのひとは首を横に振った。
こうやって、目に入ったものにつぎつぎ触れてった―七ドルのランプ。二ドルの写真たて。五ドルの服だらけのクローゼット。あたしたちの生活をすべて足しても、四桁にだってならなかった。
算数はいつも苦手だった、でもこのさきなにがあるかははっきり見えた、つまり、薄暗い照明と、支払い期限と、シャワー代わりのバケツが、待ち受けてるってのがね。だから、あれこれ計算した三日後、おまえたちを学校に送ると、あたしは道端にたってヒッチハイクした、あのひとのハンティングナイフを鞄に入れてね。金をかけずヒロまで四〇マイルの旅をして、ハワイ州の役所の家賃補助窓口までは、じとじとした雨のなか、歩いてって申請ってのをした。「どうしました?」って、カウンター越しに女がたずねてきたよ、つめたい感じじゃなかった。色の濃い肌にしみのある腕、袖のないブラウスからはたっぷりとした肌が突きでてた。あたしの姉妹でもおかしくないひとだった、というか実際あたしたちは姉妹だ。
「どうしました」って、あたしはくりかえした。こたえがわかってたら、そこにたってるはずない。蒸し暑いヒロまで来て、家賃を助けてくださいなんて、頼んでるはずなかったろ。
あたしたちはそんな調子で、その頃にみっつめのしるしが来た。これ以上そぎ落とせる無駄は、残ってなかった。でもロイスが連絡をよこした、たった電話一本であのひとに「なんとかしてやれると思うぜ。ってのはよ―」とか話して、とつぜんなにもかもオアフにむかいはじめた。自分たちのものをいくらか売って、そのあとさらに売った。ワイメアの道路ぞい、公園のそばで、道をはさんでカトリック教会の正面にある、一面木陰になった駐車場に陣どって。ビーチに行くひとたちがかならず通るとこだった。その売りあげと、フードバンクの援助と、おまけの家賃補助に、かろうじて銀行に残ってた金額を足せば、オアフ行きのチケット五枚を買えるくらいにはなった。
あのひとは余った金の使いみちも決めてた―床がガラス張りになったボートでコナの海をクルーズするってね。だめだ、そんなことはしない、って反対したのも憶えてる。オアフのために最後の一セントまでとっておかなくちゃいけなかった。でもあのひとはききかえしてきたんだ、子どもたちに息ぬきもさせてやれないような父親になれっていうのかよ、ってね。
「あいつらだってもっとましな目にあうべきなんだ」ってのが言い分だった。いまでもよく憶えてる。「実際ましになるんだって思いださせてやりたい」
「でも観光客みたいにクルーズすることない」って、あたしは言った。「うちはそういう家族じゃない」
「まあ」って、あのひとはこたえた。「いちどだけ、そういう家族になってみたいってことさ」
なにも言えなかった。
それで、カイルアコナのアリイ通りまで出かけてった。山盛りの砂糖みたいな砂浜とまぶしい海、そのすぐ横にのびる低い岩壁とくねくねした歩道。観光客をねらった売りものがちいさな店にならんでて、パンくずのように海ぞいのホテルまでつづいてた。あたしたちはコナの船着場にたった、手にはボートのチケット、もちろんおまえたちの分も一枚ずつ。潮(しお)が満ちてきて、きれいに磨かれたボートがうねる波ではしからゆれて、しずんで、かがやくのを見てた。細ながいアスファルトの桟橋には釣り竿が何本もたってて、まんなかあたりまでならんだ地元の若い子たちは、ぎりぎりのとこからつぎつぎとびこんでった。飽きずに、何度も。自分の前の子がこさえたしぶきめがけて。じゃぼんっ、と鳴ったかと思えば、濡れた足で木の階段をぺたぺた歩いて元のとこに戻ってった。
こうしてコナの船着場から出発した。ハワイアンアドベンチャー号の、ふたりがけの気どりきったソファに座ってね。夕暮れ時なんかに、かすんだコナの海にういてるのをよく見かける三胴船だった。後ろには滑り台までついてて、屋根のあるデッキでロブスター色の観光客がぺちゃくちゃ喋りまくってるようなやつさ。でも、あたしたちの船は、まんなかの床がぶあついガラスになってて海を覗くこともできた。エンジンがデッキじゅう心地よく震わせて、海の色は青緑からもっと深い紫になってった。サンゴも太くおおきなかたまりに変わって、ところどころ指を突きだしたり、脳みそが花ひらいてるように見えた。イソギンチャクの尖った赤い輪っかは風にそよぐように波にゆれてた。太陽のにおいだった、ボートの枠にこびりついた塩がじりじり熱せられてたせいでね。フルーツパンチのマロロシロップは強烈に甘ったるい果実の香りだった。まわるエンジンが吐きだすディーゼルの空気は鼻につんときた。
ほぼずっと室内で腰かけてた。スタジアムのようにならんだきれいな座席のいちばん前で五人、ずっとガラス越しに海を見てたんだ。あたしはどの動物がどの神さまで、いちばんはじめのハワイ人たちを助けたのがこれで、戦ったのがあれだとか話してた。あのひとは自分のフィリピン人の祖先が、鼻のながいツノザメやゴンドウクジラばかり食べてたってことを面白おかしく喋ってた。天井からは陽が斜めに射しこんで、モーターの振動は椅子を伝ってきた。ぬるいようなおそいような感じがして、カウイがあたしの腕で眠ってるんだと気づいたのは、あたし自身がわけもわからず眠りから覚めた時だった。
おまえもディーンもあのひともいなかった。というか、展望室にはだれひとり残ってなかった。デッキで声があがってた。カウイを膝からどかして―あの子は文句をたれてた―たちあがった。やりとりは早口になって、みじかい命令になった―引きかえすぞ、見うしなうな、救命具を持ってこい。洞穴のむこうから、ずっととおくから、おまけに頭にコットンを詰めこまれてるような、そんなきこえかただったのを憶えてる。
カウイの手をつかんだ。目をこすったまま、ぶつくさ言いだしても、手を引いて展望室の階段からデッキに出た。とんでもなく真っ白だった。手をかざして、唇と歯ぐきが持ちあがるくらい、うんと目を細めなくちゃならなかった。なめらかな白いデッキを囲むケーブル手すりのそばに、ひとが集まってた。海を見てた。なにかを指さしてね。
あのひととディーンが見えたのも憶えてる。あたしとカウイからは三〇フィートくらいのとこだった。おかしいなと思ったのは、あのひとが手すりの前でディーンにしがみついてて、ディーンが大声をあげてたからだ。行かせろよ、おれがつれてくる、ってね。白いポロシャツに野球帽の乗組員が、赤い浮輪を放りなげるとこだった。ロープをしならせて、ゆらゆらとまわりながら、空へととびだしてった。
あたしはあのひとめがけて駆けだしてたんじゃないか? ディーンは手すりから引きはがされて、あたしの手は痛いくらい強くカウイの手をにぎってたんじゃないか? たぶんそうだ、でもそこは憶えちゃいない。記憶にあるのは、目を灼くほどに白いデッキであのひとの横にたったってこと、波でゆれて、あたしたちがいるのにおまえだけがいなかったってこと。
おまえの頭は海にぷかぷかうかぶココナッツのようだった。どんどんちいさくとおくなってって、波は音をたてて船に打ちつけてた。ぺちゃくちゃお喋りしてるやつなんかはひとりもいなかったはずだ。船長だけが、上の階から叫んでた―「見うしなうな。旋回するぞ。見うしなうな」
おまえの頭は見えなくなって、水面はまたまっすぐしずかになった。
スピーカーの音楽は鳴りっぱなしだった。薄っぺらくて甘ったるい「More Than Words」のハワイアンカバー、いまでもこいつだけはだめだ、昔好きだった曲でもね。エンジンはまわりつづけてた。上で舵をとる船長の声もきこえてて、テリー見うしなうな、って指示してた。テリーってのは、波にぽつんとうかんでおまえの頭からはどんどんはなれてく浮輪をなげたやつさ。
見うしなうなとか、待てとか言われるのに我慢ならなくなって、あたしはテリーになにか言ったんだ。嫌そうな顔してたよ。ひげの奥の口を動かして、あたしに言いかえしてきやがった。あいかわらず船長は上から叫んでた。おまえの父ちゃんも我慢ならなくなって、四人みんなで言ってやった。一気にまくしたてたとこでテリーはたぶん涙ぐんだ、そのせいでサングラスのまわりがぽっと赤くなった。あたしの顔がレンズに反射してた、思ってたよりずっと黒いから妙にうれしくなったんだった、それにバスケットボールの肩も見えたんだった、細めてた目はその時かっぴらいた。あたしが手すりに足をかけると、テリーはまゆ毛を吊りあげて、あたしになにか言おうとした。手ものばそうとした―父ちゃんもおなじ格好だっただろうね―でもあたしはだだっぴろい海に身をなげた。
たいして泳がないうちに、あたしの下をサメが通りぬけた。はじめは黒いもやだったのを憶えてる、でも水をゆらしてるのは動物の重みで、そいつらが通ったあとは流れになってあたしの足と腹を押した。あたしを追いこして、四匹ともひれを水の外に突きだして、黒い波のてっぺんからナイフが生えたようで、おまえがずたずたにされそうだった。おまえの頭が見えてたとこまで行くと、やつらはまた潜った。あたしも後ろから泳ぎだした、でもやつらは日本くらいとおくにいた。いちど潜って目を凝らしてみた。海のなかで見えたのは、ぼやけた闇と、サメがいるあたりからわいてくる泡だけだった。あとはいろんな暗い色。ピンク色がじゃれあうようにつらなって、泡のとこから上に、のびてった―いやな予感はしてた。
もう息はつづかなかった。水面から顔を出して、酸素をめいっぱい吸いこんだ。なにか音がして、あたしは叫んで、ボートはちかよってきたのかどうか、そんなのも憶えちゃいない。もう一回潜った。おまえがいたあたりでは水がめちゃくちゃにかきまわされてた。サメどもはむちのようにしなって、しずんで、うきあがった、まるでダンスみたいに。
息を吸おうとまた顔を出すと、おまえも水面にいて、頭をかたむけて、寝そべってた、ぬいぐるみのように、サメの口んなかで。でもね、サメはおまえを優しく抱いてたんだ、わかるかい? まるでガラス細工のように。自分の子どもを抱くように。あいつらはまっすぐあたしにおまえをとどけてくれた。おまえをくわえてたサメは犬みたいに頭をあげて、海に入らないようにしてくれてた。あいつらの顔といったら―これは嘘じゃない。サメがこっちに寄ってくるあいだ、あたしは目をぎゅっととじてた、あたしにむかってきてるんだってことも、もちろんわかってた。みんなは吠えて叫んでたかどうか、そうだったとは思うけど、それにあたしがなにか考えてたかどうか。なんも憶えちゃいないんだ。とじたまぶたの黒さと、言葉にならなかった祈りの他は、なんもね。
サメがぶつかってくることはなかった。あたしの体の下をぐるりと避けて通りぬけてった、暴れる風のような水のいきおいだった。そこで目をあけた。おまえはボートにいた。浮輪にしがみついてた。おまえの父ちゃんが手をのばしてた―もたもたしやがって、どれだけ腹がたったか、いまでも憶えてるさ。あんだけ時間があったんだ。こう言ってやるとこだった、おまえはあほなパウハナ(仕事終わり)の郡職員か? どうしてあたしたちの子に手をのばさない、まだ死んでもない子どもに―おまえは咳をしてたよ、つまり息をしてるってことだ、海のなかの赤い影はきえ失せてた。
よくあることじゃ、なかった。
きいてるかい。いまならわかるんだ、なにひとつよくあることじゃなかった。その頃から、あたしは、信じはじめたんだ。
(つづきは本編で)

*****
『サメと救世主』
カワイ・ストロング・ウォッシュバーン
日野原慶訳
http://www.kankanbou.com/books/kaigai/0616
四六判、並製、424ページ
定価:本体2,400円+税
ISBN978-4-86385-616-5 C0097
装幀 山田和寛(nipponia)
装画 原倫子
【著者プロフィール】
カワイ・ストロング・ウォッシュバーン(Kawai Strong Washburn)
ハワイ島のハマクアコーストに生まれ育つ。2020年出版の『サメと救世主』により、PEN/Hemingway Award for Debut NovelとMinnesota Book Awardを2021年に受賞。現在は、ミネアポリス在住。
【訳者プロフィール】
日野原慶(ひのはら・けい)
大東文化大学にてアメリカ文学を教えている。共訳書にモナ・アワド『ファットガールをめぐる13 の物語』、共著に『現代アメリカ文学ポップコーン大盛』(ともに書肆侃侃房)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
