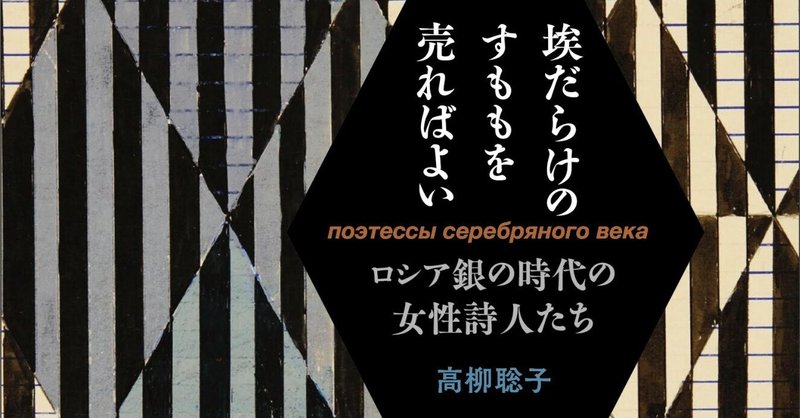
【試し読み】高柳聡子「マリア・シカプスカヤ 私の身体は私のもの」(『埃だらけのすももを売ればよい ロシア銀の時代の女性詩人たち』より)

『埃だらけのすももを売ればよい ロシア銀の時代の女性詩人たち』
高柳聡子
四六判、上製、184ページ 定価:本体2,000円+税
ISBN978-4-86385-604-2 C0095 装幀 名久井直子 2024年2月下旬発売
詩集とはある世界観の具現であった
ロシア文学におとずれた興隆期「銀の時代」(1890~1920年代)。ペテルブルクの古書店で偶然見つけた詩集を手がかりに、100年前の忘れられた15人の女性詩人たちのことばを拾い上げる。『女の子たちと公的機関』が増刷を重ねる著者による「web侃づめ」の好評連載が書き下ろしを加えて書籍化!
マリア・シカプスカヤ 私の身体は私のもの
「私の初めての本が出ました、私にとっては思いもよらない成功です。あなたにこの本をとっても送りたいのです、私の最初の師のあなたに」
1921年12月9日付けの手紙で、詩人マリア・シカプスカヤはクリミアにいるマクシミリアン・ヴォローシンにこう喜びを伝えている(チェルビナ・デ・ガブリアックを世に出したヴォローシンは、ほんとうに数多くの詩人たちにとって身内のような存在だった)。

マリア・シカプスカヤ(1891-1952)の詩人としての生はわずか15年、ロシア革命の後の1925年以降は詩作をやめ、ジャーナリストとして活動している。彼女の三人の子どもたちも、母がかつて有名な詩人であったことを知らなかったという、母の死後にようやく知ったのだと。子どもたちにも告げぬほどきっぱりと詩人であることと決別したのはなぜなのか、それすら語らぬまま去ってしまった詩人に、違う時代の違う国で思いを馳せることができるのも、詩が残されたからだ。詩人であることをやめるなんてできるのだろうか。
銀の時代の詩人の中でもひときわ個性的な彼女の詩は、「未来的」といってもいいほど。21世紀のフェミニズム詩だと言っても誰も疑わないのではないかとさえ思う。その作品は、「月経詩」などと揶揄されもしたが、それまでの詩人が語ることのなかった女性の身体の痛みをストレートに、そして豊かに表現するものであった。シカプスカヤの主題は、初めての性行為、そして月経、中絶の痛み、それから子を亡くした母の悲しみである。
私の体には入口がなかったから
黒い煙が体を焼きひらいた
人間という種の黒い敵は
獰猛に私の体に覆いかぶさっていた
そしてそいつに、傲慢さをしばし忘れ
私は最後まで血を与えた
親愛なる顔立ちをした
息子の誕生という希望のためだけに
(1921)
初めての性行為を描いたこの詩は、あまりにも大胆な言葉でどきまぎしてしまう。子どもが欲しくて〈獰猛〉な〈黒い敵〉に身を任せている〈私の体〉には〈入口〉がないというのだ。だから〈黒い煙〉に〈焼きひらかれ〉なければならず、その痛みは耐えがたい。けれども、獰猛な男に血を与える代償として可愛い息子に会える、その〈希望のためだけに〉激しい痛みに耐えたのだと。
ちなみに、ここで〈焼きひらいた〉と訳出した動詞палитьは、「焼き焦がす」という意味のほかに「発射する」という意味もある。そのためか、シカプスカヤの詩は、ポルノグラフィックだと批判されもした。けれどもむしろ逆だ。性的な含みをもつはずの語が、彼女の詩においては、あまりにも相手の人間性が削ぎ落されているために性的に感じられない。相手は男性ですらなく、痛みをもたらす何かなのだ。エロスは、今自分の体の上にいる性行為の相手ではなく、〈息子〉を授けてくれる高次の祈りとなっており、それが読む者に衝撃を与える。
20世紀初頭のこの時期、女性たちはそれぞれに、女性であること、自身の身体のことを謳ったが、シカプスカヤほど直截的に「痛み」に言及した詩人は稀だ。それもあってか、同時代人たちによる彼女の評価は明確に二分されている。象徴派の重鎮ワレーリイ・ブリューソフは、「いうまでもなくシカプスカヤの詩はよくない、これは詩というよりは私的な日記のページ」だと言ったという。ブリューソフのこの言葉には、詩とは、「私のからだ」のことではなく、より普遍的なものであるべきで、例えば、ギッピウスの詩行のように、形而上学的、精神的な高みを目指すものなのだといった芸術に対する先入観を見ることができる。「処女」膜が破れて痛いなどという女性の「私的」なことは、創作においてのみならず、日常生活においても黙っているべきだという社会通念がここにはある。
しかし、彼女を高く評価した人たちも多い。ソ連の代表的な作家となったマクシム・ゴーリキーもそのひとりだ。彼は、「あなた以前の女性は、こんなにも大きな声で確信をもって自分の意義を語りはしなかった」と、シカプスカヤに直接手紙で伝えているし、宗教哲学者のパーヴェル・フロレンスキイに至っては、「ツヴェターエワに比肩する詩人で、アフマートワよりも上だ」とも評価している(彼の神学者としての偏見はあるにしても、この評価は興味深い)。
そう、それが必要だった……
獰猛なハルピュイアどものための餌があった
そして体はゆっくりと力を失っていき
クロロフォルムが気を鎮め、寝かしつけた
私の血は流れていた 乾いて固まることもなく
前回のように嬉しくもなく
そのあとも私たちの困惑した目を
空っぽの揺りかごは喜ばせはしなかった
再び、異教徒のように我が子の命と引き換えに
われわれは人間の生贄を捧げている
だが汝は、おお、神よ、汝は死者らの中から
赤子の骨が割れるこの音に応えて立ち上がることはない!
(1921)
この詩は、冒頭でご紹介した詩の続編と考えればよいだろうか(同年に書かれている)。
ここで〈必要〉だという〈それ〉とは、中絶手術のこと。ギリシア神話の〈ハルピュイア〉は、女性の顔と鳥の身体をもった怪物で、鋭い爪で死者の魂をつかみ冥府へと連れ去っていく。中絶は、このハルピュイアへの〈餌〉やりに喩えられ、次の行では主語となった〈体〉が麻酔によって〈力を失ってゆく〉。またもや〈私の血は流れてい〉たが、前回は息子を宿す希望があったというのに、今回の出血はその嬉しさもない。〈目〉は〈空っぽの揺りかご〉を悲し気に見ている。
シカプスカヤにとっての愛は、常に子に捧げられるものだ。真の深い関係は、子どもとのあいだにだけあるのだと彼女は考えていた。大人は愛の対象とはならない、とりわけ男性は、痛みをもたらす存在でしかない。性行為や中絶の痛みはすべて男性のせいだと。
この詩では、生まれることなくあの世へ旅立った我が子への想いが吐露されているのだが、そもそも、この詩が収められた彼女の第一詩集『Mater Dolorosa(マーテル・ドローローサ)』(1921年)全体が、生まれなかった子へ捧げられたものだ。「マーテル・ドローローサ=悲しみの母」というタイトルは、磔刑となった我が子イエスを思う母マリアの悲しみの詩を指している。みずからを聖母マリアになぞらえ、会うことも叶わず天に召された子をイエスに見せんとする詩人の意図はおそらく、父や夫といった大人の男性が介在しない母と息子の純粋な関係に昇華させることにあったのではないか。おそらく彼女は、聖母マリアの処女懐胎を理想としていたのではないかとも思えてくるのである。

そんなシカプスカヤが詩を捧げる唯一の男性がいる。それは、神だ(神は男性なのかという問題はあるが)。けれども、その関係は複雑で、やはり私たちの想像を超えている。上に訳出した中絶手術についての詩においても、最後の連で、神は責められている。死者たちの中にいる神には生の苦しみなどなく、したがって、子を喪う悲しみとも無縁だろう、自分たちが苦悩するこちらへは来ないのだからというのである。詩人にとって神は、懐胎をもたらす力であると同時に、中絶の痛みと流血をもたらす者でもあって、まさに地上の男性と重なる。そして、その未来での出会いのために性行為の痛みに耐えたにもかかわらず、死んだ子は神に〈犠牲〉となって召されてゆく。痛みと出血だけを残し、子を奪う神をなぜ素直に愛することができようか。
このように、早く生まれ過ぎたフェミニストともいえるシカプスカヤは、1891年にサンクトペテルブルグに生まれた。両親とも相次いで病気になり、五人きょうだいの長女だったマリアは、11歳の頃から洗濯や床磨きなどの仕事をして家計を支えていた。1910年には同級生だったグレープ・シカプスキイとともに19歳で早い結婚をしている。そして3人の子が生まれた。
一方、1912年4月、シベリアを流れるレナ川の沿岸で、金鉱労働者らがストライキを起こす。英国資本のこの金鉱では、労働者らが過酷な労働を強いられ、危険な事故も相次いでいたからだ。しかし、これに対し帝国政府は軍を派遣、労働者らのデモ行進に兵士たちが発砲する事態となり、多くの死傷者が出た(レナ虐殺事件)。これに抗議するデモは首都ペテルブルグでも始まり、シカプスカヤは夫とともにこれに参加、逮捕されて二週間の監獄を体験している。
二人は一年後にも再び逮捕される(シカプスカヤの夫は電気技師だったが、活動家でもあった)。北方のカレリア半島にあるオロネツという町への追放を言い渡されたが、知人の助けを得てこれを免除され、ヨーロッパへの出国を許された。二人は、フランスのトゥールーズの大学で学び、その後はパリで一年間、中国語を勉強している。この時期、ヨーロッパにいたロシア文学者の面々とも知己を得て、どうやら充実した時を過ごしたようだ。
そのおかげで、1916年にロシアに帰国した二人の家は文学サロンのような趣を見せることになる。詩人のオーシプ・マンデリシタームや作家のニコライ・チーホノフ、フォルマリストのユーリイ・トゥイニャーノフらが訪れ、シカプスカヤは詩人として幸福で実りある時間を過ごしたに違いない。
その後は、1921年からの4年間で6冊の詩集を出したシカプスカヤだったが、詩人としての活動は、1925年をもって途絶えてしまう。以後は、ジャーナリストとなってルポや社会評論を専門とし、記者として、ベラルーシや中央アジア、シベリア、極東と各地をまわった。
そういえば、ガブリアックも同じような道を歩き、中央アジアで最期を迎えたのだったが、シカプスカヤは、1927年に無事にモスクワへ戻る。そして、第二次世界大戦後は、なんと犬のブリーダーになって、1952年に亡くなった際も、ソコーリニキ公園での犬展覧会の最中に心臓発作で倒れたのだという(この時期の彼女は犬に夢中だったと娘が語っている)。
彼女の三人の子どもたちのうち、末っ子のスヴェトラーナは2017年までご存命だったが、家族の手元には、1925年以降に書かれた詩はひとつもなかったそうだ。どうやら本当に完全に詩とは決別し、書くこともまったくしていないようだ。理由は定かではないが、いずれにせよ、当時としては非常に実験的で、エロティックにも捉えられがちな彼女のテーマが、20年代後半以降のソ連の文学界で受け入れられないことは火を見るよりも明らかだ。
実の子どもたちも知らなかった「詩人マリア・シカプスカヤ」は、後に欧米のフェミニストたちによって発見されることになるわけだが、ソ連では長いあいだ忘れられていた(彼女のルポ『方法と探索』は1968年に出版されている)。彼女の詩が思い出されるのは90年代の半ばになってからのこと。とはいえ、1996年になってようやく出版された彼女の選集の発行部数はわずか150部、2000年に出た選集も500部だった。そもそも1991年の生誕100年も、1992年の没後40年も忘れられたままだった。
けれども、文芸批評家のイリヤ・ククーリンが言うように、20世紀のソ連・ロシア文学には、フェミニズム批評というものがなく、1990年代に登場した女性詩人たちも正当な評価を得られないままだ。ここ数年でようやくフェミニズム詩というジャンルが定着し始めた。生まれるのが100年早過ぎた感のあるシカプスカヤの作品は、今こそ理解されるときなのではないか。

ちなみに、革命後のロシアでは、1920年に医療行為としての中絶手術が世界で初めて合法化されている。1921年に書かれた中絶の詩にはこうした背景もある。
私の身体の痛み、出血を伴う激しい痛みは、私だけにしかわからない私の出来事。子どもの命は奪うことができても、私の痛みを奪うことはたとえ神であろうともできない。その確信が私の存在の証となっている。そして、私の身体のことを語ることができるのは、ただ私ひとり。この権利もまた誰にも奪うことはできない。男が女の身体を語る時代は終わりなのだ、革命の雰囲気に満ちた新しい芸術の時でもあった銀の時代に、女性が自分の身体を取り戻そうとした抵抗の歴史がマリア・シカプスカヤの詩には刻まれている。
(※こちらは連載時の原稿です。書籍『埃だらけのすももを売ればよい ロシア銀の時代の女性詩人たち』とは一部ちがいがあります)
プロフィール
高柳聡子(たかやなぎ・さとこ)
1967年福岡県生まれ。ロシア文学者、翻訳者。早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。おもにロシア語圏の女性文学とフェミニズム史を研究中。著書に『ロシアの女性誌━━時代を映す女たち』(群像社、2018年)、訳書にイリヤ・チラーキ『集中治療室の手紙』(群像社、 2019年)、ローラ・ベロイワン「濃縮闇━━コンデンス」(『現代ロシア文学入門』垣内出版、2022年所収)など。2023年にロシアのフェミニスト詩人で反戦活動家のダリア・セレンコ『女の子たちと公的機関 ロシアのフェミニストが目覚めるとき』(エトセトラブックス)の翻訳を刊行。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
