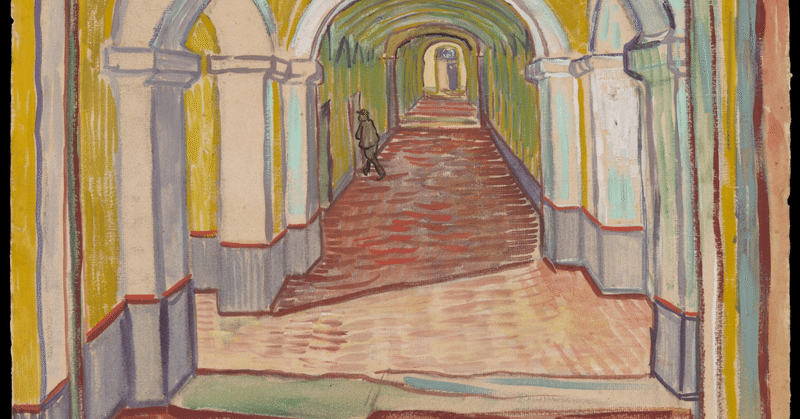
パーツ類のブランディング
第1 このエッセイでお話したいこと
ボルトやナットといったパーツ類のカタログをご覧になったことはありますか?
パーツの図面があって、寸法がズラッと表になって並んでいる、パーツ類のカタログはそんな感じです。
こんなパーツ類をブランド化しその価値を上げるにはどうすれば良いでしょうか?これがこのエッセイのテーマです。
以下の「パーツ類」を皆さんご自身の商品に読み替えて頂くとお役に立てるかと思います。
第2 何をブランディングと言うか
パーツ類をブランディングしその価値を上げるためにまず考えたいのはマーケティング系で言うブランディングなのか商標法で言うブランディングなのかと言うことです。
マーケティング系のブランディングをざっくりと定義するならば、
「売り物の理念を定義」して
「売り物の理念を消費者に伝える」と共に
「売り物の理念に相応しい品質を確保」して
「消費者の信頼を獲得し」以て
「永続的な取引を目指す」
という一連の活動でしょうか。
これに対して、商標法が説くブランディングとは、
商標を決まった商品に使用する
です。これによって商標と信用との一体化(=化体)を促します。
商標に信用が化体すると、その商標がつけられた商品は利益率が高くても売れると言うのが商標法の立場です。
お気づきの方もいらっしゃると思いますが、商標法が言う信用の化体とマーケティングの「売り物の理念に相応しい品質を確保」とはかなり似通った概念です。まぁ、後者の方が視野が広いでしょうが。
いずれ後者の話もさせて頂きたいと思いますが、ここでは前者の話に特化してお話をさせて頂きます。マーケティングの観点では信用の化体に重点を置き辛いのです。つまり見落としが生じやすい。
第3 品質で顧客を惹き付けるには
信用の化体をブランディングというなら、どう信用を化体させると良いのか。言い換えると、品質で顧客を惹き付けるにはどうすれば良いのか。
パーツ類というのはJISなどで寸法が決められています。その分制約も多い。他社との違いが出し辛い。品質が悪いのは論外ですが良ければいいと言う訳でもない。
品質に差があれば良いのではなく顧客が気付く差でないとダメなのです。顧客が気付くからこそ善き信用の化体がありますので。
では、顧客が気付く差とは何か?その前に皆さんどの程度の頻度でパーツ類を買いに行かれますか?私は十年ほどは買ってないと思います。
次に、パーツ類をどうやって選ぶか?私の場合、建設会社にいた頃は、パーツ類というのは資材庫にあるか、商社に規格を指定して注文するものでした。メーカーごとの品質の違いなど考えたこともありません。
つまり、パーツ類というものは商標を使っても信用を化体させることが難しい商品なのです。汎用性の高いパーツであればあるほどその傾向が強いように感じます。ではどうやって品質で顧客を惹きつけるか。
過去の知識経験を総動員して考えましたが、大まかには二つの選択肢があると思います。一つは顧客の再定義、もう一つは顧客の選択です。
まず顧客の再定義について。パーツ類を実際に使用するユーザを顧客と考えるのではなく、そのユーザにパーツ類を販売する商社・小売店を顧客と考えるというものです。
消費者はパーツ類のメーカーなど知らなくても、それらのパーツを販売する商社は当然メーカーを知っています。
メーカーを知っている商社は、顧客の苦情や行動を通じてパーツの商品を知ることになります。例えば大きな袋にたくさん入っていて安いとか、売り場の環境が多湿でも錆が生じにくいとか、包装が頑丈なのでそれにまつわる消費者のクレームが少ないとか。
そうすると商社は個々のメーカーについて「A社はとにかく安い」「クレームが少ない」といった印象を持つことになる訳です。それは信用の化体につながります。
こういう場合、商標は商品自体あるいはその包装につけるよりも見積書とかパンフレットとかそういった商社向けの資料に付けた方が良いと言えることでしょう。
一方、顧客の選択について。ありふれたパーツだけがパーツ類という訳ではありません。どこからでも入手できるような汎用性のあるパーツの他に、消費者がメーカーに直接発注するような特殊なパーツがあります。
そういったパーツの場合、消費者はパーツ自体の性能に加えメーカーのあらゆる対応をもとにしてメーカーへの印象を構築していくことになります。それもまた信用の化体でしょう。
この場合も商標は商品自体あるいはその包装につけるよりも見積書とかパンフレットといった資料に付けた方が良いと言えることでしょう。
第4 まとめ
パーツのような汎用性の高い商品でブランド化する場合には顧客の再定義や顧客の選択が必要だし、それに応じた商標の使用対象があるということをお話しました。
パーツ類に限らず、商標を使いこなすことは難しいものです。このエッセイがそういった使いこなしのお役に立てましたら幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
