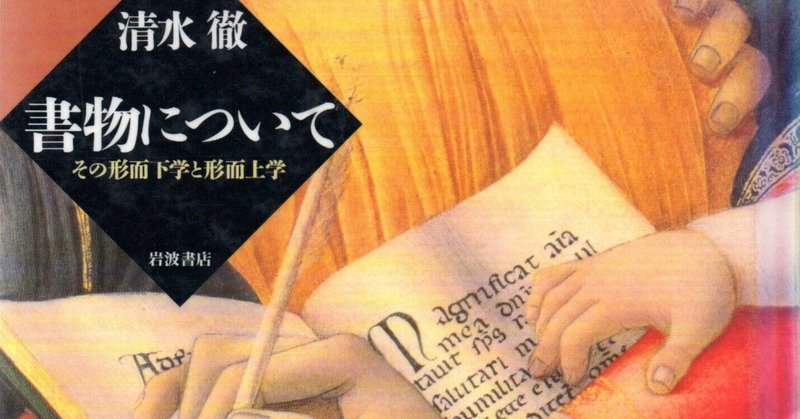
清水徹『書物について——その形而下学と形而上学』

岩波書店、2001年7月25日第1刷発行
ここ8年ほど、夜は8時頃に就寝し、朝は4時頃に起床する習慣で、2時間弱の「朝勉」を続けている。タイピングの練習を兼ねて、読みたい本をパソコンに入力するのが「朝勉」。知らない言葉や人名、作品などをネットで検索し、註釈をつけたり考えたことをメモしながら、本を丸ごと(一部だけの場合も)入力している。図書館で何度も貸出と返却を繰り返し、3か月ほどかけて入力し終えた本もある。
この清水徹著『書物について――その形而下学と形而上学』も、すでに4度ほど図書館で借り直している。「I 書物の考古学」「II 近代性と書物」「III マラルメと《書物》」は素読し、「IV バベルのあと」のみを入力し終えた。フランス中心とはいえ、これほど深く「書物の形而下学と形而上学の両面」について書かれた本は類例がないのではないだろうか。
「IV バベルのあと」では、ミシェル・ビュトールの厖大な著書群を軸に、「リーヴル・ダルチスト(Livre d’artiste、英語ではArtist’s Book)」が「書物」界に齎した美しい波紋について語られている。
▼マラルメの『賽の一振り』について触れたときに言ったように、白いページのうえに黒い活字の連続が描きだす「レース模様」は、活字の抽象性を補足する視覚性なのであり、わたしたちはページ面が活字の行の単純な排列――いわば活字配置のゼロ座標――というかたちをとっているときは、その「レース模様」のニュアンスをほとんど意識しない。しかし行の配置がふつうとはちがう何らかの形象性を見せているときは、活字から眼が汲みとる意味がただちに脳髄へと移行してゆくのではなく、活字から汲みあげられた意味に対して活字の配置具合の形象性は、単純には要約できぬ形象であるために意味と衝突し、次元を異にするそれらのあいだに改めて対話と相互滲透とが行われる。そういう読書過程はふつうのそれにくらべてはるかに複雑で、また豊かであるとも言えるだろう。(p.345)
※メモ書き
文字構成体=字面の入り組んだ複雑な灣(リアス式海岸)のような形象性と意味。
複数の文字の配列が生み出すいくつもの入り組んだ複雑な灣(リアス式海岸)のような形象が、それらの文字から眼が汲みとる意味と拮抗関係を結ぶように、あるいは相互滲透するように縺れ合う。「詩」を読む楽しみとは、その縺れ合いを解(ほぐ)すのではなく、縺れたままの形象と意味に眼を泳がせ、さ迷うことではないだろうか。
「そして、いま」と題されたIV章最後の節では、「紙」を「基底材(subjectile)」とした従来の書物を「石」に喩えた後、《電子革命》を経たスクリーン上の読書が「水」に喩えられ、現在の書物が孕まざるをえない「全体性と散乱への分裂」について語られる。
▼スクリーン上の読書の流動性は、《水》のそれである。《電子革命》とともに書物はわたしたちの想像界において「石」から「水」へという変貌を示しているかのようだ。実際、地球をとりまいてたえず無数の情報が「流れ」、そういう情報の「海」のなかを「滑りゆき」――そんな言葉がスクリーン上の読書についてたえず語られている。重さをもってせまってくるものから、重さからの離脱としての軽さへ、いかつさから柔軟さへ、ざらざらしたものから滑らかなものへ、――電子的エクリチュールはそんな変貌を感じさせる。しかし、いまの多くの著作家たちはパソコンを使って書いていても、そのテクストを伝統的な書物の形態で出版する場合が大多数であり、そこでは流動性、軽快性、柔軟性という想像界は消える。いやもしかしたら、《電子革命》以後の書物は、その側面のどこかで、流動、軽快、柔軟という電子的エクリチュールの作用を、いわば半透明で可動的な隔壁の向こうに位置させているのかもしれない。《究極の書物》と『賽の一振り』におけるマラルメの冒険以後、書物は、みずから意識するとしないとにかかわらず、全体性と散乱とを両極とする亀裂を内部にかかえているのだから。(p.352-353)
そして、《電子的書物》の理想的な在り様が、武満徹作曲の『ジェモー』に関連づけて語られる。
▼これまでの書物におけるように線形的で演繹的な想像力と論証の展開――文学の領域でたとえどれほど多義性が語られようと――によって言語表現の意味作用が編成されてゆくのではなく、個別化されたテクストや画像のストックのなかから、読み手の側の意向にもとづき選択と結合がなされ、選びだされたもののあいだの関係からつぎの選択を改めて考える、というような、非線形で、開かれた方式にもとづくさまざまな意味作用の構成を可能ならしめるような書物がここにある。武満徹の作品に、ふたつのオーケストラとふたりの指揮者によって演奏される『ジェモー』という曲があったが、いわば複数のオーケストラと複数の室内楽団と複数の独奏者とを可能態として含み、それらのひとつないしいくつかが組合せを変えながら代わるがわる演奏をつづけるような音楽総体に類比されるような書物=読書を想いうかべればいいだろうか。
そのような非線形で開かれた《書物》が、「紙」=「基底材(subjectile)」なしの《電子場》で、すでに達成されているのだろうか。それをなお《書物》と呼べるかどうかは差し置いて。
清水徹さん編集の懐かしくも奇妙な本『これは本ではない』の画像もアップしておこう。ミシェル・フーコーの『これはパイプではない』のpasticheだろうか。1969年『美術手帖』9月号には、宮川淳によるこの本の抄訳が掲載されているという。私はまだ9歳、小学校3年生。

エディション エパーヴ
1975年7月10日発行

1960~70年代は、日本における「アート」と「詩」との蜜月時代だったようだ。1992年、栃木県立美術館で開催された『本の宇宙――詩想をはこぶ容器』展での出品作も、ほぼ1960~70年代の作品が中心ではなかったか。あの頃は「アート」と「詩」とは、「睦みあい」ではない共振を実現していたのではないか。「詩画集」を見ることが稀れな今は、「アート」も「詩」もそれぞれに多様に複雑化し、互いが互いを意識し、響きあうような緊張した「磁場」を結べないのではないだろうか。私が目にして購入したものは、2011年7月29日 初版発行の平出隆さんと加納光於さんの共作『雷滴』(普及版)のみ。加納光於さん、平出隆さんついては、また稿を改めて書きたいと思う。

2011年7月29日 初版発行
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
