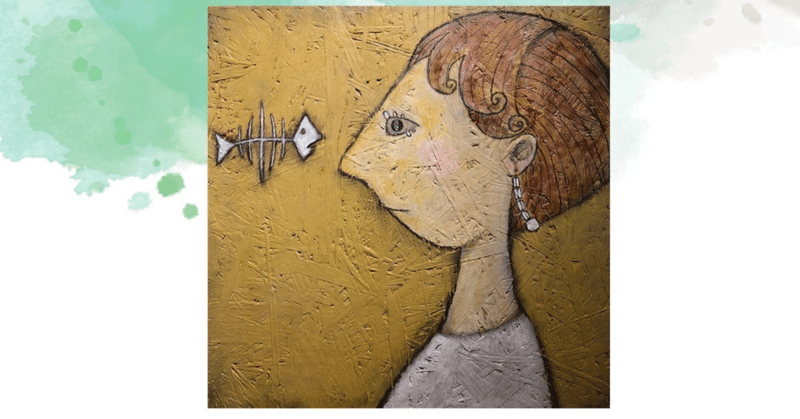
ピスポスホネートの構造式
以前、製本の仕事でとある劇団と関わりを持った。
演劇企画ニガヨモギ。
役者のほか、画家や造形作家などが所属しており、幅広いアートを取り扱った表現をする集団で、実は僕も製本屋として所属している。
製本屋。つまり美術製作のような立ち位置で入ったこの劇団だったが、この度役者として、新作「ピスポスホネートの構造式」の主人公役を務めることとなった。
昨日、その公演を終えた。
演劇に参加するのは初めてのことだった。
これまで、自分のライブなどで朗読をしたりすることはあったし、ちょっとしたひとり芝居をすることもあった。けれど、そのひとり芝居も、内容は基本的にアドリブで、決められた台詞を喋ることはしたことがなかった。
台本を渡されて間もない頃、他の役者たちと初めて台本の読み合わせをしたときのことを、今でもよく覚えている。
「本読み」と呼ばれるそれは、まだ誰も台詞を覚えていない状態で、台本を見ながら声だけでお芝居をするもの。そこに書いてあるものを読むのだけど、音読するだけではなくて、ある程度は「台詞」として演技しながら読む感じ。やってみてわかったけれど、これが本当に難しい。
普段やっている「読む」という行為は、もちろんほとんどが黙読だ。文章を文章として、自分のペースで、時には立ち止まったり後戻りしながら、頭の中をゆっくり整頓しながら進んでゆく。また、たまに朗読をしたりするときも、あくまでテンポを握っているのは自分だし、何より「ひとり」なのだ。そう、「読む」ときはいつも「ひとり」。それがこれまでの常識だった。
その日、本読みは2回やった。1回がだいたい1時間くらい。
1回目を読み終えたあと、演出から何点かの指摘が入る。この台詞はこういう意味、だからこういう気持ちが感じられるとよい、少し意識してみて。なるほどふむふむと聞きながら、台本に書き込みを入れる。
そうして迎えた2回目。あの時の感じは多分しばらく忘れないと思う。みんなで台詞を順番に読み上げていく中で、すごくすごくわかりやすく、僕だけがついていけなかった。それは、読むところがわからなくなったとか台詞をとばしたとかそういうことではなくて、僕だけが、ただただ音読をしているのを感じた。演技を乗せたい思いもあるし、さっき言われたことに意識を向けたいのに、思考が間に合わない。「読む」ということに手一杯になって、考えたり想像したり、それを表現したりすることに頭が回らない。けれど、他の役者が読みあげる台詞には、意思があり機微があり、そして1回目を踏まえた調整が感じられた。自分だけが、ただ追いかけるように文字を声に出していた。
ひゃー! と思った。声にも出たかもしれない。
それはとても色んな感情を含んだ「ひゃー」だったけれど、一番大きかったのは興奮だったと思う。今まで感じたことのない、まったく新しいつまずきだった。「読む」ということがこんなにも上手くいかなかったのは初めてだった。役者ってすごい。「読む」ことに相手を持つことって、こんなに難しいんだ。
でもその「上手くいかなさ」も、やってみるまで予想のつかないタイプのものだった。なにこれ難しい。全然思い通りにならない。こんなの久しぶりなんだけど。やったことないことをやってるんだなあ。ひゃー。
今回、演劇が未経験なのは僕だけだったので、周りには色々と心配をかけていたと思う。けれど僕自身は、本読みをはじめとした様々な「上手くいかないこと」を楽しんでいた。今までの自分の表現活動の中にはなかった、朗読やひとり芝居のような、一見よく似た形での表現の中にもなかった様々な困難が、演劇の中にはあった。それらひとつひとつが、いちいち面白かった。
この本読み以降にも、もちろんそれはそれはたくさんのつまずきがあったのだけれど、それは書き起こせばキリがない。とにかく色んなことにつまずきながら稽古を繰り返し、本番を迎えた。
「ピスポスホネートの構造式」は、飛行船を待つ青年の物語。
いつか見た飛行船をもう一度見たいと願う青年が、再会を夢見て河川敷を何度も訪れては、空を見上げる。そんな彼が、同じように様々な事情から河川敷を訪れる人々によって、とある事件に巻き込まれてゆく物語。
いずれ再演もあるかもしれないので、内部から詳しいことは語らないけれど、本番当日、はじめて見えたものがたくさんあった。今までやったどの稽古よりも楽しかったし、気持ちが入っていた分、苦しみは苦しかったし、美しいものを美しいと思った。一瞬みたいな時間だった。
この作品は、製本屋として関わった前作「バラと飛行船」とつながる物語である。バラと飛行船の時に思っていた飛行船の姿を、昨日はステージの上で見ていたように思う。
こういうことは終わってみればいつもあっという間だ。
昨日の終演後の楽しかった打ち上げを思い返し、今日はちょっぴり寂しい気持ちで過ごした一日だった。
「バラと飛行船」の時にも、翌日が寂しくてたまらなかったことを思い出す。そういえば、その気持ちをどこかに書きたくて始めたのがこのnoteだった。
このたび初めて役者というものを体験してみて、まだまだきっと僕が見たものは演劇の世界のほんのちょっとの端っこなのだろうと思う。だから、まだなにもわかったようなことを言うつもりはないけれど。
それでも体験として、誰かを演じるということは、自分の中にその役の居場所を作ることなのかも知れないと思った。
今、僕の中には「青年」の居場所がある。そして彼が、今日も河川敷を目指したがっているような気がする。そこで出会った人に、会いたがっているような気がする。
この言いようのない寂しさを、今はそんな風に考えている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
