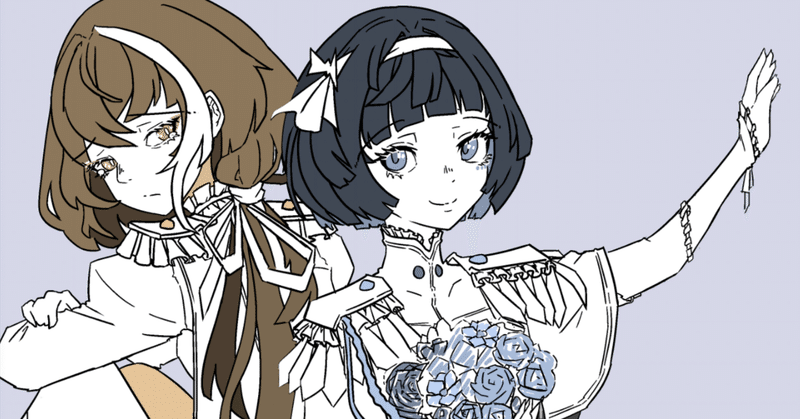
罪と楽園 : 情熱が残る離別
『罪と楽園』が終わったあと、自分の中には良い映画を観終わった感動と同じような感覚が渦巻いていた。それと同時にこう考える、このライブを観てそんな受け止め方をしている自分には、きっと彼女たちについて何か書く資格は無いと。
資格なんて無いまま無責任に通りすがりの人間として書こう。
『罪と楽園』は別れの舞台としてあまりにも綺麗だった。
第一印象
かつてライブ『Albemuth』を観たとき、明透に対してはその天真爛漫さの背後に隠れた聡明さに驚きつつ好感を抱いた。特にメタ認知の領域、つまり「自分がどんな風に感じているのか、どういう思考の癖があるのか、それは何故なのか」と客観視する能力の高さが伝わってくる。
その一方、ライブという舞台で改めて存流の言葉を聞いて抱いた最初の印象は「掴みどころのないフワフワとしたイメージ」だった。
自分に語彙力が無いので不躾な表現しかできないが、ネガティブに言えばどこか非常に微妙な点において「本心が話されているように感じにくい」という印象があった。これは実際にどうかという話ではなく、受け手にとっての印象だ。語られる言葉が慎重に選ばれているような、感情すら不意に出るのではなく意図して出されているような。
存流はしばしば「話すのが得意じゃない」と語っているが、それは別に言葉にする能力が低いということじゃない。むしろ言語感覚が優れているからこそリアルタイムで言葉を紡ぐことにどこか躊躇があるようにも思える。自分の話す言葉がどれくらい的確か、相手にどういう印象を与えるのかに鋭敏だからこそ口に出す前に考え込んでしまう。率直に表現することへの怖れであり慎重さのように自分は感じる。
そうした性格に加えて、存流が明確なイメージ像を纏うタイプのアーティストであることが組み合わさって冒頭の「掴みどころがない」印象を自分に与えていた。
この印象それ自体は良いとも悪いとも言えるものではない。ないが、おそらく自分はこれで存流への見方を間違った。彼女の話を素直に受け取るのではなく「言葉や表現が何を意図しているのか」「作為のない率直な部分がどこかに現れるか」とまず無意識に考えてしまうようになったからだ。
『罪と楽園』
ともすればアーティスト自身の魅力や能力だけが注目されがちだが、ユニットという活動形態ではプロデュースをする側の「やりたい・創りたい・魅せたい」という意欲と創造性が魅力に強く影響するのだと思う。
Albemuthはプロデュースの面からも意思と演出が注がれてきたユニットだった。それはライブの構成といった骨子から、楽曲の命名規則といった枝葉に至るまで行き渡っていた。冒頭の「良い映画を観終わった感動と同じような感覚」という感想もおそらくそうした部分から生まれている。
対照的な個性を持つ二人の組み合わせ、理想的な美しさを描く「皓」と退廃的な人間らしさを歌う黑の多面的な楽曲展開、二人だけしかいないような世界観。
二人のソロパートが重視された去年の『Albemuth』が「存流・明透 1st TWO-MAN LIVE」と冠されていたのに対して、『罪と楽園』が「Albemuth 1st ONE-MAN LIVE」と冠されることに象徴される通り、今回はAlbemuthというユニットへ全振りする構成になっている。
例外は長く続くアンコールの声に答えた『いのり』だが、それも寄り添う明透によって「生まれ変わったら巡り合いたいよ」と声を重ねられる。『Albemuth』も『罪と楽園』も、今までに歌われてきたどの曲も素晴らしい。しかし、もっとも印象深いのはこのアンコール後の『いのり』『饒舌な星』、そしてAlbemuth最後の曲である『舟』だ。
『いのり』と『饒舌な星』は、この別れに先んじて作られていたことが信じられないほど歌われる内容が突き刺さる。そして『舟』はあまりに完成された曲で、自分なんかがここで何かを付け加えて言及する気にもならない。曲そのものと彼女たちの軌跡が全てだ。
そして、この3曲を聴いていてようやくわかったことがある。先に書いたように自分は存流の言葉を素直に受け取れず、変に考えすぎていた。しかし一方で、彼女の歌はなんの引っかかりもなく、率直な本心として受け取れている。
これは全く理屈に合わない話だし、なぜそう感じるのかという根拠もない。しかし考えてみれば、まさにそうしたことが歌が魔法に例えられる理由で、彼女が歌うことを選んだ理由なのかもしれない。
情熱が残る離別
『Albemuth』のパンフレットで他でも無い存流自身が語っていたように、一緒に歩んでいける人間は簡単に出会えず、その関係を続けていくことも当然に叶うことではない。この世界では日常として誰かしらが舞台を去っていく。
そして、大抵の場合はその別れ方すらも不本意なものだ。活動の節目も別れの場すらもなく、事務的な広報文だけで紡がれてきたものがあっさり切れる。それどころか、明確な終わりや別れすらもなく、少しずつ活動が絶えて人々の耳目が離れるままに去っていくことも多い。
アーティストの活動に限らずプロジェクトやビジネス全般で言えることだが、関わる人間の情熱が失われたものは終わるのではなく、凍結される。
きちんと区切りや収拾をつけるにはそれを始めるのと同様に労力と手間がかかるが、終わらせるときには関わりたい人間もオーナーシップを持つ人間もいなくなってしまうことが多い。誰だってこれから素晴らしい未来や利益が見込めるものに時間と労力を注ぎたいのだ。
ゆえに送り出されることもなく、ただただ凍土の上に置かれる。契約が切れるまで、誰かがWebサイトからその名前を削るまで。
なぜ存流が舞台を去るのか。それは語り得ず、語るべきでなく、語りたくない。だが一つ言えるのは、この『罪と楽園』というライブには、『存流』の離別には、悲しさの中に燃えるような情熱があった。当人も支える人々も真摯に別れと向き合って、労力と想いと慈しみを惜しみなく注いでいる。だからこそ、ライブを観た人間の記憶にこれからも残り続ける。
自分がいまさらにライブから、インタビューから、歌詞から、存流とAlbemuthをもっと知ろう理解しようとしているのはいくらか馬鹿げている。終わってしまったものに、もう続くことがないものに「もっと知りたい」「もっと聴きたい」なんて、タイミングが遅すぎる。だがそうしてしまう人間は決して自分だけではないだろう。きっとこれからも多くの人々が残された歌を聴いては彼女がいた日のことを思い出す。
本当はこうした機会にもっと存流のことを、彼女に関する思い出や感謝でも書くべきなのに、自分は演出がどうだの構成が何だのつまらない話ばかりこうして書いてしまう。
冒頭で前置きした通り、通りすがりの客である自分には本来なにかを語る資格なんてない。Albemuthの二人によって生み出される曲を、存流が作り出すものをもっと聴きたかったなんてことを自分が口にすべきではきっとないし、これからも彼女のことをずっと心に留めておくなんてことも言えない。
それでもせめて今だけは、新たな旅へと舟出する存流に、舞台に留まり歌い続ける明透に、きっと望ましい未来があることを祈りたい。また自分が彼女たちの歌に感動したことを一度でも多く思い出せるように書き留めておきたい。
