
歌の翼に~とみのいのみず・亀井の歌と聖徳太子の歌・全(約1万字)
「日出ル国」の原風景~史跡四天王寺亀井水2015年作成レポートより、抜粋
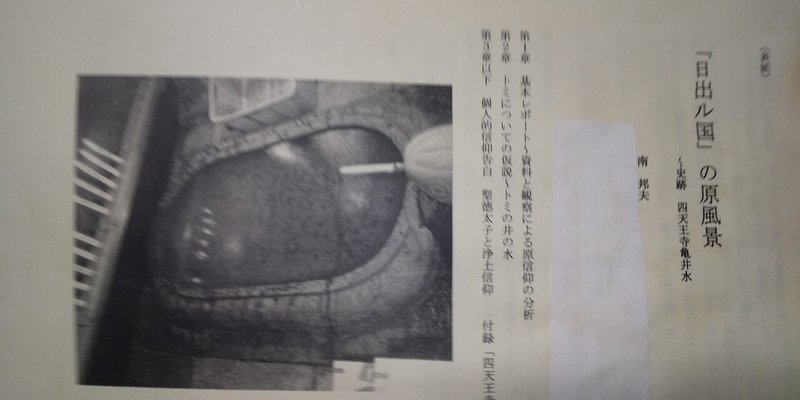
亀井の歌・とみのをがは
亀井という名前が確認できるのは、相模家集の中の次の歌が最古のもののようです。
「千代すぎてはちすの上にのほるべきかめ井の水に影は宿さん」
「栄花物語」によれば、1031年、時の皇后藤原彰子(しょうし)が四天王寺に参詣し、亀井の水を手にすくい歌を詠みました。
「濁りなき亀井の水をむすびあげて心の塵をすすぎつるかな」

(紫式部日記絵巻・鎌倉時代、より藤原彰子)

彰子の文化サロンの才女達が、亀井を歌に詠み交わします。残念なことに、紫式部はすでに亡くなっていたようです。紫式部の証言が残されていたら、亀井水はもっと注目されていたでしょう。まず、栄花物語の作者ではないかと推測されている、赤染衛門。
「こふをへてすくうこころのふかければかめ井の水はたゆるよもあらじ」
むすぶ(掬ぶ)にかけて、すくう、という言葉で彰子の歌に答えています。
そして、わが息子を宮廷サロンにデビューさせるべく和歌の代作までしたといわれる教育ママとして知られる、弁乳母は。
「よろず代をすめるかめ井の水やさはとみのをがわのながれなるらん」
赤染衛門の歌の、こふをへて(永遠に)という言葉に、よろず代をすめる(澄む、と住むのかけ言葉)と応じるのです。
しかし、ここでふと首をかしげます。
「とみのをがわ」とはなんでしょうか。
江戸時代の文献の引用では、とみ、は、富の字に書きかえています。
片岡山の餓え人
この、とみのをがわ、の語源は、998年の「拾遺和歌集」の、聖徳太子の伝説の次の歌にあるようです。全文を引用します。
「聖徳太子、高岡山辺道人の家におはしけるに、餓たる人、道のほとりに臥(こや)せり。太子の乗り給へる馬、とどまりて行かず。鞭を上げて打ち給へど、後(しり)へ退きてとどまる。太子すなはち馬より下りて、飢えたる人のもとに歩み進み給ひて、紫の上の御衣を脱ぎて、餓人の上に覆ひ給ふ。歌を詠みて、のたまはく
しなてるや片岡山に飯(いい)に餓へて臥せる旅人あはれ親なし
になれになれけめや、さす竹のきねはやなき、飯に餓へて、臥せる旅人あはれあはれという歌也
餓人頭をもたげて、御返しを奉る
いかるがや富緒河(とみのをがわ)の絶えばこそ我が大君の御名をわすれめ」
この餓え人は、実は高貴な真人(しんじん)であったと、日本書紀は解釈します。さらに、それは達磨大師の御変化であったという伝説へと展開し、そのゆかりの地に達磨寺が創建されるのですが、あえて現代的な解釈を試みるならば、素朴に行路病者への太子の心配りを伝えるものと考えるほうがより純粋な精神性を感じさせます。

(達磨寺。奈良県王寺町)
富雄川水源地とタナバタツメ伝説発祥の地私市(きさいち)
この、トミノヲガワ、は現在も斑鳩の地を流れている富雄川のこととされています。古くは富小川とも書かれましたが、本来の意味はこの歌の表記のように、トミを水源とする川、緒はその元という意味です。
トミは、生駒山地北部の丘陵地。現在は登美丘と書きますが、古代畿内の原住民トミの本拠地です。推古帝が大后となったときに与えられたとされる領地を意味する私市(きさいち)=キサキの土地、の地名が残る私市園地のハイキング公園になっています。日本書紀には、私市部と同時に日祀部(ひのまつりべ)が大后に与えられたと、書かれていますが、私市の一帯は、星田、天の川、妙見、といった地名が残り、日本の七夕の始まりである織姫タナバタツメの伝承が語られます。天の川の上流にはニギハヤヒの降臨の地とされる巨大な舟形岩を祀る磐船神社が鎮座します。


(磐船神社)
皇后直属の天文観測センターであり、ヤマト王権成立前のやまとの歴史を秘めた宗教ゾーンでもあります。前章(本稿では省略)で簡単にふれておきましたが、四天王寺亀井水から見ると、夏至の日の太陽の日の出の地でもあります。一方、冬至の日の日の出の地である生駒山地南端部は、聖徳太子開山の山岳霊場である信貴山となります。
富雄川はトミから、斑鳩を通り、大和川へと合流します。
弁乳母は、亀井水は富雄川のように神聖なものであると、歌ったわけです。
太子の人徳をトミノヲガワにたとえる歌がよく知られているならば、亀井水もまたそのようなものである、という解釈には何の不自然さもないといえます。しかし、具体的な富雄川と四天王寺の位置関係を考えるなら、どうにも不自然です。弁乳母が方向オンチであった、というならそれまでの話ですが、後世の人々は西方浄土とトミノヲガワをむすびつけるのに多少のためらいはあったのではないかと思います。
東への太陽信仰があった、という私の分析によれば、トミと亀井水をむすびつけるのにそう躊躇いはありませんが、弁乳母の時代には西方極楽浄土信仰のみが語られていたでしょう。もし、亀井水の原初の名前がトミの井であった、それが一部のお坊様に語り継がれていたということがあったならば、話は簡単です。が、早急な判断は避けておきましょう。
「とみのをかは」と無熱池
この、トミノヲガワの伝承の歌の元をたどってゆけば、「上宮聖徳法王帝説」に残された、巨勢三杖大夫(こせみつえのまえつぎみ)という人物がうたった歌です。ただしこちらは、太子の死の直後、それを嘆く悲歌で、ニュアンスはちがっています。助詞の使い方も異なります。原文は上代かなで漢字表記ですが、ひらかなに書き下すと、
「いかるがのとみのおがわのたえばこそわがおおきみのみなわすらえめ」
となります。この歌については、あとでまた考えてみたいと思います。
時代が下って、1533年三条西実隆は四天王寺参詣の奉納歌として次のように詠います。
「汲みてしれ絶せぬ法の水はみなとみの緖河の末にやはあらぬ
まれにきてむすぶ亀井のみづからや浮木にあへるたぐいなるらん」
江戸時代の文献では、トミの表記は、すべて富におきかえられてしまいますが、古代のトミの表記は富の発音とは異なるものです。ここでは、まだトミは弁乳母にならって、とみ、とひらかなのままです。ささいなことですが、気をつけておきたいと思います。
さて、これも前章(本稿では省略)でふれましたが、実隆の時代のすこし前、15世紀、世阿弥・元雅父子による謡曲「弱法師(よろぼし)」では次のように語られます。この場面は、四天王寺の縁起を語っておめぐみをもらう弱法師とよばれた盲目の乞食が、我が子俊徳丸であると父通俊(みちとし)が気付くクライマックスに朗々と語られます。重要な資料ですから、再確認しておきます。
シテの語りは、弁乳母の歌をほぼそのまま引用しています。
「シテ(俊徳丸)。万代(よろずよ)に、澄める亀井の水までも、
地歌。 水上清き西天の、無熱池(むねつち)の、池水を受け継ぎて、流れ久しき世々までも、五濁の人間を導きて」

(弱法師)
弁乳母が、とみのをかは、とする亀井水の源を、無熱池、と語ります。
無熱池は、無熱悩池とも言われ、仏典のなかではサンスクリット語anavataptaの音写として阿耨達池(あのくだっち)と呼ばれる湖です。毘沙門天の宮殿があるとされるカイラーサ山の麓にあり、マーサナ湖とも呼ばれる。カイラーサ山、マーサナ湖とも実在のモデルのある聖地で、ガンジス、インダスの両大河、プラマプト川の源流ヤルンツアンボ川などの分水嶺にあたるカンリンポチェ山一帯の地域とされる。無熱池は、「大唐西域記」には、菩薩が龍王として潜み、清涼な水を吐きだしていると述べられています。文字通り、熱も悩みもない涼やかで美しい湖です。
亀井水が東へ流れる水ならば、水源は西の彼方にある。自然な発想ですが、チベット高地のはるか向こう、ヒマラヤ山脈の彼方へと展開する思想と、斑鳩の富雄川との結びつきはいささか混乱してきます。やはり弁乳母の方向オンチというしかないのでしょうか。

(あのくだっち、無熱池のモデルとされる、マナサロワール湖。中央に見えるのがカンリンポチェ山、カイサル山)

(カンリンポチェ、カイサル山)

(カイサル山上空からマナサロワール湖を見る)
上町台地の大地下水脈

(大阪城、歴史博物館10階からの展望)
さて、上町台地の地下水は南から北へと流れているはずです。その終点は大阪城のお堀です。広大なこのお堀の水は、すべて地下水で満たされていて、回りの川(大川、寝屋川)とはつながっていません。その巨大な水脈の一部が台地の頂上部である古代荒陵(あらはか)つまり四天王寺に湧出しているのです。あたかもその支流であるかのように、四天王寺の東西に地下水の湧出地が集中しています。西には天王寺七名水と呼ばれた水源はじめ、愛染さんの井戸や名料亭浮瀬(うかむせ)の井戸などがありました。東には、谷の清水と呼ばれた名泉があったとされますが、場所は定かではありません。また、四天王寺の東北、表鬼門の艮(うしとら)の位置には方位除けのご利益がある五条宮があり、その裏には毘沙門池という大きな池がありました。名前を印した石碑がありますが、今は埋められて、天王寺区役所が建っています。
聖徳太子の歌、日本書紀と万葉集
さきに「拾遺和歌集」の聖徳太子の歌を見ましたが、この歌の原型は、日本書紀、万葉集にも残されています。
いずれも、路上死者や行路病者に対して、太子が慈悲のまなざしをもって歌われたものです。四天王寺は単なる寺院ではなく、四箇院と呼ばれる医療、福祉を総合した国家政策のもとに創建されました。寺院は仏教を中心とする学問研究をする場として敬田院とよばれます。医療をになうのが、薬学部にあたる施薬院と、医学部にあたる療病院。そして貧者救済など多様な福祉にあたるのが、悲田院です。
この四箇院制が、推古元年の創建時に計画として存在したのか、あまり真剣な議論はされてこなかったのではないでしょうか。もっとも、四天王寺の太子創建さえも否定するのが常識のようになってきました。地元有力渡来系豪族の氏寺が、勝手に太子創建と名乗ったにすぎない、という説が一部の学者には硬く信じられています。四天王寺の歴史的価値を否定するのは、明治政府の文教政策からはじまり、ひとつの知的ファッションになってしまったこと、そのなかで四天王寺関係者がいかに権威をとりもどそうと苦しんだのかは、先の基本レポート(本稿では省略)に述べたとおりです。そんななかでは、亀井水は、ありえない遺物として無視されてきたのです。くりかえすのは、愚痴になりますからやめましょう。
悲田院は、今はJR天王寺駅の一帯の町名として残っています。また、その活動の記録は江戸時代の詳細な文献として残されています。貧者救済施設は被差別部落として扱われながら、重要な治安活動に従事していたようです。
文献上、施薬、療病、悲田、といった庶民救済事業が確認できるのは、聖武天皇の時代、国分寺(金光明四天王護国之寺)と国分尼寺(法華滅罪之寺)の造営を全国に指示したときのようです。国分尼寺の総本山、法華寺には、光明皇后自ら病人の垢すりをした伝説が伝わっています。滅罪の寺という名前からも感じられるように律令制国家の成熟とともに人間の業の深さも自覚されていったのでしょうか。その淵源として、聖徳太子信仰と四天王寺が果たした役割はどんなものだったのでしょう。国分寺とその総本山である東大寺の名前が、四天王護国之寺、と四天王寺そのものと同じであったことも気になる所です。そういえば、東大寺にもまた、水の信仰が守られていることも注目されます。

(東大寺、奈良の大仏は、毘盧遮那如来。太陽の仏です。後の密教の大日如来とおなじとされます)

(四天王寺亀井水。私の調査では、太陽礼拝の水鏡。聖武天皇の東大寺の太陽と水の信仰は、亀井水の聖徳太子の思想を継承するものと考えられます)

(新潟弥彦山につたわる原初の稚児舞としての天王寺舞楽)
四天王寺は舞楽によっても知られています。日本の芸能の原点とされる天王寺舞楽ですが、芸能者もまた非差別民として社会の底辺を支える存在でした。
いつの時代も、差別は再生産されてゆきます。福祉、芸能、また酪農食肉などの社会の底辺の人々によりそってきた四天王寺の確固とした歴史は、創建のときに組み込まれた遺伝子と考えないわけにはいきません。
聖徳太子の姿が、常に餓人との出会いの場面に強調されて伝えられてきたことは、そうした四天王寺の歴史を前提とするならば当然のことでしょう。
日本書紀の聖徳太子の歌
推古21年12月条
「十二月の庚午(かのえうま)の朔(ついたち)に皇太子、片岡に遊行でます。時に飢者、道のほとりに臥(こや)せり。よりて姓名を問いたまふ。而るに言さず。皇太子、視(みそなは)して飲食(おしもの)与えたまふ。即ち衣裳(みけし)を脱きたまひて、飢者に覆ひて言はく、「安らに臥せれ」とのたまふ。則ち歌いて曰く、
しなてる 片岡山に 飯に飢て 臥せる その旅人あはれ 親無しに 汝生りけめや さす竹の 君はや無き 飯に飢て 臥せる その旅人あはれ 」
さす竹の君、とは恋人、妻のことです。
親も恋人もいないのか、いやそうではないだろう、お前を悲しむ者はいるだろうに。太子の言葉に、私も涙がにじんできます。この語りかけの言葉には、その病者が真人(ひじり)にちがいない、という後日譚とはそぐわないものがあります。あくまで、弱者への理屈ぬきの慈悲のまなざしが語られているとみなすべきでしょう。
しかし、日本書紀の作者は、理由もなく太子な行き倒れの賤民にかまうわけがない、と考えたのです。ですから、その病者は達磨大師の化身であったという話が生まれてゆきます。
芹つむ姫伝説
しかし、聖徳太子信仰の面白いところは、太子と共に亡くなった膳(かしわで)夫人にかんしては、実は膳氏の実の娘ではなく、卑賤の民の娘が太子にみそめられて、膳氏の養女という口実をもうけて結婚したのだという、シンデレラ物語が生まれます。
芹つむ姫伝説、といわれます。村人たちが野に出て芹つみをしているところに、聖徳太子が通りがかった。村人たちは、太子に気がついてあいさつをした。ところが、一人の娘だけが父母のために芹をつむのに夢中で気が付かない。太子はその娘に一目惚れしてしまう。思うに、彼女は太子に背を向け身をかがめて夢中になっていた。太子は、後ろ姿に惚れ込んだ、ということでしょうか。
ともあれ、信仰はその担い手によって変容します。
権力者によって語られる太子像と、庶民に流布する太子像が、渾然としてひろまってゆく。超人性と俗人性がからまりながら、太子信仰は変容しつづけています。
それにしても、太子信仰はとらえどころがない。御利益も定かではないし、救済の仏様という明確な菩薩像も結ばない。ただ、聡明で情緒豊かな人物像が、無数の人々の心をとらえてきただけのように感じているのは、私一人でしょうか。
説明不可能な純粋さ。あたかも、亀井水の水のイメージのような。
古代律令制の時代や、あるいは明治政府の要請として聖人化された太子像を否定して、それで太子信仰の全体を否定したつもりになるのは愚かなことでしょう。虚実がないまぜになっているのは、現代も含め、あらゆる時代の歴史上の人物について言えることです。聖徳太子ひとりが、虚実さだかならざるわけではありません。
この私ひとりとっても、得体のしれないコンプレックスな存在です。宮沢賢治にならって表現するなら、「仮定された有機交流電灯のかすかな煌き」とでもいえるでしょう。聖徳太子が謎の存在であるというなら、すべての人にとって「私」もまた謎です。
万葉集の歌
万葉集では、単にいち俗人としての悲しみを記録しています。
「上宮聖徳皇子、竹原井に出遊でましし時に、竜田山の死人を見悲傷して作らす歌一首
家ならば 妹が手まかむ 草枕 旅に臥やせる この旅人あはれ」
日本書紀が片岡山の飢人、とするのを、万葉集は竜田山の死人、としています。
別の機会の話なのか、同じモチーフが変容して伝えられたのかはわかりません。それぞれ歌そのものが太子の真作かどうかはわかりません。ただ、行き倒れの人を見て、太子の胸の内の為政者としての責任感と無力感を、素朴に語り継ごうとした人々の心は、歴史的真実でしょう。
上宮聖徳法王帝説
では、太子の歌として真筆である可能性のある作品はないのでしょうか。
私は「上宮聖徳法王帝説」に記録された、死のまぎわの遺言というべき歌に注目します。それは、どちらかというと意味不明で下手な歌です。後世の偽作ならば、もうすこし分かりやすい上手な歌を作ったのではないかという意味で、かえって真実味を感じるのです。
「大刀自者(膳夫人)、二月廿一日卒(うせたまう)也、聖王廿二日薨(みまかりぬ)也。是以、明知、膳夫人先日卒、聖王後日薨也。則、証歌曰、
伊我留我乃止美能井乃美豆伊加奈久爾多義弖麻之母乃止美乃井能美豆
いかるがのとみのいのみずいかなくにたぎてましものとみのいのみず
斑鳩のトミの井の水 生かなくに 食ぎてましもの トミの井の水
是歌者、膳夫人臥病而将臨没時、乞水。然、聖王不許。遂夫人卒也。即、聖王誅而詠是歌。
この歌は、膳夫人が病にふしまさに没せられんとする時、水を乞われた。しかるに、聖王は許されなかった。ついに夫人は亡くなられた。すなわち、聖王はみずからをいましめ、この歌を詠まれた。」
歌の意味としては、亡くなった膳夫人に水を飲ましてやりたかった、というだけのものに見えます。トミの井の水とは、井とはいえ、これも富雄川の水のことであろうと解釈されてきました。しかし、それだけなら、トミの井の水、のリフレインが無駄な装飾に見えてきます。
さらに、続く説明がまた意味が分かりません。病人が水を下さいと願ったのに、太子はそれを許さなかった。仮にこれが末期の水の意味で、太子は夫人にまだ死ぬんじゃないと、許さなかったとしても、未練がましい判断です。まして、病人が熱にうなされて喉の渇きを訴えたならば、わざわざ看護人が太子の許可を求めにいくでしょうか。まさか、昔の迷信で病人に水を与えるのはよくないというのであれば、死後に後悔して水を飲ましてあげたかったというのも愚かな話です。
くりかえし、に見える、とみのいのみず、ですが、よく見ると、の、の字の使い方が異なります。乃と能が交互に使われており、一定の法則があるようです。
下の句を見ると、
たぎてましも乃とみ乃い能みず
と乃が続いています。つまり、言葉の区切りとしては、
たぎてましもの・とみのいのみず
となり、一区切りの言葉のなかでは、
乃→能→乃、
という法則があることになります。
すると上の句、
いかるが乃とみ能い乃みず、
がひとつの言葉、ひとつの概念であることになり、いかるがの、は単なる装飾句として場所を示すだけの言葉ではないことがわかります。
いかるがのとみのいのみず、が、全体で、いかなくに=生きていない、の主語となりますから、これは膳夫人を意味する比喩であることがわかります。
夫人が、いかるがのとみのいのみず、であるとされるなら、とみのいのみず、はいかるがにある水ではないということも可能です。それならば、富雄川とは関係ありません。
夫人の喩えとされる、何処にある水なのでしょう。しかもそれは、聖徳太子の最後の歌、遺言に語られるほどの、貴重な水なのでしょう。
仮説とお断りしたうえで判断しておきますが、亀井水こそがその可能性のある水ではないかと私は考えます。
我田引水ではありますが。
王権のシンボルであり、王家の特別な地位のあるものだけが触れることの触れることの許される水。夫人がいまわのきわに、その水を求めたというのは「どうか私を正后として認めてください」という願いであったということになります。
当然、それは許されることではありません。
しかし、夫人の死後、太子もまた命つきようとするとき、太子は死後の世界で、夫人とともに、とみのいのみず、を飲もうと約束するのです。
これで、この不可解な歌は崇高な意味を持ちます。
私訳
いかるがのトミの井の水というべき清らかなあなたはもう生きてはいない
私もまもなく死ぬ
共にトミの井の水のほとりで再会しその水を飲んで仏の世界へ旅立とう
上宮王家の混乱
膳夫人が太子の正后として、母間人大后と共に三尊として、上宮王家では当然のごとく礼拝されることになります。
当然のごとく、とは言いましたが、そうでしょうか。
よく考えたら、聖徳太子の正后は、推古帝の孫娘、若き未亡人、橘です。
推古帝はその証に、天寿国繍帳を作らせます。長男の嫁、膳夫人の長女ツキシネにとりそれはまた我慢ならない。
山背大兄王は板ばさみとなる。王家の継承者として、橘を第一夫人として結婚するという手段もある。しかし、踏みきれない。
そうした前提で日本書紀を読み直すと、実にすっきりと解釈できます。
長くなりますからまた別の記事で。
「帝説」にはこんな一言があります。
「後の人、父の聖の王と相みだるトいうは、非ず」
なるほど、王家の継承者として、山背大兄王のうろたえぶりを表しているようです。
参考記事
巨勢三杖の歌
さて、後のとみのをかわ、の典拠となる歌が、「帝説」に記録されています。太子の死後、巨勢三杖大夫(こせのみつえのまえつぎみ)が斑鳩の宮において歌ったとされる、三首です。まず、原文で書き出しておきます。
伊加留我乃止美能乎何波乃多叡婆許曽和何於保支美乃弥奈和須良叡米
美加弥乎須多婆佐美夜麻乃阿遅加気爾比止乃麻乎之志和何於保支美波母
伊加留我乃己能加支夜麻乃佐可留木乃蘇良奈留許等乎支美爾麻乎佐奈
ひらかなに書きくだしますと、
いかるがのとみのをかわのたえばこそわかおおきみのみなわすらえめ
みかみおすたばさみやまのあじかげにひとのもをししわかおおきみはも
いかるがのこのかきやまのさがるきのそらなることをきみにまをさな
第一首が拾遺和歌集の典拠となった歌ですが、拾遺和歌集では、いかるがや、と場所を限定しています。三杖の歌では、いかるが乃トミ能をかわ乃、とひとつの言葉で主語となっています。三杖は、聖徳太子の遺言歌を知っていたでしょう。その、いかるがのトミの井の水=膳夫人、を意識していたならば、いかるがのトミのをかわ、は聖徳太子自身ということになります。の、の漢字、乃と能、のつかい方を見れば「いかるがのとみのをかわの」がひとつの言葉となっていますから、このとみのをかわを斑鳩の富雄川ではないと考えることも可能でしょう。太子の遺言歌の、とみのいのみず、に対応する言葉ならば、亀井水の流れを表していると考えることもできるのではないかと思います。太子の魂も、亀井水もともに不滅なのです。
この仮説は、次の第二首の解釈ともかかわってきます。
第二首は意味のわからない歌です。
解釈のヒントとして私が注目するのは、あじかげ、の、あじ、です。聖徳太子生誕の地とされる、飛鳥の橘寺に、阿字池という小さな池があります。梵字サンスクリット語のアの字の形の池ということですが、極楽浄土信仰からいえば阿弥陀池ということになりますが、四天王信仰からいえば、多聞天の山のふもとにあるアノクダッチ、無熱池と考えるべきでしょう。池をジと発音して、あじかげ、は、ア池影、無熱池を囲む森の水辺の木陰ということになります。ならば、たばさみやま、とは多聞を多間(はざま)と解釈し、多聞天の山、須弥山となります。
三杖の歌、とくに第2首は、解釈不可能といえるものです。
しかし、〈とみのをかわ〉を亀井水と仮定すれば、聖徳太子を多聞天とみなす信仰に、くっきりとイメージが収斂します。
であるなら、聖徳太子の遺言歌の〈とみのいのみず〉も、亀井水を意味するものとすれば、その情感は深いものとなります。
短歌を素材に、聖徳太子信仰を多面的にとらえる。
無駄に長い作文になりました。
最後までお読みいただいた方に、感謝いたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
