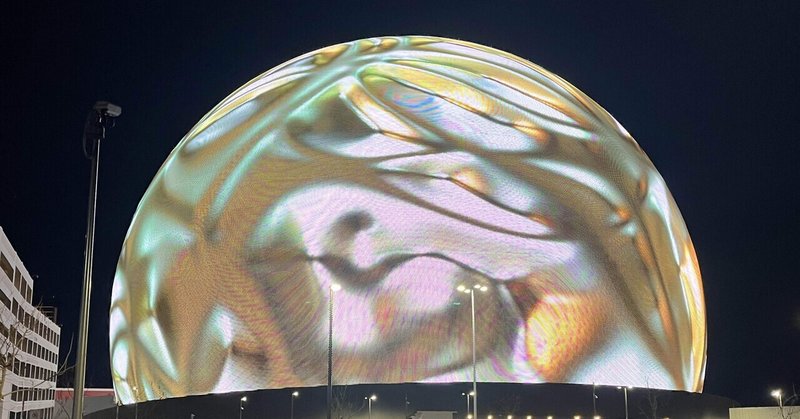
「映える」は流行とかじゃないのかも
「映える」という言葉が一般化したのはごく最近のことだと思うけど、「映える」という感覚自体はむかしからあったはずだよなぁと思った。
テレビで、ヴェルサイユ宮殿内にあるホテルの内装をやっていたのだけれど、それを見て女性アイドルが「どこでも映える」と言っていたのだ。
そうか、フランスの貴族たちも、そのようなことを考えて、内装にこだわったのかもしれないな。この宮殿はどこからでも映えるような、言葉を変えるなら、どこからでも魅力的に映るような建物にしよう。そんな想いがあったのかな、なんて想像をする。
近年、映える料理だとか、映える体験、みたいなものが重宝されている。作り手も、「映え」を意識しながら作ることが、多くの人にその作品を届けるためには効率的な手段ともいえるだろう。
ぼくはどこかで、そのような風潮にうんざりしていた。「映える」だけで盛り上がりが過激になる様子は、内側にこだわったものたちが淘汰されていくような感覚がして嫌だったのかもしれない。
だけどヴェルサイユ宮殿のホテルを見てみると、「映える」という感覚をほんとうにむかしからあるもので、それを否定することも違うのではないかと思うようになったのだ。
人間には、美しいもの、目を惹きつけるものを作りたいという欲望がある。その欲望が、写真やSNSの普及により、経済的な価値をもつようになっただけで、それ自体はごく普通の発送なのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
