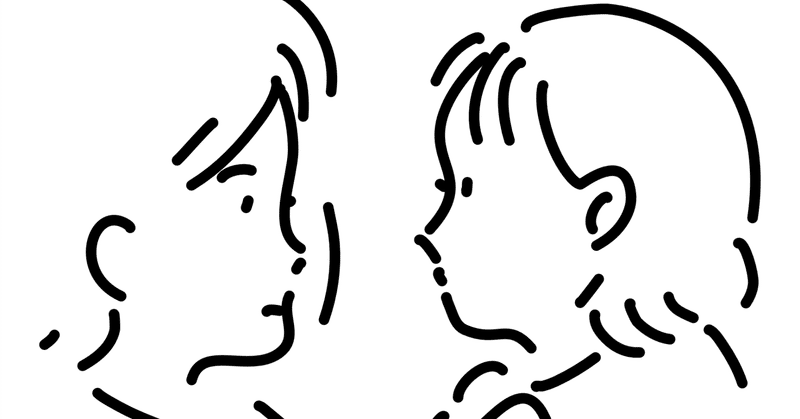
復職後のロールモデルを考える
子供が生まれていないため、育児に関しては何とも言えない状況ではありながらも復職後の働き方について考えている。
まず大きな目標としては
毎日、いらいらしない楽しそうな母ちゃんでありたい。
なぜかというと、子供時代 私の母が教員としてフルタイム勤務をしていたのだが、帰宅すると疲れ切っており同僚や上司の悪口を口にすることが多かったからだ。父は単身赴任で平日は家を空けることが多かったため、
私は母に対して腫物を扱うように接していた思い出がある。
私も切羽詰まると、瞬間湯沸かし機のようにイライラをぶつける傾向がある。
自分と家族の安寧を守るためにも「ギリギリでいつも生きていたいから~♪」といったKAT-TUN Realfaceなライフスタイルは捨てていきたい。
さて、そんな目標に対して今後の仕事と生活の両立を考えたロールモデルについて模索をしており、そんな状況をシェアさせていただきたい。
ロールモデル①現職の先輩ST
私は現在、回復期リハビリ病棟で言語聴覚士(ST)として勤務している。
保育園が決定後は子供が1歳になった時点で復職予定。
職場では2人先輩ママSTがいる。
・フルタイム勤務(管理職):
確か担当患者4‐5人 14単位/日 8:30-17:00勤務
・時短勤務:
確か担当患者4-5人 16単位/日8:30-15:30勤務
【先輩を見ていて思うこと】
・書類業務により日によって30分超の残業があり、時々帰り際にバタバタとしている。
・フルタイムになると定時上がりが更に難しくなる。
(他スタッフから声を掛けられたり、カンファレンス・面談前の情報共有を業務時間外に行うことが多い)
・先輩は2人とも旦那さんが同職場にいるため、急なお迎えの依頼等もタイムリーに話し合えており、それを見ているとちょっと羨ましいな、と思うことがある。
※STあるあるなのが昼に食事評価を入れてしまうと、昼休みの時間に多職種との情報共有ができず、どうしても朝や終業後になってしまうことが多い
。ほか、カルテ記載や評価まとめ、教材作成等も業務終了後にしわ寄せされることが多い。
回復期に携わるようになってから、訓練において患者さんの機能改善に貢献できているというやりがいはあるものの回復に関わる重要な期間に携わるというプレッシャーが常にある。
時短勤務であろうがフルタイムであろうが、私が楽しく継続して働き続けることを考えると いささか難しい気もしている。
ロールモデル②全国で発信している先輩ST編
これまで、同職種で発信をしている方について見る機会は無かったのだが、これを機に全国または世界ではどんな働き方をしているSTがいるのか探してみた。
そんな中、目に留まったのが リハツバメさん
現在、復職後の働き方について視野に入れている非常勤で生活期ST+無理しない程度の副業を実現しているSTさん
STの転職や訪問リハビリ、教材に関する情報を発信されており
ブログを見つけた時に、訪問リハビリに携わっていた時に出会えていたら
もっと働き方が変わっていたかなあ、なんて思いました。
(周囲に訪問STがいない環境下であり、日々手探りかつ利用者・利用者家族との関わり方に常に悩んでいた)
ロールモデル③ワーキングママ編
数年前から散歩や家事の合間にポッドキャストを聴いている。
最近、やはり育児やワーキングママの働き方について意識して聴く機会が増えた。
今すごく参考にして聴いている方は尾石晴さん、Emiさん
会社員で働いていた際に結婚・出産を経て独立したというお二人。
会社員時代の育児との両立エピソードはもちろんのこと、現在独立したなかで会社の経営や学びに関する発信に、いつもこちらも学びを得ている。
思考の整理や言語化が明瞭であり、耳で聴いていてストンと心に落ちていく言葉選びが私もできるようになりたい。
ロールモデル③生き方・ライフスタイル編
ワーキングママ編とやや重複する部分もあるけれど、こちらもポッドキャストでお世話になっている方や書籍から元気・勇気をいただいていて育児に限らず、生き方について考えさせられている方を選んだ。
いずれの方も、発信内では肩の力は入っておらずゆったりとした気持ちで聴いていられる、見ていられる方々ではあるが、言葉の端々から垣間見える仕事への強い思いに「私も頑張ろう」と奮いたたせてくれることがある。
ただ、その奮い立たせる何かも炎のようにボォォオと燃え上がるものでは無く、暖かい間接照明のように行く先に仄かな光を灯してくれるような存在。
おわりに
今回は自身の今後の働きかた、生き方について考えた経験から得たロールモデルにしたい方たちをシェアさせていただいた。
また、子供が実際に生まれ復職も近づいてきたころには気持ちは変わりつつあるかもしれないが
いろんな生き方の多様性を知ることで、心にも余裕が生まれるのでは無いかと思っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
