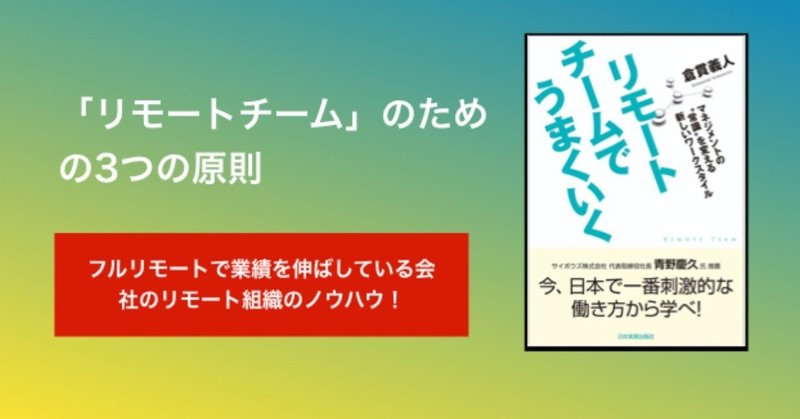
【1日1冊書評】リモートチームのための3つの原則 / リモートチームでうまくいく
リモートチームのための3つの原則
1 仕事中の雑談を推奨する
2 ワークタイムを揃えておく
3 社員全員でリモートワーク
これは、「リモートチームでうまくいく(著)倉貫義人」に書いてあることです。著者は社員が全員リモートワークを行うソニックガーデンの代表取締役社長です。「納品のない受託開発」や「社員全員がリモートワーク」で業績を伸ばし続けているという会社です。
<リモートチームのための3つの原則>
本書のなかにある3つの原則について、自分のリモートワーク x プロジェクトマネジメントの経験も踏まえて紹介します。
<1. 仕事中の雑談を推奨する>
オフィスにいると気づかなかったもので、リモートになったときにはじめて重要性に気づけるのが「雑談」だと思います。
オフィスでは、気軽に話しかけやすく、ランチやMTG前後のちょっとした時間など、意識することなく「雑談」する場が多くあります。この「雑談」を通して、会社や事業の方針、考え方について、認識をすり合わせることや、気軽に発言できるという空気を醸成することが大切です。(集中して作業を中断するような雑談は、生産性にとっては良くないのですが、、)
リモートワークでは、こういった「場」が存在しません。そのためリモートワークでは、意識的に「雑談」をする必要があります。「雑談」がうまくされない場合や、テーマが事業や組織のすり合わせの場になっていない場合は、「会社・事業の方向性について」「組織改善施策」などテーマを決めて話す機会を提供することもよい効果があると思います。
①は雑談の重要性に関する原則です。特に大事な雑談は、チームや働き方などの仕事についての話をすることです。オフィスであれば、廊下ですれ違ったときや食堂で食事をするときなどに、自然に交わしていた会話が失われてしまうのがリモートワークの弱点で、それを補うためには意識的に雑談をする必要があります。そのためにも、形やツールはともかく、雑談を奨励するくらいでちょうどいいでしょう。
倉貫義人. リモートチームでうまくいく (Japanese Edition) (Kindle の位置No.794-798). Kindle 版.

<2 ワークタイムを揃えておく>
オフィスへの出社していたときは、基本的に同じ時間、同じ場所に全員がいました。いるかいないかが判断できるかというより、いることが当たり前だったのです。
しかし、リモートワークの場合は、オフィスに出社していないため、本当にいるのかいないのかがわかりません。実際にいたとしても作業に夢中で返事ができなかったり、ちょっと席を外していると、働いていないのか?という気になってしまいます。もともとオフィスで働いていたときも、同じようなことはあったはずですが、同じ場所・時間に全員いるはずという認識があれば、いない場合でも、「たまたまいないだけかな?」と考えるだけで不安にはならないのです。
なので、出社しているか、していないかをSlackやスケジュールに記載しておくというより、全員でコアタイムを決め、その時間には全員(リモート)出社する。と決めておくと不安が減ってうまくいきます。
リモートワークといえば、自由に好きな時間に好きな場所で働けるイメージですが、チームであるからにはいつでも話し合えることが重要です。そのために、働く時間を揃えるのです。いつ働いているのかわからない人と一緒に働くのはやはり不安になります。厳密にワークタイムを設定するかどうかは、会社やチームによるでしょうが、だいたい同じ時間に働くことを前提とするのがよいでしょう。
倉貫義人. リモートチームでうまくいく (Japanese Edition) (Kindle の位置No.800-804). Kindle 版.
<3 社員全員でリモートワーク>
リモートワークで一番難易度の高いシチュエーションが、オフィスの会議室に10名くらいいて、そこにリモートで1-2名で参加する場合です。
大抵の場合、オフィスメンバーで議論が白熱すると、オフィス側はリモートメンバーの存在を忘れて話をします。同じ会議室にいれば、1:1で話している場でも話をちゃんと聞くことはできるのですが、リモートの場合は、マイクから離れられたり、カメラに見えない表情や雰囲気、またホワイトボードや資料を使われると何をしているかがわかりません。
しかし、社員全員がリモートワークであれば、こういったことはおきないので、全員が配慮しながら仕事をすることができます。
ただ全員をリモートワークにするというのは、いきなりは実施することはできません。それよりも、こういったことが発生するという前提をオフィス側にも理解してもらい、リモート側が情報がわからないときは、積極的に発信することが大切です。リモート側が遠慮してしまうと、後で二度手間になったり、認識齟齬が発生してしまい双方にとってデメリットになってしまいます。
社内でイレギュラーな存在になってしまうと、オフィス側にとっては負担に感じるし、そう感じられるとリモート側は改善の提案がしにくくなってしまいます。それではリモートワークを続けていくのが困難になってしまいます。オフィスも含め全員がリモートワークをしているという前提にして、それが特別なものではないようにするべきでしょう。
倉貫義人. リモートチームでうまくいく (Japanese Edition) (Kindle の位置No.806-810). Kindle 版.

まとめ
どうでしょうか。リモートワークは既存のテクノロジーを使えば、実行することは難しくありません。ただオフィスで働いていたときは意識せずに実行していたことのいくつかは、意識的に実行する必要があります。
最近は、東京オリンピックだけでなく、コロナウイルスにより在宅勤務が実施されているケースがあります。事業継続性という観点で、BCP (Business Continuity Plan)を作成しているという話を聞きますが、リモートワークは実際に実行したときに気づくことも多くあります。
まずは、リモートワークを実施してみて、実施した立場から不便だったことを共有し、改善につなげていくのが良いと思いました。
---
Twitter でも、プロジェクトマネジメント x リモートワークのノウハウをつぶやいていますので、よろしければ繋がってください。
支援は、コミュニティ研究の取材、サービス開発などに費用にあてさせて頂きます。
