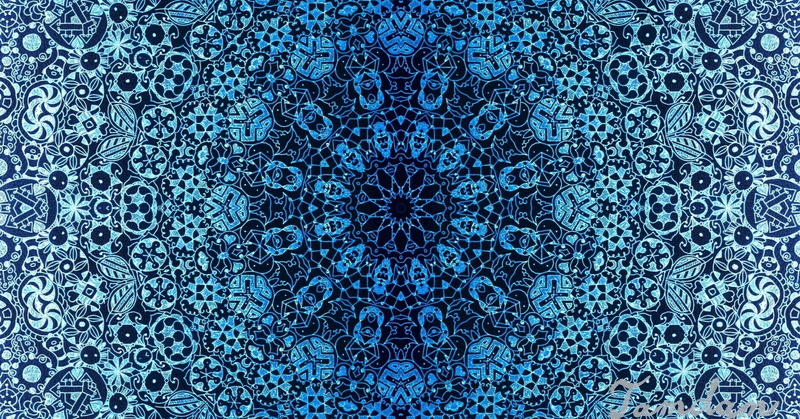
28. 判別方法アラカルト 論理的・直感的
その情報は真か偽か?
その物、人、事柄は自分にとって好ましいものか?
皆さん、色々な判断基準、判断方法を持っていることでしょう。
長い間、ウソとホントが真逆になっているこの地球。その上、日常には怪しい誘惑、判断が難しいことだらけに取り囲まれています。
今回は以前記事にしました、2.セルフ審神者(審神者)の時代 の具体的方法の概略です。
大前提として、物事に対する姿勢は最低限、次の6つを携帯するのがよいでしょう。
1.すぐに飛びつかない
2.信じ切らない
3.保留にする
4.複数の意見を参考にする
5.権威、評判に左右されない
6.自分のちょっとした感覚を無視しない
本来の意味の審神者は、霊感、直感を使いますが、娑婆での判断としては論理的考察=左脳と、直感力=右脳を使うのがバランス良いと思っています。
A 論理的考察
1.情報源を少なくとも3つ以上は持ち、比較検討する
2.合致点、矛盾点を探す
3.ひとつの情報が正しいから、その情報源がすべて正しいとは限らない
4.その情報源が正義側であっても偽情報は出すので、すべてをNGにすることは避ける
5.白・グレー・黒の3種類を念頭にいつも置いておく
6.中庸の感覚を大切にする
B 直観力
1.自分の中にふと浮かぶ感覚、考え
2.身体の反応をさぐる
A 論理的考察を効率的に働かせるためには、感情に左右されず、冷静に物事をみつめることが必要です。怒っていたり、悲しかったり、落ち込んでいるときは深い考察ができません。体調も大切ですね。
大部分が正しい、良いから、他の部分も正しい、良い、とは限りません。情報、物、人、表面だけではなく、中身も観察してみる。
B 直観力の1.自分の中にふと浮かぶ感覚、考えも、チャネリングをしているつもりは無くても、ひょっとしたら、乗っ取られた自分ではない感覚かもしれません。それを判断するには、A 論理的考察もツールとして使います。内容が矛盾しているなどチェックします。一番大切なのは、その感覚に対して、自分が納得するかどうかです。
2.身体の反応をさぐる これは人によって様々な反応があります。耳にした話や目撃した話も例に挙げます。
1)背筋がゾクッとする 前に思った事、話していたことと照らし合わせてその意味を判断する
2)首 YES=首が縦に動く NO=首が左右に動く YESとNO=両肩に倒れる
3)手をかざす 何らかの反応がある
4)身体全体の心地 快か不快か
ランチのお店を決めるのに、親指と薬指を合わせてOリングテストをしている人を見たことがありますが、OKとなったのが全部「休店日」でした。この方法は、どれが自分に合っているかどうか、には使えることがありますが、外の事象に対しての判断には自分の願望が混じることがあるような気がしました。
人に関しては、その人の様子、声の波動、眼の様子、体臭で判断することもできます。長く聞けない声、気分が悪くなる声、それはきっと自分に合わない声なのでしょう。ネット上で内容を聞きたいときは、ミュートにする方法もありますが、その番組自体がグレーなのですぐに消すことになります。
どうもグレーだな、と思って離れていた番組が、ついに真っ黒な情報源を出してきたときには、やっぱり、と思います。
それでも、わからないこと、当たらないことも山程あります。それだけ、わかりにくいことが多いのです。
上記は最初からできる人もいれば、経験を積んでだんだんとできるようになる人もいます。できるけれども蓋をしている人も多いでしょう。
食べ物の好き嫌いも否定してはいけないと思います。本来、自分にとって必要なもの、害があるかないかは、わかるはずです。
食べなければいけない、これは義務だ、やった方がいいのかな、気が進まないけれど人のためだから、と本来の自分の感覚から離れたことには、立ち止まったほうがいいかもしれません。論理的思考で○○だから、○○したほうがよい、にも注意です。
貴方は本当はどう思うの?どう感じているの?
イヤならイヤでいいのです。人の目は気にしない。
物事はイチゼロではありません。この部分がおかしいからすべてがおかしい、とはならないこともあります。たとえば、玉石混交といわれるスピリチュアルですが、言葉通り、石ころの中に玉が隠されています。本物を隠すのが狙いなのです。全部を否定すれば、それは闇側の思うつぼです。
Aが偽と気づいてBに誘導され、実は別の所のCが良いものだったりします。
Dは悪いものと認識されている。しかし、本当はDの一部は身体にとって有効なもので、その他の部分が害があるもの。良いものを悪いものでくるんでいるのです。
左右の脳をバランスよく使って、真実を掘り当てたいものです。
当サイトへお越し頂きありがとうございます! 宜しければサポートお願い致します。執筆の励みにしたいと思います。
