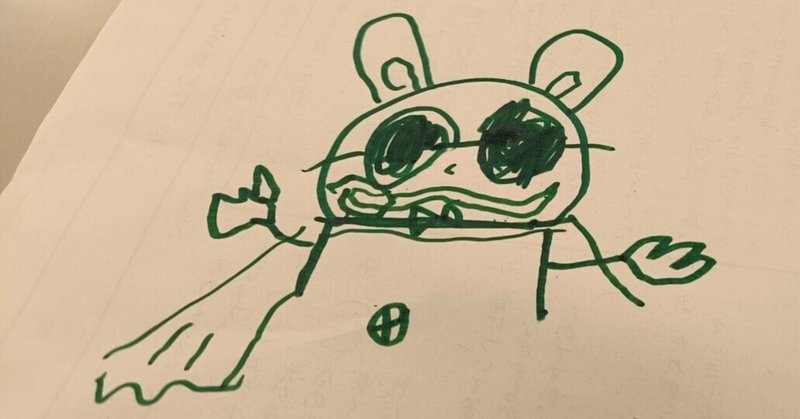
#011 YOKOHAMA PACEに参加しました。
2024年5月6日(月)、YOKOHAMA PACEという学習会に参加しました。
子どもたち(6歳、1歳)を連れて参加しましたが、主催者のタクヤさん、参加者の皆さんのあたたかい関わりのおかげで、私も子どもたちも楽しく過ごさせていただきました。
ありがとうございました。
感じたことや学んだことがたくさんありましたので、アウトプットをして、整理をしてみようと思います。
#YOKOHAMAPACE が無事に1回目の立ち上げを終えました!本当にあっという間で楽しいひとときでした…
— タクヤ (@ayukaTotomihsaH) May 6, 2024
ふりかえると反省ばかりですが、それと同じくらい参加者の皆さんの笑顔や姿が目に焼き付いています!
次回の告知は明日行います\(^o^)/ pic.twitter.com/hLhfOUREtq
PAとは?
プロジェクトアドベンチャー(PA)は、アドベンチャー体験から学ぶ、アクティブラーニングプログラムです。子どもから大人まで幅広い世代で、実体験から成長するための「気づき」を効果的に得ることができます。
約束を参加者と確認し、レクリエーションを行い、振り返り、気づきを共有する。
体験したことを簡単に説明すると、そのような流れでした。
PAの中で大切なこととして、Full Value Contract(フルバリューコントラクト)と、Challenge by Choice(チャレンジバイチョイス)の2つを紹介していただきました。
Full Value Contract
【フル バリュー コントラクト】Full Value Contract(FVC)
PAプログラムでは、プログラムを始める前に簡単な約束をしてもらいます。
これをフルバリューコントラクトといいます。
これは、お互いの努力を最大限に評価するという約束です。
つまり、「自分を含めたメンバーをけなしたり、軽んじたりしない」、具体的には「お互いの心の安全と身体の安全を守る」、「自分に正直である」、「ネガティブなことにこだわらない」などがあげられます。
会の中では、5つの約束を確認しました。
Be here 今、この瞬間に意識を向ける
Play safe 安全第一
Play hard 一生懸命
Play fair 正直に、誤魔化さずに
Have fun 楽しんで
Challenge By Choice
【チャレンジ バイ チョイス】Challenge By Choice(CBC)
PAプログラムには強制はありません。
挑戦への選択の自由が常に保証されています。
個人の挑戦レベルとその方法は、自分自身が決定します。
また、自分が挑戦を選択しなかった場合でも、グループから外されるのではなく、グループの仲間にどのような方法で協力できるのかを考えることも選択のひとつになります。
会の中でも、それぞれのプログラムに対して、参加不参加の選択ができました。
自分の身体や心の状態を考えて、参加しないという選択も可能でした。
参加しない場合でも、仲間が活動している様子を見て、考えることも可能でした。

迎えにきた妻に、早速餃子じゃんけんを教えていた長男(6歳)
感じたこと、学んだこと
プログラム構成
会の中で、色々なレクリエーションを行いましたが、その順番がよく考えられているなぁと思いました。
心理的なハードルが低いものから高いものへ、自己開示のないものからあるものへ、身体接触がないものからあるものへなど。
例えば、最後に行ったヤートサークルというプログラムが、もしも序盤にあったとすると、参加するのに心理的なハードルを感じたかもしれないなぁと。
また、自分の経験を振り返ってみると、クラスでレクリエーションなどをするとき、参加しない子どもがいるときがありました。
もしかしたら、その子にとっては、心理的なハードルが高かったのかもしれません。
そうであれば、より心理的なハードルの低いものから設定する、単発の取組みではなく長期的な視点で内容を選択していくなど、柔軟な対応が必要だなと感じました。
ゲームとPAの違い
ゲームやレクリエーション(単発で行うもの)と、PAの違いはなんだろうか?と、考えながら参加していました。
私は、Full Value Contractと振り返りだと考えました。
Full Value Contractがあるおかげで、ゲームが楽しかった・楽しくなかった、上手くいった・上手くいかなかったという自分の気もちや結果だけに着目した振り返りではなく、友だちと安全に取り組めたか、一生懸命に取り組めたかなど活動の過程にも意識を向けた振り返りができるように感じました。
授業でいうめあてや、学級でいう学級目標にも通じるところがあるように思います。
今回の会の流れでいえば、教師がFull Value Contractとして提示したものに子どもたちが同意し、更新可能ということで、現時点でのFull Value Contractとしました。
Full Value Contractを意識して、活動し、振り返っていく中で、Full Value Contractの中に示されていることの大切さに気づいたり、より意識が高まり自分ごととして考えたりできるようになっていくのではないかと考えました。
Full Value Contractを更新していった結果、学級目標が決まる場合も考えられるし、一から学級目標を決めるとしてもFull Value Contractの要素を含んだ学級目標がつくられていくのではないでしょうか。
自身の実践を振り返ってみれば、学級目標を決めた後は、日常や行事の振り返りを学級目標に照らして行なってきていました。
年度当初の仲間づくりを意識した活動を行う前に、Full Value Contractを確認することで、活動の振り返りが変わり、学級目標にもその意識がつながり、年間を通して一本の矢で貫くような学級経営となっていくのではないかと思いました。
ファシリテート
タクヤさんのファシリテートする姿が、とても勉強になりました。
参加者の気づきを大切に扱い、決して押し付けない。
教師にとって都合のよい意見を取り上げ、教師の思うところに着地させたり、教師がまとめてしまったりしない。
その姿勢のおかげで、参加者としては素直に考えたことを述べることができたし、与えられた学びではなく、自分たちで学びとった感覚がありました。
「何が見えましたか?」「何が聞こえましたか?」などの、声かけもあるとおっしゃていたことも心に残りました。
失敗を笑える
レクリエーションをしていく中で、失敗してしまったことに対して、あたたかな笑いが生まれることが何度もありました。
そこに信頼関係があって、失敗を楽しめる雰囲気、とても素敵だなと感じました。
振り返ってみれば、学級などでレクなどをしているときも、あたたかい笑いがあったなぁと。
命令ゲームの中で間違えて行動してしまったり、早口言葉が上手にいえず噛んでしまったり。
そういう活動を通して、失敗や笑いに対しての感覚を共有していくことも大切だなと。
「失敗を笑ってはいけない」と言うことがありますが、「失敗を笑い合える」関係は、もっと素敵だなと改めて思いました。
横浜には・・・
今回、体験したレクリエーションの中には、横浜市で使われている体育読本、Y Pプログラムなどに掲載されているものもありました。
それらのものも断片的に行うのではなく、PAの手法や考え方でつないでいくことで、より効果が得られるのではないかと思いました。
PAの手法や考え方を子どもたちと共有しておくことで、様々な経験から学びやすくなるのではないかと思いました。

寝息を響かせ妨害をしていた次男(1歳)
まとめ
会の中で、タクヤさんに「Full Value Contractは、活動中にだけ適用するのか、それとも、普段の生活の中でも適用するのか」と、質問させていただきました。
タクヤさんの考えは、後者でした。
私自身も今回の学びを通して、PAの手法や考え方を取り入れることで、初めはレクリエーションの中で意識していたことが、徐々に授業や生活に広がっていくイメージがもてました。
学びを深め、教室で実践していきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
