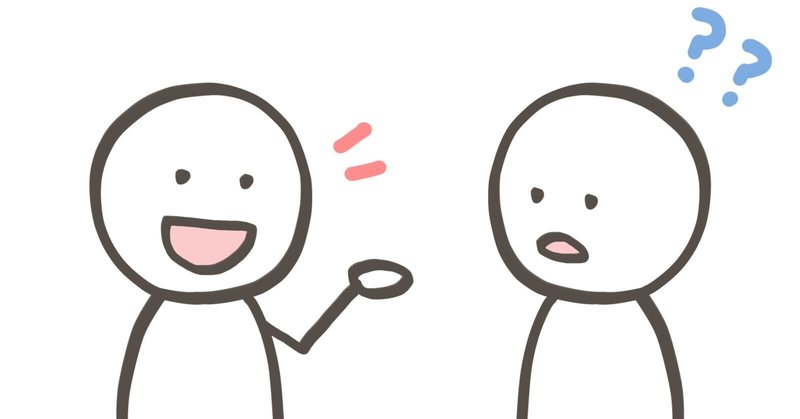
良い指示を構成する5要素(悪い指示を出さない為の備忘録として)
先日、仕事でそこそこ大きな打ち合わせがありました。その会議では、現場のメンバーに対して、とある取り組みを実施するうえで、どういう方針で、またどういう伝え方で、どうやって現場のメンバーを巻き込んでいくか、というテーマで議論したのですが、どうも議論がグダグダで、なんだかなあ・・・という感じの議論に終始して不完全燃焼気味・・・。
ちょうど先日、木下斉さんのVoicyの「良い指示を構成する5要素を意識しよう!」という回を聞いたところだったので、余計にそう思えたのかもしれません。
私も日常で現場のメンバーにいろいろと指示することが多く、私自身悪い指示を出さないための備忘録として、良い指示を構成する5要素について書いてみたいと思います。
●良い指示を構成する5要素
木下さんのVoicyでは、良い指示を構成する要素として下記の5つを挙げられています。
指示の内容が具体的で明確
指示される側にとって理解しやすい
目的を伝える
質問の機会を提供する
合理的な期限を設定する
ひとつずつ掘り下げてみたいと思います。
1.指示の内容が具体的で明確

「指示の内容が具体的で明確」、すごく大事なことですよね。よく「解像度が高い」という表現で言い表すこともあります。ここで大事なのが、始めはアイデアとしてこういうふうにやりたい、みたいなぼんやりしていた抽象的な内容を、どこまで具体的に解像度を上げていくか、ということ。
稲盛和夫さんのベストセラー書籍「生き方」でも、「現実になる姿が『カラーで』見えているか」ということで、すみずみまでイメージできるか?くっきりと見えるまで考え抜くことが重要、と述べられています。
指示する前に、指示する側がどこまでその内容をくっきりと解像度の高いイメージを持って理解しているかが重要ですね。指示される側も、指示するる側がどこまで深く理解した上で指示しているかは、結構見透かされていたりします・・・。
2.指示される側にとって理解しやすい
1の「指示の内容が具体的で明確」、それをいかに相手に理解してもらえるような言葉で発信するか、これもとても重要です。特に専門的な用語は注意が必要ですし、無用な横文字とかの乱発も避けるべきでしょう。自分自身は当たり前のようにつかっている専門用語も、理解できていない人からすると、想像以上に置いてけぼり感を感じてしまうものですし、「なんかインテリ気取りで理由のわからん言葉ばかり並べやがって!!」みたいな変な印象を与えてしまうことも・・・。
3.目的を伝える
私はココが一番大事だと思っていて、「なんのためにやるのか?」これが伝わっていない限り、熱の入った仕事にはならないかと思っています。目的が伝わらないまま指示してしまい、仮に業務が指示通りに行われたとしても、それは単なる作業であり、目的目標に向かって努力して達成したという達成感ややりがいは得られることはないでしょう。きちんと目的を伝えて、その業務の意義を全員が理解すること、ものすごく大事だと思います!しかしながら、私の周りでも結構できていないケースが多いように思います・・・。
4.質問の機会を提供する
指示を出したところで、人はすぐにすべてを理解できるほど賢くありません。私も会議に参加していて、会議終了後になってから「・・・結局何が決まったんだったっけ?」なんていうふうに、会議の最初の方の内容とかは頭の中からぶっ飛んでいることも多いです。さらに人は時間が経てば経つほど覚えていた記憶も頭から抜けてしまうため、できる限りその場で質疑応答して、わからないことを少しでも理解していく必要があります。また、質疑の時間をとることで、一方的な指示ではなく、きちんと足並み揃えて一緒に頑張っていこう!という意思表示にもなり、職場内での一体感にもつながったりします!
5.合理的な期限を設定する
指示には必ず期限を設定すべきですが(期限のない指示はグダグダになって忘却されてしまったりします・・・)、とはいえ、無茶な期限は非実現なものとして考えられてしまい、実行度も低くなってしまいます。指示する側としては、なるべく早く仕上げてくれたほうが助かるのは間違いないですが、相手の通常行っている業務も含めてどう分担して、無理なく実行できるのか、相手の負担感も配慮した期限の設定が必要ですね。
●ちなみに私が参加した会議での違和感の正体は「目的がぼんやりしていたこと」
これらの5つの要素を見返してみて、私が先日参加した会議での違和感を改めて考えてみると、この違和感の正体は「目的がぼんやりしていること」でした。
現場メンバーに指示をするにも、何のためにやるのか?という部分が非常にぼんやりしていて、そこがはっきりしていないことで、議論全体も筋が通っていないやりとりになり、皆が好き勝手に自分の意見を言う、というものになってしまっていました。まずは、何のためにやるのか?この動機づけについて、なにか議論があった際は、必ずきちんと定義し、共有したうえで話し合いを行っていくべきだと再認識した次第です。
ではでは。
・福祉用具屋さんのブログ👇
・介護の三ツ星コンシェルジュのコラム👇
・X(旧twitter)はこちら
https://twitter.com/kaigoyouhin1
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
