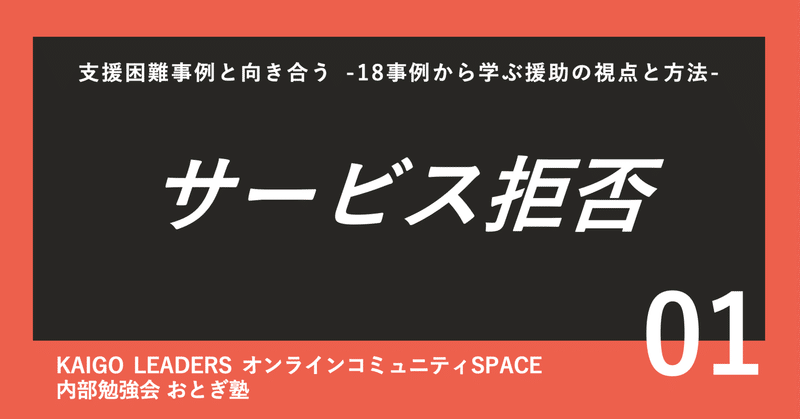
連続事例検討会:第1回 「サービス拒否」
初回の事例検討、テーマは「サービス拒否」いきなりのボス戦である。介護の現場にいる方なら誰しも出会ったことがあるのではないだろうか?
事例について
・専門職の訪問に「サービスサービスって、もうウンザリ!放っておいて頂戴」「私は大丈夫」と突っぱねる。
・ひどい腰痛で日常生活の維持に何らかのサービス導入が必要。
・77歳。とても良い小学校の先生だった。年の離れた弟妹がいる。若い頃両親が他界。
さて、ケアを拒否するこの方に、私たちは何ができるだろうか?この仮想フィールドに集まった参加者たちには、様々な経験と知識そして技術がある。ただし同じチームでの経験はない、組み立てほやほやのパーティだ。様々に語ってゆく。
▶参加者一覧
社会福祉士(地域包括支援センター)/介護福祉士(訪問介護、特別養護老人ホーム、通所介護事業所、緩和ケア病棟)/言語聴覚士/看護師/認知症専門の医師/理学療法士/公認心理師/IT企業(ビジネスケアラーに関心) 等
よく家族などから「専門の人に任せたい」という要望を聞く。セルフネグレクトからの“介護拒否”、例えば、着替えない・常に尿臭がする・ゴミ屋敷などのケースに相対したことがある。本人の「自分でやれます」と援助者の「お手伝いした方がいいんだけどなぁ」のせめぎ合いに悩まされる。
自分の衰えを認めたくないのだろう。
言語聴覚士:リハの時間に利用者さんから水をぶっかけられたことがある!「やりたくない」と拒否がありながら、リハの時間ずっと喋っている方もいたなぁ。
衰えに向き合わずとも、その人らしさを引き出すケアはできないだろうか。その人の好きな一面から関われないだろうか…。人となりを掴むための記録を残すことが大切かもしれない。これは、神奈川県の介護施設〈あおいけあ〉さんの取り組みが参考になる。
“できないことへの絶望”については、障害受容のプロセスを参考にして支援にあたってみては?
緩和ケア病棟で働く介護職:終末期ケアを行うホスピスでは、信頼関係の構築が重要で、それも短い時間で構築する必要があります。しかも、本人は終末期の受容が難しく、ケアの拒否はよく見受けられる。気持ちを受け止めながらもどうしたらよいか悩みことはしばしばです。
医師(Tettyさん):「周りの人がこうあるべきだ」と「本人の要望」の間に大きなギャップがあるのでは?医療職の言うことには、従う利用者が多いという肌感もある。でも、もうちょっと時代が進むと、医師の言うことに聞く耳を持たない世代になっていく気もする。
家族ケアの視点をもつメンバー意見:私の気持ちが誰もわかってくれないという気持ちを解きほぐしていくことが大切だと思う。私は、ビジネスケアラーに関心があり、彼らにインタビューをする活動を続けています。
他にも、参加者一人ひとりが、次々意見を述べていく。静謐で熱い夜のひと時、画面から一つひとつ出力される想い。「待つって大事だと思う。その人の主張を汲み取るのならば、表現ができるまで待たないと…」
最後に、参考図書「支援困難事例と向き合う」の著者・岩間先生のまとめが提示される。
“介護拒否”の内面的背景としては、①援助への抵抗と、②変化への抵抗の二つが存在する。①援助への抵抗については、「自分のケツは自分で拭け」という自己責任論が根本にあると感じる。できなくなることによって社会的評価が暴落する恐怖が、人の心を縛る。②変化への抵抗については、実は「変わること」そのものが、良し悪しに関わらず試練となる(例えば、結婚や出世もストレスとなりうる)。つまり、変化は、どこにでも転がっているリスクと言い換えることもできる。
そして、何より大切な行動は、「あなたの価値は変わらない」と宣言し続けることである、と。

現場ケア職であり記録者として感想
やはり、初回にして即ボス戦突入であることを否定できない。さすがは困難事例だ。介護に携わる仕事には、拒否がつきものである。しかし、拒否即諦めへと直結するのではなく、“拒否がある=あなたにならNOと言える”と考えるのはどうだろう。上下関係に厳しく、自分の意見を出せなかったこの国のお年寄りが、苦悩を包み隠さず我々に伝える、これって特別な関係性の一里塚ではないだろうか?理想論なのかもしれない。それでも、泥くさく、地を這うように「貴方の価値は変わらない」と宣言し続ける。その行動の動力源として使えるのではないだろうか?
初回:サービス拒否はこれにて終了。我々はまだ、始まったばかりである。
今後の予定

介護のオンラインコミュニティ「SPACE」について
「SPACE」は、“介護”に関心を持った仲間が集うオンラインコミュニティです。組織や地域を越え、前を向く活力が得られる仲間とのつながりや、 自分の視点をアップデートできる新たな情報や学びの機会を通じて、 一人ひとりの一歩を応援できるコミュニティを目指しています。入会できるタイミングは、毎月1日と15日の2回です。詳しくは以下をご覧ください。
書いた人
もっちぁん
現場で働きつづける介護福祉士。特別養護老人ホーム勤務(グループリーダー)、他に介護支援専門員と社会福祉士を名乗れる。
※おとぎ塾では、『支援困難事例と向き合う』(中央法規)に掲載された18事例を元に、オンラインコミュニティ“かいスペ”の有志メンバーが意見を出し合う検討会を開催。本記事はその様子をレポートしています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
