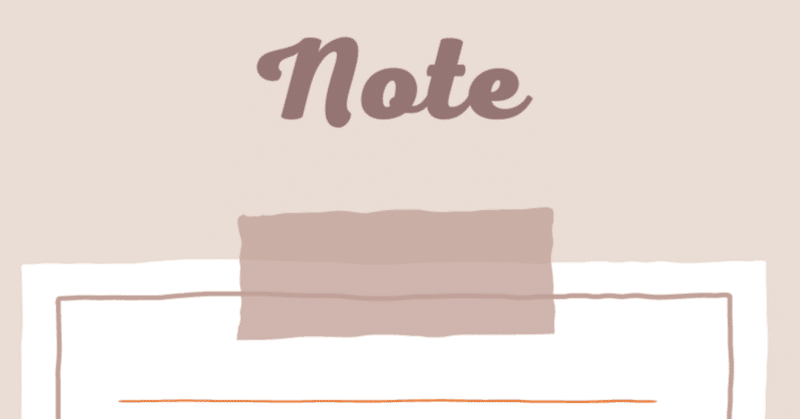
何でもかんでも捨てれば良いわけではない〜学校図書館図書廃棄規準〜
公益社団法人全国学校図書館協議会が2021年に改訂した規準です。
(引用はすべて公式HPより)
この学校図書館協議会(SLA)には多くの都道府県・自治体の学校が会費を払って加盟しているはずです。
「学校図書館では、利用者の立場に立って適切で優れた図書の選択収集に努め、かつ常に蔵書の更新を行う必要がある。」
その通りです。
「(略)蔵書の点検評価に伴い図書を廃棄する場合には、個人的な見解によることなく客観性のある成文化した規準にもとづき行わなければならない。
この規準は、学校図書館において
蔵書を点検評価し、廃棄を行う場合の拠りどころ
を定めたものである。」
◆そう、あくまでも
「拠り所」
です。
これを基に、自校図書館の蔵書を客観的に見直してみてね?ということであって、ケースバイケース、蔵書のバランスや利用状況を無視してまでこの通りにしなさい、ということではないはずです。
ただこの条文が独り歩きしているのか、うちの本が捨てられてしまうのでは…など不安の声が出版社から上がっているのを見ました。
その条文がこちら。
Ⅰ 一般規準
次の各項のいずれかに該当する図書は、廃棄して更新の対象とする。
1.受入後 10 年経過した図書。
以下、解説。
◎学校図書館には、20 年~30 年以上も前の図書が廃棄されずに残っている場合も多い。こうした図書はいつまでたっても廃棄・更新の対象にならない。そこで、「Ⅰ 一般規準」で廃棄して更新する対象とする項目の最初に「刊行後 10 年経過した図書」を入れて、廃棄されずに放置されることが無いように、
全ての図書について 10 年で廃棄・更新の対象として検討することとした。
なお、長く読み継がれている図書は、買い換えなども適宜行われるため、「刊行後」ではなく「受入後」とするのが妥当との意見から、
一般規準の1を「受入後 10 年経過した図書」と改めた。
…本やジャンルにもよりますが、特にレファレンスツール、
確かに2,30年以上前の図書が「廃棄されずに」
というよりは
「今でも利用されているので」
残っています(装丁がしっかりしているので見た目もキレイ)。
そのため廃棄の対象になっていません。
◆いくつか書籍の例を挙げますと
「新釈漢文大系」(明治書院)
私の知る限り、どの高校でも利用があり、これがないとレファレンスに支障を来します。1冊1万円超え、100冊以上あります。
10年ごとにこのためだけに100万円を学校がくれるか?
そして今では品切れの巻もあります。
「新日本古典文学大系」「日本古典文学大系」(岩波書店)
「新」があるから「旧」は不要かと思えば、「旧」の方の解説がいい(好みかも)とか、「新」と「旧」はすべてかぶっているわけではないなどで、どちらも利用されています。
「新編 日本古典文学全集」(白)「日本古典文学全集」(赤)(小学館)
上に同じく。旧版の赤を好む、若い国語の先生がいます。
「大漢和辞典」(大修館書店)全15巻
今HPを見たら26万円超でした。文化祭・体育祭のスローガンなんかで見ている生徒が毎年います。
なお、
長く読み継がれている図書は買い替えなども適宜行われる
とのことですが
この場合の「適宜行う予算」は、いったいどこにあるのかー?
通常予算も少なすぎるのに?
1年に数回程度使われる本とはいえ、多額の費用を充てる余裕などないので捨てられませんね。
◆どの本を捨てて、どの本を残すかは、利用度と更新費とスペースによります。
書籍の取捨選択には本来、知識と経験が必要で、時間もかかります。
流れとして…利用頻度の低い本はまず書庫に入れます。
廃棄対象にするかどうかは
「現在も出版社が新品として販売しているか」
が私の幾つかある基準の一つです。
販売中で状態が良い書籍は捨てません。
◆もちろん、古い本ばかりの図書館が魅力的でないというのは大変よくわかります。
大事なのは兼ね合いです。
科学、医療系などの自然科学。
スポーツなどトレーニング方法やルールが変わるもの。
言語。
政治・経済・福祉・ジェンダーなど社会科学…
この辺りは古びないように注意しないといけません。
そして小説も「名作」と呼ばれるものなら、本の状態が良い限りは棚に並び続けますが、流行に流されやすいライトノベルなどはシリーズによっては数年もたないことも。
アニメ化した時だけ読まれて、数年後は閑古鳥が鳴くこともしばしば。
かと思うと20年ぶりに「続き!」「新シリーズ!」など出てきて意外と人気だったりするので、本当に難しい…。
◆「学校図書館図書廃棄規準」が「法律」なら、現場で司書が行うことは「判例」です。
『廃棄台帳に記載せず「赤木流に3千冊捨てた」』ととある校長先生のネット記事がありましたが、どの本が現在図書館にあり、どの本がないかというデータは管理上、必要です。それがなければ紛失がわからないままになります。
記事では触れていませんでしたが、廃棄台帳など記載しなくても、恐らくそこの司書はデータ上で除籍手続きをしているはずです。
(データで除籍手続きをすれば、廃棄台帳もデータ上で簡単に出せる。)
廃棄したせいで、利用者や図書館自身が困ることになっては本末転倒です。
もちろん古い本ばかりで、魅力がない図書館は問題ですが。
以下は上の条文の続きです。
個人的には2〜8は図書館として当然の内容で、後は学校の状況によると思います。
2.形態的には使用に耐えうるが、記述内容・掲載資料・表記等が古くなり
利用価値の失われた図書。
3.新しい学説や理論が採用されていない図書で、史的資料としても利用価
値の失われた図書。
これは大いに参考にしないといけません。
ただ、昔の研究内容の方が正しかった、今は圧力かけられて本当のことが言えないなんてこともありうるので、これも難しいところです。
