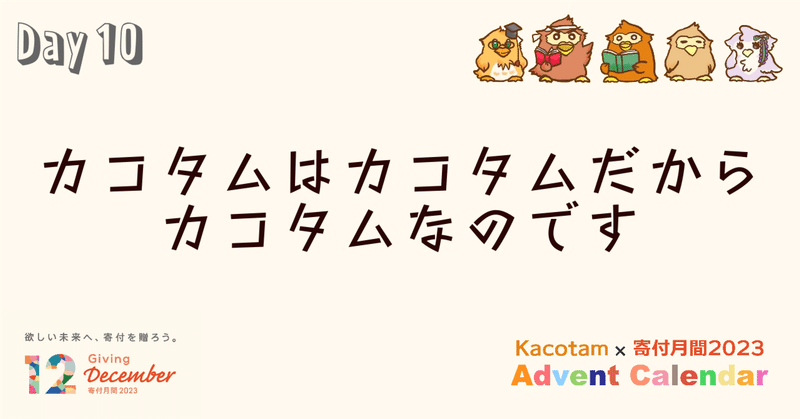
カコタムはカコタムだからカコタムなのです
この記事は、Kacotam × 寄付月間2023アドベントカレンダーの10日目の記事です。
◆◇◆
————カコタムの本質を一言で表すとしたら、それは「カコタム」だと思う。
いきなり、国語力の低そうな構文でごめんなさい。
まずは、改めて、認定NPO法人Kacotamの名前の由来からお話します。
「かんがえる」の「カ」
「こうどうする」の「コ」
「たのしむ」の「タ」と「ム」
……合わせて、「カコタム」
私たちカコタムのメンバーはみんな、「考えて、行動して、楽しむ」ことを何より大事にしています。
「名は体を表す」とはまさにこのことで、団体の名前はそのまま、Kacotamの活動の軸であり、特徴であり、譲れない一線であり。
だから、カコタムの本質を問われたら、その答えは「カコタム」になるわけです。
初めまして。ボランティアメンバーのたいきです。
活動歴は、かれこれ8年を超えました。
それなりに長い期間、この団体に関わってきたなかで、数多くの「カコタム」な場面に出会ってきて、自分自身もたくさん「カコタム」してきました。
「カコタム」の誕生秘話は別の記事に譲りますが、私なりの視点で、いかにKacotamが「カコタム」なのかを伝えられたらと思います。
1.かんがえる
学習支援の現場において、私たちメンバーは、常に色々なことを考えながら動いています。
Kacotamにおける子どもとの関わりには明確な正解がなく、目の前の子どもに対して今の自分が何をすることができるのか、常に模索する必要があるからです。
英語の文法や数学の解法を、手順通りに教えれば良いというものではありません。
物事の伝え方、子どもからのメッセージの受け取り方、関係性の持ち方、場の雰囲気の作り方……。
かんがえた結果、自分が導いた最善手は、行動してみたら成功するときも失敗するときもあります。成功なのか失敗なのか、最後まで分からないことも多いです。
それでもなお、その結果を踏まえてまた次の行動を考え直して、目の前の子どもと本気で向き合うこと。
これがカコタムの難しいところであり、強烈に楽しいところでもあるわけです。
2.こうどうする
メンバーだけでなく、子どもにも、考えて行動することを楽しんでもらいたい。
それがカコタムの願いであり、制度として表れているのが、「カタチ化」や「お仕事カコタム」です。
カタチ化は、子どもの「やりたい」を実際に「カタチ」にするプロジェクト。まさに、頭の中にある想いを「行動」に移すための枠組みです。
私たちメンバーは、手助けはしますが、すべてをお膳立てすることはしません。それでは「考える」プロセスが無く、ただの「コタム」になってしまうからです。
カタチ化シートと呼んでいるフレームを使い、子どもに「どうしたら楽しく行動できるか」を考えてもらいます。
そうして子どもが考え抜いた行動プランの実現を、団体の力でそっと後押しするのが、Kacotamの学習支援以外のもう一つの大切な役割なのです。
3.たのしむ
Kacotamメンバーが大事にしている考え方(クレド)のひとつに、「楽しいかどうかを常に問う」という言葉があります。
いくら考えて行動をしても、楽しくなければ、それは「カコタム」したことにはならないのです。
活動をするうえで「楽しさ」を必須事項とするのは、ある意味ではとても難しく感じれるかもしれません。
そんな中で、私が常に実践していることは、「まずは自分がカコタムの活動を楽しむこと」です。
もっと言えば、「大人が楽しんでいる様子を、惜しげもなく、恥ずかしげもなく、堂々と子どもに見せること」です。
例えば、中高生の居場所ゆるきちでの、メンバーの過ごし方。
何をする場所なのかが明確でない施設であり、さまざまな配慮やバランス感覚も含めて大人の振る舞いは難しい場所なのですが、基本的には、「自分が楽しんでいる姿を見せる」で良いと思っています。
何年か前にゆるきちのレギュラーメンバーだった頃は、「紙粘土を使って骨の模型を作ってみよう!」とか、「1階から2階まで全部使ってドミノ倒しやってみよう!」とか、思いついたことは勝手にどんどん行動して、ひとりで楽しんでいました。
大がかりなときは、勝手に予算申請して企画にしてしまうこともあります。一番印象に残っているのは、リアル脱出ゲームをゆるきちでやったら面白そう、と思って企画した「ゆるきちからの脱出」です。
たいていの場合は、私がひとりで勝手に楽しんでいると、そのうち子どもも乗っかってきて最終的には一緒に大笑いしています。たまに全く見向きもされないこともありますが、それはそれで、各々の楽しみ方の尊重を提示できたと自分に言い聞かせています(笑)。
さいごに
とはいえ、いつもうまくいくわけではありません
考えたのに行動できなかったとき。行動したのに楽しめなかったとき。私たちはとても悔しく、無力さを感じます。
以前、「ラグビーをやってみたい」という子どもがいて、実現プランまで一緒に考えたことがありました。そのときの彼の目はとても輝いていましたが、実現の段になってネックになったのは、予想外に高かった練習場の使用料の問題。
私たちは資金繰りのために奔走しましたが、それに時間がかかっているうちに彼の目の光はなくなり、プランは自然消滅してしまいました。
現実問題として、Kacotamに通ってくれている全ての子どものあらゆる「やりたい」に応えるには、Kacotamはヒトの面でもカネの面でも、まだまだ圧倒的にリソースが不足しています。
そのことを実感してから、私は少しずつ現場に出る時間をバックオフィス活動に充てるようになり、組織整備に尽力するようにしています。
Kacotamは来年13年目になります。
拡大を続ける団体規模に見合うだけの、組織体制、財務体制を整えること。現実問題の壁に阻まれることなくひとつでも多くの「カコタム」事例が実現できますように。
来年は勝負の年になりそうです。
引き続き、Kacotamの応援を、どうぞよろしくお願いいたします。
◆◇◆
★ 「寄付月間」について★
★Kacotamをお金で応援する★
★Kacotamで一緒に活動する★
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
